
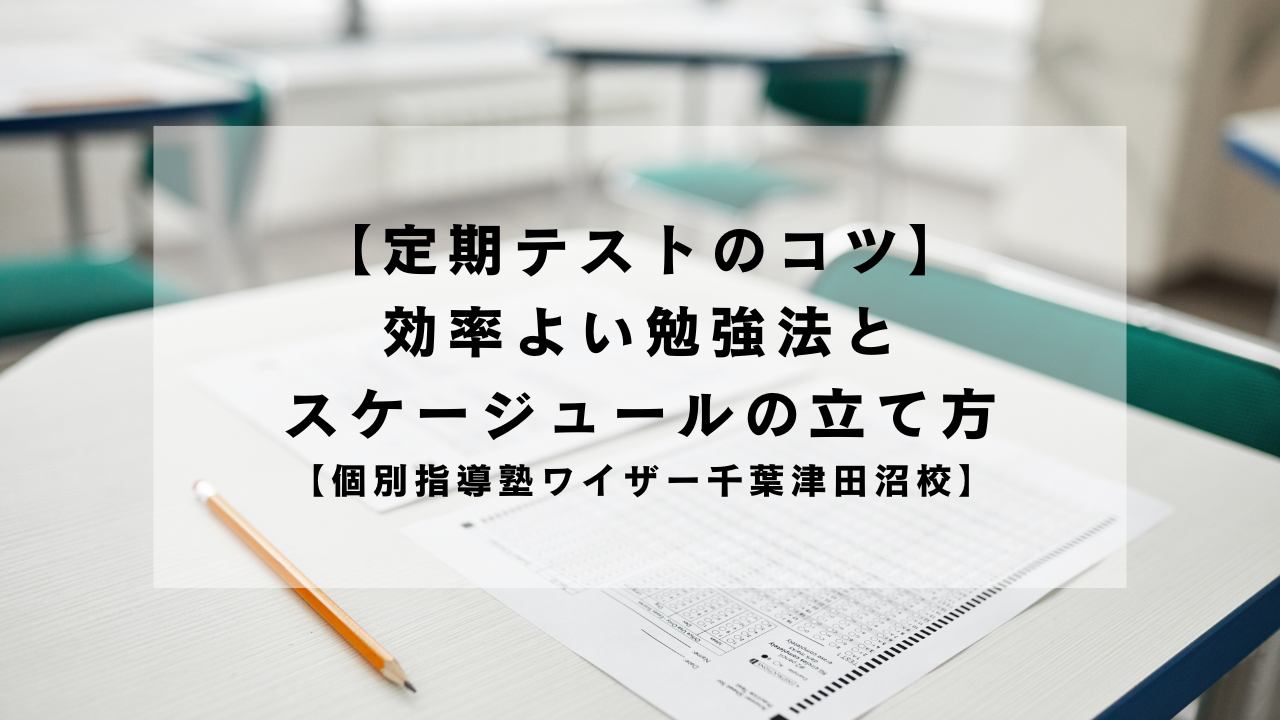
テスト直前だけ勉強する…そんな勉強法、もうやめませんか?
「うちの子、毎回テスト前日だけ勉強して終わりなんです…」
「とりあえずワークを終わらせて終わり、内容は頭に入っていない…」
そんな風に悩んでいませんか?
しかし、それはお子様の「やる気がないから」ではありません。
実はほとんどの場合、
「正しい勉強の仕方」や「学習計画の立て方」が分からないだけなのです。
子どもに「勉強しなさい」と言っても、
何をどうすればいいのか分からなければ、
「とりあえずワーク」
「とりあえず教科書をパラパラ」
という「なんとなく勉強」に終始してしまいます。
その結果、点数が上がらず、
「やっぱり自分はできない」と自信を失い、
ますますやる気をなくしていくという悪循環に陥るのです。
定期テストは“やった分だけ結果が出る”チャンス
受験勉強と違い、定期テストの範囲は明確で、
出題傾向も予測しやすいのが特徴です。
つまり、正しい方法で事前に対策すれば、
誰でも点数を伸ばしやすい試験と言えます。
さらに、定期テストの結果は中学・高校での内申点に直結するため、
推薦入試や総合型選抜を目指す場合は、なおさら無視できません。
「受験の勉強だけやっていればいい」
「テストはその場しのぎでいい」
そう考える人もいますが、
定期テストでしっかり結果を出すことが、
結局は受験への近道になるのです。
なぜ定期テスト対策が必要なのか?
「定期テストって、受験に関係あるの?」
「どうせ一夜漬けで乗り切れるでしょ」
そう思っている中高生、
あるいは保護者の方も少なくないかもしれません。
ですが、それは定期テストの本当の重要性を知らないだけです。
ここでは、「なぜ定期テストの対策が必要なのか?」を
3つの視点から整理してお伝えします。
① 内申点に直結する
定期テストの点数は、
学校でつけられる「通知表の成績」に大きく関係します。
そして、この通知表の評価(いわゆる“内申点”)は、
高校・大学の推薦入試や総合型選抜において非常に重視されます。
たとえば、公立高校の推薦入試では、
内申点と面接、小論文だけで合否が決まることもあります。
私立高校でも、
内申点を一定以上とっておけば「単願・併願推薦枠」が狙えます。
大学の学校推薦型選抜では、高1から高3の成績がそのまま評価対象になります。
つまり、定期テストで結果を出せば、進路の選択肢が大きく広がるのです。
② 基礎学力の確認と定着に役立つ
定期テストは、基本的に「授業+教科書内容」から出題されます。
そのため、日々の学びがどこまで身についているかを確認する絶好の機会です。
ここでの理解があいまいなまま進んでしまうと、次の単元でもつまずき、
最終的には「何が分からないかも分からない」という状態になってしまいます。
たとえば数学で公式を覚えていなければ、次の関数や図形の単元は理解できません。
英語も、文法や単語をおろそかにすると長文読解が難しくなります。
このように、定期テストへ取り組むことをしなければ、
いざ勉強のやる気が出たとしても、
わからなさすぎてすぐ挫折してしまいます。
なので実力確認や、定着だけでなく、
将来の自分がやる気を出した時の挫折を避けることもできるのです。
③ 学習習慣のきっかけになるから
勉強に身が入るきっかけは、
ネガティブなものでも、ポジティブなものでも、
何でも大丈夫です。
「友達にバカにされる」
「先生に怒られる」
そういったきっかけでも、
一度やる気にさえなり、
努力が実れば、自然とやる気は湧き上がってくるようになります。
なので、定期テストが大切なのです。
定期テストがあるからこそ、
「勉強しなきゃ」というモチベーションが生まれます。
これをうまく活用すれば、
学習習慣を身につける“チャンス”に変えることができるのです。
「ダイエットをしよう」と言いながらしない人が、
ちょっとしたきっかけ火がつき、
そのまま筋トレや運動が習慣化されるのと同じです。
毎回のテストごとに計画的に取り組むことで、
「勉強のサイクル」が生活の一部になり、
いざ受験勉強などが本格化したときにも、
慌てることなくスタートが切れます。
逆に、定期テストを軽視して「勉強はまた次のテストもあるし」と考えると、
いつまでたっても勉強の習慣がつかず、どんどん学力は下がっていきます。
定期テスト対策の基礎3ステップ
では実際、定期テスト対策とはどのようにすればいいのでしょうか?
定期テストで結果を出すためには、
「やみくもに勉強する」のではなく、
戦略的にステップを踏んで取り組むことが大切です。
ここでは、個別指導塾ワイザーでも取り入れている、
誰でも実践できる定期テスト対策の基本3ステップを紹介します。
▼ステップ1:苦手の把握と基礎固め(テスト3週間前〜)
テスト範囲が発表されたら、
まず最初に行うべきは全体の見渡しと苦手の洗い出しです。
✅ 具体的な行動例
・教科書・授業ノート・ワークをざっと確認して「苦手そうな単元」に印をつける
・英語や数学は、前の単元の理解が土台になるので、基礎に立ち返る
・教科書の例文・公式・図などを「読んで分かる」レベルに整える
たとえば英語なら、文法(時制・助動詞など)の基礎が抜けていないかをチェックし、
数学なら、基本の計算パターンを反復して「瞬時にできる状態」にしておきましょう。
この段階での“基礎の穴”を放置すると、
応用問題にも太刀打ちできず、点数に繋がりません。
まずはベースとなる基礎知識や苦手な部分を補う事に時間を使いましょう。
▼ステップ2:わからないところを潰していく(テスト2週間前〜)
基礎の確認が終わったら、ここからが“実戦フェーズ”です。
間違えた問題、あやふやだった内容を、
完全に理解・定着するまで繰り返すことが大切です。
✅ ここでのポイント
・間違えた問題にチェックを入れ、なぜ間違えたかをノートに書く
・「なぜその答えになるのか?」を自分の言葉で説明できるようにする
・理科・社会などの暗記科目は“理解+関連づけ”で覚える(例:歴史は年号+背景)
またこの時期から、国語や理科、社会といった
「演習量がものを言う科目」も並行して進めていきましょう。
理解しきれていないところをあいまいにしたまま先に進むと、
テスト本番で「見たことあるけど解けない」状態になってしまいます。
▼ステップ3:暗記と問題演習の反復(テスト1週間前〜)
テスト1週間前になったら、アウトプット中心に切り替えるタイミングです。
ここで重要になるのが、「エビングハウスの忘却曲線」の考え方。
人は、何かを覚えても1日後には約70%、
1週間後には約80%を忘れてしまうと言われています。
✅ 効果的な学習法
・すでに解いた問題を「再び解き直す」ことで記憶を再活性化
・暗記科目は朝・夜・隙間時間に分けて“分散学習”する
・ワークは最低3周。3回目は「解ける問題だけ」で時間短縮
また、「暗記しっぱなし」で終わらず、
必ず“テスト形式で確認”することも重要です。
自分でテストを作る、親や友達に出題してもらう、
という形でアウトプットに慣れておきましょう。
テスト勉強スケジュールの立て方
しかし、定期テストの対策法はわかっても、
実際これを行動に落とし込んでいくのが一番大変です。
運動でも「頭ではわかってるけどできない」
ということはよくあると思います。
勉強も同じです。
「計画の立て方がわからない」
「スケジュールを作っても守れない」
これは、勉強が苦手な生徒・学習習慣がない生徒によく見られる悩みです。
ですが、定期テストの成功は
スケジューリングが9割と言っても過言ではありません。
なのでここからは、
テスト勉強の計画を実行できるスケジュールに落とし込む方法を、
実践的に解説します。
▼STEP1:まずは目標を設定する
スケジュールを立てる前に、
「今回の定期テストでどんな結果を出したいのか?」
という目的地を明確にすることが大切です。
✅ 目標の立て方例
・前回より各教科+10点を目指す
・平均80点以上
・英語だけは90点超えたい
・推薦に必要な内申4.0をキープする
数字が明確であるほど、モチベーションも保ちやすくなります。
▼STEP2:やるべきことを“見える化”する
「勉強する」と一言で言っても、実際にやることは山ほどあります。
そのため、やるべきことを“紙に書き出してリスト化”する作業が不可欠です。
✅ チェックポイント
・教科書、ノート、ワーク、プリントなどの確認
・ワークのページ数、授業進度、テスト範囲の範囲を割り出す
・「教科書p.18〜35」「ワークp.10〜20」「単語30語」など、細分化して記述
このとき、「やるべき量」が視覚的に整理されるので、
頭の中がスッキリして動き出しやすくなります。
▼STEP3:残り日数を逆算して、1日ごとの予定を割り当てる
「テストまであと何日あるか?」をカレンダーで数えて、
書き出したタスクを“1日ごと”に分配していきます。
✅ 実際のスケジューリング例
・テストまで14日 → 1周目インプット7日/2周目復習4日/仕上げ3日
・英語ワークが30ページ → 1日5ページ×6日間
・社会の教科書が10単元 → 1日2単元×5日間
ポイントは、「1日にやることが具体的で少ない」ことです。
大人でも「今日は3時間がっつり仕事」と言われるより、
「午前に○○の資料作成、午後は会議30分」と言われるほうが動きやすいのと同じです。
▼STEP4:実現可能な量に調整する(詰め込みすぎNG)
せっかく計画を立てても、内容が現実離れしていれば、
達成できずに挫折してしまいます。
部活・習い事・通塾など、
“実際に使える勉強時間”をベースにスケジュールを調整することが重要です。
✅ 平日2時間、休日5時間が限界と想定
・平日:夕方~夜のうち1時間はインプット、1時間はアウトプット
・休日:3教科に分けて集中タイムを設ける(午前・午後・夕方)
詰め込みすぎず、「10分休憩」などもスケジュールに組み込みましょう。
▼STEP5:勉強ログをつけて見直す
スケジュール通りにできたかどうかを記録することで、
「達成感」+「改善点の把握」の2つを得られます。
個別指導塾ワイザーでは、
「1日ごとのタスク報告+講師からのフィードバック」があるため、
学習を“振り返る習慣”が自然と身につきます。
家庭でやる場合は、
・チェックリスト方式
・カレンダーに○×を記録
・学習日記をつける
などでも効果があります。
効率的に点数を伸ばすための勉強法
ここまで解説した、
「定期テスト対策の基礎3ステップ」
「テスト勉強のスケジューリング法」
を実践していただければ、総合的に点数は上がると思います。
しかしこれはあくまで、
定期テスト前の1ヶ月、3週間前からの勉強法であって、
本当に大切なのは毎日の勉強法です。
「勉強しているのに点数が伸びない…」
「時間はかけてるのに、全然結果につながらない…」
そんな悩みの多くは、“やり方の間違い”にあります。
なのでここからでは、どんな生徒でも明日から真似できる
「効率的に点数を伸ばすための毎日やるべき勉強法」をご紹介します。
① 毎日10分の“即復習”がテスト勉強の土台になる
人間の記憶は、「学んだことをすぐに復習する」ことで
何倍も定着しやすくなります。
つまり、テスト勉強は“テスト2週間前から”ではなく、
“毎日の復習習慣”で始まっているのです。
✅ 具体的には
・授業が終わったその日のうちに、教科書やノートを見返す(10分でOK)
・その日に出された宿題を“その日のうちにやる”ことで復習完了
・「わからなかった問題」に印をつけて、後日まとめて再確認
たとえば、1日10分の復習を1ヶ月続ければ、
300分(5時間)分の蓄積になります。
これがテスト前の“貯金”となり、
余裕をもって本番に臨めるのです。
② ワークは「授業ペースで進める」が勝ちパターン
よくあるNGパターンが、
「ワークをテスト直前にまとめてやる」という行動です。
これは、“作業としてワークをやる”だけになり、
身につかない原因になります。
✅ 効果的な進め方
・授業で進んだら、その週のうちに該当ページを解く
・1回目は“理解しながら解く”、2回目以降は“スピードと正確さ”を意識する
・解けなかった問題にマークして、2回目以降の復習に活用する
定期テストの点数は、「ワークを何周やったか」ではなく、
「どれだけ“意味のある演習”をしたか」で決まります。
③ “反復演習”が知識と解法の定着を生む
学校のテストでは、「ちょっと形を変えた問題」や
「数字だけが違うパターン」など、
見た目は違っても本質は同じ問題がよく出されます。
これに対応できるようにするには、“解けた問題も含めて反復”が必要です。
✅ おすすめの反復方法
・1回目:普通に解く(ミスに印をつける)
・2回目:印をつけた問題だけを再トライ
・3回目:全体を確認しながら“確実にできる”状態へ
「分かったつもり」が最大の落とし穴です。
本当にできるかどうかは、“もう一度解いたときに正解できるか”で判断しましょう。
④ ケアレスミスは「意識」だけでは減らない
「計算ミスをなくせば、あと10点上がるのに…」
そう感じたことがある人は多いはず。
ケアレスミスは、「気をつけよう」だけでは減りません。
自分がどんなミスをしているのかを“記録”することで、はじめて改善に向かいます。
✅ ミスの管理法
・ノートに「ミスチェック欄」をつくる(例:記号のミス/見落とし/途中式抜けなど)
・ミスの傾向が見えてきたら、“ミスしやすい問題だけ”を集めて再演習
・「テストでは○○に注意」と自分なりの“事前ルール”を設定する
たとえば、数学なら「符号を必ずチェック」「答えを箱で囲む」など、
自分の弱点に合わせた“確認ポイント”を事前に仕込むと、驚くほど精度が上がります。
⑤ 自分に合った“暗記法”を見つけると勉強が楽しくなる
暗記が苦手な子は、「自分に合った暗記法」が
分かっていないケースが大半です。
暗記は、“自分が覚えやすいやり方”を見つけることで、
効率と楽しさが一気に変わります。
✅ 代表的な暗記スタイル
・赤シートで隠して反復(視覚タイプ)
・音読しながら覚える(聴覚タイプ)
・書いて覚える(運動感覚タイプ)
・単語カード/スマホアプリ/語呂合わせ/図解ノート/人に教える…など
※覚えるべき内容によって使い分けるのもおすすめです。
例えば、英単語は「音読と綴りのセット練習」、
歴史の年号は「語呂合わせ+人物ストーリー」で関連づけると、
記憶の定着度が一気に上がります。
これらの方法を習慣的に実践していただければ、
定期テストの1か月前に焦ることなく、
着実に高い点数をとることができます。
まとめと無料相談のご案内
ここまでお読みいただき、ありがとうございます。
本記事では、
「定期テストで点数が取れない…」
「勉強の仕方が分からない…」
という悩みに対して、根本原因から具体的な解決策まで、
ステップを踏んでご紹介してきました。
▼もう一度おさらい!定期テスト対策の成功法則
✅ 定期テスト対策が必要な理由
→ 内申点UP・受験準備・学習習慣の形成など、未来を広げる大事な土台になる。
✅ 3ステップで進めるテスト勉強法
→「苦手と基礎の把握」→「理解の深掘り」→「暗記と反復」で、確実に実力がつく。
✅ スケジュールは逆算思考で、無理のない形に分解
→ 目標→やること→1日単位に落とし込む。無理のない実行量が成功の鍵。
✅ 点数が伸びる子は“やり方”が上手いだけ
→ ミス分析・反復練習・暗記法の最適化など、やる気より“勉強戦略”が大事。
▼学習習慣がなくても、成績は上げられる
個別指導塾ワイザーでは、これらのノウハウを【習慣化】させるために、
徹底したサポートを行っています。
特に学習習慣がない子どもにとって大切なのは、
“自分一人では管理できない部分”を支えてくれる仕組みや環境を整えています。
🌟個別指導塾ワイザーの特徴🌟
✅ 365日提示される「毎日の学習タスク」
→ 「今日は何をやればいいの?」をゼロに。迷わず毎日机に向かえる。
✅ 完全個別カリキュラム設計
→ 生活リズム・学力・目標に合わせて、今の自分に“最適な計画”が届く。
✅ 毎日の学習報告&成果フィードバック
→ 毎日の取り組みが“見える化”されるから、親も子も安心して続けられる。
✅ 24時間質問受付OKの安心対応
→ 「わからない」を放置しない。すぐに聞けるから、つまずきにくい。
▼まずは無料相談で、今の悩みを聞かせてください
・勉強が続かない
・テストで点が取れない
・そもそもやる気がない
・どうやって勉強させたらいいのか分からない
そんな悩みを抱えている保護者の方。
個別指導塾ワイザーは、
そんな子どもたちが“自然と勉強できるようになる仕組み”を提供しています。
ご興味ある方はぜひ、無料相談へお申し込みください!
1人ひとりに合った最適な学習カリキュラムをご提案させていただきます!
▼無料相談はこちらをクリック▼



