
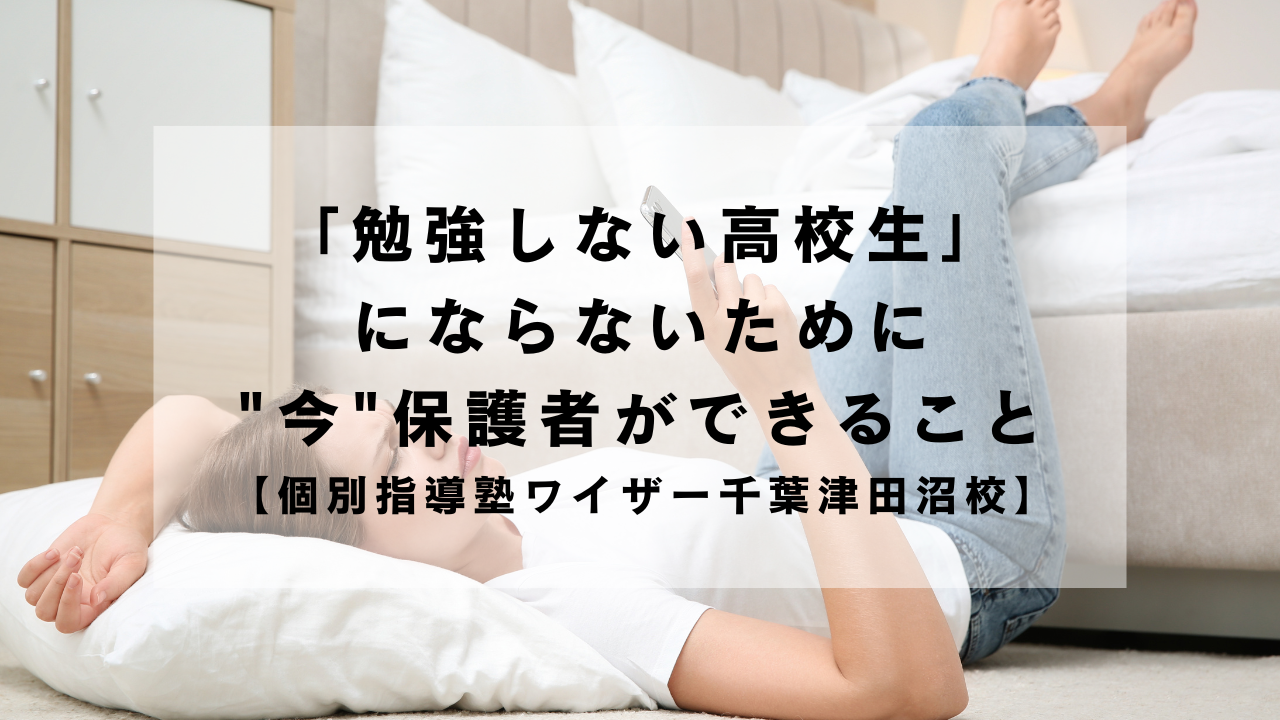
「うちの子、全然勉強しないんです…」
そんな悩みを抱える保護者の方、多いのではないでしょうか。
特に高校生になると、勉強の優先順位がどんどん下がっていきます。
部活にバイト、SNS、動画配信、友達との交流…。
楽しいことが増える一方で、
「勉強しなければいけない理由」がぼやけてしまい、
自然と学ぶ姿勢が薄れていくのです。
実際、
「高校受験までは頑張っていたのに、入学後はまったく勉強しなくなった」
という声は少なくありません。
努力の末に高校へ進学し、ようやく一息ついた途端、
勉強が“過去のもの”になってしまう。そんな高校生が増えています。
ここで重要なのは、
「高校生になってから勉強しなくなる」のではなく、
小学生や中学生の頃から、
“勉強が続かない環境”ができあがっていたということです。
つまり、「勉強しない高校生」にならないためには、
もっと前の段階での関わりが必要なのです。
今この瞬間、保護者としてどんな関わり方をすれば、
お子さんが将来つまずかずに済むのか。
この記事では、「勉強しない高校生」を未然に防ぐために、
今すぐ家庭でできる具体的な取り組みをお伝えしていきます。
勉強しないのは怠けているからではない
「勉強しない高校生」になってしまう理由は、
怠けているからでも、能力が足りないからでもありません。
そこには、明確な“原因”があります。
1. 「勉強は期間限定」という誤った意識
子どもたちの多くは、テスト前だけ頑張ればいい、
受験が終わればやらなくていい、
といった“短期集中型”の発想を持っています。
これは、学習そのものが日常に根付いておらず、
「やらなければならない時だけやるもの」として捉えられている証拠です。
この意識のまま高校生になると、
「今、困っていないから勉強しなくていい」という思考に陥りやすくなります。
2. 成績が落ちても“危機感”を抱かない構造
高校の勉強は一気に難易度が上がります。にもかかわらず、
部活動やアルバイト、SNSなどに時間を取られ、
学習の優先順位が下がっていくのが現実です。
しかも成績が下がったとしても、
すぐに生活に支障が出るわけではないため、
「なんとかなる」と考えてしまう。
これが、ずるずると学習から離れていく負のスパイラルの入り口です。
3. 家庭内での“勉強の管理”が通用しなくなる
小学生の頃は「勉強しなさい」と言えば素直に机に向かっていたお子さんも、
中学生〜高校生になると、親の言葉に反発したり無視したりするようになります。
「勉強しなさい」が逆効果になるこの時期、
保護者としての関わり方も変える必要があります。
しかし、多くのご家庭ではここに戸惑いが生じ、
「もう本人の問題だから」と、見守ることと放任することを混同してしまうのです。
4. 「やるべきことがわからない」から始まる無気力
高校生の中には、やる気はあるのに
「何から始めればいいかわからない」
と感じて手が止まってしまう生徒も少なくありません。
これは、「自己管理スキル」が育っていない証拠です。
やるべきことが明確になっていなければ、
学習へのハードルはどんどん高くなり、
結果としてスマホやYouTubeに逃げる日々が続いてしまいます。
これらの原因に共通しているのは、
“学習が習慣になっていない”という構造的な問題です。
日々の積み重ねがないまま年齢だけが進むと、
学年が上がるごとに勉強への抵抗感が大きくなり、
最終的に“勉強から完全に離脱”してしまう危険性すらあります。
次の章では、
これらの原因を根本から解決するための具体的な方法をご紹介します。
どうすれば自主的に勉強するようになるのか?
「勉強しない高校生」にならないためには、
中学生、さらには小学生の段階から
“学習を習慣化する仕組み” を家庭内・塾内で整えることが最も重要です。
勉強が得意かどうかではなく、
勉強することが当たり前の生活リズムに組み込まれているかどうか。
この差が、のちに大きな学力・進路の差として表れてきます。
以下では、保護者が今すぐ取り組める「3つの具体策」をご紹介します。
1. 家庭内で「毎日少しだけ勉強する時間」を確保する
「勉強は特別なもの」ではなく、
「毎日ちょっとやるのが当たり前」という空気を家庭内でつくりましょう。
最初は5分でもかまいません。大切なのは“量”ではなく“頻度”です。
【実践法】
・夕食後の30分を「おだやかに集中する時間」にする(子どもが勉強、親は読書など)
・「今日は何分やった?」を習慣にする(内容より“勉強に向き合った時間”を褒める)
・勉強後に“少しだけ”ごほうびを用意する(好きなおやつ・スマホ時間など)
こうすることで、「勉強=苦痛」ではなく「勉強=日常の一部」へと変わっていきます。
2. ルールではなく“流れ”をつくる
「ゲームは1日1時間」「勉強が終わるまでスマホ禁止」
などの“ルール”は一時的な効果しかありません。
むしろ反発を生みやすく、思春期の子どもには逆効果になることも。
重要なのは、「自然と机に向かう生活の流れをつくること」です。
【実践法】
・朝起きたら英単語5個、夜寝る前に10分復習など“生活習慣とセット”で学習を設計
・週1回は“振り返りタイム”を親子で設ける(できたことを認め、改善点は一緒に考える)
・勉強する姿を親が見せる(親も自己学習・仕事に取り組む姿勢を見せる)
ルールは「破るか守るか」になりがちですが、“流れ”は破る理由がなくなります。
3. 「習慣化」に特化した塾を活用する
家庭だけで学習習慣を築くのが難しいと感じたら、
習慣化に特化した塾の力を借りるのが効果的です。
たとえば「個別指導塾ワイザー」では、
ただの授業ではなく、以下のようなシステムで“自発的に学ぶ子ども”を育てています。
【ワイザーの実践内容】
・徹底した生活習慣ヒアリング
起床・就寝時間、スマホ利用時間などを確認し、学習が自然に入るスケジュールを設計。
・365日、毎日の授業外タスク提示
「4月12日 英語 p.45〜48」のように、1日単位で細かく具体的な課題を提示。子どもが“今日は何をやればいいか”で迷わない設計。
・タスク成果申告制度で自発性を育てる
毎日「できたこと」をフォームで報告。やらされる勉強から、“自分で進める勉強”へと意識が変化。
・24時間質問対応
わからない問題をそのままにしない。放置によるモチベーション低下を防ぐサポート体制。
これらの取り組みにより、スマホ漬けだったのに、
毎日120分の学習を自分の意思で続けられるようになった中学生の生徒様もいます 。
「勉強ができるようになる」の前に、「勉強する習慣を作る」。
これこそが、将来の学力と自立の土台です。
まとめ
「うちの子、高校生になったらちゃんと勉強するだろう」
そう思っていたのに、気がつけばスマホばかり、テスト前すら動かない。
そんな高校生は、実は“突然”勉強しなくなったわけではありません。
小学生・中学生の時期に、
「毎日コツコツ机に向かう」という習慣が根づいていなかっただけなのです。
勉強は才能でも、気合いでもありません。
毎日少しずつ積み重ねる力、つまり「習慣化」こそが、
将来の学力と可能性を決定づける本質です。
そのためには、次の3つが大切になります。
・家庭内で“勉強が当たり前になる環境”をつくること
・ルールではなく、生活の流れに学習を組み込むこと
・必要であれば、“習慣化”に特化した専門塾のサポートを得ること
「高校生になってから何とかする」のではなく、
「今この瞬間から、未来を変える行動を取る」。
この意識の違いが、お子さんの高校生活とその先の人生を大きく分けます。
最後に
ここまでお読みいただき、
「やっぱり今のうちから何か始めないといけない」と感じた保護者の方も多いはずです。
けれど、いざ行動に移そうと思っても、
・「うちの子はそもそも机に向かう習慣がない…」
・「どうサポートしていいのかわからない…」
・「市販の教材や他の塾では続かなかった…」
このように、不安や行き詰まりを感じている方も多いのではないでしょうか。
そこで、私たち個別指導塾ワイザーでは、
お子さまの学習状況や生活リズムに合わせた個別学習カリキュラムを作成するための
【無料相談】を実施しております。
▶ 無料相談でできること
・今の学習習慣や生活スタイルについて丁寧にヒアリング
・習慣化を目指した具体的な学習プランをご提案
・家庭でできる小さな一歩からサポート
・入塾の勧誘ではなく、“ご家庭で今できること”を一緒に考えます
「ちゃんと勉強させなきゃ」とひとりで悩む必要はありません。
“やらされる勉強”から“自分で進める勉強”へ変えていくために、
私たちが全力で伴走します。
まずは、お気軽に公式LINEまたはフォームからご相談ください。
お子さまの「勉強が当たり前になる日常」は、今日から始められます。
▼無料相談はこちらをクリック▼



