
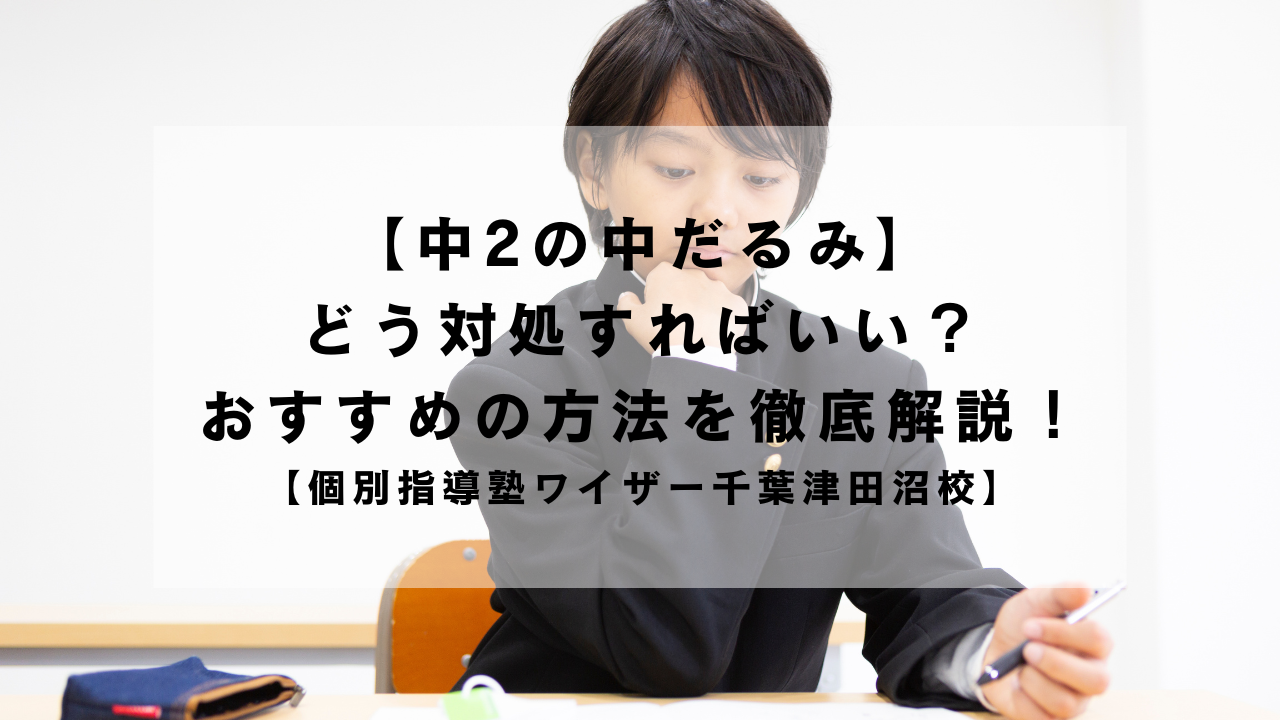
「最近、うちの子が全然勉強しなくなってきたんです…」
「前は自分から机に向かっていたのに、今はスマホばっかり…」
中学2年生をもつ保護者の方から、こうした悩みを伺うことが増えています。
1年生の頃は宿題もきちんとこなして、
テスト前には自分から勉強に取り組んでいたような子が、
2年生になったとたんにガラリと態度を変え、
「まあいいや」「あとでやるよ」と無気力な様子を見せるようになる。
この変化に戸惑う親御さんは非常に多いです。
このような現象は、教育現場では「中2の中だるみ」と呼ばれており、
決して珍しいことではありません。
実際に、多くの生徒が中学2年生という時期に何らかの形で
意欲の低下や態度の変化を経験しています。
特に学習面での停滞や後退、そして家庭内での会話の減少などが目立ち始め、
「このままで大丈夫なのだろうか」と不安になる保護者も少なくありません。
重要なのは、この時期の変化を単なる“やる気の問題”として片づけないことです。
子ども自身も「なぜやる気が出ないのか」
「自分がだらけているのはまずいと分かっているのに、体が動かない」と、
内心で戸惑い、葛藤していることがあります。
頭ごなしに叱っても、根本的な解決にはなりません。
中学2年生というのは、思春期と発達段階の大きな分岐点であり、
心と体の成長が加速し、価値観や行動パターンに大きな揺れが生じる時期です。
この「中だるみ」は、
そうした成長のプロセスにともなって一時的に現れる現象である場合がほとんどです。
つまり、これは一種の“通過儀礼”ともいえるもので、適切な対応とサポートがあれば、
多くの子どもは自然とその谷を乗り越えていきます。
逆に、親が焦って叱責ばかりしてしまうと、子どもはさらに心を閉ざし、やる気を失い、
最悪の場合は不登校や学力の著しい低下につながってしまうこともあります。
この記事では、中学2年生がなぜ中だるみを起こすのか、
その原因を客観的に解説するとともに、
今日から実践できる具体的な対処法をご紹介します。
勉強への意欲をどう取り戻すかだけでなく、部活動や人間関係、
生活リズムといった周辺の課題にも丁寧に触れていきます。
親としてどのようなスタンスで子どもに接するべきか、
どんなサポートが子どもを救うのか。
「中だるみ」に悩むすべてのご家庭にとって、ヒントとなる内容をお届けします。
なぜ中だるみが起きてしまうのか?
中学2年生で見られる「中だるみ」には、単一の原因ではなく、
さまざまな要因が複雑に絡み合っています。
子どもの性格や環境、家庭での関わり方によっても症状や程度は異なりますが、
共通して見られる主な原因を以下にまとめました。
1. 思春期による心理的・身体的変化
この時期の子どもは、第二次性徴を迎えて心身ともに大きな変化を経験しています。
身長の急激な伸び、ホルモンバランスの変化、異性への関心の芽生え、
自意識の高まりといった、内外の揺れに日々さらされている状態です。
また、思考が「具体的思考」から「抽象的思考」に移り始めるため、
自己と他者を比較したり、
「自分は何者か」
「この先どうなるのか」
といった悩みを持ち始めます。
これらの心理的負荷が積み重なることで、
勉強や生活全般への集中力が落ちやすくなるのです。
2. 自立心の高まりと親や教師への反発
中学2年生は、第二次反抗期のまっただ中。
保護者や教師に対して
「干渉されたくない」
「言われた通りに動きたくない」
という意識が強まる一方で、
自分一人で物事を進めるスキルや判断力はまだ発展途上です。
この「自立したいのに、まだできない」というギャップが、
内面的な苛立ちや自己否定につながることもあります。
勉強に対しても「なんでこんなことやるの?」という根源的な疑問を持ち始め、
ただの「やる気のなさ」に見える行動の裏には、
価値観の再構築が行われていることもあります。
3. 勉強内容の難化と成功体験の減少
中学2年生になると、学習内容が一段と難しくなります。
数学では一次関数や証明、英語では文法が複雑化し、覚えるべき単語も急増します。
成績がなかなか上がらず、「頑張っても成果が出ない」という挫折体験が積み重なると、
次第に「どうせやっても無理」という諦めにつながってしまいます。
とくに学年順位や通知表に敏感な子ほど、成績が下がることで自己肯定感を失い、
「勉強が嫌い」「やりたくない」という感情を持ちやすくなります。
4. 部活動や趣味に熱中しすぎて時間と体力を消耗
中学2年生は部活動がもっとも活発になる時期です。
1年生の頃は受け身だった練習が、
2年生になると「中心メンバー」「後輩の指導役」として責任が増し、
日々の活動がハードになります。
また、ゲーム・SNS・動画コンテンツなどの娯楽に触れる機会も増え、
「好きなこと」に時間を使いたい欲求が強くなることで、
勉強への優先順位が自然と後回しになってしまうのです。
5. 高校受験への危機感が薄い
中3のように明確な受験プレッシャーがない中2は、
「受験はまだ先」という気持ちが強く、緊張感が薄れていきます。
「ちょっとぐらいサボっても平気」「今は楽しみたい」といった油断が、
学習習慣の乱れにつながっていきます。
一方で、「中2の成績が内申点に関わる」という現実を知らない、
あるいは実感できていない子どもが多いのも現状です。
6. スマホ依存・生活リズムの崩れ
スマートフォンの使用時間が増えることにより、生活リズムが乱れがちになります。
特に夜間にSNSや動画視聴をしてしまうことで、就寝時間が遅くなり、朝起きられない、
授業中に眠くなるといった悪循環に陥ってしまいます。
さらにスマホには「短時間で気持ちよくなれる」仕組み(脳内報酬回路)があるため、
ついつい学習よりスマホを選びたくなる心理が働きやすくなります。
7. 人間関係や学校生活でのストレス
この時期は、友人との関係性が変化したり、
グループ内の上下関係や仲間外れなどに敏感になります。
表面的には元気に見えても、内心では
「学校に行きたくない」
「誰にも相談できない」
といったストレスを抱えていることも。
こうした精神的負担が日常生活に影響し、
結果的に学習意欲の低下として表れてくることがあります。
これらの要因はそれぞれ単独で起こるというより、
複数が同時に作用して「中だるみ」として現れます。
たとえば、スマホの使用が増えて寝不足になり、成績が下がって自信を失い、
そこに友人関係のストレスが重なるというような悪循環も少なくありません。
大切なのは、子どもの変化を「怠け」や「反抗」と決めつけず、
背後にある本当の要因に目を向けること。
中だるみの背景には、
子どもなりの必死な葛藤や未消化の悩みが潜んでいる場合が多いのです。
どうすれば中だるみが改善されるのか?
中2の中だるみに対処するには、子どもの行動そのものを無理に正そうとするのではなく
その背景にある「心理・環境・習慣の変化」に目を向けながら、
具体的かつ現実的な改善策を講じていく必要があります。
ここでは、7つの代表的な原因に対応する形で、
保護者が今日から取り入れられる実践的なサポート方法を紹介していきます。
方法①:将来の選択肢を一緒に調べ、学習の意味づけをしてあげる
中学2年生は、「なんのために勉強するのか分からない」と感じ始める年頃です。
目の前のテストや宿題に対して
「やらなきゃいけないのは分かってるけど、気が乗らない」と言う子が増えるのは、
学習の目的や価値を実感できていないからです。
このときに重要なのは、「勉強は将来の選択肢を広げるためにあるんだ」ということを、
親子で一緒に確認することです。
ただし
「将来困るよ」
「いい高校に行けなくなるよ」
といった“脅し型の声かけ”は逆効果です。
子どもにとって勉強が
「自分の好きなことや得意なこととつながっている」と感じられることが、
最も自然なモチベーションにつながります。
▼実践例
・「○○ってマンガが好きなんだね。編集者やイラストレーターって、どんな仕事してるか調べてみようか」
・「動物に詳しいね。獣医さんになるには理科のどこが大切なのか一緒に見てみる?」
・「人と話すのが得意そうだし、接客の仕事とか向いてそうだね。それって英語が役立つかもよ」
このように、子どもの興味関心から逆算して、
勉強がどう役立つかを見せていくことが重要です。
加えて、地域の高校のオープンスクールや説明会に親子で参加するのもおすすめです。
制服姿の先輩や、実際の授業の様子を見た子どもは、
「あの学校、楽しそう」「自分も行けたらいいな」
と具体的なイメージを持つようになり、勉強を前向きに捉え始めます。
▼ポイント
・押しつけや誘導ではなく、“一緒に探す”姿勢が大切です。
・「今の成績じゃ無理」と言うのではなく、「どうすれば近づけるか」を対話の中で引き出すこと。
・子どもが興味を持ちそうな職業図鑑や進路本、動画教材などを一緒に見るのも効果的です。
学ぶ意味が“点”ではなく“線”としてつながった瞬間、
子どもの表情や行動は確実に変わります。
中2の中だるみを抜けるきっかけは、そうした「意味の再発見」にあるのです。
方法②:成功体験を積ませる“設計”をする
中学2年生の中だるみの背景には、
「やっても結果が出ない」「頑張っても報われない」
という体験の積み重ねがあります。
特に成績が下がったり、難しい単元に苦戦したりすると、
子どもは無意識のうちに「自分は勉強に向いていない」と思い込むようになります。
この“学習性無力感”に陥ってしまうと、自ら行動を起こす気力が湧かなくなります。
だからこそ必要なのが、本人の手が届く範囲の「小さな成功体験」を積ませることです。
なぜ「小さな」成功体験が重要なのか?
大人の感覚で考えると、
「テストで90点取らせる」
「学年順位を上げる」
などの目標を与えたくなります。
しかし、今まさに自信を失っている子にとって、それらは“高すぎるハードル”です。
たとえば、
・1日10分の勉強を1週間継続できた
・ワークを1ページやりきれた
・分からなかった問題を自分で調べて解決できた
このような「本人が無理なく達成できる課題」をクリアすることで、
「自分はできるかもしれない」という感覚が少しずつ戻ってきます。
成功体験は、勉強に対する自己肯定感を再構築する“足がかり”になります。
具体的な実践方法
- 目標は「短期」「具体的」「達成可能」なものに絞る
・「1日30分だけ、スマホを置いて机に向かう」
・「英単語10個を、3日で完璧に覚える」
・「数学の関数の公式を5分で言えるようにする」
- 達成条件を“本人と一緒に”設定する
・親が一方的に「これやりなさい」と決めると、拒否反応が出やすくなります。
・「どこまでならやれそう?」「いつならやれそう?」と問いかけ、子ども自身にプランを立てさせることがコツです。
- できたらすぐ褒める、できなかったら責めない
・成功した瞬間に「やったね!」「ちゃんと続けてえらいね」と言葉にして伝えることが大事です。
・逆に、もし失敗しても「今日は疲れてたもんね、明日またがんばろう」と、次へのステップに切り替える言葉かけを。
- できた記録を“見える化”する
・チェックリストやカレンダーに「できた日」を記録すると、自分の頑張りが目に見えて自信になります。
・紙でもアプリでもOK。視覚的な“積み上がり感”は子どものやる気を引き出します。
注意点:やりすぎると逆効果になる
・「ゲーム感覚で目標をこなす」のは効果的ですが、報酬型のご褒美(お金・物)ばかりに頼りすぎると、「ご褒美がないと勉強しない」という状態になります。
・あくまで「できたことに対する満足感」「頑張った自分への誇り」を感じさせる方向での設計が理想です。
中2の中だるみは、「結果が出ないならやる意味がない」
と思い込んでしまうことから加速します。
だからこそ、小さな達成と成功を積み重ねることで、
勉強に対する“希望”を取り戻すことが、最も確実なリカバリー策になるのです。
方法③:朝と夜の“習慣リズム”を整えるサポートをする
中2の中だるみは、学習意欲や精神的な問題だけでなく、
生活習慣の乱れが大きく影響していることも多くあります。
特に夜ふかし・朝起きられない・睡眠不足・朝食抜きなどは、
脳のパフォーマンスを著しく下げ、結果的に勉強への集中力や記憶力、
やる気の持続に悪影響を及ぼします。
つまり、「生活リズムの乱れ=学習意欲低下の土台」
となっているケースは決して少なくないのです。
リズムが乱れる原因とは?
・スマホやゲームの長時間使用:特にベッドの中でのSNSや動画視聴は、寝るタイミングを逃し、脳が覚醒したままになりやすい。
・休日の“昼夜逆転”:平日は起きていても、土日に昼まで寝てしまうと、週明けの生活リズムが崩れ、学校が億劫に感じやすくなる。
・成長ホルモンの乱れ:思春期は体の変化が著しく、睡眠不足は身体的な疲労やイライラを助長します。
このような状態が続くと、「勉強しよう」という前向きな気持ち自体が
生まれにくくなってしまいます。
実践的な改善アプローチ
1. 親子で「生活リズムの見直しミーティング」を開く
ただ注意するのではなく、
週末に「最近寝るの遅くなってきたね」「朝ごはん、食べてる?」
と雑談ベースで話し合いの場を設けます。
本人が“自分の状態を言葉にする”ことで、
「ちょっと直さないとまずいかも」と気づくきっかけになります。
2. スマホのルールは“強制”でなく“合意”で作る
例:「夜9時以降はリビングに置いて充電する」
「ベッドにはスマホを持ち込まない」などのルールを、
親子で“交渉”しながら決めましょう。
押しつけではなく、「こうすればスッキリ眠れるようになるかもね」と、
“自分のためのルール”として設計することが重要です。
3. 休日の起床時間も「起きる時間」だけは一定にする
休みの日にお昼まで寝てしまうと、夜寝られなくなり、月曜の朝がつらくなります。
休日であっても「9時までには起きよう」と決めておくだけで、
リズムの崩れを最小限に抑えられます。
起きたあとにもう一度横になる“2度寝”を防ぐために、
朝食後に散歩や買い物に誘うのもおすすめです。
4. 就寝前は「脳を休める時間」に切り替える
夜寝る前にスマホやテレビを見るのではなく、間接照明の部屋で静かな音楽を流す、
読書をする、親子で軽く会話をするなど、
リラックスモードに移行する時間を5〜15分設けましょう。
自律神経が整い、入眠がスムーズになります。
ポイント:親も“生活リズムのお手本”になる
親自身が夜遅くまでスマホを見ていたり、朝ギリギリまで寝ている場合、
子どもは「大人も同じじゃん」と感じてしまいます。
できる範囲で構いませんが、親も生活リズムを整える姿勢を見せると、
子どもも自然と意識を変えやすくなります。
また、「一緒に朝ごはんを食べる」「休日の朝に散歩に行く」など、
親子でリズムを整える習慣を共有できると、生活習慣の改善が長続きします。
生活のリズムは、本人の“気合い”や“根性”だけではなかなか整いません。
だからこそ、仕組みづくりと環境の調整がカギを握ります。
朝起きられるようになっただけで、「学校に行きやすくなった」「授業中眠くない」と、
本人が実感できるようになることも少なくありません。
勉強は、その土台となる生活が整ってこそ前向きに取り組めるもの。
だからこそ、この“リズムの再設計”は、中だるみ脱出の本質的な第一歩です。
方法④:部活動の影響を肯定しつつ、学習との両立を支援する
中学2年生になると、部活動はより本格的になります。
1年生のときは“お試し”や“見習い”的なポジションだった子も、
2年生になると実質的な中心メンバーとして動く機会が増えます。
練習時間が長くなるだけでなく、後輩指導や大会出場などの責任も出てきて、
日々の疲労感は格段に大きくなります。
この「部活による疲れ」は、表面的には見えづらいですが、学習習慣に大きく影響します。
よくある悪循環
・部活で疲れて帰宅 → 勉強に手が回らない → 成績が下がる → 自信を失う → やる気がなくなる
・テスト前に部活が忙しい → 準備不足で成績ダウン → 「どうせやっても無駄」と思い込む
このようなループにハマってしまうと、部活も勉強も中途半端になり、
自己否定感が強まってしまう恐れがあります。
保護者がやってしまいがちなNG対応
・「部活より勉強でしょ!」と部活を否定する
・「疲れてるのはみんな同じ」と努力不足を責める
・「部活辞めるなら塾行かせる」と極端な選択を迫る
これらはすべて、子どものモチベーションを一気に下げてしまう声かけです。
なぜなら、部活動は子どもにとって“自分が認められる数少ない居場所”であり、
やりがいや自信につながる活動でもあるからです。
両立を支えるための具体策
1. 「部活がんばってるね」とまずは肯定することから始める
努力を認めてもらえたと感じた子どもは、
「じゃあ、勉強も少し頑張ろうかな」と前向きになります。
2. 1日のスケジュールを一緒に見直し、スキマ学習を設計する
「部活から帰って30分だけ」「お風呂の前に暗記ものだけ」といった、
“短時間集中型”の学習スタイルに切り替えることで、
負担感を減らしながら継続しやすくなります。
3. 定期テスト前は、部活顧問に相談して練習量の調整をしてもらう
学校によっては「テスト1週間前は活動休止」というルールがありますが、
そうでない場合でも顧問の先生に相談することで、
無理のない対応をしてくれるケースも多いです。
4. 土日は「片方を部活、もう片方を勉強に使う」とバランスを整える
完全に遊びも勉強も禁止するのではなく、
「日曜の午前だけは宿題に集中しよう」とルール化すると、
子どもも納得しやすくなります。
5. 食事・休息・入浴など“回復の質”を高める
疲れが取れないと、何をするにもやる気が湧きません。
部活後にしっかり栄養をとる、入浴でリラックスする、十分な睡眠時間を確保するなど、
“リカバリー力”を整えることも保護者の重要な支援です。
親の役割は「部活の味方」と「勉強の伴走者」の両立
部活と勉強は“どちらかを捨てる”という選択ではありません。
むしろ、部活で培った集中力・体力・達成感は、学習にも活かされる要素です。
「あなたの努力はちゃんと見ているよ」
「だからこそ、勉強もうまく乗り越えていけるように、一緒に考えていこう」
このようなメッセージを送り続けることで、
子どもは部活と勉強のバランスを取る力を少しずつ身につけていきます。
勉強に疲れているのではなく、
“部活に全力すぎて余力が残っていない”というだけのケースも多くあります。
だからこそ、まずは子どもの頑張りを認め、
そこから生活のリズムと学習環境を設計し直していくことが、
長期的な「中だるみ」対策になります。
方法⑤:家庭内で安心できる会話環境を整える
中2の中だるみは、勉強そのものに対する意欲低下だけでなく、
学校生活のストレスや人間関係の悩みが根底にあるケースも少なくありません。
部活での上下関係、グループ内の空気、先生との相性、
思春期特有の「自意識の強まり」など、
本人しか気づいていない葛藤を抱えている可能性があります。
そのため、
表面的な行動(だらだらしている・寝てばかり・スマホばかり)だけを見て判断せず、
「もしかして、見えない部分に原因があるのでは?」と想像力を持って関わることが、
保護者に求められます。
よくある“サイン”とその見逃し
・急に話さなくなった
・「別に」と返事が多くなった
・食欲や睡眠が不安定
・学校のことをあまり話さなくなった
・「学校行きたくない」とポツリと漏らす
こういった変化は、子どもからの“無言のSOS”であることがあります。
]思春期の子は言葉でうまく自分の気持ちを表現できないため、
態度や行動に変化が出るのです。
家庭内に“話せる空気”をつくる5つのステップ
1. 「なんで?」より「どうしたの?」という声かけを
・「なんでやらないの?」ではなく、「最近疲れてるみたいだね、何かあった?」
・否定や詰問ではなく、気づきと共感を含んだ問いかけが効果的です。
2. アドバイスより“まず聞く”を徹底する
・子どもが話し始めたら途中で遮らず、最後まで話を聞くことが大切です。
・「でもそれって違うんじゃない?」などの指摘は一旦脇に置きましょう。
3. 会話の場面は“非対面”が理想
・正面で座って「話して」と言われると、子どもは構えてしまいます。
・横並び(食卓、車、散歩など)や“ながら会話”が心の壁を下げるポイントです。
4. 「言ってくれてありがとう」の一言を忘れずに
・打ち明けてくれたこと自体が大きな前進です。
・どんな内容であれ、「教えてくれてうれしい」「話してくれてありがとう」と伝えてください。
5. 内容に関係なく“味方の立場”を貫く
・たとえ学校で問題が起きていたとしても、「あなたの味方だよ」「一緒に考えよう」という姿勢を崩さないこと。
・子どもは「この人にだけは見放されたくない」と感じている相手にしか本音を見せません。
専門機関との連携も前向きに考える
もし、話を聞いていて「これは少し重たい悩みかもしれない」と感じたら、学校の担任やスクールカウンセラー、
地域の相談窓口への連絡を検討しましょう。
・無理に子どもを連れて行くのではなく、まず親だけが相談する形でもOKです。
・そのうえで「こういう場所があるけど、行ってみる?」と提案すると、子どもも選択肢として受け入れやすくなります。
“話せる家”は子どもの回復力を飛躍的に高める
中学2年生の心はとても繊細です。
同級生とのちょっとした言い合い、SNSでの既読無視、
先生からの注意…それらが本人の中では想像以上の重荷になっていることもあります。
そんなときに、家に帰って「ただいま」と言える場所があること。
何を話しても責められず、
「あなたのことを信じてる」と言ってもらえる環境があること。
それこそが、子どもの“折れない心”を育てる一番の土台になります。
「口数が減った」
「笑顔が減った」
それは、ただの“反抗期”ではなく、助けを求めるサインかもしれません。
叱るよりも、気づくこと。
導くよりも、寄り添うこと。
このバランスが、中2の中だるみに対する最後の、そして最も大切な処方箋です。
中2の中だるみは「成長の証」。焦らず、でも見逃さず、親子で乗り越える
中学2年生という時期は、子どもにとって心身ともに大きな変化のまっただ中にあります。
学習内容の難化、人間関係の複雑化、思春期特有の葛藤、
そして自立への揺らぎそのすべてが、子どもにとっては想像以上に負荷のかかる環境です。
「中2の中だるみ」は、その結果として現れる“症状”にすぎません。
つまり、本人の怠けではなく、成長の途中で必ず通る過程でもあります。
まとめ | 中だるみは「3つのズレ」から起こる
- 能力と課題のズレ:「難しくなったのに、勉強のやり方が変わっていない」
- 気持ちと身体のズレ:「やらなきゃとは思っていても、動けない」
- 親の期待と子の本音のズレ:「何をどう頑張ればいいのか、本人にも見えていない」
この“ズレ”を無理に正そうとすると、子どもは反発したり、
ますます自信を失ってしまいます。
だからこそ、必要なのは「押しつける」ことではなく、「整える」ことです。
本記事でご紹介した5つの対策
| 原因 | 保護者にできる対策 |
| 将来のイメージが持てない | 興味関心と結びつけて「学ぶ意味づけ」を一緒に考える |
| 成功体験が少ない | 小さな目標を設定し、達成感と承認を繰り返す |
| 生活リズムが崩れている | 朝と夜の習慣を見直し、スマホや睡眠の質を整える |
| 部活動で疲れ切っている | 頑張りを認めつつ、短時間学習と両立の設計を |
| 家で話せる空気がない | 否定せず、共感して話を聞く“安心基地”をつくる |
この5つを意識するだけでも、中だるみの“底”を抜けるきっかけが見えてきます。
すぐに効果が出なくても構いません。
むしろ子どもが変わるスピードに、大人が焦りすぎないことがとても大切です。
保護者の“あり方”がすべての土台になる
「なんでできないの?」ではなく、「一緒にできる方法を考えようか」
「やる気あるの?」ではなく、「最近どう過ごしてる?」
そうした言葉の選び方ひとつで、子どもの心の扉は開いたり閉じたりします。
子どもは、他人からの指導ではなく、親のまなざしと信頼から立ち直る力を得るものです。
そして、保護者自身も「見守る」ことの難しさに悩んだときは、
ひとりで抱え込まず、周囲の力を借りることが重要です。
中2の中だるみは、“崩れる”時期ではありません。
“整え直す”時期です。
子どもはその中で、自分なりに揺れながら、考えながら、少しずつ進んでいます。
親としてできるのは、その歩みを止めず、支え続けること。
そうすればきっと、今は曇って見える未来も、少しずつ晴れ間が見えてくるはずです。
ひとりで抱え込まず、まずはご相談ください
ここまで読んでくださった保護者の皆さま。
「まさにうちの子のことだ」と感じられた方もいれば、
「何から手をつければいいのか分からない」と感じた方もいらっしゃるかもしれません。
中学2年生の中だるみは、一人ひとり理由も表れ方も異なります。
ある子にとっては勉強のつまずき、ある子にとっては人間関係の悩み。
また、本人でさえうまく言語化できない「なんとなくしんどい」
という感覚が背景にある場合もあります。
そうした見えにくい“もやもや”を、保護者がすべてひとりで抱え込む必要はありません。
私たち「個別指導塾ワイザー」ができること
ワイザーは、学力アップだけを目的とした塾ではありません。
私たちは、「学習習慣を整えるプロフェッショナル」として、
日々多くの生徒の中だるみや学習迷子と向き合っています。
特徴的なのは、以下のようなサポート体制です
・365日毎日の学習管理(週単位ではなく、日単位で課題を明示)
・個別ヒアリングに基づいた学習カリキュラム作成(性格・生活リズムまで考慮)
・学習タスクの成果報告制度(子どもが“やりっぱなし”にならない仕組み)
・24時間体制の質問対応(つまずきを翌日に持ち越させない)
・保護者への定期レポートと三者面談制度(現状を“見える化”)
つまり、子ども自身が「ひとりで頑張らなくていい」と思える学習環境と、
保護者が「見えない不安」を手放せる安心設計を両立しています。
こんなお悩み、まずはお聞かせください
・「何を言っても聞かなくなったけど、このままで大丈夫か不安」
・「勉強が手につかないみたいだけど、声のかけ方がわからない」
・「塾に通わせたいけど、本人が乗り気じゃない」
・「中2のうちに生活習慣を立て直しておきたい」
ひとつでも当てはまったら、どうかお気軽に無料相談をご利用ください。
無料相談はオンラインでも対応可能です
・対面が難しい方でも大丈夫。スマホひとつでOK。
・所要時間は30〜60分程度。個別の状況をヒアリングし、最適な提案をいたします。
・無理な勧誘は一切いたしません。お子さまの状況を共有いただくだけでも歓迎です。
「どこに相談していいかわからなかった」
「もっと早く相談すればよかった」
そうおっしゃる保護者の方が、これまでに何人もいらっしゃいました。
中2の中だるみは、対処が早いほどスムーズに改善へと向かいます。
ひとりで悩まず、まずは一歩。
お子さまの“リスタート”を、私たちと一緒に設計していきましょう。
▼無料相談はこちらをクリック▼



