
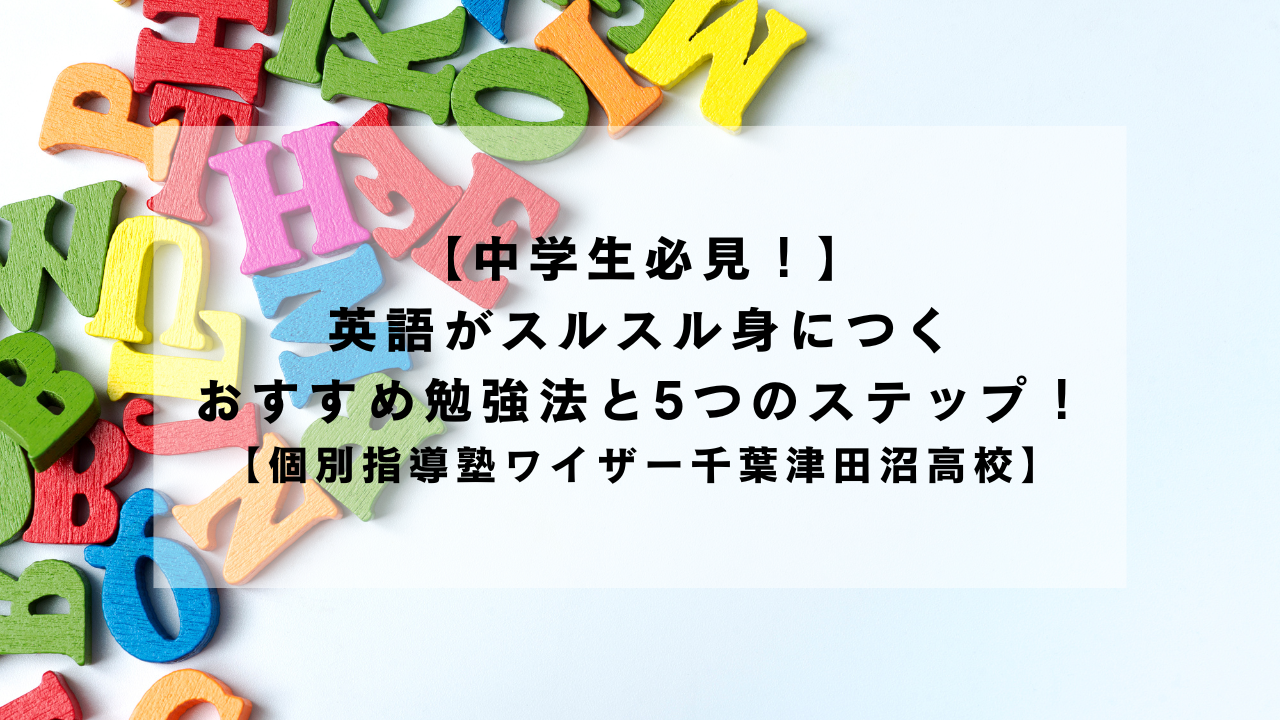
「英語が苦手…」は卒業!中学生にとって本当に必要な英語学習とは?
英語の授業が本格的に始まる中学生の時期、
多くの生徒が
「英語って難しい」
「単語が覚えられない」
「文法がわからない」
といった悩みを抱えがちです。
小学校では「英語に慣れる」ことが主な目的でしたが、
中学校に入ると一気に本格的な学習が始まり、
テストの点数が成績に直結するようになります。
しかも、英語はすべての教科の中でも積み重ねが非常に大切な科目。
1年生でつまずいたまま2年生になると、さらに理解できないことが増えていきます。
これは、英語という教科の特性に由来しています。
単語、文法、リスニング、リーディング、ライティング、スピーキング
この6つの要素はそれぞれが密接につながっており、
どれか1つが極端に苦手だと、全体の理解に支障をきたしてしまいます。
例えば、単語の意味がわからなければ長文読解はできませんし、
文法を理解していなければ作文も正しく書けません。
さらに、英語の音に慣れていないとリスニングで点を取るのが難しく、
スピーキングも恐怖感が先立ってしまいます。
こうした問題に直面した中学生の多くが、
「どうやって勉強すればいいかわからない」と立ち止まってしまいます。
実際、
「何から始めればいいの?」
「毎日どれくらいやればいいの?」
といった疑問は、中学生本人だけでなく保護者からもよく聞かれる声です。
英語の学習において最も大切なのは、
“自分に合った学習ステップを見つけて、それを継続すること”です。
そしてそれを可能にするためには、
「スルスル身につく」感覚を体験することが非常に重要です。
努力が結果につながる実感を持てれば、学習は苦痛ではなく、
むしろ楽しいものに変わります。
では、「スルスル身につく」とは具体的にどんな状態を指すのでしょうか?
これは、1週間前に覚えた単語が自然と口から出てくる、
リスニングの内容がスッと頭に入ってくる、
英文を読んでいても途中でつまずかなくなる
そうした“理解が定着する感覚”のことです。
英語の成績を上げるために必要なのは、単なる暗記や根性論ではありません。
科学的な学習ステップに沿って、
効率よく「聞く」「話す」「読む」「書く」の4技能を
バランス良く鍛えていくことがポイントです。
そしてそれを習慣化させることで、確実に“英語力”は伸びていきます。
このブログでは、「英語がスルスル身につく」状態を目指す中学生に向けて、
以下の5つのステップに分けて具体的な学習法を解説していきます
- 英単語の効果的な覚え方
- 英文法を無理なく理解する方法
- リスニング力を伸ばす習慣づくり
- リーディングで英語力を底上げ
- ライティング&スピーキング力を育てる練習法
どれも今日から始められるシンプルな方法ばかりです。
ぜひ、日々の学習に取り入れて、英語に対する苦手意識を克服し、
“わかる・できる・楽しい”というサイクルを実感してください。
ステップ1:英単語の効果的な覚え方 ~「意味を覚える」から「使える」単語へ~
英語の勉強でまずつまずきやすいのが、「単語の暗記」です。
「せっかく覚えたのにテストになると出てこない」
「1週間経つともう忘れている」
といった悩みを持つ中学生は非常に多いものです。
しかし、英単語は英語学習の“土台”です。
この土台がグラグラしていると、どれだけ文法を理解していても、
文章が読めず、書けず、聞き取れず、話せないという事態になります。
では、どうすれば英単語を“スルスル”覚えられるのでしょうか?
それには、「記憶の定着」に関する科学的な知見を活かしつつ、
中学生でも無理なく続けられる習慣づくりが鍵となります。
1. 単語は“短時間×高頻度”で覚える
人間の脳は「一度に大量の情報」を処理するよりも、
「少しの情報を繰り返す」方が圧倒的に記憶に残りやすい性質があります。
英単語も同様で、1日100個を一気に覚えようとするよりも、
1日10個を3日連続で反復する方が、はるかに記憶に定着します。
中学生におすすめなのは、
「朝起きて5分」「学校に行く前の5分」「寝る前の5分」というように、
1日の中で“複数回、短時間”を意識した学習スタイルです。
具体的には、1回10単語程度に絞り、3〜4回繰り返すのがベスト。
これだけで、記憶の定着率が2倍以上に跳ね上がるという研究もあります。
2. 音声とセットで覚えると忘れにくい
視覚(文字)だけで覚えるよりも、聴覚(音声)も同時に使うことで、
脳の記憶領域をより多く活用できるため、記憶が強化されます。
たとえば「apple」という単語を「ア・プ・ル」とだけ見て覚えるのではなく、
「アポー」と耳で聞きながら、声に出して一緒に発音する。
これを“目・耳・口”の三つを使った「三感覚記憶法」と呼びます。
特にリスニング力やスピーキング力を高めたい中学生には、
英単語アプリやCD教材を使って「音声付き単語学習」を習慣にすることが有効です。
3. 書いて覚えるのは最後の仕上げに
「単語はノートに100回書けば覚えられる」と考える人もいますが、
実際は「書くこと」だけでは効率が悪いです。
むしろ、“意味がわかっていないまま書く反復”はほとんど意味がありません。
まずは「見て」「聞いて」「話して」覚えた後、確認としてノートに数回書いてみる。
間違えた単語や苦手な単語だけを重点的に書いて定着させるようにしましょう。
1つの単語をただ書くだけでなく、“例文の中で使って書く”のが最も効果的です
(例:「I eat an apple.」など)。
4. 単語帳を自作して「自分専用」の記憶ツールに
既存の単語帳や教科書に加えて、「自分だけの単語帳」を作るのも有効です。
例えば、自分が間違えた単語・苦手な単語だけを抜き出して
小さなメモ帳や単語カードにまとめる。
これにより、重点的に復習すべき単語が一目瞭然になります。
中学生には100均の単語カードや、スマホの単語アプリを活用するのもおすすめです。
アプリの場合は、音声付きやテスト機能が付いているものもあり、
通学時間やちょっとした隙間時間に学習できるのが魅力です。
5. 忘れる前に「思い出す」仕組みを作る
暗記で最も重要なのが「忘れる前に思い出す」ということ。
エビングハウスの忘却曲線によると、
記憶した情報の多くは1日以内に忘れてしまうとされています。
そこで、「1日後」「3日後」「1週間後」に
同じ単語を再テストする仕組みを作ることが非常に効果的です。
例えば、以下のような復習スケジュールを組むと良いでしょう
・初日:新しい10単語を覚える
・翌日:前日の10単語を復習+新しい10単語
・3日後:最初の10単語をもう一度復習
・1週間後:初週に学習した単語すべてをまとめてチェック
このように“復習タイミングを管理”することで、
長期記憶にしっかり定着させることができます。
ステップ2:英文法を無理なく理解する方法 ~「暗記」から「納得」へ変える文法学習~
英語を使いこなすためには、英単語の習得だけでは不十分です。
正しい語順やルールに従って文章を組み立てる力、つまり「英文法の理解」が不可欠です。
ただし、多くの中学生がこの英文法に苦手意識を持っています。
「主語?動詞?過去形?…よくわからない!」という声も少なくありません。
では、なぜ文法はつまずきやすいのでしょうか?
それは、文法を“丸暗記”しようとしてしまうからです。
文法は本来「ルール」であり、「理解して納得するもの」です。
この節では、文法を感覚的に身につけ、使える知識に変えるための学習法を紹介します。
1. 文法を「ゲームのルール」としてとらえる
文法を覚えるとき、
ただ「文型」「時制」「助動詞」などの専門用語を丸暗記しようとすると、
すぐに混乱します。英語の文法は「文章を正しくつくるためのルール集」と考えた方が、
ずっと理解しやすくなります。
たとえば、
「三単現のS」は「主語がHe/She/Itの時だけ動詞にsがつく」というルールです。
これはサッカーで「ゴールキーパーだけ手を使ってもいい」
といった特例ルールと似ています。
“ゲーム感覚”で文法を捉えれば、暗記ではなく、
納得しながら覚えることができ、忘れにくくなります。
2. 「なぜそうなるのか」を必ず意識する
文法問題を解く際、
「なぜこの答えになるのか?」と自分に問いかけながら解くことが重要です。
たとえば、以下のような英文があるとします。
She goes to school every day.
このとき、「なぜ“go”ではなく“goes”なのか?」
を説明できるようにするのが学習の本質です。
「主語がShe=三人称単数で現在形だから、動詞にsがつく」と説明できれば、
本当に理解していると言えます。
“文法用語”を使って説明できるようになると、
定期テストや高校入試で記述問題が出ても対応しやすくなります。
3. 書く練習は「短文作り」から始める
いきなり長文を書こうとすると、文法がバラバラになってしまいがちです。
まずは主語+動詞の2語から始めて、
少しずつ語を足していく「段階的な短文作り」が効果的です。
例)
・I play.
・I play soccer.
・I play soccer after school.
・I play soccer after school with my friends.
このように1文ずつ育てていくことで、自然と語順や文の構造が身につきます。
4. イラストや図を使って視覚的に覚える
英文法は抽象的なルールが多く、文字情報だけでは理解しにくい場合もあります。
そこで、図解やイラストを活用するのが有効です。
たとえば、時制の違いを「時間軸」で図に表したり、
前置詞(in, on, at など)の使い分けを「場所のイメージ」で視覚化することで、
理解が深まります。
市販の文法参考書やYouTubeなどにも、イラスト付きの解説が豊富にあります。
文字だけで学ぶのが苦手な生徒は、
こうしたビジュアル教材を取り入れると効果が倍増します。
5. 自分の間違いノートを作る
文法学習で忘れてはいけないのが「間違い直し」です。
どれだけ勉強しても、間違えた部分を放置していれば成長は止まります。
そこでおすすめなのが、自分専用の「文法ミスノート」を作ることです。
・自分がよく間違える文法項目(例:過去形、不定詞、助動詞)を記録
・どんな問題で間違えたのか具体的に書く
・正しい文と、なぜその文が正しいのかを一緒に書く
このノートを繰り返し読み返すことで、自分の弱点を克服できるだけでなく、
「自分の文法学習の地図」を手に入れることができます。
英文法は「使ってこそ身につく」
英文法は、単に覚えるだけでなく、実際に使うことで初めて「定着」します。
音読、短文作り、会話練習、問題演習など、
いろいろな形でアウトプットすることが重要です。
最初は「合ってるかどうか不安…」と感じても構いません。
むしろ、間違えて覚え直すプロセスこそが、文法理解を深める一番の近道です。
ステップ3:英文をスラスラ読めるようになるためのリーディング練習法 ~「読めない」から「読める」に変わる3つの工夫~
文法も単語もそれなりに勉強しているのに、文章になるとまったく頭に入ってこない。
そんな“リーディングの壁”にぶつかっている人は多いのではないでしょうか。
英語を読む力(リーディング力)は、学年が上がるにつれて必要性が増していきます。
高校入試では長文問題が出題の中心ですし、
その先の大学受験でも英語長文は重要な得点源になります。
この節では、リーディング力をゼロから伸ばすための3つの練習法と、
具体的な実践方法をご紹介します。
1. 短い英文から段階的にレベルアップする
いきなり教科書の長文や入試問題に取り組むのではなく、
まずは1文、次に2文…というように段階を踏むのが効果的です。
例えば、以下のような流れで少しずつ文章量を増やしていくと、
自然と慣れていくことができます。
段階的なリーディングのステップ
・Step1:中学1年レベルの1文英語(例:I like soccer.)
・Step2:2文以上の会話文(例:I like soccer. How about you?)
・Step3:パラグラフ構成の短い物語文
・Step4:英検3級・準2級レベルの読解素材
・Step5:入試問題形式の長文読解
「難しい文章を頑張って読む」よりも、
「自分の読める範囲でどんどん読む」ことが読解力の土台になります。
2. 英文を“返り読み”しないための「スラッシュリーディング」
日本語と英語では語順がまったく違うため、
日本語に訳しながら読む癖(返り読み)がついている生徒が多いです。
返り読みは読みづらく、スピードも遅くなります。
この対策として、「スラッシュリーディング」という方法がおすすめです。
英文を意味のかたまり(チャンク)ごとにスラッシュで区切り、
それぞれの意味を“前から”理解していくのです。
例)
I / went to the park / with my sister / last Sunday.
これをいちいち「私は/先週の日曜に/妹と/公園に行きました」と日本語にしないで、
「I(私は)/went to the park(公園に行った)/with my sister(妹と一緒に)
last Sunday(先週の日曜に)」というように、前から前からイメージで読んでいく。
この方法に慣れると、読解スピードが大幅にアップしますし、
英語のまま理解する力が育ちます。
3. 音読とシャドーイングで「読む力」を「体に覚えさせる」
リーディング力は、読む「技術」だけでなく、英語の音やリズムへの慣れも必要です。
そこで有効なのが音読とシャドーイングです。
音読とは
声に出して英文を読むこと。
英語の語順や語感に慣れると同時に、発音・アクセントの練習にもなります。
シャドーイングとは
音声を聞きながら、少し遅れて真似して発音していくトレーニング。
リスニングとスピーキングの両方に効きますが、
実は「英文の語順のまま理解する」力にもつながるため、
リーディングにも効果があります。
特に教科書の音声CDやYouTubeのリスニング教材を使って、
毎日5〜10分でも続ければ、大きな成果が期待できます。
4. 読んだ英文を「内容で確認」する習慣
英文を読んだら「何となく分かった気がする」で終わるのではなく、
自分の言葉で要約したり、内容について考える習慣が重要です。
たとえば以下のような確認が効果的です。
・「この文章は誰が、何を、どうした話?」
・「この段落のポイントは何?」
・「この出来事の理由は?」
読んだ内容に対して質問を作って自分で答えてみる。
これができるようになると、
「表面的に読む」から「理解して読む」へのレベルアップが図れます。
読む練習も「筋トレ」と同じ。毎日の積み重ねがカギ
英語のリーディングは、単発で成果が出るものではありません。
毎日少しずつ積み重ねていく“筋トレ”のようなものです。
いきなり長い英文を読もうとせず、1日10分でもOKなので、
継続して取り組むことが成果を分けます。
・最初は短い英語の物語や教科書の会話文から
・英文の意味を理解しながら前から読む練習をする
・音読・シャドーイングで語順の感覚を体に覚えさせる
この3つを意識していくだけで、
「英語が読めるようになる」実感が少しずつ湧いてくるはずです。
ステップ4:使える英語を育てる「書く」トレーニング法 ~書けることで“わかる”が深まる~
「書く力」は軽視されがちです。
ですが実際には、「書ける=理解している」証拠。
自分の頭の中にある英語力を“アウトプット”することで、
定着度や応用力が飛躍的にアップします。
この章では、英語学習で「書く」力を伸ばすための具体的なステップと、
日常に取り入れやすい練習方法を解説します。
1. 英文を書くことで「文法」が本当の意味で身につく
単語を覚える、文法問題を解く
これらはインプット型の学習ですが、書くことはアウトプットの練習。
つまり、覚えた知識を「使う」ことで本当に理解できるようになります。
たとえば「三単現のs」や「be動詞と一般動詞の使い分け」といった文法は、
実際に英文を書いている時に「あれ?ここってsつけるんだっけ?」と立ち止まることで、
知識が定着していきます。
書く練習をしないと、いくらルールを頭で理解していても、
テストや実際の会話で使いこなすのは難しいのです。
2. 中学生におすすめの英作文トレーニング法
「英作文」と聞くと「難しそう」と身構えてしまう生徒も多いですが、
最初から難しいテーマに取り組む必要はありません。
まずは「1文から始める」「書き写すことから始める」ことがコツです。
【ステップ1】短文日記を書く(1日1文でもOK)
・例:I played soccer with my friends today.
・簡単な過去形を使って、自分の行動を1文にまとめてみる
・間違いを気にせず“書く習慣”をつけるのが目的
【ステップ2】日本語文を英語に訳す(和文英訳)
・例:「私は犬を2匹飼っています」→ I have two dogs.
・最初は教科書にある例文からスタート
・わからなければ辞書や先生に聞きながら「正しい言い方」を学ぶ
【ステップ3】自分の意見を書く(意見文・自由作文)
・例:「あなたの好きな食べ物とその理由」
・自分の気持ちを英語で表現する練習に最適
・接続詞(because, and, but)を覚えておくと便利
3. 書いた英語は必ず「見直し」「修正」するクセをつける
書いたら終わり、ではもったいない!
「見直す→間違いに気づく→直す」というプロセスこそが、英語力の底上げに直結します。
・三単現のsが抜けていないか?
・時制は合っているか?(現在 vs 過去)
・語順は正しいか?(主語+動詞の基本を守れているか)
書いたものを自分で音読すると、より違和感に気づきやすくなります。
また、可能であれば先生や保護者に添削してもらうのも非常に有効です。
4. 入試や検定にもつながる「書く力」
中学英語の学習では、英作文の力がそのまま高校入試や英検対策にもつながります。
たとえば神奈川県の高校入試では
「条件英作文(●●について、25語以上で書く)」が出題され、
英検3級以上でもライティング問題があります。
日頃から1文でも自分の言葉で英語を書く練習をしている生徒は、
こうした問題にも強く、得点差がつきやすくなります。
5. 英語が「話せる」ようになりたいなら、「書く」ことから始めよう
英語を話せるようになるには、いきなり口に出すよりも、
まずは「書いてから話す」ステップを踏むのが実は近道です。
理由は簡単で、「自分の英語の型」ができていない状態では、
話すこともできないからです。
・自分の名前や家族について英語で書けますか?
・自分の好きなものや将来の夢を1文で書けますか?
このようなことを“書けるようにする”練習を積み重ねれば、
話せる内容も自然と増えていきます。
書くことで「英語が自分のものになる」感覚を得る
英語を聞く・読むだけでは、「なんとなくわかる」で終わってしまいます。
書くことで初めて、頭の中の知識が整理され、「使える英語」へと変わっていきます。
・文法が苦手な人こそ「書く練習」を。
・単語を覚えるだけでなく「使ってみる」意識を。
・最初は短くてもいい。続けることで力になる。
書く英語が増えるたびに、「あ、こんな表現使えたんだ」と気づく瞬間が増えていきます。
これが英語学習の“楽しさ”の正体かもしれません。
ステップ5:自然と話せるようになる英語スピーキングの鍛え方 ~恥ずかしがらず口に出すことが第一歩~
中学生の多くが英語を「読む」「聞く」ことはできても、
「話す」ことに対しては苦手意識を持っています。
その主な理由は、「間違えるのが恥ずかしい」
「どうやって練習すればいいのかわからない」といったものです。
しかし、英語を話せるようになるには、まず“口を動かす”ことが必要です。
この節では、スピーキング力を自然に伸ばしていくための実践的なステップと、
自宅でもできるトレーニング法を紹介します。
1. 英語は「口に出してナンボ」:黙読より音読を優先しよう
スピーキング力をつけるうえでまず必要なのは、「口を動かす習慣」を持つことです。
特別な教材やネイティブとの会話がなくても、音読だけで大きな効果があります。
たとえば、教科書の本文を毎日1ページ声に出して読むだけでもOK。ポイントは次の通り
・できるだけハッキリ、ゆっくり読む
・感情をこめて読む(抑揚・イントネーションを意識)
・読めない単語は調べてから練習する
黙って読む(黙読)だけでは脳に入ってこない表現も、
音読することでリズムや言い回しが記憶に残りやすくなります。
2. シャドーイングで耳と口を同時に鍛える
スピーキングとリスニングを同時に鍛えたい場合は「シャドーイング」がおすすめです。
これは、英語の音声を聞きながら、少し遅れてマネして口に出す練習法です。
具体的なやり方
- 短い英文音声(10〜20秒)を用意(教科書の付属CDや無料アプリでも可)
- 音声を流しながら、聞こえた通りに後を追って話す
- 発音やイントネーションをそっくりマネするように意識
シャドーイングは最初難しく感じるかもしれませんが、3日もすれば慣れてきます。
耳が慣れてくると、自然と話すスピードも上がっていきます。
3. 英語で「独り言」を習慣にする
「英語を話す練習」として、実は最も手軽で効果的なのが“独り言”です。
たとえばこんなフレーズを日常生活に取り入れられます
・I’m so sleepy today.(今日はめっちゃ眠い…)
・I have to do my homework.(宿題やらなきゃ)
・I don’t like this weather.(この天気好きじゃないな)
誰にも聞かれないから恥ずかしくないし、自分のことを話す表現ばかりなので、
覚えた表現がすぐに使えるようになります。
しかも、自分の感情に直結した英語は記憶にも残りやすいのです。
4. オンライン英会話やAI会話アプリの活用もおすすめ
もし可能であれば、
オンライン英会話やAIを活用した英語学習アプリを使うのも効果的です。
最近では、
スマホ1つでネイティブ講師やAI相手に英会話の練習ができる時代になりました。
【中学生に人気のスピーキングツール例】
・スタディサプリENGLISH(リクルート)
・SpeakBuddy(AI英会話練習アプリ)
・Kimini英会話(学研)
・YouTube英会話チャンネル(シャドーイング用にも◎)
「毎日は無理」という場合でも、週1回だけでも定期的に英語を“話す場”を持つと、
アウトプット力が格段に向上します。
5. スピーキング力UPに必要なのは「完璧さより慣れ」
英語を話すとき、多くの生徒が
「文法が合ってるかな?」
「発音が正しいかな?」
と不安になって口が止まってしまいます。
しかし、最初から完璧な文法で話せる人などいません。
・間違ってもいい
・単語だけでもいい
・ジェスチャーを使ってもいい
大切なのは、「言いたいことを英語で表現しようとする姿勢」です。
その積み重ねが、結果として「使える英語」につながっていきます。
「話せる英語」は、毎日少しずつ育てるもの
英語のスピーキング力は、「一夜漬け」で手に入るものではありません。
ですが、毎日10分の音読や独り言、週1回のシャドーイングでも、
3ヶ月後には確実に変化が現れます。
・英語が口から自然と出てくる
・聞き取れるフレーズが増える
・英語で「考える」力がついてくる
こうした力は、テストの点数を超えて、将来の“武器”になるものです。
中学生が英語をスルスル身につけるための学習スケジュール設計法 ~ムリなく続く学びのリズムをつくる~
どれだけ良い勉強法を知っていても、それを「継続」できなければ意味がありません。
特に中学生は部活動や他教科の勉強もあるため、
英語学習を毎日続けるのが難しいと感じる人も多いでしょう。
この節では、英語をスルスルと身につけるために必要な、
現実的かつ効果的なスケジュールの立て方を紹介します。
ポイントは、「毎日の負担を最小限にしながら、最大の効果を引き出す」ことです。
1. 「時間」ではなく「内容ベース」で管理する
「1日30分やる」と時間だけで計画を立ててしまうと、
忙しい日はこなせず挫折しがちです。
そこでおすすめなのが、「タスクベース」でスケジュールを組む方法です。
たとえば
・月曜:英単語10個暗記+例文3つ音読
・火曜:教科書1ページを音読+文法ドリル5問
・水曜:リスニング(シャドーイング)5分+独り言練習
・木曜:長文読解1題+わからない単語をメモ
・金曜:今週の復習+ミニテスト
・土曜・日曜:好きなYouTube英語動画で聞き取りチャレンジ
こうすれば、「時間がない日でも1タスクだけはこなす」ことが可能になり、
習慣化のハードルが一気に下がります。
2. 週の中で強弱をつける「メリハリ型スケジュール」
すべての曜日に同じ分量を詰め込もうとすると、疲れやすく続きません。
大切なのは「バランス」です。
例
・月曜・金曜:軽めのタスク(音読や復習)
・火曜・水曜:中ボリューム(文法や単語練習)
・木曜:リスニング重視
・土日:英語で「楽しむ」日(ゲーム・動画・アプリ英会話)
“水曜日は部活がキツイから軽めにする”“土日は好きな英語コンテンツで遊ぶ”など、
自分の生活リズムに合わせて調整しましょう。
3. 朝・夜どちらがベスト?自分に合った「英語タイム」の見つけ方
どの時間帯に勉強するかも、習慣化には非常に重要です。
中学生の場合、以下のように分かれる傾向があります。
・朝型タイプ
学校に行く前に英単語や音読をするのが効果的。脳がスッキリしているので記憶に残りやすい。
・夜型タイプ
学校や部活後の方が集中できる場合は、夜にリスニングや読解がおすすめ。
ただし、寝る直前はNG。睡眠の質を落とす可能性があります。
大切なのは、「1日のどこかで確実に英語に触れる時間をつくる」ことです。
たとえ5分でもOK。
1日の終わりに「今日も英語できた」と実感できることが続けるコツです。
4. 学習スケジュールは「記録」することで定着する
勉強した内容や時間を記録することで、自分の努力を“見える化”できます。
これは学習モチベーションを保つうえで非常に大きな効果があります。
たとえば
・「英語学習チェックシート」を使う
・スマホのメモアプリや日記に記録する
・カレンダーに学習日を◯で記入する
毎日英語に触れた日が積み重なると、「続いている」という自信が生まれます。
この“見える努力”は、やる気の維持に直結します。
5. 挫折しないための「2日ルール」を取り入れる
学習を続けるためには、「完璧を目指しすぎない」ことも重要です。
どうしてもできない日があっても問題ありません。
おすすめは「2日ルール」です。
・1日サボってもOK
・でも2日連続でサボらない
このルールを決めておくと、多少のブレは許容しつつも習慣が崩れるのを防げます。
何より「続いている」実感が失われず、リズムが崩れません。
英語学習は“継続さえできれば、誰でも身につく”
英語の学習成果は、「一気にやった量」ではなく
「どれだけ長く、毎日続けられたか」で決まります。
・最初は1日5分からでもOK
・完璧を求めず「昨日の自分より少し進歩」がゴール
・小さな成功体験を毎日積み重ねること
これこそが、英語が“スルスル”と身についていく秘訣です。
まとめ:英語を得意科目にするために今日からできること
ここまで、英語がスルスルと身につくための考え方と具体的な勉強法、
5つのステップ、そして継続のためのスケジュール設計法を紹介してきました。
この最終節では、これまでの内容を総括しつつ、
中学生が「今日からすぐに始められること」を明確に整理していきます。
英語習得のカギは「やり方」ではなく「続け方」
最も大切なのは、「自分がやっていて面白い」「続けられる」と感じる方法を選び、
それを長期的に習慣化することです。
英語ができるようになる中学生の多くは、
必ずしも特別な才能があるわけではありません。
ただ、地道に毎日続ける力がある。それだけです。
「何か1つを毎日やる」
これが最強の英語勉強法とも言えるでしょう。
これまでの7つのステップを振り返ろう
ここで、英語習得の流れをもう一度整理してみましょう
- なぜ英語を学ぶのかを自分の中で明確にする(モチベーション)
- 英語に「毎日」触れる環境をつくる(インプットの習慣化)
- 英語を「声に出す」習慣を持つ(発音・音読・シャドーイング)
- 間違いを恐れず「使ってみる」機会を持つ(英作文・独り言・英会話)
- 英語に「楽しさ」を見出す(ゲーム・動画・SNS・アプリ)
- 自分に合った学習スケジュールを作り、継続する仕組みを整える
- 小さな成長を記録し、自分の頑張りを“見える化”する
このサイクルを一度作り上げてしまえば、英語は“特別な科目”ではなくなります。
やる気がなくても自然に手が伸びる。そんな状態を目指しましょう。
今日からできる英語勉強の3つの一歩
「ここまで読んでも、まだ何から始めていいかわからない…」という人は、
まずこの3つの行動から始めてみてください。
- 1日1単語を覚える(英単語帳でもアプリでもOK)
- 1日1文を音読する(教科書や好きな英語のフレーズでOK)
- 1日1つ、“英語で自分のことを言う”練習をする(例:「I like curry.」)
この3つを1週間続けるだけで、英語が「わかる感覚」が少しずつ芽生えてくるはずです。
英語は「未来の自分への贈り物」
英語を身につけることは、入試での点数アップだけではありません。
将来、海外旅行や留学、外国人の友達との会話、
英語で情報を集めて新しい世界を知る
英語を使って得られる経験は計り知れません。
中学生の今、毎日の5分が積み重なれば、
1年後には「英語が得意です」と胸を張って言える自分が待っています。
未来の自分に誇れる今日を、一緒に積み重ねていきましょう。
英語が苦手でも大丈夫。あなた専用の勉強法を一緒に作ります
ここまで読んでいただきありがとうございます。
英語の勉強には正解がありません。
どんなに効果的な方法でも、「自分に合っていなければ続かない」という現実があります。
だからこそ、ワイザーでは一人ひとりに合わせた
「勉強の設計図」を作ることを大切にしています。
私たち個別指導塾ワイザーは、
「学習習慣がない」
「何をどう勉強すればいいかわからない」
そんな中学生を専門にサポートする個別指導塾です。
特徴は以下の通りです
・勉強のやり方から徹底サポート
「英単語の覚え方」「音読の方法」など、基本から一緒に練習します。
・1人ひとりに合わせた学習計画を作成
学年・現在の学力・生活リズムに合わせて、毎日の学習タスクを個別設計。
・勉強を習慣化する“仕組み”を提供
LINEでの進捗管理、週1回の学習面談などで「やる気が続く」状態を支えます。
・授業だけで終わらない徹底サポート
「授業外」の時間にこそ差がつくので、365日サポート体制を整えています。
英語が苦手な子も、「塾に通っても成果が出なかった…」という子もご安心ください。
私たちの目標は、“英語が得意”になることではなく、「続けられる習慣」をつくること。
その結果として、英語も含めた全教科で成績が安定していく
それが、ワイザーの目指す学び方です。
【今なら無料で個別相談受付中です】
「うちの子、どこから始めればいいかわからない」
「そもそも勉強習慣がなくて…」
そんな保護者の方からのお問い合わせも多くいただいています。
ワイザーでは、入塾前の無料相談を随時受付中です。
・英語学習の進め方に悩んでいる
・成績を上げたいけど何をしたらいいかわからない
・習慣化を一緒に考えてほしい
といったお悩みがある方は、ぜひお気軽にご相談ください。
あなたのお子さま専用の学習ステップを一緒に考えましょう。
▼無料相談はこちらをクリック▼



