
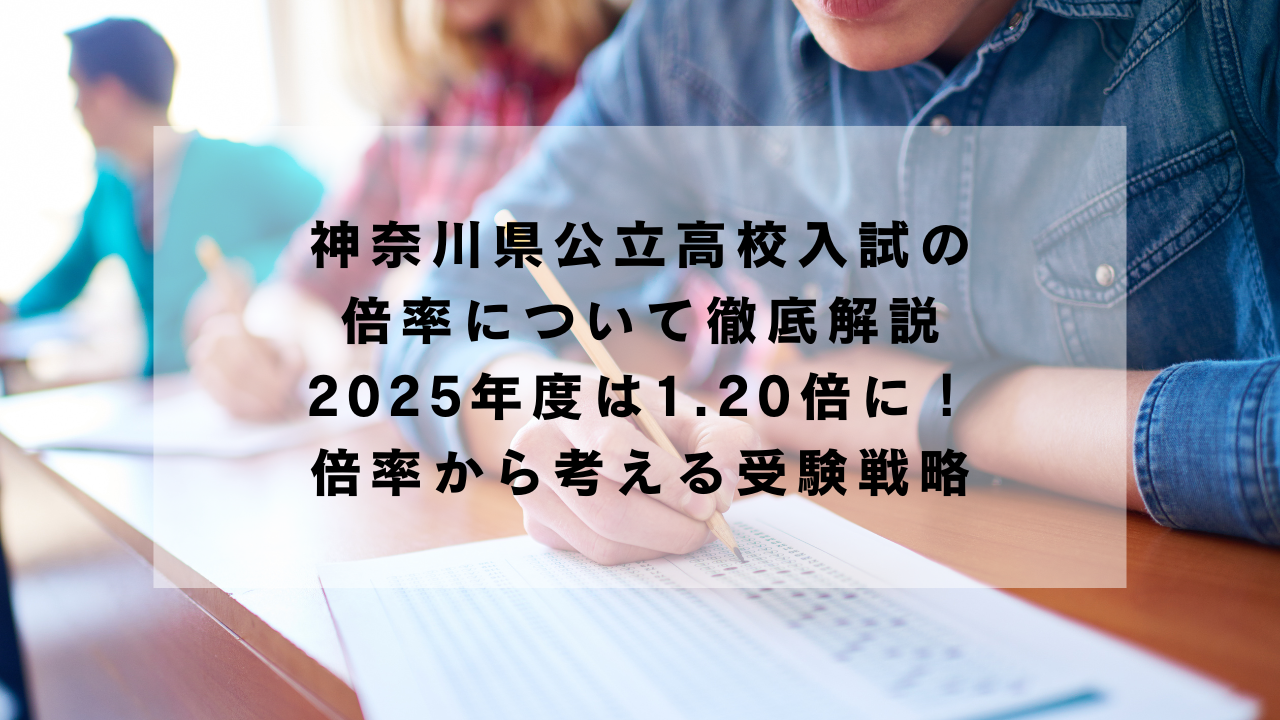
倍率から見る2026年度受験戦略の重要性
「志望校の倍率って、結局どれくらい気にしたらいいの?」
「うちの子の志望校、倍率が高いみたいで不安…」
そんな声を保護者や受験生から多く耳にします。
特に、神奈川県の公立高校入試は毎年細かな倍率変動があり、
2025年度も例外ではありませんでした。
2025年度の入試では、全日制の平均倍率が1.20倍と前年とほぼ同水準で推移しましたが、
一部の進学重点校では競争が激化。
一方で定員割れを起こす学校も存在し、
「どこを受けるか」だけでなく「どのように受けるか」の戦略がますます重要になっています。
この記事では、
神奈川県教育委員会の公式データをもとに2025年度の倍率動向を振り返りつつ、
2026年度入試に向けてどのような受験準備・志望校選びが求められるのかを解説していきます。
特に次のような方におすすめです
・第一志望校に合格したい中学生とその保護者
・倍率を正しく理解し、戦略的に志望校を決めたい方
・模試や偏差値だけでなく、実際の志願動向を知っておきたい方
「倍率が高いから諦める」ではなく、
「どう準備すれば勝てるか」を一緒に考えていきましょう。
神奈川県立高校入試における倍率変動の傾向と注目校の動向(2025年度の振り返りと2026年度への戦略)
高校入試において「倍率」は毎年微妙に変動します。
特に神奈川県のように、受験者数や募集定員の動きが激しい地域では、
ちょっとした要因で志願者が大きく増減することもあります。
この節では、2025年度の志願状況や倍率の変動傾向をもとに、
2026年度に向けて注意すべきポイントを詳しく解説します。
2025年度の神奈川県立高校の平均競争率(受験倍率)は1.20倍で、前年の1.18倍よりやや増加しました。
全体として大きな変動はなかったものの、個別の高校を見れば明暗がはっきりと分かれています。
たとえば、横浜翠嵐高校(普通科)は2025年度も依然として高い人気を誇り、
受験倍率は2.11倍。横浜サイエンスフロンティア高校(理数科)も1.65倍と高水準です。
いずれも難関大学への進学実績や先進的な教育カリキュラムが評価され、
受験生の関心を集めています。
一方で、定員割れや低倍率の高校も存在感を増しています。
2025年度は募集人数を満たさなかった県立高校が30校、市立高校が2校、
合計で欠員は1,400人超。
人口減少や受験生の分散化、
さらには私立高校との併願志向の高まりが背景にあると見られます。
こうした倍率の変化には、さまざまな要因が影響しています。
まず、進学重点校やエントリー校への人気集中が挙げられます。
たとえば厚木高校は、東京大学や東工大への現役合格実績が伸びたことで、
志願者数が前年比で10%以上増加しました。
また、前年の倍率の高さを敬遠し、別の高校を選ぶ「反動」も頻繁に起こります。
川和高校はその一例で、2024年度の高倍率を受けて2025年度は志願者がやや減少し、
倍率も落ち着きました。
さらに、各校の定員調整も倍率に影響します。
横浜市内の一部普通科高校では10〜20名規模の定員削減があり、
それにより一時的に倍率が上昇しました。
逆に定員を維持した学校では志願者が流れ込まず、結果的に倍率が低下する傾向が見られました。
また、新校舎や施設の整備も人気に直結しています。
2025年度は数校で新校舎の完成やICT環境の拡充が話題になり、
これが志願者数の増加に結びついています。
高校選びにおいて、学力や進路だけでなく、
環境面の充実度も無視できない要素となりつつあります。
受験傾向の変化には、私立高校との併願率の増加も影響しています。
2025年度は私立併願率が前年比で5%以上増加しており、
公立高校一本で勝負する受験生が減少。
これにより、特定の公立高校に志願者が集中しにくくなり、倍率が分散する結果となっています。
これらの傾向を踏まえると、2026年度入試に向けては、
前年の倍率情報だけに頼るのではなく、自分の学力、志望動向、定員の変化、
学校の最新情報などを総合的に分析することが不可欠です。
倍率が低くても安心はできませんし、
高くても自分の得意教科や出題傾向が合っていれば十分に勝算があります。
志望校を決める際には、単なる数字としての倍率にとらわれず、
自分にとって最も可能性を広げられる選択が何かを見極める姿勢が求められます。
倍率だけでは測れない!模試結果の活用と2026年の受験戦略の立て方
倍率という数字は確かに志望校選びにおいて重要な参考指標のひとつですが、
倍率だけを頼りに合否を判断するのは極めて危険です。
特に2025年度のように、神奈川県全体の平均受験倍率が1.16倍と比較的緩やかだった場合、
数字上では「行けそう」と感じてしまいがちです。
しかし、実際の入試では合格ラインが学校によって大きく異なるため、
数字の裏側にある実情を正しく読み取る力が求められます。
ここで役立つのが模試の結果です。
模試は単なる“合格可能性”という数字を示すだけではなく、自分自身の学力の伸びや偏り、
そして苦手分野の炙り出しに非常に役立ちます。
特に神奈川県公立高校入試では、5教科均等型の評価が基本となるため、
苦手教科が1つでもあるとそれだけで全体の評価を大きく下げてしまうリスクがあります。
模試を活用するにあたっては、「何点だったか」ではなく、
「なぜ取れなかったのか」「どの問題で落としたのか」を明確に分析することが重要です。
例えば、英語のリスニングパートで毎回失点している場合は、ただ“英語を頑張る”ではなく、
“音声に特化したトレーニングを導入する”という具体的な対策が必要です。
また、数学の空間図形が得意で高得点を取れているのであれば、
その得意分野を活かせる出題傾向を持つ高校を選ぶという戦略も可能になります。
2026年度に向けて、模試を活かした受験戦略を立てるためには、
以下の3つの柱を意識しましょう。
① 模試の結果を「記録」として蓄積する
模試の帳票や結果用紙をすぐに捨ててしまっていませんか?
これらのデータには、学習の優先順位を決めるための重要なヒントが詰まっています。
模試を受けるたびに、
・5教科の得点
・各教科の正答率と失点パターン
・合格判定(A〜E)
などをノートやExcelなどで記録し、前回との変化をチェックする習慣をつけましょう。
これにより、自分の「勉強の方向性が合っているか」「次に改善すべき箇所はどこか」が
一目でわかるようになります。
② 弱点科目を“点が取れる”レベルに引き上げる
B判定・C判定の受験生に多いのが「苦手科目で大きく失点している」パターンです。
たとえば理科で20点以上、社会で10点以上差がついている場合、
得意科目を伸ばすよりも苦手を平均点まで引き上げたほうが合格可能性は大きく上がります。
具体的には、
・理科:分野ごとに出題傾向が異なるため、天体や電流など「捨て分野」をなくす
・社会:語句暗記に偏らず、資料の読み取り・記述対策にも時間を割く
・英語:長文読解よりも文法や語彙を優先し、安定的に得点を稼ぐ
といった教科別の戦略が有効です。
③ 志望校ごとの出題傾向・内申基準・変更情報を常に確認する
神奈川県の公立高校入試では、
特色検査の有無や選考比率(学力重視型・内申重視型など)によっても
合格のしやすさは変わります。
模試の偏差値が高くても、内申点が足りていなければ合格は厳しくなるケースもあります。
逆に、内申点で優位に立てる受験生は、
当日の得点に多少ブレがあっても合格できる可能性があります。
したがって、必ず
・各校の選抜比率(内申:学力:面接の配点比)
・特色検査の内容と過去の出題例
・近年の合格者平均点と倍率推移
を確認し、模試の結果と照らし合わせながら戦略を立てましょう。
必要であれば、志望校を再検討する柔軟さも重要です。
このように、倍率や噂に流されず「模試×分析×戦略」で2026年度入試に挑むことが、
合格への最短ルートになります。
「定員割れ」でも油断は禁物!志望校を見直すタイミングと注意点
受験生や保護者にとって、「定員割れ」という言葉には安心感があるかもしれません。
実際に、神奈川県教育委員会は
「定員内不合格や募集枠を残したままの選抜を実施しない」
と明言しており、基本的に定員割れした高校は全員合格できる可能性が高いとされています。
しかし、定員割れ=合格確実と短絡的に判断してしまうことには、多くの落とし穴があります。
2025年度の入試では、県立高校30校、市立高校2校の合計32校が定員割れとなり、
欠員数は1,400人超という状況でした。
こうした学校に出願する受験生の中には、
「これなら安心」と思って勉強の手を緩めてしまうケースも見受けられます。
ですが、これは非常にリスクの高い判断です。
なぜ「定員割れ」でも気を抜いてはいけないのか?
1. 志願変更期間に受験者が流入する可能性がある
倍率発表後には志願変更期間が設けられており、他校を受験予定だった生徒が、
「倍率が低そうだから」と変更してくることがあります。
そのため、当初定員割れだった高校も、
最終的にはしっかり競争が発生する可能性があるのです。
特に、近隣に人気校がある場合は、
その人気校の倍率を見て受験生が“回避策”として流れてくることが多く、状況は一変します。
2. 勉強を止めると学習習慣が崩れる
定員割れを理由に勉強をやめてしまうと、
受験本番前の最も伸びるタイミングを無駄にしてしまいます。
高校に入学した途端、授業スピードが上がり、
基礎が抜けた状態ではついていけないケースも多いのです。
特に数学や英語は“積み上げ型”の科目であり、
中学内容が抜けていると高校内容の理解に大きな支障が出ます。
3. モチベーションの低下と自己管理能力の損失
「どうせ受かるから」と目標が曖昧になると、学習計画や時間管理が乱れがちになります。
これは高校生活全体に悪影響を与え、学習への意欲も下がり、成績低下の原因となることがあります。
一度落ちたモチベーションは、取り戻すのにかなりの労力が必要です。
受験を「自己管理を磨く場」と捉え、気を抜かずに学び続けることが大切です。
定員割れ校を受ける場合に意識しておきたい3つのポイント
1.「想定外」の志願変更を常に想定しておく
倍率は変動するものという前提で、
最後まで学力を維持・強化しておくことが不可欠です。
志願変更後の倍率を見てから学習再開、では遅い可能性があります。
2.高校入学後のスタートダッシュを意識する
高校1年の1学期は成績が大きく分かれる時期です。
この時期に躓くと、大学受験にも影響を及ぼす可能性があります。
合格が見えていても、「高校入学後の勉強の準備」として学習を継続する姿勢が必要です。
3.「自分の成長」を受験の目的にする
受験勉強は単なる合否のための作業ではなく、
問題解決能力・継続力・自己管理力といった将来にも直結するスキルを育む場です。
入試直前まで粘り強く努力できた経験は、自信にも繋がります。
倍率に左右されない志望校選びのコツと2026年度に向けた実践的アドバイス
受験生や保護者が志望校を決めるうえで、倍率は非常にわかりやすい指標です。
しかし、「倍率が高い=避ける」「倍率が低い=安全」といった短絡的な判断は、
必ずしもベストな進路選択にはつながりません。
2026年度の入試を控える今こそ、志望校選びの軸を見直し、
自分に合った高校を選ぶための視点を持つことが大切です。
倍率はあくまで「一時的な数値」にすぎない
神奈川県公立高校入試では、毎年志願変更の動きがあり、倍率は最終的に変動します。
2025年度も、最初は低倍率だった高校に志願者が流れ込む「逆転現象」が
複数の学校で確認されました。
逆に、前年高倍率だった学校が敬遠され、今年は落ち着くというケースもあります。
つまり倍率は「その年の人気動向」によって変わるものであり、
翌年に同じ傾向が続く保証はありません。
「倍率が高いからやめておこう」と考えても、翌年また倍率が下がる可能性があるため、
倍率だけで志望校を選ぶことは極めて不安定なのです。
自分に合った高校を選ぶための3つの軸
1. 学力と出題傾向のマッチング
志望校の入試問題が自分の得意分野と一致しているかは、
合格可能性を左右する大きな要素です。
たとえば、記述問題が多い学校を志望するなら、日頃から記述力を鍛えているか。
図形問題や応用問題に強みがあるなら、それが評価されやすい学校か。
このように“問題の相性”に注目しましょう。
2. 高校の教育方針・進路実績
どんな進路を目指しているかによって、選ぶべき高校は変わります。
難関大学進学を希望するなら、
進学指導に力を入れている高校や指定校推薦の枠が豊富な高校が選択肢になります。
一方で、自分の興味のある分野(理系・文系・国際系・芸術系など)に強い学校を選ぶことで、
モチベーションを維持しやすくなるというメリットもあります。
3. 通学距離と学校生活のイメージ
意外と見落とされがちなのが「通学時間」と「学校生活の雰囲気」です。
片道90分以上かかる学校に通うことが本当に現実的かどうか、
高校生活が想像できるかどうかは、3年間の学びに直結します。
文化祭、部活動、行事なども含めて、
自分が「ここで学びたい」と思えるかどうかを重視しましょう。
2026年度受験生が今からできる実践アクション
学校説明会・見学に参加する
実際に足を運ぶことで、
ホームページではわからない学校の空気や生徒の雰囲気がつかめます。
特に「通いたいと思えるか」「自分に合うか」を見極めるために、積極的に参加しましょう。
複数年分の過去問を分析する
過去問は1年分だけでなく、3年分ほど解いて傾向を確認することで、
出題形式に慣れ、必要な対策が明確になります。
模試や実力テストを志望校選びの参考にする
模試の判定だけでなく、どの科目に強みがあるか、苦手がどこかを把握し、
「この高校なら自分の力が生かせる」と感じられる学校を選ぶことがポイントです。
倍率は「最後に見るべき情報」だと心得る
志望校選びの初期段階で倍率を気にしすぎるのではなく、
自分の意思と目標に基づいた選択を優先し、
最後に倍率も含めて再検討するという流れが望ましいです。
まとめ|数字に惑わされず、自分に合った高校選びを
本記事では、神奈川県公立高校入試における倍率の意味とその変動、
そして模試結果や個々の戦略に基づく受験準備について詳しく解説してきました。
特に2025年度の振り返りをもとに、
2026年度に向けた実践的なアプローチを重視してまとめてきましたが、
最後に改めて強調したいのは、「数字に振り回されない選択の大切さ」です。
倍率は、あくまで“参考値”に過ぎません。
もちろん、倍率が高ければ競争は激しくなりますし、
定員割れしていれば合格の可能性が上がるかもしれません。
しかし、倍率がすべてではありません。
出題傾向や自分の得意・不得意、受験当日のコンディション、
試験問題との相性など、合否を分ける要因は多岐にわたります。
また、「倍率が低いから安心していい」「倍率が高いから諦めよう」といった考えは、
受験生としての判断力を鈍らせます。
逆に、倍率に関係なく「自分はこの高校に通いたい」
「この学校で3年間を過ごしたい」という意志をもって学習を続けている受験生は、
本番での集中力や覚悟が違います。
これからの時期、模試や学校説明会、三者面談、出願校決定といったイベントが続きますが、
最終的に受験を乗り越えるのは「数字」ではなく「人」です。数字を見る目を養いつつ、
それに振り回されず、自分自身の意志と努力に基づいて志望校を選んでください。
そして、努力して手に入れた合格は、数字以上の価値があります。
志望校選びや勉強法に悩んでいる方へ|無料相談実施中
個別指導塾ワイザーでは、
学習習慣がない中学生や高校生に特化したサポートを行っています。
進路に不安がある方、倍率や志望校選びで迷っている方は、ぜひ無料相談をご利用ください。
講師が一方的に話すのではなく、お子様の学習状況や生活習慣を丁寧にヒアリングし、
現状に合ったアドバイスをお届けします。
さらに、最新の受験情報を踏まえた学校選びのコツや、やる気の引き出し方など、
保護者の方の疑問にも寄り添います。
▼無料相談はこちらをクリック▼



