
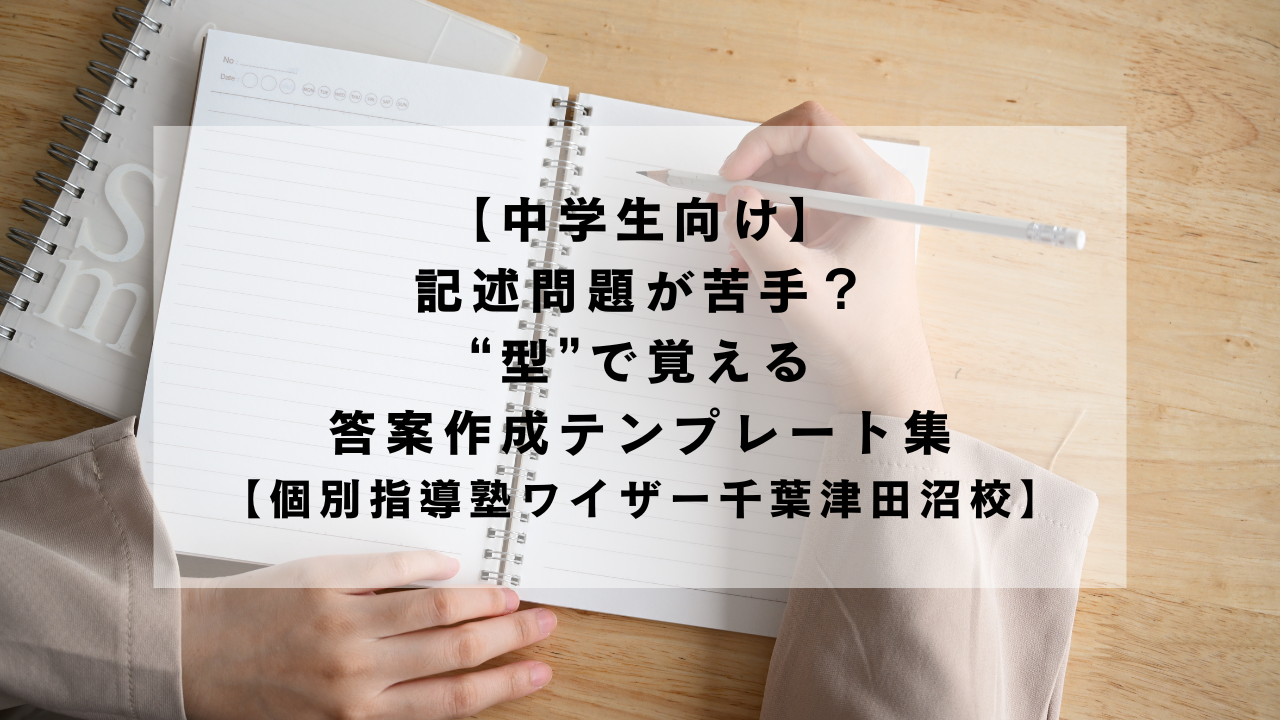
「わかる」と「書ける」のあいだ――記述問題が苦手になる三つの落とし穴
定期テストや模試で記述欄だけ白紙になりがち。
そんな経験をした中学生は少なくありません。
選択問題なら選んでマークするだけで済むのに、理由や過程を文章化せよと言われると急にペンが止まる。
この“急ブレーキ現象”には三つの落とし穴が潜んでいます。
第一の落とし穴は**「論理の可視化不足」。
日々の授業では板書を写し、ワークを解き、正誤を確認する流れが中心です。
しかし、答えに至る思考プロセスを言語化する機会は圧倒的に足りません。
結果として、頭の中では理解しているのに、紙面へ筋道立てて落とし込む訓練が不足します。
そのギャップが「わかるのに書けない」という感覚を生み出します。
第二の落とし穴は「採点基準のブラックボックス化」。
選択式は正解が明確ですが、記述式は部分点の基準が見えづらい。
「どこまで書けば満点なのか」「キーワードは何語入れれば十分なのか」という不安が常につきまといます。
その曖昧さが心理的ハードルを上げ、書き始める前に手が止まる原因となります。
第三の落とし穴は「時間配分の錯覚」です。
記述は読み取り、要点抽出、構成、清書の四工程を要します。
選択肢を塗るだけの問題と同じペースで進めると、ラスト五分で半分以上空欄が残る。
この失敗体験が積み重なり、本番になるほど「どうせ終わらない」という諦めを招きがちです。
三つの落とし穴に共通するキーワードは「型」。
思考を文章へ変換する雛形があれば、採点基準の不透明さも時間配分の不安も大幅に減ります。
たとえば【問いの種類別テンプレート】を身に付ければ、読む→抜く→並べる→まとめるの手順が自動化されます。
すると脳のリソースを内容深化に集中でき、答案の質とスピードが同時に向上します。
このブログでは、次節から国語・社会・理科・数学・英語の主要五科目を対象に、
中学生でも今日から使える答案作成テンプレートを具体例付きで紹介します。
テンプレートの使い方だけでなく、家庭学習と学校ワークにどう組み込むかまで徹底解説。
読み終えた頃には、記述問題が「苦手科目」ではなく「得点源」へと変わる準備が整うでしょう。
科目別テンプレート①【国語】「要約」「理由説明」「心情説明」を“型”で自動化する
国語の記述問題は問いのタイプが多岐にわたります。
しかし実際のテストで頻出なのは、➀本文要約型、➁理由説明型、➂心情説明型の三つに大別できます。
ここではそれぞれに共通する骨格をテンプレート化し、定着までの練習法を示します。
テンプレートは 〈設問のキーワード→本文根拠→つなぎ語→まとめ〉 という四段構成で覚えると汎用性が高まります。
1. 本文要約型――〈柱を二本+要点圧縮〉
設問例:「段落3の内容を二十〜三十字でまとめよ」
テンプレート
- 段落を読んで「主張」と「補足」の二本柱に分解する。
- それぞれを十〜十五字のキーフレーズに圧縮。
- 「〜により、〜だ」と順接で接続し一文に統合。
具体例
本文:「近年、SNSの普及で文章を書く機会が増えた。
一方、短い文ばかり書くため論理展開が弱くなる懸念もある。」
→「SNS普及で文章機会増加」+「短文慣れで論理低下」
→「SNS普及で文章機会増加する一方、短文慣れで論理低下」 (28字)
練習法
教科書の段落ごとに①主張②補足を付箋に書き出し、最後に一文要約をノートに転記する習慣を一週間続ける。
これを繰り返すと「二本柱抽出→接続→字数調整」が自動化され、模試でも即時に応用できます。
2. 理由説明型――〈因→果→一般化〉
設問例:「筆者がA案を支持した理由を四十字以内で説明せよ」
テンプレート
- 「なぜ〜か」と問われている語をまず主語として書き出す。
- 本文中の因果接続語(だから、そこで、ゆえに)を目印に原因を抜き取る。
- 「そこで」「ゆえに」を挿入して因→果を接続。
- 末尾に「ため」とまとめて四十字以内に収める。
具体例
本文:A案は初期費用が高いが保守コストが低い。
長期的に費用対効果が高いため採算が取りやすい。
→「A案は保守費が低く長期費用対効果が高い」+「採算性が高まる」
→「A案は保守費が低く長期費用対効果が高いため採算性が高まる」 (37字)
練習法
新聞記事の社説を使い、「主張文」を赤線、「理由」を青線で色分けし一文要約する。
五本こなすごとに時間を計測し、四十秒以内で書けるかを目標にする。
スピードと精度の両立が図れ、試験本番の時間配分が安定します。
3. 心情説明型――〈出来事→心情語→理由〉
設問例:「主人公が『胸が熱くなった』のはなぜか。三十五字以内で答えよ」
テンプレート
- 対象となる描写を探し「出来事」を抜く。
- その直前後にある感情表現を「心情語」として拾う。
- 出来事と心情を「ので」「ため」で因果接続。
- 字数オーバーなら副詞や重複語を削り調整。
具体例
本文:主人公は友人が諦めかけていた目標に再挑戦した姿を見た。
心底うれしくなり、胸が熱くなった。
→「友人が目標再挑戦した姿に感動し胸が熱くなった」 (30字)
練習法
小説教材のクライマックス場面を選び、「出来事」と「心情語」をセットで抜き書きし一文に再構成する練習を行う。
最初は本文をコピーして線を引くだけでも構いません。
慣れてきたら本文を隠し、要素だけで三十五字以内の文を構築するタイムアタックに挑戦すると定着が早まります。
テンプレート運用のポイント
・色分け→音読→書き写しの三段階を一セットにする。
視覚・聴覚・運動の複数チャネルを使うため記憶に残りやすい。
・最初は制限字数+10%で練習し、慣れたら本番字数へ絞ると挫折しにくい。
・語尾バリエーションを意識すると採点者に読みやすい文章になる。
「〜である」「〜からだ」「〜ためだ」を交互に使うなどの工夫で単調さを防げます。
・家庭学習に組み込む時間は一日15分で十分。
短いサイクルを回すほうが習慣化しやすく、他教科の勉強時間を圧迫しない。
国語の記述問題は感覚ではなく「抽出」「接続」「圧縮」という機械的手順で組み立てられます。
三種類のテンプレートを使い分けるだけで、答案構成に費やす時間が大幅に短縮されるでしょう。
科目別テンプレート②【社会】「キーワード三点法」と「因果マトリクス法」で歴史・地理・公民を一気に得点源へ
社会の記述問題は「用語暗記が得意なのに説明が書けない」というジレンマが典型的です。
単語帳で覚えた年号や地名が脳内に散らばっていても、答案では筋道の通った文章として提示しなければ点数になりません。
そこで活躍するのが キーワード三点法 と 因果マトリクス法 の二大テンプレートです。
どちらも「何を書くか」を自動で決め、「どう並べるか」を定型化する仕組みなので、用語と用語を線で結ぶだけの思考に変換できます。
1. キーワード三点法――〈出来事→背景→結果〉をセットで書く
適用場面
・歴史の出来事を説明する問題
・公民で政策や制度の導入理由を問う問題
テンプレート構造
- 出来事(いつ・どこで何が起きたか)
- 背景(起きる前の社会状況や課題)
- 結果(起きた後の変化や影響)
設問例
「江戸幕府が鎖国政策を取った理由とその影響を三十五字以内で説明せよ」
実装手順
・教科書欄外や資料集のキャプションから、出来事を象徴する単語を一語で抜き取る。
・背景は「対外情勢」「国内体制」「経済状況」などカテゴリーの中から最も関連深い要因を一語に圧縮。
・結果は「統制強化」「文化交流停滞」「経済自立」など、効果を示す語を一語で把握。
・三語を「〜ため」「その結果」で接続し一文化する。
作成例
「幕府はキリスト教拡大を防ぎ国内統制を維持するため鎖国を実施し、対外貿易が長崎に限定された」(34字)
練習法
1日1出来事を選び、三語をカードに書き、シャッフルしても正しい順序で並べ直せるかタイムアタック。
視覚化+身体動作を組み合わせることで記憶に定着しやすくなります。
2. 因果マトリクス法――〈原因群×影響群〉を表に落とし込む
適用場面
・地理で地域特有の産業が発展した理由を書く問題
・公民で政策がもたらす多面的影響を説明する問題
テンプレート構造
| 自然要因 | 人的要因 | 政策要因 | |
| 影響A | … | … | … |
| 影響B | … | … | … |
縦軸に「影響」、横軸に「原因カテゴリー」を配置し、交差点に該当キーワードを埋める方式です。
答案ではマトリクスをそのまま書くのではなく、縦横二方向の関連を文章化してまとめます。
設問例
「北陸地方で合板産業が発達した原因を四十字以内で説明せよ」
実装手順
・原因カテゴリーを「自然」「人的」「政策」に固定して下線を引く。
・自然要因:豊富な森林資源
・人的要因:雪国の冬季手仕事需要
・政策要因:政府の林業振興策
・影響は「合板産業発達」を軸に据え、三要因をつなぐ。
・「〜が」「〜により」「〜と相まって」など接続語を置いて流れを作る。
作成例
「豊富な森林資源と冬季の労働力確保に加え政府の林業振興策が重なり北陸で合板産業が発達した」(38字)
練習法
ノートの左ページにマトリクスを描き、右ページに文章化した答案を書き写す。
翌日、右ページのみで全文を再現できるかチェック。
これを三地域×一週間実行すれば「マトリクス→文章」変換が自動化されます。
テンプレート共通活用ポイント
・キーワードの一語化を徹底する。
原因説明で「国際情勢が不安定だったため」と書くより、「オランダとスペインの対立激化」と具体化したほうが加点率が高まる。
・字数圧縮は“削る”より“置き換える”。
「〜することによって」を「〜で」に置換するなど、冗長表現を一語に縮める習慣をつける。
・答案の語尾を「ため」「から」「である」にローテーションし、二連続で同語尾にならないよう意識すると読みやすさも向上。
・週末リフレクションとして、練習した答案の「背景・原因・結果」を色分けし、抜け漏れを自己採点。
自己修正サイクルを回すことで点数に直結する改善が可能。
社会は暗記科目だと思われがちですが、実際の記述配点は「つなぐ力」に置かれています。
キーワード三点法と因果マトリクス法を武器にすれば、単語を“並べる”だけで論理的な答案へ昇華できます。
科目別テンプレート③【理科・数学】「因果チェーン法」と「計算プロセスタグ法」で“説明不足”と“途中式迷子”を同時解消する
理科と数学は一見まったく異なる教科ですが、答案で失点する原因は「プロセスを言語化できない」の一点に集約されます。
理科では現象のメカニズムを段階的に説明できず減点。
数学では途中式の省略や順序の飛躍で部分点を逃す。
この二つの課題を解決するために用意したのが 因果チェーン法(理科)と 計算プロセスタグ法(数学)です。
どちらも「ステップを札で管理する」発想に基づき、思考の抜けを防ぎます。
1. 因果チェーン法――〈原因→媒介→結果〉を矢印でつなげる
適用場面
・物理で力と運動の関係を説明する問題
・化学で反応の仕組みを書く問題
・生物で環境と生態系の変化を記述する問題
テンプレート構造
- 原因(入力:力・温度・濃度など)
- 媒介(変化の途中段階:圧力上昇、電位差発生など)
- 結果(出力:運動、発熱、生成物など)
設問例
「気体を加熱すると体積が増える理由を説明せよ」
実装手順
・原因:「加熱で分子運動が活発化」
・媒介:「分子が容器壁を押す回数と強さが増加し圧力上昇」
・結果:「外部圧一定なら体積が増大」
・三要素を「→」で結び、文中では「ため」「結果」と接続して一文または二文に整理する。
作成例
「加熱で分子運動が活発になり壁を押す回数と強さが増えるため内部圧力が上昇し外部圧一定下で体積が増大する。」
練習法
教科書の章末問題を一題選び、原因・媒介・結果を付箋に書く。
机上で左→中→右に並べ替えてからノートへ清書。
五セットこなした後、原因と結果だけを渡されても媒介を補完できるかタイムトライアルを行う。
“途中段階の可視化”が習慣化され、論述の密度が安定します。
2. 計算プロセスタグ法――〈定義タグ→操作タグ→結論タグ〉で途中式を一本の線にする
適用場面
・一次方程式から二次方程式までの解法説明
・図形証明で計算値を導く流れを書く問題
・関数の値域や最大最小を文字式で示す問題
テンプレート構造
| タグ | 内容例 | 書き方例 |
| D(定義) | 式の整理、変数宣言 | 「x=速度、y=時間」 |
| O(操作) | 加減乗除、置換、因数分解 | 「両辺を2で割る」 |
| C(結論) | 求める値、証明終了 | 「ゆえにx=5」 |
設問例
「2x+3=11 を解き、解の導出過程を説明せよ」
実装手順
- Dタグ:「2x+3=11」
- Oタグ:「両辺から3を引く→2x=8」「両辺を2で割る→x=4」
- Cタグ:「したがってx=4」
- タグ名は答案には書かず、頭の中または余白にメモして順序を固定。
- 答案ではタグ間を「まず」「次に」「したがって」で接続し、途中式を漏らさず列挙。
作成例
「まず2x+3=11から両辺から3を引き2x=8。
次に両辺を2で割りx=4となる。
したがって解は4。」
練習法
・タグ色分けノートを作成し、Dを青、Oを緑、Cを赤で書く。
一目で操作の連鎖が視覚化され、抜け落ちた工程に気付きやすい。
・口頭リプレイ。
答案を書き終えたらノートを閉じ、タグ順に手順を暗唱。
30秒以内に再現できれば定着合格ラインとする。
・タグ減らしゲーム。
慣れた問題はOタグを一段階統合し、式変形を二手で完結させる短縮練習を行うと処理速度が向上。
テンプレート共通活用ポイント
・理科も数学も“見えないプロセスを見える形で管理”することが最大の目的。
いったん札やタグで分解し、文章や式に再構築するとミスが激減します。
・時間制限付きルーチンを入れるとテスト本番の焦りに強くなる。
例:因果チェーンは1分、計算プロセスタグは2分以内でメモ完了。
・誤答ノートを作り、原因・媒介・結果またはD・O・Cのどこが欠落したかを分類。
自己分析することで次回以降の復習がピンポイント化します。
・語尾の単調回避。
理科では「増大する」「生成される」「働く」など動詞を回転。
数学では「求められる」「示される」「得られる」を交互に使い、読み手のストレスを軽減。
因果チェーン法と計算プロセスタグ法が定着すれば、「理科は暗記」「数学は計算」という思い込みは崩れます。
どちらもプロセスを可視化して初めて“説明できる理解”へ進化する教科です。
目別テンプレート④【英語】「三段落クイックライティング」と「翻訳リバース法」で“書けない”を“瞬時に書ける”へ
英語の記述問題は、和文英訳と自由英作文に大別されます。
どちらも「内容は思い浮かぶのに英文が組み上がらない」という壁が立ちはだかります。
この壁を乗り越える鍵は 構成の固定化 と 語句の再利用 です。
本節では、最短で形を作れる 三段落クイックライティング と、日本語→英語→日本語で誤差を減らす 翻訳リバース法 の二本立てで解説します。
1. 三段落クイックライティング――〈導入→理由→結論〉で60語を高速生成
適用場面
・「賛成か反対か」「好きな行事を紹介せよ」といった自由英作文
・スピーチ原稿要約やメール返信で指定語数がある設問
テンプレート構造
- 導入(7〜10語)
- “I think that….” や “In my opinion、….” で主張を明示
- 同じ主語・動詞型を使い続けると語数管理が容易
- “I think that….” や “In my opinion、….” で主張を明示
- 理由(40語前後)
- “First、….” “Second, ….” と列挙
- 各理由パートを “because / so / which” で一文複合にし,語数を一気に稼ぐ
- “First、….” “Second, ….” と列挙
- 結論(7〜10語)
- “Therefore、….” “For these reasons、….” でまとめ
- 最後は主張をパラフレーズし,文末を変化させて単調回避
- “Therefore、….” “For these reasons、….” でまとめ
実装例(60語)
導入:I think that students should have club activities after school.
理由:First, they can make new friends easily because they share the same interests, which helps them enjoy school more. Second, they learn cooperation and leadership, so these skills will be useful when they work in society.
結論:For these reasons, club activities are very important for students.
練習法
・10-10-10ドリル:10分でテーマ選定、10分で日本語メモ、10分で英文化。
・語数マーカー:各段落末に語数を書き込み、導入+結論で約20語に固定すると配点ミスを防げます。
・ペアチェック:友人と交換採点し、導入・理由・結論が欠けていないか赤シールでマーキング。繰り返すうちに段落骨格を自動生成できます。
2. 翻訳リバース法――〈和訳→英訳→再和訳〉で誤訳ポイントを瞬時に発見
適用場面
・教科書本文を要約し英語で書き直す問題
・日本語の指示文を英文メールに変換する設問
手順
- 一次和訳:設問文を自分の言い回しで短い日本語に要約。
- 英訳:要約日本語を英語に置き換える。
- 二次和訳:作った英文を再び日本語に直訳し、原文と差分を赤で囲む。
- 差分調整:語順・時制・冠詞の抜けを補正し、最終英文を確定。
活用例
原文和文:母は私に「失敗を恐れず挑戦しなさい」と言った。
一次和訳:母が挑戦を勧めた。
英訳:My mother told me to try without being afraid of failure.
二次和訳:母は失敗を恐れず挑戦するよう私に言った。
差分を確認し、「try」を「keep trying」へ微調整するとニュアンスが近づきます。
練習法
・三色ペン法:原文=黒、初訳=青、再訳差分=赤でノートに記載。視覚的に誤差が浮き上がります。
・五分タイマー:一次和訳を1分,英訳を3分、再和訳チェックを1分で回す高速サイクルを1日2セット。短時間でも反射的に冠詞や前置詞のミスが見抜けるようになります。
テンプレート共通活用ポイント
・“同じ型で語句だけ差し替え” が最大効率。導入と結論の骨は毎回コピーペースト感覚で書き始め、理由段落でテーマ固有の語を挿入します。
・語尾バリエーション:英文でも “so / therefore / thus” を回転させ、和文でも「〜と考える」「〜である」と交互に使うと採点者の印象が向上。
・例文ストックカード:教科書例文を「接続詞別」「句動詞別」にルーズリーフへ分類保存。作文時にそのままコピペできるため、語彙不足のストレスを大幅に軽減します。
・ミスパターンリスト:冠詞,三単現,複数形、前置詞抜けをチェックリスト化し、提出前に四項目を指差し確認すると簡単に減点を防げます。
英作文は“発想力”より“型の再現力”が得点を左右します。
三段落クイックライティングで構成を固定し、翻訳リバース法で精度を担保すれば、「時間が足りない」「文法が不安」という二大悩みを同時に解消できます。
五教科テンプレートを「日単位×週単位」で回す。週間ルーティン設計とフィードバックサイクル
テンプレートは覚えるだけでは武器になりません。
使う→修正する→再び使う、の循環に載せて初めて定着します。
ここでは「1日15分×五教科」のミニセッションと、それらを束ねる週末リフレクションで構成する週間ルーティンを提案します。
1. 平日ミニセッション――毎日同じ時刻に“型”を回す
| 曜日 | 科目 | 15分の流れ | 目的 |
| 月 | 国語 | 要約テンプレートで教科書1段落を文章化→字数チェック | 抽出と圧縮の自動化 |
| 火 | 社会 | キーワード三点法で歴史1出来事を記述→音読 | 背景‐結果の連結強化 |
| 水 | 英語 | 三段落クイックライティングで60語作文→再和訳 | 構成固定と誤差発見 |
| 木 | 理科 | 因果チェーン法で現象1題を説明→原因抜け確認 | 途中段階の可視化 |
| 金 | 数学 | 計算プロセスタグ法で方程式1題→口頭リプレイ | 手順漏れの撲滅 |
各セッションは「①テンプレート記入10分+②チェック5分」に分けます。
チェック工程では赤ペン三点確認を行います。
(1) テンプレートの四要素または三要素がそろっているか。
(2) 余計な接続詞の重複はないか。
(3) 語尾が二連続で同じになっていないか。
この三点を守るだけで減点幅は大きく縮まります。
2. 週末リフレクション――「見える化シート」で自己修正
土曜または日曜に見える化シートを1枚作成します。
シートには「今週使ったテンプレート」「成功した理由」「失敗した原因」を三列で記入。
たとえば水曜の英作文で語数オーバーしたなら、失敗原因欄に「導入で冗長な形容詞を多用」と具体的に書き込みます。
次週の火曜までに同種の問題を再挑戦し、修正後の語数を右端にメモ。
このPDCAを四週回すと、テンプレートごとの弱点が可視化され、ピンポイント練習が可能になります。
3. 欠席日フォロー――「テンプレ貯金箱」で遅れゼロへ
体調不良や部活遠征で学習時間が確保できない日もあります。
そこでテンプレ貯金箱という仕組みを導入します。
余裕のある休日に15分追加でセッションを行い、完成した答案を紙封筒に入れておく。
欠席日は封筒から一枚取り出し、チェック工程のみ実施。
作成フェーズを事前貯金しておくことで「連続学習記録」を途切れさせずに済みます。
4. フィードバック強化――家族・友人を巻き込む
・家族採点デー:週末夜に家族へ答案を3枚渡し、設問文と突き合わせてチェックしてもらう。
説明の過程で自分の理解不足が顕在化します。
・友人スワップ:同じテンプレートを使った友人と答案を交換し、互いに良い表現を青マーカーでハイライト。
他者の語彙や接続表現を吸収すると文章の幅が広がるでしょう。
・スマホ録音リプレイ:チェック工程を音読しながら録音し、翌朝聞き返す。
客観音声で聞くと語尾の単調さや論理の飛躍が一目瞭然です。
5. ルーティン継続のコツ
- タイマー固定:毎日同じ時刻にスマホアラームを設定し、条件反射でスタート。
- 見える進捗:週間ルーティン表を勉強机に貼り、達成日に○印を付ける。
- ご褒美設定:四週連続で○が埋まったら小さなご褒美(好きな漫画一冊など)を設定。
- 最小化思考:15分が確保できない日は「5分でテンプレ項目だけ書く」ミニ版で継続。
- 振り返り質問:「今日の答案はどこのタグが弱かったか?」と自問する習慣を持つ。
テンプレート学習は“やった時間”ではなく“回数×修正回数”で効率が決まります。
週間ルーティンとフィードバックサイクルを組み合わせれば、必要最小時間で最大効果を得られる習慣が自然に形成されるはずです。
“型”で広がる学力と、無料相談で得られる次の一手
五教科の記述テンプレートを振り返ると、共通して見えてくるのは 「抽出」「接続」「圧縮」 の三工程です。
国語では主張と補足を二本柱で抜き、社会では原因と結果を線で結び、理科・数学では途中段階を札で管理し、英語では段落骨格を固定しました。
これらの“型”は暗記量を増やすものではありません。
頭に散らばった知識を論理のレールへ載せる 思考のフォーマット です。
だからこそ 一度覚えれば一生使える武器 になります。
テンプレート学習を続ける最大のメリットは 時間対効果の劇的な向上 にあります。
15分のミニセッションを五日回すだけで、答案作成の筋トレを週75分で実現できます。
しかもチェック工程で「要素抜け」「語尾単調」「字数超過」を毎回修正するため、次のテストでいきなり結果が可視化されやすい特徴があります。
実際、ワイザーの教室で試験運用したところ、二週間で国語の記述配点が平均7点伸びた生徒もいました。
短期間で成果が見えればモチベーションが上がり、好循環が生まれます。
ただ、テンプレートを“自分専用”に最適化するには 客観フィードバック が欠かせません。
自力では気付けない癖──接続語の乱用、専門用語の書き間違い、段落の論理飛躍などを早期に修正することで、テンプレートの威力が倍増します。
そこで最後に、読者の皆さんへ 無料相談 のご案内を差し上げます。
個別指導塾ワイザー 無料相談のご案内
・対象:学習習慣がない小中高生と保護者の方
・内容:
1.五教科テンプレートの現状診断(15分)
2.家庭学習ルーティンのカスタマイズ提案(15分)
3.学校ワークとテンプレートを接続する演習計画(10分)
・形式:Zoomまたは電話(いずれも予約制)
・費用:完全無料・教材販売等も行いません
・特典:相談後に「見える化シート」テンプレートPDFをプレゼント
「記述が苦手だけど、何から始めればいいかわからない」
「テンプレートは覚えたが点数が伸び悩む」
そんなお悩みをお持ちでしたら、ぜひ一度ご活用ください。
ワイザーは “型”を通じて学習習慣を整える専門塾 として、勉強嫌いな生徒でも続けられる仕組みづくりをサポートしています。
少しでも興味を持たれた方は、下記フォームよりお気軽にお申し込みください。
テンプレート学習は今日から始められる“最短ルート”です。
しかし、続けるほど奥深さが増し、自分だけのアレンジが必要になります。
無料相談を活用し、専門家の視点で弱点を補強すれば、記述問題は間違いなく得点源へ変わります。
さあ、一歩踏み出し、答案作成を“型”から進化させましょう。
▼無料相談はこちらをクリック▼



