
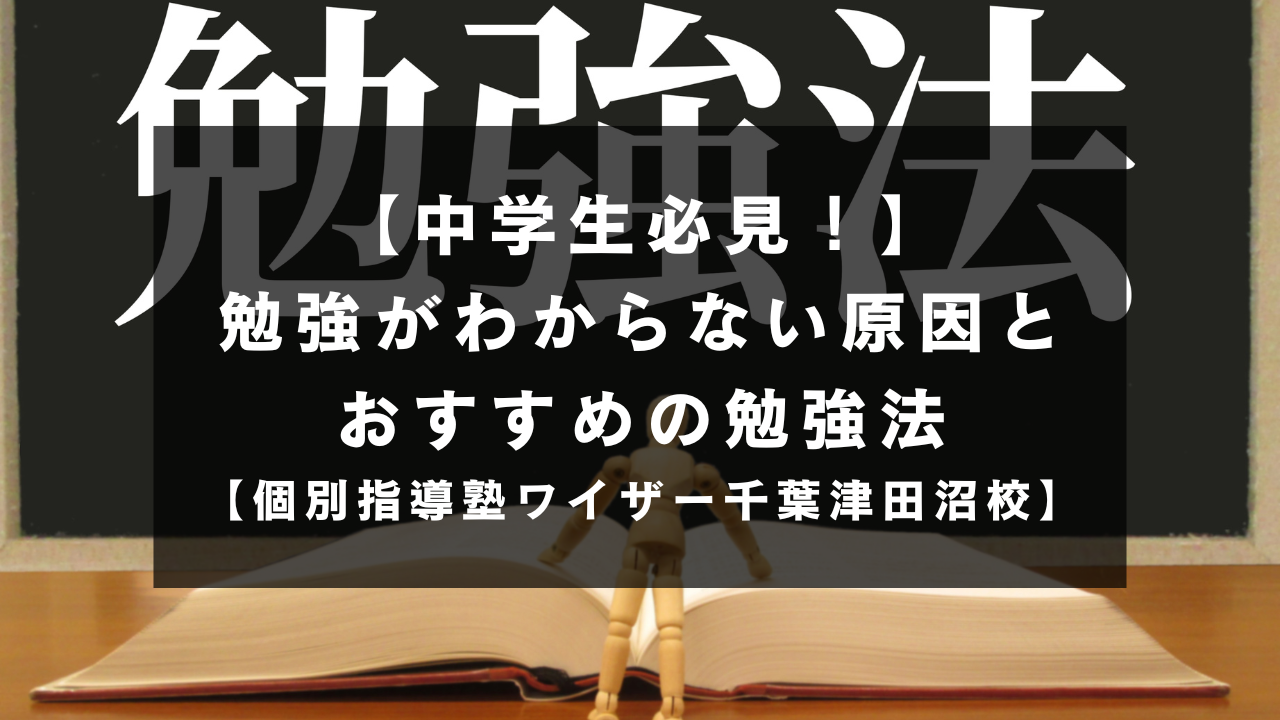
「勉強がわからない…」と悩んでいる中学生の皆さん、
そして保護者の方、とても多いですよね。
特に中学校に入ったばかりの頃や、
部活動や友人関係など勉強以外に意識が向きがちな時期には、
勉強へのやる気が起きず、「どうして自分は勉強が苦手なんだろう?」と悩みがちです。
勉強ができる友達を見ると、
「あの子は自分より頭がいいから…」
「自分には元々才能がないから…」
と落ち込んでしまった経験がある方も少なくないでしょう。
また、中学校では、小学校のときよりも一気に学習内容が難しくなります。
例えば数学では、小学校の計算問題が中心だった内容から、
中学校になると「方程式」や「関数」といった抽象的な概念を扱うようになります。
国語でも、小学校では簡単に感じていた文章問題が、
中学生になると急に難しく感じられたりしますよね。
英語に関しては、小学校の頃に「簡単で楽しい」と感じていた内容から一転、
中学校に入ってすぐに「英文法」や「単語の暗記」が始まり、
多くの生徒が挫折感を覚えることも珍しくありません。
また、近年ではスマートフォンやタブレット、ゲーム機など、
勉強以外の誘惑が非常に多くなっています。
学校から帰宅後は、ついついSNSをチェックしたり、動画サイトを見たり、
ゲームをしたりと、あっという間に数時間が過ぎてしまいますよね。
「やらなきゃ…」という気持ちはあるのに、実際には勉強する気が全く起きない。
気がついたら寝る時間になっていて、「また今日も勉強できなかった…」
と自己嫌悪に陥る…そんな繰り返しに悩んでいる人もいるでしょう。
親御さんにとっても、このような状況は悩みの種です。
子どもが勉強をしない姿を見ると、
つい感情的になって「勉強しなさい!」と強く叱ってしまったり、
「どうしてこの子は勉強しないんだろう」と悩んでしまったりしますよね。
「自分の子だけが勉強しないのではないか」
「このまま放っておいていいのだろうか」
と不安になる気持ちは、とてもよく分かります。
しかし実際には、
「勉強がわからない」
「勉強する気が起きない」と感じる中学生は決して少数派ではありません。
むしろ、多くの生徒が似たような悩みを抱えています。
ただ、それを相談できる場が少なく、
本人も保護者も孤立感を感じてしまうことが多いのです。
重要なのは、
「勉強ができないのは決して本人の能力や才能のせいではない」
ということを知ることです。
勉強が苦手なのは、
「やり方が分からない」
「勉強の環境が整っていない」
という、方法や環境の問題がほとんどです。
そのため、この原因をしっかり把握して対処していけば、
「勉強が分からない」という悩みから抜け出すことは難しくありません。
この記事では、中学生がなぜ勉強を苦手だと感じるのかをしっかり分析し、
その原因を具体的に明らかにしていきます。
さらに、その原因を解決するために、
すぐにでも実践できる効果的な勉強法も後ほど紹介しますので、ご安心ください。
「勉強が分からないのは自分だけではない」、
まずはその安心感から始めて、一緒に悩みを解決していきましょう。
勉強がわからない原因①:勉強方法が分からない
中学生が「勉強がわからない」と感じる最も大きな原因のひとつが、
実は「勉強の方法が分かっていない」ということです。
小学生の頃は、「宿題をこなす」「授業を聞く」という比較的単純な勉強法で、
ある程度学習内容を理解できていた生徒も多いでしょう。
しかし、中学校になると状況は一変します。
内容の難易度が格段に上がるだけでなく、授業のペースも早くなるため、
小学校の頃と同じ勉強法では全く対応できなくなってしまうのです。
例えば、小学校までは「授業を聞いていればなんとなく理解できる」
と感じていた子どもが、中学に入ってから突然、
数学の授業で「方程式」や「比例・反比例」、
英語の授業で「文法」や「単語の暗記」を教わるようになります。
このとき、生徒は初めて自分から予習・復習する必要性に直面しますが、
その具体的な方法を知らないまま、
授業についていけなくなってしまうことが多くあります。
多くの生徒は、
「予習ってどうやるの?」
「復習って何をすればいいの?」
と疑問を抱えたまま、時間だけが過ぎていきます。
さらに深刻なのは、勉強方法が分からないまま学年が進むにつれて、
徐々に「苦手科目」が増えてしまうことです。
特に、積み上げ式の科目である数学や英語などは、
一度でも基本的な部分を理解できないと、
その後の授業内容はますます理解しにくくなります。
「わからない」をそのままにして放置していると、
学習内容が蓄積されるにつれて、
やがて完全に「ついていけない」状態に陥ってしまうのです。
また、勉強方法が分からないという状態が続くと、
生徒の中に「勉強してもどうせ分からない」という諦めの感情が芽生えます。
この感情が根付くと、「どうせやっても無駄だから」
と学習そのものを避けるようになり、
結果的に勉強習慣を身につけることができなくなります。
このような負の連鎖に入ってしまうと、たとえ能力がある生徒であっても、
勉強に対する自信を失い、自己評価が著しく下がってしまいます。
また保護者側も「なぜうちの子は勉強ができないのか?」と、
子どもの能力不足を疑いがちですが、
実際には子ども自身が勉強法を知らないだけであることが多いのです。
「自分は勉強が苦手だ」という誤解が固定化され、
本人も保護者も焦りやストレスを感じるようになり、
家庭の雰囲気が悪くなってしまうことも珍しくありません。
このように、「勉強方法が分からない」という問題は、
単なる学習成績の低下だけに留まらず、
生徒の心理面や家庭環境にも大きな影響を与えます。
勉強がわからない原因②:勉強環境が整っていない
中学生が勉強をする際、「環境」は想像以上に重要です。
どんなに勉強する気持ちがあっても、
自宅や部屋が勉強に集中しにくい状態になっていると、
なかなか思うように学習が進まず、
「勉強がわからない」と感じる原因になってしまいます。
まず、家庭内の物理的な環境について考えてみましょう。
多くの家庭では、子どもの学習スペースがリビングにある場合があります。
リビングで勉強すること自体は決して悪くありませんが、家族がテレビを見ていたり、
会話をしている中で集中するのは難しいでしょう。
特に中学生の勉強内容は、
静かで落ち着いた環境の中でじっくり考えることが必要なため、
家族がいる空間で集中するのは容易ではありません。
また、自分の部屋がある生徒でも、
実際に勉強スペースを見てみると、机の周りが漫画やゲーム機、
スマートフォンなどの誘惑でいっぱいになっているケースも少なくありません。
特にスマートフォンやゲームは一度手に取ってしまうと、
ついつい長時間使ってしまい、気がつけば数時間が経過しているということもあります。
このような誘惑が身近にある環境では、本人がどんなにやる気を出しても、
意識が散漫になり集中が途切れやすくなります。
また、机や周囲の整理整頓も大切な要素です。
勉強に必要なノートや教科書、参考書がすぐに取り出せないような状態では、
勉強を始める気持ちがどんどん薄れてしまいます。
さらに、散らかった机は心理的なストレスを生み、
「勉強したくない」という気持ちを強めてしまうこともあるのです。
次に考えたいのが、家庭内の時間的な環境です。
例えば、家族の生活リズムが乱れていて、
夜遅くまでテレビやゲームの音が鳴り響いている場合や、
早く寝たいのに兄弟姉妹の生活音がうるさい場合などです。
このような環境では、中学生が規則正しく勉強時間を確保することが難しくなります。
その結果、「今日はもういいや…」と諦める日が増え、
習慣化する前に学習そのものを断念してしまうことにつながります。
また、「勉強時間を固定していない」という点も問題です。
毎日の勉強時間がバラバラだと、勉強の習慣を身につけるのは非常に困難です。
特に部活動などで帰宅時間が遅れる日があると、
定期的な勉強時間の確保が難しくなります。
「毎日決まった時間に勉強する」という明確な習慣が身につかないままだと、
勉強が面倒になり、ついつい後回しにしてしまいます。
また、最近増えているのが、家庭でのサポートが十分でないケースです。
子どもが勉強していて分からない問題があったときに、
すぐに質問できる相手がいない環境では、疑問を放置してしまいがちです。
その結果、学習内容の理解が浅くなり、
「勉強がわからない」と感じる悪循環に陥ってしまいます。
特に、共働き家庭などで、保護者が忙しく子どもの勉強を見る余裕がない場合は、
この問題が深刻化しています。
このように、勉強環境が整っていないことは、
中学生の勉強に対する意欲や習慣形成に深刻な影響を与えます。
そのため、
「勉強がわからない」
「勉強する気が起きない」と感じている場合、
まずは「家庭で落ち着いて勉強できる環境が整っているか?」
という点を見直すことが非常に大切です。
勉強がわからない原因③:勉強の習慣が身についていない
「やる気はあるのに、なぜか毎日勉強が続かない」
「テスト直前だけ必死にやるけど、結局点数が伸びない」
このような悩みを抱えている中学生は非常に多く、
その大きな原因が「勉強の習慣が身についていないこと」です。
習慣とは「やろうとしなくても、自然とやってしまう状態」のこと。
つまり、勉強習慣がない状態では、
どれだけ意志が強くても継続するのはとても難しいのです。
勉強は、スポーツや楽器と同じように、「日々の積み重ね」が力になります。
1日2時間集中して勉強したとしても、それが1週間に1回だけでは力にはなりません。
逆に、1日15分でも毎日続けられるほうが、
長期的にははるかに大きな成果につながります。
ところが、多くの中学生は、
「勉強はやる気が出たときにやるもの」
「テスト前だけ頑張ればいい」と考えてしまいがちです。
そうした考え方では、学習内容が定着しにくく、
毎回「また最初から復習し直し」という状態になり、
勉強に対して疲れやストレスを感じやすくなります。
また、習慣がないと勉強への心理的ハードルが高くなり、
「今日は部活で疲れたからやめておこう」「明日から頑張ろう」と、
先延ばし癖が定着してしまいます。
これが続くと、
「勉強=しんどいこと」「嫌なこと」と感じるようになり、
勉強そのものを避けるようになってしまいます。
本人の中では「やらなきゃいけないのは分かってるけど、できない」
というジレンマが生まれ、自己嫌悪につながるケースも多いのです。
さらに、「そもそも何を勉強すればいいか分からない」
「やるべきことが曖昧」という状態も、習慣化の妨げになります。
例えば「今日は数学を頑張るぞ!」と意気込んでも、
いざ机に向かったときに「何の問題をやればいいんだっけ…?」と迷ってしまうと、
その時点で集中力が切れてしまいます。
人間は「やることが明確でないと行動しづらい生き物」です。
つまり、習慣化の第一歩は、
「何を・いつ・どれくらいやるか」をあらかじめ決めておくことなのです。
また、家庭によっては勉強時間やペースを
完全に本人任せにしてしまっている場合があります。
中学生はまだ自己管理能力が発展途上ですので、自分で学習計画を立て、
それを守るのは難しいのが現実です。
「毎日勉強しなさい」と言われても、
「何をどうやればいいか」が明確になっていないと、習慣化にはつながりません。
さらに、周囲の環境の影響も無視できません。
友達の多くが勉強習慣を持っていない場合、
自分も「やらなくていいか」という気分になりやすいですし、
逆に常に勉強している友達がいると、
「自分も頑張らなきゃ」という気持ちが芽生えます。
つまり、勉強を習慣化するには、
「周囲に勉強している人がいる」
「自分の努力を見てくれる大人がいる」
という環境づくりも非常に重要なのです。
このように、勉強ができない原因が「能力」ではなく
「習慣の有無」にある場合は非常に多いです。
しかし裏を返せば、正しい方法で習慣さえ身につけてしまえば、
どんな生徒でも「勉強が日常の一部」になっていくということでもあります。
勉強がわからない原因④:スマホやゲームなどの誘惑による集中力低下
スマホは、ひとたび通知が鳴るだけで
脳の集中が一気に分断されてしまう強力なツールです。
LINEやInstagram、YouTube、TikTokといったアプリは、
短時間でも手軽に刺激が得られるため、
一度手に取ると何十分、何時間と時間を奪われてしまいます。
しかも「ちょっとだけ見よう」と思って見始めたはずが、
無限に続くタイムラインや関連動画に吸い込まれ、
気づけば勉強時間を全て失っていたということも珍しくありません。
さらに困ったことに、
こうしたスマホやゲームの刺激は脳にとって“快楽”として処理されます。
つまり、脳が「勉強よりもスマホの方が楽しい」と無意識に判断してしまい、
勉強を避ける方向へと自動的に向かうのです。
これでは、どれだけ本人にやる気があっても、
集中すること自体がとても難しくなってしまいます。
また、夜遅くまでスマホを見ていると、睡眠の質が低下し、
翌日の集中力も著しく落ちてしまいます。
睡眠不足は思考力や記憶力に直結しますから、
「前の日に勉強したはずなのに、全然覚えていない」
という状況が頻発するようになります。
こうなると「頑張っても成果が出ない」と感じてしまい、
ますますやる気が失われてしまうという悪循環が生まれてしまいます。
ゲームについても同様です。
RPGやオンライン対戦型のゲームは、
達成感や報酬がすぐ得られるように設計されており、
勉強よりも“楽しく・簡単に成功体験を味わえる”仕組みになっています。
これに慣れてしまうと、勉強のように時間がかかることに対して集中力を保つのが
苦痛に感じるようになってしまうのです。
このように、スマホやゲームが勉強に与える影響は、
単に「時間を奪う」だけにとどまりません。
「集中力の低下」「学習意欲の低下」「自信の喪失」など、
学習に必要なすべての要素に悪影響を及ぼす可能性があるのです。
とはいえ、現代社会においてスマホやゲームを完全に排除することは
現実的ではありません。
大切なのは「どう付き合っていくか」という視点です。
勉強中はスマホの通知を切る、リビングに預ける、
タイマーで使用時間を管理する、勉強後の“ご褒美”として使うなど、
ルールを自分で決めて制限する力を育てることが求められます。
勉強がわからない原因⑤:自信の喪失と自己肯定感の低下
中学生が「勉強がわからない」と感じる原因の中でも、
見落とされがちなのが、自信の喪失と自己肯定感の低下です。
実はこの心理的要素こそが、学習意欲や継続力に大きな影響を与えており、
成績の伸び悩みと深く関係しています。
例えば、小テストで連続して低い点数を取ったり、
友達と比べて自分の成績が悪いことに気づいたりすると、
生徒の心の中には「自分は頭が悪いんだ」「どうせやっても無駄だ」
という思いが芽生えます。
これは一度生まれると根深く残り、勉強をするたびに
「またできなかったらどうしよう」「頑張っても意味ないかも」
といった不安や恐怖を引き起こします。
特に思春期の中学生は、周囲との比較に敏感な時期です。
自分と同じくらいの成績だった友達が急に伸び始めたり、
親や先生から期待されることが増えたりすると、
「期待に応えられない自分はダメだ」と思い込んでしまうこともあります。
こうした自己評価の低下は、「勉強しよう」という気持ちにブレーキをかけ、
やる気をそいでしまう原因になります。
また、周囲の大人の言動が無意識のうちに自信を奪ってしまうこともあります。
たとえば、テストの点数を見た親御さんが
「なんでこんな点数なの?」「もっと頑張りなさい」と厳しい言葉をかけてしまうと、
本人は「自分は否定された」と受け取り、
「努力しても認めてもらえない」と感じるようになります。
これは「やる気が出ない」「勉強が嫌い」という感情につながりやすく、
次第に勉強から距離を置くようになってしまうのです。
さらに、「できなかった経験」が積み重なると、
生徒自身が勉強に対して“恐怖心”を持つようになります。
教科書を開くことすら億劫になり、
問題に取り組む前から「どうせ分からない」と思い込んでしまう。
こうなると、実力に関係なく「勉強がわからない」という状態に陥ってしまいます。
ここで大切なのは、
「自信がない子ほど、努力できないのではなく、努力するきっかけがつかめないだけ」
という視点です。
つまり、「小さな成功体験」を積ませてあげることが、
勉強への前向きな姿勢を取り戻す第一歩になります。
たとえば、
「昨日より5分長く机に向かえた」
「1問でも自分で解けた」
「宿題を自力で終わらせられた」
といった小さな達成を、しっかり言葉で褒めてあげることで、
子どもは「やればできるかも」という感覚を少しずつ取り戻していきます。
この“できた感覚”が、自己肯定感を育て、
「もう一度やってみよう」と自発的な行動につながっていくのです。
また、「自分だけができないわけじゃない」と気づくことも大切です。
多くの生徒が「勉強がわからない」と悩んでいることを知るだけでも、
自分を責める気持ちはやわらぎます。
家庭でそうした声かけができると理想的ですが、それが難しい場合は、
第三者の存在、つまり、
生徒の努力や成長を見守ってくれる大人(先生・塾の講師など)の存在が重要です。
【5教科別】おすすめの勉強法
ここまで中学生が「勉強がわからない」となってしまう原因について解説してきました。
自分に合った勉強法を見つけられないままでいると、
手当たり次第に教科書を読んでみたり、
問題集をなんとなく解いてみたりしていると、
「こんなに頑張っているのに点数が取れない…」という悪循環に陥りやすくなります。
実は、教科ごとに「勉強の仕方のコツ」はまったく異なります。
なのでここでは主要5教科(国語・数学・理科・社会・英語)に絞って、
それぞれの特性に合った効果的な勉強法をご紹介します。
どれも今日から始められる実践的な内容ですので、ぜひ参考にしてみてくださいね。
国語は「読む・考える・言葉を知る」で“読解の地力”を鍛える
「国語が苦手なんです」と相談に来る中学生は意外と多いものです。
「何が問われているのか分からない」
「選択肢を選ぶときにいつも迷ってしまう」
「とにかく点数が安定しない」
このような声の裏には、読解力不足と語彙力不足が隠れています。
国語は“センスの科目”だと思われがちですが、
実際には日々の練習で確実に力がつく科目です。
しかも、国語力がつくと、英語・社会・理科など他教科の
「読む力」にも波及効果があります。
ここでは、今日から始められる実践的な国語の勉強法をご紹介します。
音読×要約で“読む力”を強化する
まずおすすめなのが、「教科書の音読」と「段落ごとの要約」です。
音読は、目と耳と口を使うことで、文章全体のリズムや構成、
表現に自然と慣れることができます。
特に現代文では、「この言い回し、よく使われてるな」
「接続語の使い方にルールがあるな」など、読解のヒントがたくさん見えてきます。
やり方は簡単で、1日1つの文章(1ページ程度)を音読し、
そのあとに「この段落は何が書いてあったか?」を1〜2行でまとめます。
これをノートに書きためていくことで、
「読み取る力」と「要点を抜き出す力」が同時に鍛えられます。
設問の“意図”を読み解くクセをつける
国語のテストで点数が伸び悩む理由の1つは、
「設問の意味を正確に読み取れていない」ことです。
選択肢問題でも、「なんとなく」で選んでしまっては正答率が安定しません。
たとえば「筆者の考えとして最も適切なものはどれか?」と問われたとき、
焦って「似た言葉が使われている選択肢」を選んでしまうケースが多いですが、
それが必ずしも正解とは限りません。
そこで大切なのが、
「設問のキーワードに線を引く」
「問いが何を求めているかを意識する」練習です。
問題演習をするときは、
「なぜこの選択肢が正解で、他が違うのか?」
まで説明できるようにすると、理解が深まり再現性が高まります。
語彙力アップは“辞書×ノート”が最強
国語の読解において、
「言葉の意味が分からない」は大きなハンデになります。
文章中に知らない言葉が出てきたとき、
「なんとなくスルーする」習慣がついてしまうと、
理解の浅い読み方が癖になってしまいます。
そこでおすすめなのが「語彙ノート」の活用です。
教科書や問題文で分からなかった言葉を、その場で辞書やアプリで調べて、
意味をノートに書いていきます。
できればその言葉を使った自作例文も添えると、記憶への定着率が大幅にアップします。
この語彙ノートを1日1語でも続ければ、1ヶ月で30語、半年で180語。
語彙力が増えれば増えるほど、文章の理解力も確実に伸びていきます。
読書は「強制」でなく「習慣」に
国語力を上げたいなら、読書の習慣は外せません。
ただし、「読書しなさい」と強制しても効果は薄いです。
大切なのは、
「好きなジャンルからでいいから、毎日数ページでも本に触れる」
という習慣を作ることです。
ミステリー、エッセイ、小説、ノンフィクションなど、ジャンルは問いません。
とにかく“言葉に触れる時間”を生活の中に取り入れていくことが、
読解力と表現力を養ううえで非常に重要です。
数学は「手を動かす」「間違いを活かす」が鉄則
中学生の数学につまずくタイミングは、実はかなり多いです。
小学校までは“計算中心”だったのに、
中学に入ると文字式・方程式・関数・証明と、抽象的な概念が一気に増えます。
しかも授業の進むスピードが早く、
ついていけなかった内容をそのまま放置してしまうと、
次の単元がまったく理解できない…という悪循環に陥りがちです。
そんな数学の苦手を克服するためには、
何よりも大切なのが「自分の手で問題を解いて、わかるまで繰り返す」ことです。
以下、数学の力をしっかり身につけるための実践的な勉強法を紹介します。
ステップ①:まずは例題を「真似る」ところから始めよう
いきなり問題集を解こうとしても、
「解き方がわからない…」と固まってしまう生徒は少なくありません。
まずは教科書や参考書にある「例題」や「解き方の手順」をじっくり読み、
それを自分のノートに何も見ずに再現できるかを試してみましょう。
「なぞり勉強って意味あるの?」と思うかもしれませんが、
これは非常に大切なプロセスです。
いわば“スポーツの素振り”のようなもの。
頭で理解したことを、実際に自分の手で解いて初めて、
知識が「使える力」に変わっていきます。
ステップ②:「わかる」と「できる」は全く違うと知る
数学では「授業では分かったのに、テストでは解けない」という声をよく聞きます。
これは、「解説を読んで“なんとなく分かった”気になっている」状態が原因です。
頭で理解しているだけでは、本番では歯が立ちません。
そこで重要なのが、「解けるまで自力で繰り返す」という姿勢です。
同じ問題を3回以上解いてみて、
「何も見ずにスラスラと解けるか?」を確認してみましょう。
特に苦手な単元は、間違えた問題だけを集めた「間違いノート」を作ると効果的です。
ステップ③:間違いから学べる人が、数学が伸びる人
数学が得意な人と苦手な人の違いは、「間違えたときの向き合い方」にあります。
多くの生徒は、間違えると「自分はダメだ」と落ち込んでしまいますが、
実は間違いこそが最大の学びポイントなのです。
重要なのは、「なぜ間違えたか」を考えること。
計算ミス?公式の使い方を間違えた?問題文の読み違い?
原因を明確にし、それに対する“対策”を一言メモに残しておきましょう。
「次は気をつけよう」で終わらせるのではなく、
「次はどうするか」まで書いておくことで、同じミスを繰り返さずに済みます。
ステップ④:基礎を飛ばさず、反復で定着を
特に数学が苦手な生徒ほど、「応用問題」や「難問」に挑みすぎて、
結局何も身につかないという状態になりがちです。
まずは、教科書レベルの基礎問題を完璧にすること。
基礎がぐらついていると、応用にも太刀打ちできません。
ワイザーでも、最初に取り組むのは
「マイクリア」や「学校ワーク」などの基本的な教材です。
定期テストで高得点を狙うためには、応用問題を解く前に、
基本問題を「確実に」正解できるようになることが最優先。
これを無視してはいけません。
「毎日1問」でいいから継続しよう
数学は“感覚”の教科でもあるため、
空白期間を空けると、すぐに感覚が鈍ってしまう傾向があります。
だからこそ、毎日1問でも良いので手を動かすこと。
忙しい日でも「計算問題だけ」「公式だけ確認」など、
短時間でも継続する工夫をしましょう。
理科は「暗記と理解を分けて考える」がコツ
「理科って、覚えることが多すぎて苦手」
「計算問題が出ると手が止まる…」
このような悩みを抱える中学生は非常に多いです。
理科は、生物・化学・物理・地学という4分野に分かれていて、
それぞれで学習スタイルが少しずつ異なります。
そのため「とにかく全部覚えなきゃ!」と無理に詰め込もうとすると、
途中でパンクしてしまい、勉強そのものが嫌になってしまうケースもあります。
でもご安心ください。
理科は「覚える部分」と「理解する部分」を明確に分けて学ぶことで、
苦手意識がグッと軽くなります。
ここでは、分野別の特徴に合わせた、実践的な勉強法をご紹介します。
生物・地学は「覚える+図でまとめる」
植物や動物、人体、天気や地層などが出てくる生物・地学分野は、
基本的に暗記型の内容が多いです。
教科書や資料集の図やイラストが豊富なため、
まずは「視覚で覚える」ことを意識しましょう。
たとえば、葉のつくりや光合成のしくみ、火山の種類などは、
「言葉だけで覚えようとせず、図に書いて説明できるか?」
を意識すると記憶に残りやすくなります。
ノートにイラストを描きながらまとめたり、
穴埋めプリントを活用したりすると、頭に入りやすくなります。
特に効果的なのは「自分の言葉で説明する練習」です。
たとえば、「なぜ昼と夜ができるのか?」といった基本的な内容を、
自分の言葉で紙に書き出してみる。
すると、どこが理解できていないかがはっきりします。
ここで調べ直して、自分なりの言葉に変えて理解すると、
長期記憶にもつながりやすいです。
化学・物理は「公式+実例」でイメージをつかむ
化学や物理の分野では、「質量」「力」「電流」「溶解度」など、
計算問題や概念理解が中心になります。
この分野でつまずく生徒の多くは、
「用語や公式は知っているけど、使い方が分からない」という状態にあります。
例えば、「電流=電圧÷抵抗」という公式があることは覚えていても、
「問題文のどこをどう読み取ればいいのか?」が分からず、手が止まってしまうのです。
これを防ぐには、まず“例題の解き方を真似する”ことから始めるのが効果的です。
ワークや教科書にある例題を丁寧に写して、
「どの数字がどの公式に当てはまるのか?」を色分けしたり、
単位を書き込んだりして、手順を体で覚えていきます。
計算問題は、「覚える」より「慣れる」ことが大切。
最初の10題くらいは全て解説を見ながら解いてもかまいません。
大切なのは、“意味がわかる状態”を増やしていくことです。
用語暗記は「ポイントごとに小分けにする」
理科はとにかく用語が多く、
「漢字も難しいし、何をどう覚えたらいいか分からない」と混乱しやすい教科です。
そんなときに役立つのが、「1日3項目だけ覚えるルール」です。
たとえば今日は「炭酸水素ナトリウム」「中和」「BTB溶液」の3つを覚える。
次の日はまた別の3つというように、「少量を毎日続ける」ことがポイントです。
できれば、覚えた用語は自分なりの例文で使ってみたり、
友達や親に説明してみたりすると、さらに記憶が深まります。
動画や実験映像も積極的に活用しよう
理科は、文字や図だけではイメージしづらい内容も多いので、
「動画」を活用するのも非常に効果的です。
YouTubeなどで「○○ 中学 理科 実験」などと検索すると、
視覚的に理解できる実験映像が数多く見つかります。
たとえば「酸とアルカリの中和反応」や「磁石の力の働き方」など、
文章で読むだけではピンと来なかったことも、
動画で見ることで「そういうことか!」とスッと理解できるようになるのです。
「なぜ?」を大切にする習慣を
理科は単なる暗記教科ではなく、
「なぜそうなるのか」を理解することで成績が伸びます。
教科書やノートを読んだときに、「これはどうして?」と自分に問いかけてみること。
わからなければ調べて、「なるほど!」と納得する。
これが理科を楽しくする第一歩です。
社会は「流れ×関連づけ×アウトプット」で記憶に残す
社会科目と聞くと、
「ひたすら暗記」「年号や地名が苦手」「一夜漬けで詰め込むしかない」
といったイメージを持つ中学生も多いのではないでしょうか。
しかし、社会は“暗記だけ”で乗り切ろうとすると、すぐに忘れてしまいがちです。
なぜなら、人の脳は“意味のない情報”や
“関連づかない情報”を覚えるのが苦手だからです。
実は社会こそ、「覚える」よりも「理解する」「つなげる」ことが大切な教科。
地理・歴史・公民のどれも、“点”で覚えるのではなく、
“線”としてつなげる学習”を意識することで、
記憶が驚くほど定着しやすくなります。
ここでは、社会が苦手な子でも実践しやすい勉強法を分野別にご紹介します。
【地理】は「地図×資料×具体例」の三点セットで学ぶ
地理分野では、
「どこの国・どこの都道府県に、どんな特徴があるのか?」を覚える必要がありますが、
単なる地名暗記に終わるとすぐ忘れてしまいます。
そこで効果的なのが、「地図×資料×具体的な事例」をリンクさせて覚える方法です。
たとえば「北海道は酪農が盛ん」と習ったら、
①地図で北海道の位置を確認 → ②気候条件(夏でも涼しい)
→ ③なぜ酪農が向いているのか → ④代表的な都市(帯広、根室など)
と組み合わせて、「地図に書き込む」などして視覚的に学ぶことが大切です。
教科書や資料集にある統計グラフや写真を積極的に活用し、
数字や事例を“ストーリー”として覚えると、地理の学習は一気に楽しくなります。
【歴史】は「物語として流れで覚える」のが鉄則
歴史分野が苦手な生徒の多くは、
「用語ばかりを丸暗記」しようとしています。
ところが、それでは年号や人物名がごちゃごちゃになってしまい、
テストになると「あれ?あの人は何をしたんだっけ?」と混乱してしまいます。
だからこそ、歴史は「物語として流れを追う」ことが重要です。
特に重要なのが、「時代の変わり目」に注目すること。
「なぜ平安時代から鎌倉時代に変わったのか?」
「戦国時代の混乱がなぜ江戸の安定につながったのか?」
このような“時代の因果関係”を理解することで、内容が頭にスッと入ってきます。
さらに、人物・出来事・場所をセットで覚えると記憶が強化されます。
たとえば
「織田信長=桶狭間の戦い=尾張」
「聖徳太子=十七条の憲法=飛鳥時代=法隆寺」
といった具合に、“パズルのピース”のようにつなげる意識を持つと、
用語暗記の負担が減ります。
【公民】は「身近なことと結びつける」と一気に理解が進む
公民は抽象的な言葉が多く、特に中学3年生で初めて習うと
「難しそう…」と感じやすい分野です。
たとえば「三権分立」「市場経済」「国会の役割」など、
言葉は聞いたことがあっても、実際の生活とどう関係しているかが分からないと、
すぐに頭から抜けてしまいます。
そこでおすすめなのが、「身近なニュースや経験とつなげる」学び方です。
ニュースで「選挙」や「国会」が取り上げられていたら、
「これは教科書のどの単元と関係しているのかな?」と照らし合わせてみましょう。
選挙の仕組みを「自分が有権者だったら…」と仮定して考えるのも、
理解が深まる良い方法です。
また、学校で配られる副教材やワークには、「図でまとめるページ」や
「実際の制度を簡略化した解説」が載っていることが多いので、
それをノートに写しながら整理すると、複雑な内容も視覚的にすっきり理解できます。
アウトプット学習で“知識を使う”練習を
社会は“覚えて終わり”にしてしまうとすぐ忘れてしまうため、
アウトプット(書く・話す)を意識した学習が非常に大切です。
たとえば、単元ごとに「○○ってどういうこと?」と自分に問いかけて、
簡単に説明する練習をしてみましょう。
また、教科書を閉じて「図や表を自分で再現してみる」
「記述問題を自分の言葉で書いてみる」など、“思い出しながら使う”プロセスが、
記憶を深く強化します。
英語は「音読×書く×毎日5分」で“自然に使える力”を育てる
英語に対して、「単語が覚えられない」「文法が難しい」
「テストでは読めるけど話せない」と悩む中学生はとても多いです。
特に中1の最初でつまずいてしまうと、
そのままずるずると「英語苦手…」という意識が定着しやすく、
苦手意識を克服するのが難しくなってしまいます。
でも、英語は正しく学べば、実は最も“得点が安定しやすい”教科です。
なぜなら、ルール(文法)と頻出単語がはっきりしていて、
毎日の積み重ねさえできれば誰でも着実に点数が伸びる科目だからです。
ここでは、英語を苦手から得意に変えるための、実践的な勉強法をお伝えします。
音読は最強のインプットトレーニング
英語の上達において、最も効果的で、
かつ中学生でも簡単にできる学習法が「音読」です。
教科書の英文を毎日音読するだけで、
英語の語順、リズム、発音、文法パターンが自然と身についていきます。
おすすめのやり方は次のとおりです
- 教科書の1パラグラフを毎日音読(できれば3〜5回)
- 意味が分からない単語には印をつけ、あとで辞書で確認
- CD音声や学校のリスニング音声があれば「シャドーイング」(後追い読み)にも挑戦
これを毎日10分続けるだけで、
英語が“読める”だけでなく“使える”力に変わっていきます。
特にテスト前は「本文丸暗記」を目標に音読練習をすると、
並び替え問題や英作文問題への応用力も自然と養われます。
単語は「毎日5語」×「3回復習」が効く
英単語は“コツコツ型”の代表格です。
一気に30語覚えようとしても、次の日にはほとんど忘れてしまいます。
だからこそ、1日5語でも毎日継続することが大事。
たとえば、英単語帳やワークブックの「今日の5語」に印をつけて覚える、
という方法がおすすめです。
単語を覚えるときは以下のように“五感”をフル活用しましょう
・声に出して発音する
・ノートに3回書く
・カバーをして意味を言えるか確認
・3日後・1週間後に復習
「人の記憶は1回では定着しない」ことを前提に、
復習タイミングもスケジュールに組み込みましょう。
アプリや単語カードを使ってゲーム感覚で学ぶのも効果的です。
英文法は「書いて・使って・話して」覚える
英語が苦手な生徒に共通しているのは、
「文法を読んでなんとなく分かった気になっている」こと。
英文法は「使って初めて身につく」ものです。
たとえば、be動詞・一般動詞・助動詞などを学んだら、
自分の生活を例にして短い英文を作ってみましょう。
・I am a soccer player.
・She can play the piano.
・We study math every day.
このように、自分で英文を作ってノートに書き、それを音読するだけでも、
文法の使い方がグッと理解しやすくなります。
さらに、「誰かに説明するつもりで練習する」と、理解が深まりやすいです。
リスニング対策も音読でOK!
「リスニング問題が全然聞き取れない…」という声も多いですが、
実はリスニング力は“音読力”に比例します。
なぜなら、聞き取れない音の多くは「自分が発音できない音」だからです。
だからこそ、日頃から音読練習をしていると、
自然と「耳が英語の音に慣れてくる」ようになります。
英語の発音やリズムは、
日本語と違って「強弱」「イントネーション」がはっきりしているので、
口に出して練習することで、聞き取る力も育っていきます。
「毎日5分」で英語は確実に伸びる
英語は1回に1時間やるよりも、
「毎日5〜10分」を地道に積み重ねる方が効果的です。
習慣化すれば、英語に対する“苦手意識”は驚くほど薄れ、
「わかる!読める!話せる!」という実感に変わっていきます。
個別指導塾ワイザーでは、教科書の進度やテスト範囲に合わせて、
「英語の音読・単語暗記・文法演習」を365日分のタスクとして日割りで提示しています。
「今日は何をすればいいか?」が明確なので、生徒も迷わず実行に移せます。
毎日続けられる学習習慣をつくる方法
ここまで勉強法について解説してきました。
しかし「そもそも学習習慣がない」という中学生にとっては、
勉強法よりもまずは机に向かって勉強をするという習慣をつくることが大切です。
やる気はあるけど続かない、始めてもすぐにやめてしまう。
その原因は“根性”や“意志の弱さ”ではなく、学習が「習慣」になっていないからです。
勉強習慣がついている生徒は、「特別なこと」として勉強するのではなく、
「歯磨きみたいに当たり前の日課」として机に向かっています。
では、どうすればそんな習慣が作れるのでしょうか?
今日からできる5つのステップで解説していきます。
ステップ①:勉強時間を“固定”する
習慣をつくる最初のカギは、
「いつ勉強するかを決めておくこと」です。
「できたらやろう」「気が向いたらやろう」という気持ちでは、
誘惑や疲れに負けてしまいます。
おすすめは、「毎日○時から15分だけ」と時間を固定すること。
たとえば「夕食後の19:30〜19:45だけ机に向かう」など、最初は短時間でOKです。
慣れてくると、脳が「この時間は勉強する時間だ」と覚えてくれて、
自然と集中できるようになります。
ステップ②:「1日1タスク」でハードルを下げる
勉強習慣を作るうえで失敗しやすいのが、「いきなり完璧を目指す」ことです。
たとえば「毎日2時間やろう」「5教科全部やらなきゃ」と欲張ると、
最初の1日目はできても、2日目で疲れて続かなくなります。
まずは「1日1教科」「1日1ページ」「1日1単語」など、
とにかく“簡単すぎるくらいのタスク”から始めることが成功の秘訣です。
「今日もできた!」という達成感を積み重ねることで、
少しずつ量や難易度を上げても自然と継続できるようになります。
ステップ③:勉強を「見える化」する
勉強習慣がある生徒は、必ず「何をやったか」を可視化しています。
たとえば、
・勉強カレンダーに○をつける
・タスクを終えたらスタンプを押す
・ノートに日付と教科、勉強内容をメモする
など、“やった証”を自分で記録に残すことで、達成感が得られ、
「明日も続けよう」という気持ちになります。
これを「習慣チェッカー」と呼ぶこともありますが、
アプリやシール、ホワイトボードなど、方法は何でもOKです。
ポイントは、目に見える形で「継続している自分」を確認すること。
これがやる気の源になります。
ステップ④:「やることを決めておく」仕組みをつくる
「勉強しようと思ったのに、何から手をつけていいか分からなくてやめた」
これ、非常によくあるケースです。
特に習慣がないうちは、「今日は何やる?」と迷った時点でやる気が切れてしまいます。
これを防ぐには、「やることを決めてから始める」のではなく、
「やることが決まっている状態」にしておくことが大切です。
たとえば、
・月曜は英語・火曜は数学など、曜日で教科を固定
・勉強する前に「ToDoリスト」をノートに書いておく
・塾やアプリで「今日のタスク」を提示してもらう
など、自分で考えなくても動けるように“型”を決めておくと、
迷いが減り、習慣化が加速します。
ステップ⑤:勉強後に“ごほうび”を設ける
最初のうちは「勉強=楽しくないこと」というイメージが強いかもしれません。
そこでおすすめなのが、「勉強したら〇〇していい」という
“ごほうびルール”を作ることです。
たとえば、
・「15分勉強したら、おやつを食べていい」
・「英語の音読が終わったら、動画を15分だけ見ていい」
・「5日連続で続いたら、日曜日は遊びに行っていい」
など、自分なりのごほうびを設定することで、モチベーションが保ちやすくなります。
スマホやゲームなどの誘惑を断ち切る方法
ここまでは学習習慣をみにつける方法について解説しました。
ここからは逆に”学習習慣の定着を邪魔するものを断ち切る方法”について解説します。
「勉強しようと思ったのに、気づいたらスマホをいじって1時間…」
「ちょっとだけのつもりが、気づいたらゲームをずっとやってた…」
中学生にとって、スマホ・ゲーム・SNS・動画配信サービスは最大の誘惑です。
そしてこれは、意志の強さとは関係ありません。
そもそもこれらは「やめられないように設計されている」ため、
対抗するには工夫と環境づくりが欠かせません。
ここでは、
今日から実践できる“スマホやゲームの誘惑に負けない仕組み”を5つ紹介します。
① スマホは物理的に「視界から消す」
最も手軽で効果的なのが、勉強中はスマホを手の届かない場所に置くことです。
目に見える場所にあると、「通知が来たかも」「ちょっとだけ…」
という気持ちが無意識に湧いてきます。
・スマホは別室に置く
・家族に預ける
・専用のタイマー付きスマホボックスに入れる
といった「触れられない仕組み」をつくるだけで、集中力は格段に上がります。
人間は視覚情報に影響されやすいため、
“見えない=存在を忘れる”状態を作るのがコツです。
② アプリの通知を完全オフにする
LINE・Instagram・YouTubeなどのアプリ通知は、
集中を何度も切らしてしまう原因になります。
勉強時間中は通知を切る、
または「おやすみモード」「集中モード」に設定しましょう。
さらに徹底したい場合は、
スマホのアプリ制限機能(スクリーンタイム・デジタルウェルビーイングなど)を使って、
「夜21時以降はSNSを開けない」など、自動で制限をかけるのも効果的です。
③ 「やるべきこと」を先に終わらせてから楽しむ
誘惑をゼロにするのは難しいので、「順番」を意識するのが大切です。
・「15分だけ英語の音読をしたら、スマホを10分見てOK」
・「学校の課題が終わったらゲームOK」
というように、“やるべきことを先に終わらせたら、好きなことをしてもいい”という
ルールを自分の中に作りましょう。
これを「ごほうび型時間管理」といいます。
習慣化できるようになると、「早く終わらせてゲームしよう!」と、
勉強への集中力も高まりやすくなります。
④ 「スマホを見る理由」を自分で言語化する
勉強中にスマホを触ってしまうとき、実は“目的がない”ことがほとんどです。
なんとなく手が伸びて、なんとなくSNSを開いて、なんとなく時間が過ぎている。
この状態を変えるには、「スマホを見る理由」を自分で書き出してみることが有効です。
・本当に友達との連絡が必要?
・その動画、今じゃなきゃダメ?
・明日でもできることじゃない?
と問いかけて、「今スマホを使うべき理由がない」と気づくだけで、
使用頻度を抑えられるようになります。
⑤ 家族とルールを共有する
一人で誘惑と戦うのは大変です。そこで効果的なのが、
家族と「スマホ・ゲームのルール」を一緒に決めることです。
たとえば、
・勉強時間中はスマホを預かってもらう
・22時以降はスマホをリビングに置く
・テスト前はゲームを1日30分以内にする
など、家族ぐるみで協力体制を作れば、無理なく続けやすくなります。
また「自分でルールを作って、それを守る」という行動自体が、
自己管理能力を育てるきっかけにもなります。
家庭でできる保護者サポートの工夫
ここまで適切な勉強法や学習習慣を身につける方法について解説しましたが、
これらはすべて中学生が自分自身で行うことです。
しかし、勉強は本人がやるものとはいえ、やはり家庭でのサポートがあるかどうかは、
子どもの学習意欲や習慣づくりに大きな影響を与えます。
ここでは、家庭で今日からできる
「声かけ・環境づくり・関わり方」のポイントを5つ紹介します。
いずれも、“押しつけ”ではなく“見守りと励まし”を軸にした方法です。
① 「勉強しなさい」よりも「どうだった?」の声かけを
「またゲーム?」「早く勉強しなさい!」という声かけは、
多くのご家庭でつい言ってしまう定番フレーズかもしれません。
ですが、これは逆効果になることが多く、
子どもは「責められている」と感じ、反発したり、自信を失ってしまったりします。
代わりにおすすめなのが、
「今日は学校どうだった?」「どんなこと習ったの?」という関心ベースの声かけです。
まずは話を聞くこと。
そして、もし勉強の話が出たら
「それ面白そうだね」
「難しそうだけど、頑張ってて偉いね」
などの共感を伝えるだけで、子どもは“認めてもらえた”と感じて、
自発的に行動するきっかけになります。
② 子どもの努力を「結果」より「行動」で認める
成績やテストの点にばかり注目すると、
「点が悪いと怒られる」「どうせ自分はダメ」と子どもが思い込んでしまいます。
そうなると、努力を見せようとしなくなり、ますます家庭での会話も減ってしまいます。
大切なのは、行動や姿勢に注目して褒めることです。
・「今日も机に向かってたね、すごい」
・「分からないところを調べてたの、えらいね」
・「毎日コツコツ頑張ってるの見てるよ」
こうした声かけは、子どもの“自己肯定感”を育てる栄養になります。
テストの結果が悪くても、「努力してたのはちゃんと伝わってるよ」と伝えることで、
「もう一度頑張ってみよう」と前向きな気持ちを持たせることができます。
③ 勉強する環境づくりは“静かさ”より“安心感”
勉強部屋を与える、静かな空間を作る──もちろん大切ですが、
それ以上に重要なのが「子どもが安心して勉強できる雰囲気」です。
家族の誰かがイライラしていたり、否定的な言葉が飛び交う空間では、集中できません。
・食事中に学校や勉強の話を自然にできる空気
・疲れているときに無理に叱らない余裕
・自分のペースで学べるように時間を確保する
こうした“家庭の温度”が、子どもの学びへのモチベーションに直結します。
勉強を「頑張っている姿を見せる場」ではなく、
「失敗しても受け入れてもらえる場」にすることが理想です。
④ すべてをサポートしようとしなくていい
「教科の内容が分からない」「進路情報に疎い」
と悩む保護者の方も少なくありません。
でも大丈夫です。全部を教える必要はありません。
むしろ、親が先生のように関わるより、
「一緒に学ぼう」
「応援してるよ」
というスタンスのほうが、子どもにとっては心の支えになります。
・「この問題難しいね、どうやって解いたの?」と聞く
・「そのテスト、どう対策してるの?」と話を広げる
・「よかったら調べてみようか?」と一緒に調べる
このような姿勢を見せるだけでも、子どもは「頼っていいんだ」と感じるようになります。
⑤ 親も“無理なく続ける”姿を見せる
習慣は、言葉より“背中”で伝わります。
親自身が、毎日少しでも何かを続けている姿(読書、ストレッチ、日記など)を
見せていると、子どもも「自分もやってみよう」と思うようになります。
大切なのは、
「勉強しなさい」ではなく「勉強することって自然なんだ」と伝わる環境を作ること。
だからこそ、保護者が無理せず自然体で過ごすことが、実は一番の教育なのです。
自信を育てる小さな成功体験の積み重ね
「どうせやってもできないから…」
「自分は頭が悪いんだと思う」
そんな風に、自信をなくしてしまっている中学生は本当に多く、
それが「勉強がわからない」という状態をより深刻にしています。
でも実は、子どもたちが本当に欲しいのは、
“テストで100点”よりも、“やったらできた”という実感です。
つまり、小さな成功体験を積み重ねていくことで、
自信はゆっくりでも確実に回復し、やる気も戻ってくるのです。
ここでは、自信を育てるために今日からできる5つの方法をご紹介します。
① 1問でも「自力で正解できた」体験を大切にする
「1ページ終わった」
「1問だけど正解できた」
「昨日より早く終われた」
これらはすべて立派な成功体験です。
勉強が苦手な子ほど、こうした“小さな前進”を大切にしましょう。
特に、「誰にも頼らず、自分の力でやり切れた」という感覚は、
子どもの自己肯定感に直結します。
「お母さんに言われたからやった」ではなく、
「自分で決めて、自分でやった」ことが何よりも大事です。
② 「できたことノート」をつけてみよう
毎日の勉強後に、「今日できたこと」をノートやアプリに記録するだけでも、
自信の種が育ちます。内容は簡単で構いません。
・英単語5個覚えた
・数学の苦手な問題が解けた
・わからないことを質問できた
このように、「できなかったこと」ではなく、
「できたこと」にフォーカスする習慣が、前向きな思考を育ててくれます。
1週間後、1ヶ月後に見返して、「こんなに頑張ってたんだ」と気づけた瞬間、
それは確かな“自己信頼”へと変わります。
③ 小テストや確認問題を“わざと”多めに活用する
学校や塾の小テストを、「できなかったら嫌だ」と避けたくなる子も多いですが、
むしろ積極的に活用すべきです。
なぜなら、小テストは「小さく成功するためのチャンス」だからです。
満点を取る必要はありません。
「前回より点が上がった」「1問多くできた」「初めて暗記した内容が出た」
そういった“小さな前進”を実感できる場が、小テストや確認問題には詰まっています。
④ 「他人と比べない」視点を育てる
「〇〇ちゃんはいつも90点なのに」
「自分だけできない」と感じると、
自信はどんどんすり減っていきます。
だからこそ、「比べる相手は“昨日の自分”」という考え方を大切にしましょう。
保護者や先生が「〇〇と比べない」「あなたのペースでOK」と伝えることで、
子どもは安心して努力を継続できるようになります。
特に学力の伸びが緩やかな子には、
「よくがんばってるね」「成長してるよ」と、
プロセスを認める言葉を多くかけてあげてください。
⑤「1日1つ成功する」ことだけ意識する
自信を育てるには、1日1個だけでも「自分を褒められること」をつくるのが効果的です。
たとえば…
・苦手な教科に3分だけ挑戦した
・宿題を先に済ませた
・ノートをいつもより丁寧に書けた
それだけで十分です。
自分の中で“今日は成功した”と感じられることがあれば、
次の日も頑張ろうという気持ちが生まれます。
まとめ|「勉強がわからない」は変えられる悩みです
ここまで、中学生が「勉強がわからない」と感じてしまう原因と、
それを乗り越えるための具体的な解決策を5つの視点から詳しく解説してきました。
最後に、これまでの内容を振り返りながら、
改めて大切なポイントをまとめておきましょう。
勉強がわからない“本当の理由”は5つある
「やる気がないから」「頭が悪いから」
そんなふうに自己否定してしまいがちですが、実際にはそうではありません。
多くの中学生が勉強につまずいてしまうのは、以下の5つの理由が重なっているからです。
- 勉強方法が分からない(教科別のやり方を知らない)
- 勉強環境が整っていない(集中できる空間・時間がない)
- 勉強の習慣がついていない(続ける仕組みがない)
- スマホ・ゲームなどの誘惑が多すぎる(自制できない)
- 自信の喪失・自己肯定感の低下(頑張る意味を見失っている)
どれも本人だけでは気づきにくい原因ですが、
ひとつひとつ丁寧に対応すれば、状況は確実に変わります。
“やり方”がわかれば、勉強は少しずつできるようになる
勉強のやり方は、実は学校ではあまり教えてくれません。
けれど、やり方さえ分かれば、
「やってみようかな」「できるかもしれない」と前向きな気持ちが芽生えます。
- 英語は音読+単語の積み重ね
- 数学は「解く→直す→もう一度解く」反復学習
- 国語は“読む+まとめる”で理解力アップ
- 理科・社会は“図や流れで理解する”のがコツ
こうした教科ごとのアプローチが明確になれば、
「わからない」は「やればできる」に変わっていきます。
大切なのは、“完璧”ではなく“継続できる工夫”
「1日1時間やらなきゃ」「5教科すべてやらなきゃ」と思うと、
勉強はどんどん苦しくなります。けれど、1日5分、1問だけでもいいんです。
“続けられる形”を作ることこそ、学習の成功の秘訣です。
・毎日やる時間を決める
・スマホを遠ざけて集中する環境をつくる
・終わったらシールや記録を残す
・「今日はできた!」を積み重ねて自信に変える
このような小さな工夫を続けることで、勉強は“日常の一部”になっていきます。
家庭での関わり方が“学びを支える土台”になる
保護者の皆さんにできることは、「教える」ことではなく、「応援する」ことです。
・結果よりも努力や過程を認める
・声かけは「勉強しなさい」より「どうだった?」
・「一緒に頑張ろうね」のスタンスで関わる
・失敗しても大丈夫と思える安心感を与える
子どもは、誰かに見守られていると感じたとき、自分の力を最大限に発揮できます。
「自分でもできる」と思えたら、勉強は自然に進むようになる
最終的に、勉強の“できる・できない”を分けるのは才能ではありません。
「わかるかも」「できるかも」と思えるようになる小さな体験の積み重ねこそが、
未来を変える力になります。
そしてその“最初の一歩”は、いつだって今日から踏み出せます。
まずは無料相談で「悩みの原因」と「解決策」を一緒に見つけませんか?
ここまで読み進めてくださった方の多くは、
「子どもが勉強につまずいている」
「どうしていいかわからない」
「でも、今のままじゃ何か不安…」
そんなモヤモヤを感じているのではないでしょうか?
その気持ちは、とてもよくわかります。
そして、それは決して「親の責任」でも「子どもの努力不足」でもありません。
中学生が勉強につまずく背景には、必ず何かしらの“原因”があります。
そしてその原因は、意外と本人にも保護者にも“見えづらい”ものです。
だからこそ私たちは、「まず話を聞くこと」を何よりも大切にしています。
学習習慣ゼロの子が、自分から机に向かうようになるまで
個別指導塾ワイザーには、
もともと「勉強が嫌い」「何をどうやればいいか分からない」
という生徒が多く通っています。
ですが、私たちは「やる気を出させる」ことを目指してはいません。
やる気があっても、何をすればいいか分からなければ、誰でも動けないからです。
だからワイザーでは、
・毎日やるべきことを「1日単位」で明確に提示
・スマホ感覚で操作できる専用アプリで、毎日のタスクをチェック
・学習報告・相談はすべてLINEでOK
・勉強に「つまずく前」に声をかける伴走型のサポート
このように、“仕組み”の力で子どもの行動を自然と変えていくのが特徴です。
「やる気がないからできない」ではなく、
「“どうやればできるか”を一緒に考える」
それがワイザーのスタイルです。
「無料相談」では、営業なし・ヒアリング重視
ワイザーの無料相談では、入塾を前提としたご案内は一切ありません。
私たちの目的は、「今の悩みの原因を一緒に言語化すること」です。
たとえばこんなことをヒアリングしています:
・毎日の生活リズム(起床〜就寝)
・スマホ・ゲームなどの使用状況
・勉強の進め方やつまずきポイント
・保護者として感じている不安やご希望
・成績・テスト結果の推移(分かる範囲でOK)
これらをもとに、
「こういうつまずきがありそうです」
「こんな対処法が考えられます」と、
個別にアドバイスをさせていただきます。
そしてもし、ワイザーのサポートが合いそうだと感じていただけたら、
改めて体験学習や入塾をご検討いただければ大丈夫です。
「まだ塾に通わせるほどでは…」という方にもおすすめです
ワイザーの無料相談は、
「今すぐ塾に通わせたい」という方だけのものではありません。
・まずは家庭で何ができるかを知りたい
・ほかの塾と迷っているので比較材料が欲しい
・子どもにどんな学び方が合っているか、専門家の意見を聞きたい
そんな気持ちを持っている方こそ、ぜひ一度お気軽にご相談ください。
お話をするだけでも、きっと“今すべきこと”が見えてくるはずです。
▼無料相談はこちらをクリック▼



