
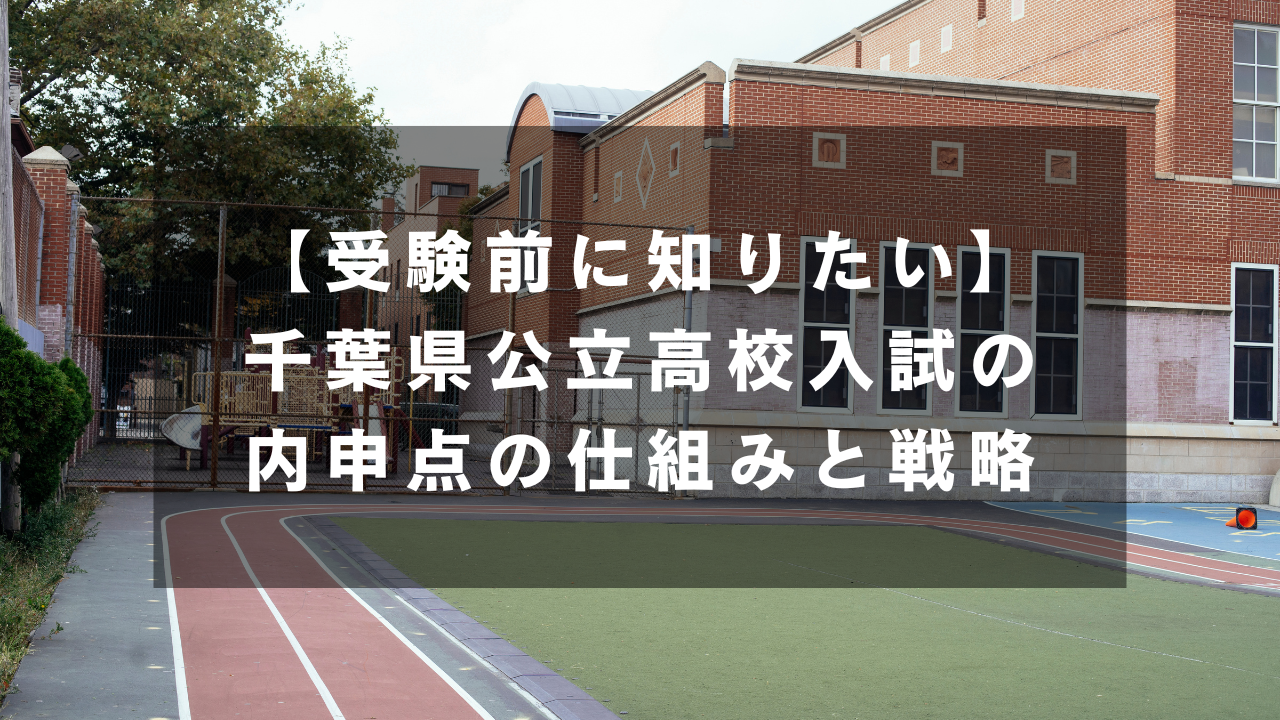
「千葉県の公立高校入試って、結局“内申点”ってどれくらい大事なの?」
「通知表に書かれている数字が、そのまま合否に関わるってほんと?」
そんな疑問や不安を抱えている保護者の方は多いと思います。
とくに2026年度入試に向けて、中2や中3を迎えるお子さんがいるご家庭では、
「まだ受験までは時間があるけど、そろそろ本格的に準備しないと…」
「成績の上げ方がわからないし、内申点ってどうすれば伸ばせるの?」
と、日々の生活の中で“見えない不安”を感じる方もいるのではないでしょうか。
千葉県の公立高校入試は、
都道府県によっては中3の成績だけで判断される地域もあるなかで、
中1・中2・中3の通知表(内申点)がすべて評価対象になります。
つまり、「もうちょっと頑張れば間に合う!」というチャンスもある一方で、
「何となく過ごしてきた日々」がそのまま“点数”として現れる厳しさもあります。
でも安心してください。
千葉県の入試制度は、きちんと仕組みを理解し、ポイントを押さえた対策をすれば、
誰でも十分に対策が可能です。
この記事では、千葉県公立高校入試の
内申点の仕組み・ルール・高校ごとの配点の違いをはじめ、
2025年度の入試を振り返りながら、
2026年度入試に向けた保護者としての具体的なサポート方法や、
今からできる対策を徹底解説していきます。
「テストだけ頑張れば大丈夫?」
「うちの子、提出物とか苦手だけど大丈夫かな?」
「今からでも内申点って上がるの?」
そんな悩みやモヤモヤに一つひとつ丁寧にお答えしていきますので、
どうぞ安心して最後まで読み進めてみてくださいね。
2025年度入試の振り返り
2025年度の千葉県公立高校入試では、制度上の大きな変更はありませんでしたが、
入試の実態や受験生・保護者の動向を見ると、いくつか見逃せない傾向や変化が見られました。
ここでは、2026年度の受験を控えるご家庭が知っておくべきポイントを4つにまとめてご紹介します。
① 内申点の重要性がより明確に
2025年度も、多くの高校でK値を1.5〜2に設定しており、
これは通知表の評定(内申点)が合否に与える影響が非常に大きいことを意味します。
特に、学力試験で思うように点が取れなかった生徒でも、
「内申点で逃げ切れた」という合格例が目立ちました。
また、逆に「学力試験は上出来だったのに、内申が足りずに落ちてしまった」という声も。
これはまさに、通知表を甘く見ずに日々の積み重ねを大切にするべきだという“警告”とも言えます。
② 学校設定検査を課す高校が増加傾向
作文・面接・自己表現・グループディスカッションといった
学校独自の検査を導入する高校が増えたことで、
受験は「テストと通知表の勝負」だけではなくなっています。
これらの検査は、学力では測れない思考力・表現力・人間性を評価するもので、
特にK=2のような「内申+人物重視」の高校で重視される傾向が強まりました。
今後もこの流れは続くと予想されるため、学校生活全般の充実や、
面接練習・作文対策も早期に視野に入れておくと安心です。
③ トップ校は学力重視傾向を維持
県内の人気トップ校(例:千葉高校・船橋高校・薬園台高校など)では、
引き続きK=0.5〜1という学力検査を重視する設定が主流でした。
このため、「通知表で満点近く取っていても、テストで点を取れなければ厳しい」という、
“実力本位”の選抜が行われています。
ただし、それでも通知表の評価はゼロにはなりません。
トップ校を目指すご家庭でも、
「授業態度・定期テスト・提出物」は、やはり当たり前に大事ということです。
④ 中堅〜準上位校での“僅差勝負”が顕著に
千葉県内の中堅〜準上位校では、
調査書と当日点が接戦になるケースが非常に多く見られました。
「総合点で1〜2点の差で不合格」「あと1点で逆転できたかも…」
といった声も各所で聞かれました。
こうしたケースでは、
「実技教科で4がついていれば…」
「あと1枚プリントを出していれば…」
といった些細な積み重ねが、合否を分ける決定打になることも珍しくありません。
特にK=1.5〜2の学校では、
通知表を制する者が受験を制すると言っても過言ではありません。
だからこそ、2026年度に向けた受験準備は、
「通知表でしっかり稼ぐこと」が最優先です。
今からなら、まだ間に合います。
むしろ、今からやるからこそ、差がつくのです。
千葉県の公立高校入試における「内申点」の仕組み
千葉県の高校入試において、「内申点」はとても重要な位置づけにあります。
特に、2021年度に入試制度が一本化されて以降、
学校ごとの内申点の配点比重(K値)に注目が集まっています。
まずは「内申点とは何か?」から、丁寧に仕組みを確認していきましょう。
① そもそも「内申点」って何?
「内申点」とは、中学校での学習の積み重ねをもとにした
「通知表の成績」を点数化したものです。
千葉県の場合、中学1年生〜中学3年生までの9教科×5段階評価(評定)が
評価対象となります。
つまり、
・1年生:9教科 × 5点満点 = 45点満点
・2年生:9教科 × 5点満点 = 45点満点
・3年生:9教科 × 5点満点 = 45点満点
合計で最大135点満点が「内申点の基本点」となります。
ここで重要なのは、「中3の通知表だけじゃない」ということ。
多くの保護者の方が「3年生になってから本気出せばいい」と思いがちですが、
千葉県では1年生・2年生の評定も本番に直結するのです。
たとえば、1年生の数学で「3」だった場合、そのまま本番の得点に置き換えると
「1点〜2点の差」として積み上がります。
3年間での“取りこぼし”があると、後から大きな差になることもあるのです。
そしてもうひとつ大事なのが、「評定=テストの点数だけで決まらない」ということ。
授業態度、提出物、小テスト、グループ活動、発表、ノートの取り方…
こういった“日常の積み重ね”が、すべて評定に影響を与えています。
つまり、内申点とは「テストの結果」ではなく、
「3年間の勉強の姿勢そのもの」が数字になって表れたもの。
そしてそれが、高校受験における“もう一つの得点”として扱われているのです。
② 高校ごとに変わる「K値」で内申点の重みが違う
千葉県の公立高校入試では、
通知表の評定(最大135点)をそのまま使うわけではありません。
各高校が設定する「K値(ケーち・係数)」によって、内申点の重み付けが変わります。
K値とは、簡単に言えば「内申点に何倍の価値を持たせるか」を決める数字です。
具体的には次の通り
・K=1.0 → 評定135点をそのまま使用(内申・学力のバランス型)
・K=2.0 → 評定を2倍して270点満点に(内申点を重視する高校)
・K=0.5 → 評定を半分にして67.5点に(学力検査重視の高校)
つまり、同じ成績でも志望校によって内申点の扱われ方がまったく違うということです。
たとえば
・K=2の高校に出願 → 1点の評定差 = 2点の入試得点差に
・K=0.5の高校に出願 → 評定1点差 = 0.5点の差にしかならない
このように、K値が大きい高校ほど「通知表の数字が超重要」になり、
K値が小さい高校ほど「テストの点数で勝負」となります。
どんな高校がどんなK値を設定しているの?
・学力重視の進学校(千葉・船橋・薬園台など)はK=0.5〜1.0が主流。内申よりも「当日の点数で決まる」傾向。
・中堅〜準上位の高校はK=1.0〜1.5が多く、内申と学力のバランス型。
・内申重視の高校(千葉南・我孫子東・市立習志野 など)ではK=1.5〜2.0を設定し、通知表をしっかり見て選抜。
実際、K=2.0の高校では、たった1教科で評定「4」→「5」に上がっただけで、
入試得点換算で+10点になることも。
これは当日点で10点分挽回するのと同じくらい大きな意味を持ちます。
K値は毎年、各高校の選抜要項に明記されますので、
志望校のK値は必ずチェックしておくことが大切です。
「うちの子、テストは得意だけど通知表がイマイチ…」という場合は、
K=0.5〜1.0の高校を中心に検討するのも一つの戦略ですし、
「テストでミスしやすいタイプだけど普段は真面目に頑張っている」という子は、
K=1.5〜2.0の高校が向いているとも言えます。
③ 内申点に「+α」で加点されることもある
千葉県の高校入試では、内申点(最大135点)に加え、
高校独自の判断で「調査書の加点評価」が行われることがあります。
これは、通知表の評定とは別に、
学校生活での頑張りや活動実績などを評価する仕組みです。
この「+α」の加点には、以下のような要素が含まれることがあります。
加点対象となる代表的な活動例
部活動での実績・継続年数
→ 3年間継続していれば+5〜10点など、評価対象になる高校も
生徒会活動への参加
→ 副会長や書記などの役職経験がある場合、評価アップ
資格・検定の取得
→ 英検(準2級以上)、漢検、数検などを取得していると、プラス評価になる高校も(特に英検は評価されやすい傾向)
ボランティア活動や表彰歴
→ 学校外での地域活動や、作文コンクールなどの入賞も一部高校では評価対象になることがあります
出席状況や生活態度
→ 欠席・遅刻がほとんどない/生活記録が良好であることが加点対象になる高校も
加点される点数の目安は?
高校や年度によって異なりますが、最大で50点程度の加点枠を設けている高校もあります。
ただし、全員が一律に加点されるわけではなく、
内容の評価・重み付けも高校ごとに基準があります。
たとえば
・「3年間部活を継続+英検準2級取得+皆勤賞」→ 合計で30点程度加点されるケースも
・「英検3級+生徒会参加」→ 10点程度の加点にとどまる場合も
加点基準は募集要項や学校説明会などで明らかにされることが多いので、
受験校の情報は必ず確認しましょう。
この加点をうまく活かすには?
・中学1年生から、コツコツと“継続的に”活動していることが大切です。
「3年生の夏に部活をやめたけど、途中まではやっていた」という場合でも、
一部加点の対象になることがあります。
・英検・漢検・数検の準備は計画的に。
3年生の秋頃までに、準2級など評価されやすい級を取得しておくと安心です。
・“表に出ない努力”も評価されることがある!
定期的なボランティアや、地域の活動(子ども会、スポーツクラブなど)も、
面接や調査書でPRできる材料になります。
内申点=通知表の数字だけではありません。
日頃の学校生活の「見えない頑張り」も、しっかり見てくれる高校はたくさんあります。
受験生本人だけでなく、保護者の方も一緒に
「どんな実績があったっけ?」と振り返ってみることが大切です。
④ じゃあ、どの高校が内申をどのくらい見るの?
「内申点が大事って分かったけど…結局、うちの子が目指している高校では、
どのくらい見られるの?」
そんな疑問を持たれている保護者の方も多いはずです。
実は、千葉県では各公立高校ごとに「どの程度、内申点を重視するか(=K値)」や
「加点要素の有無」などを明文化して公表しています。
この情報は、千葉県教育委員会が発表する「入学者選抜実施要項」や各高校の
「選抜・評価方法」資料にしっかり書かれているんです。
例:K値と評価比重の一例(※過去の実例ベース)
| 高校名(例) | K値 | 備考 |
| 千葉高校(普通科) | 0.5 | 学力検査重視、面接なし |
| 船橋高校(普通科) | 0.5 | 独自問題あり、超実力勝負型 |
| 薬園台高校(普通科) | 1.0 | 学力+内申バランス型 |
| 市立習志野高校(総合) | 1.5 | 内申点や活動記録も重視 |
| 千葉南高校(普通科) | 2.0 | 内申重視。部活・検定加点あり |
※年度や学科ごとに異なる可能性があります。必ず最新の選抜資料で確認してください。
チェックすべきは「選抜方法Ⅰ・Ⅱの配点割合」
千葉県では、多くの高校で「選抜方法Ⅰ(定員の80%)」と
「選抜方法Ⅱ(残り20%)」の2段階選抜を導入しています。
・Ⅰでは通常のK値で評価(例:K=1なら内申点はそのまま135点でカウント)
・Ⅱでは高校独自にK値や独自検査の配点を変更できるため、バランス型から内申重視型/学力重視型へ“寄せる”ことが可能です。
たとえば、選抜方法Ⅱでは
・学力検査の得点を1.5倍にする高校
・K値を2.0に引き上げて内申を重視する高校
・面接や作文の点数配分を大幅に増やす高校
など、選抜に「高校ごとの色」がはっきりと現れます。
じゃあ、どうやって調べればいい?
- 千葉県教育委員会の公式サイトにアクセス
- 「令和○年度 千葉県公立高等学校 入学者選抜・評価方法一覧」を確認
- 志望校の「K値・加点要素・選抜方法Ⅰ・Ⅱの配点」をチェック!
また、各高校が開催する「学校説明会」や
「進学フェア」で配布される資料にも詳しく書かれていることがあります。
可能であれば、説明会に参加して直接質問するのが一番確実です。
「何となく志望校を決める」のではなく、
“戦略的に”内申点を活かせる高校を選ぶことが、合格のカギになります。
内申点と当日点の比率(選抜方法の違い)
「うちの子、内申はそこそこあるけど、当日点で勝負できるのかな…」
「この通知表で受かる?それとも学力重視の高校を狙うべき?」
そんなふうに悩んでいるご家庭にとって、
「内申点と当日点の比率」がどのように扱われるのかを知ることはとても重要です。
千葉県の公立高校入試は、
一律ではなく高校ごとに“評価の重み”が異なるシステムです。
ここではその仕組みを、わかりやすく解説していきます。
① 配点の基本構成:3つの要素の合計点で勝負!
千葉県の高校入試では、主に以下の3つを合計して合否が決まります。
- 学力検査(5教科×100点=500点満点)
- 調査書点(内申点:最大135点 × K値)
- 学校設定検査(面接・作文・自己表現・実技など:最大150点程度)
この合計点により、受験生が一列に順位づけされて合否が決まります。
ポイントは、「①②③の比重をどうするかは高校ごとに異なる」ということ。
だからこそ、「自分の強みがどこにあるか」を見極めたうえで、
高校選びと対策を進めることが合格への近道になります。
② 二段階選抜(選抜方法Ⅰ・Ⅱ)の導入が標準に
千葉県では、ほとんどの高校で「選抜方法Ⅰ・Ⅱ」
という二段階選抜方式を採用しています。
・選抜方法Ⅰ(80%):
基本の配点(500点+K値×内申点+独自検査)で順位付けし、定員の8割を決定。
・選抜方法Ⅱ(20%):
高校ごとに比重を変えて再評価。
たとえば「学力検査を1.5倍する」「面接を重視する」「K値を変える」など。
この第二段階の方針は、高校の個性や理念に直結する部分で、
「この高校はこういう生徒を求めている」という意志が見えるところでもあります。
③ 当日点と内申、どっちが重視されている?
これも高校ごとに異なりますが、目安として以下のような分類ができます。
・学力検査重視型(トップ校に多い)
→ K値が0.5〜1.0。内申は参考程度、当日点と独自検査で勝負。
→ 例:千葉高、船橋高、薬園台高など
・バランス型(中堅〜人気校に多い)
→ K値が1.0〜1.5。内申と当日点をバランスよく見て選考。
→ 例:八千代、検見川、千葉女子など
・内申重視型(実技・人物重視の高校)
→ K値が1.5〜2.0。提出物、授業態度、面接の影響大。
→ 例:市立習志野、千葉南、市立千葉など
このように、高校ごとの“合格スタイル”を見て、
自分の特性に合った戦い方を選ぶのがとても大切です。
④ 模試の偏差値だけでは判断できない!
多くのご家庭が志望校を決める際に模試の偏差値を参考にしますが、
実際には「模試で合格圏内でも落ちる」「圏外でも受かる」というケースが毎年あります。
これは、模試が“当日点”の目安にはなっても、
「内申点」や「学校設定検査」の影響を反映しきれないからです。
ですので、塾の先生や学校の進路指導とも連携しながら、
必ず「当日点だけじゃない合否基準」を意識するようにしましょう。
通知表のつけ方(評価の観点)
「テストの点は悪くないのに、なんで通知表は“3”なの?」
「先生に気に入られないと“5”ってつかないの?」
そんな疑問を感じたことのある保護者の方は多いかもしれません。
でも実は、通知表(評定)がつけられる仕組みは明確な“ルール”に基づいています。
ここでは、そのルール=「評価の観点」をわかりやすくご説明します。
① 評定は“テストの点数だけ”では決まらない!
千葉県を含む全国の中学校では、通知表の評定(1〜5段階評価)は、
文部科学省が定める4つの観点を総合してつけられています。
具体的にはこの4つです
- 知識・理解(教科内容の理解度)
- 技能(実技や計算などの操作能力)
- 思考・判断・表現(応用力や表現力、記述力)
- 関心・意欲・態度(授業態度や提出物、積極性)
このうち、テストの点数に強く反映されるのは
「知識・理解」や「思考・判断・表現」の観点ですが、
通知表の評定はそれだけでは決まりません。
提出物を丁寧に出しているか、ノートは整っているか、授業中の姿勢はどうか、
発言の意欲はあるか…
こうした「日々の姿勢」も含めて総合的に評価されるため、
「テストは90点でも“3”」ということも実際にあり得るのです。
② 観点別評価は通知表にもヒントがある!
最近では、多くの中学校で「観点別評価」が◎・◯・△などの記号で記載されており、
各教科の何が良くて、何がもう一歩だったのかが見えるようになっています。
たとえば
・国語:知識◎、表現◯、態度△ → → 評定「3」
・理科:理解◯、技能◯、意欲◎ → → 評定「4」
このように、記号評価を注意深く見ると、
どこを改善すれば次の評定につながるかが見えてきます。
通知表は“ただの結果”ではなく、“次の対策のヒント”でもあるのです。
③ 評定には「学年内の相対評価」の側面もある
よく誤解されがちなのが、「頑張ったから5がつく」という考え方です。
実際には、評定は学年全体の中での相対的な評価となるケースがほとんど。
つまり、たとえば数学の評価で
学年に「ものすごくできる子」が10人いれば、
その中での上位3〜4人に「5」がつき、次の層に「4」、平均層が「3」になる…
といった“枠”のようなものがあることも。
そのため「90点で4、でもクラスの友達は95点で5」なんてことも起こりうるわけです。
これは“頑張りが報われない”という話ではなく、
「同じく頑張っている子が多い中での評価」だと理解しておく必要があります。
④ 評定は誰かの感情でつけられるわけではない
「先生に嫌われたから3をつけられたのでは?」と不安になる声も聞きますが、
現在の評価制度では客観的な記録や観点に基づいて評価することが原則です。
教師側も、指導要録に記録を残す関係上、
テスト・提出物・授業態度・観点ごとの評価シートなどをもとに、
説明責任の取れる形で評定を決定しています。
だからこそ、「なんとなく」でつく評定ではないということを理解しておくと安心です。
内申点アップのためにやるべきこと
「内申点が大事なのはわかったけど、どうやって上げればいいの?」
「うちの子、テストは頑張ってるけど“5”が取れない…」
そんなお悩みにお応えすべく、
ここでは“今すぐできる内申対策”を5つの柱に分けて具体的にご紹介します。
これを習慣にできれば、通知表の数字は少しずつでも確実に上がります!
① 定期テストで高得点を取る
内申点に最も直結するのが「定期テストの点数」です。
とくに主要5教科(英数国理社)では、中間・期末の点数=知識・思考観点の評価に大きく影響します。
・テスト2週間前からは「毎日30分でもコツコツ復習」をスタート
・目標点を設定する(例:80点以上=◎評価の目安)
・間違えた問題は、必ず解き直しをしてノートにまとめる
また、ワーク提出の内容も評価対象になるので、答えを写すだけでなく、
自分の字で丁寧に書くことが大切です。
② 提出物は“丁寧に・期限通りに”
内申点アップの“即効薬”とも言えるのが、提出物の管理です。
・ワーク・プリント・レポートは、中身の丁寧さと提出期限の厳守がポイント
・書き直しが指定された場合は、きちんと対応することも評価対象に
・提出物を「表紙・タイトル・見やすい構成」にするなど、先生が見やすい工夫も◎
たった1枚の提出物で、観点評価「◯→◎」に変わることもあります。
特に実技教科では、日頃の課題提出が評定に直結しやすいので要注意です。
③ 授業中の姿勢とリアクションを見直す
「授業中、しっかり聞いてるし、悪目立ちしてないから大丈夫」…と思っていませんか?
実は、“何もしていない”は“評価されにくい”**ということでもあります。
・ノートは「板書を写す」だけでなく、自分の言葉で整理する
・先生の問いかけには、うなずく・目を合わせる・小声で反応するなど“リアクション”を意識
・わからない時は、「分からない」と正直に言う姿勢がプラス評価に
先生方は「学びに参加しているかどうか」をしっかり見ています。
静かにしている=真面目 ではなく、前向きな姿勢が大切です。
④ 発言・質問は“1回でもOK”
「手を挙げるのが恥ずかしい」「間違えたら嫌だな…」という気持ちは誰にでもあります。
でも、実は“月に1回の発言”でも通知表に影響を与える”と言われているんです。
・授業中に答えを言えそうなときは勇気を出して発言
・質問は授業後や休み時間でもOK。意欲としてカウントされます
・実技教科でも「発表・意見を出す場面」を逃さない
発言は量より“姿勢”。
「やろうとする姿勢」が見られれば、それだけで評価にプラスになります。
⑤ 欠席・遅刻はできるだけ避ける
調査書には出欠の記録も明記されるため、内申点に直接関係なくとも、
学校によっては選抜資料として考慮される場合があります。
・体調管理をしっかりと。夜更かしや寝坊には注意
・遅刻癖があると、担任の先生からの所見にも影響が出ることも
・欠席する場合は、保護者からの連絡をきちんと入れておく
どうしてもやむを得ない理由があるときは、先生に事情を説明し、
必要があれば所見欄に考慮事項を書いてもらうことも視野に入れましょう。
これらはどれも、「才能」や「センス」ではなく、
“やる気と行動”で必ず改善できるポイントです。
2026年度の入試動向と対策
「今のうちに、どんな準備をしておけばいいの?」
「2026年度の入試は、今までとどう違うの?」
そんな疑問をお持ちの方のために、
ここでは最新の傾向をもとにした入試の動きと今からの具体的対策を解説します。
① 制度上の大きな変更はない見通し
2021年度の大きな制度改訂(前期・後期の一本化、二日制の学力検査など)以降、
千葉県の入試制度はおおむね安定しています。
2026年度入試(令和8年度)についても、
現時点では大幅な制度変更の予定は公表されていません。
ただし、各高校の配点設定や独自検査の有無など、
“高校ごとの選抜方法”には毎年小さな見直しがあるため要注意です。
特に、K値の変更や、面接・作文などの配点比率が変わることもあるので、
必ず秋以降に発表される最新資料をチェックしましょう。
② “人物重視”の選抜がさらに強まる流れ
2025年度入試では、
学校設定検査(面接・作文・自己表現など)を実施する高校が増加しました。
これは今後も続くと考えられており、「学力+内申点」だけではなく、
生徒の“人となり”や“思考力・表現力”を評価する傾向が高まっています。
たとえば
・自己表現で「自分の長所や将来の夢」を語る場面
・作文で「社会問題への自分の意見」を書く課題
・グループワーク型の面接で「協調性や発言力」を評価されるケース
このような要素に備えるには、
日常から「自分の意見をもつ」「考えを言葉にする」練習が効果的です。
③ 実技教科の評価も軽視できない
内申点に含まれる9教科には、
音楽・美術・保健体育・技術家庭の実技4教科も含まれています。
特にK=2の高校では、
実技教科1点アップが入試得点換算で+10点にもなることがあります。
「運動が苦手」「絵が下手」といった技術面よりも、
・一生懸命取り組む姿勢
・課題の提出や準備物の忘れがないか
・授業で積極的に参加できているか
などの“態度評価”がウエイトを占めるため、
ここはむしろ“努力次第で差がつけやすい分野”と言えます。
④ 英語力・記述力を問う学校がじわじわ増加中
一部の進学校では、記述問題を重視する入試傾向が見られます。
英語では長文の要約や意見記述、
国語でも文章に対する自分の考えを述べさせる設問が増えてきています。
これに対応するには、
・英語:日々の音読や多読、英検への挑戦
・国語:本を読む習慣と、要約・感想の練習
・面接対策:ニュースや社会問題に対して「自分はどう思うか」を話す訓練
など、“考える力+表現する力”のトレーニングが大切です。
受験は、「本番一発勝負」ではなく、「毎日の積み重ね勝負」。
内申点を意識しながら、今のうちからできることに一つひとつ取り組んでいくことが、
2026年度入試の最大の戦略です。
保護者ができるサポート
「子どもに任せておけばいいのかな…」
「干渉しすぎるのも良くない気がするけど、どう関わればいい?」
受験期の保護者は、つねに“関わりすぎず、
でも見守りすぎない”という絶妙なバランスが求められます。
とはいえ、やるべきことは確かにあります。
ここでは、「内申点アップ」や「受験対策」において
保護者ができる4つの具体的な支援方法をお伝えします。
① 学習リズムを整えるサポート
内申点は「毎日の積み重ね」で決まります。
そのベースになるのが、規則正しい生活と勉強習慣です。
・起床・就寝時間を安定させる
・スマホやゲームの時間をルール化する(時間を決めて管理)
・勉強のタイミング(夕食後/寝る前)を習慣化する
・リビング学習 or 個室学習、どちらが集中できるか環境を整える
保護者が「一緒に計画を立てる」ことで、
お子さんも「見てもらっている安心感」や「自分のやる気スイッチ」に繋がります。
② 学校との連携を意識する
通知表や内申点は、担任の先生が評価をつけます。
だからこそ、学校との関係性を良好に保つことも大切です。
・三者面談では、評価の付け方や改善点を具体的に質問する
・提出物の状況や授業中の様子について、必要に応じて連絡帳や電話で相談
・学校行事・保護者会への参加で「教育に関心がある家庭」と伝わることも効果的
また、欠席や遅刻がどうしても避けられない事情がある場合は、
先生に事情を説明しておくと、調査書所見で配慮されることもあります。
③ 声かけ・メンタルケアのサポート
「どうせ頑張っても評価上がらないし…」
「なんでこんなにやってるのに成績が伸びないんだろう…」
思春期の子どもたちは、内面では不安やプレッシャーを強く感じていることが多いです。
だからこそ、保護者は“結果”ではなく“過程”を見て、こんな声かけを心がけましょう
・「今週も提出物ちゃんと出せたんだね、すごいじゃん」
・「ミスがあっても、自分でやり直してて偉いよ」
・「先生に質問してみたんだ?それって勇気いることだよね」
こうした声かけの積み重ねが、お子さんの“やる気の火種”になります。
④ 食事・睡眠・健康管理
勉強も受験も、体が元気でなければ続けられません。
特に中学3年生は、部活引退後に生活リズムが乱れやすくなるので要注意です。
・食事はなるべく栄養バランスを整える(夜食は軽めに)
・寝不足は集中力と免疫力を下げるので、夜更かしは避ける
・試験直前期は、家族全体で感染症予防(手洗い・加湿など)を徹底
「なんとなく体がだるい」「朝起きるのがしんどい」が続くと、
授業態度や学習習慣にも影響してしまいます。
日常の健康管理こそ、受験支援の“見えない土台”です。
お子さんの将来を一緒に支える“パートナー”として、
できることを少しずつ積み重ねていきましょう。
まとめ:内申点を制する者が、受験を制す。
ここまで、千葉県公立高校入試における内申点の仕組みと戦略を詳しく解説してきました。
千葉県では、中1〜中3までの通知表すべてが内申点として評価され、
さらに高校ごとに異なる「K値」によって重みが変わります。
そしてその内申点は、
当日点と同じように合否を大きく左右する“もう一つの得点”なのです。
内申点は、たった1点の差が合否を分けることもあるリアルな数字です。
「定期テストの点数」「提出物」「授業態度」「発言」「出席状況」
そのすべてが評価対象。
つまり、日々の小さな積み重ねが、最終的に入試の大きな勝負を決めるということです。
今からでも遅くありません
中学1年・2年のご家庭は、今から内申点を意識するだけで将来の受験が大きく変わります。
中学3年のご家庭も、
これからの学期・定期テスト・提出物次第で巻き返すことは十分可能です。
早く動いた者が、有利に受験を戦えます。
学習習慣が身につけば、内申点も自然と上がっていく。
\ お子さまの勉強習慣にお悩みの保護者さまへ /
個別指導塾ワイザーは、「学習習慣の定着」に特化した個別指導塾です。
・365日分の授業外タスク管理
・緻密な個別カリキュラム設計
・自発性を育てるタスク成果報告制度
・生活習慣のヒアリングに基づく学習プランニング
・24時間対応の質問サポート
これらを通じて、お子さまが“自分から勉強できる”ようになる環境を整えます。
結果として、提出物や定期テストの取り組みも変わり、
内申点にも良い変化が自然と現れるケースが多数です。
学習習慣やご家庭でのサポートにお悩みの方、
ぜひお気軽にご相談ください。
▼無料相談はこちらをクリック▼



