
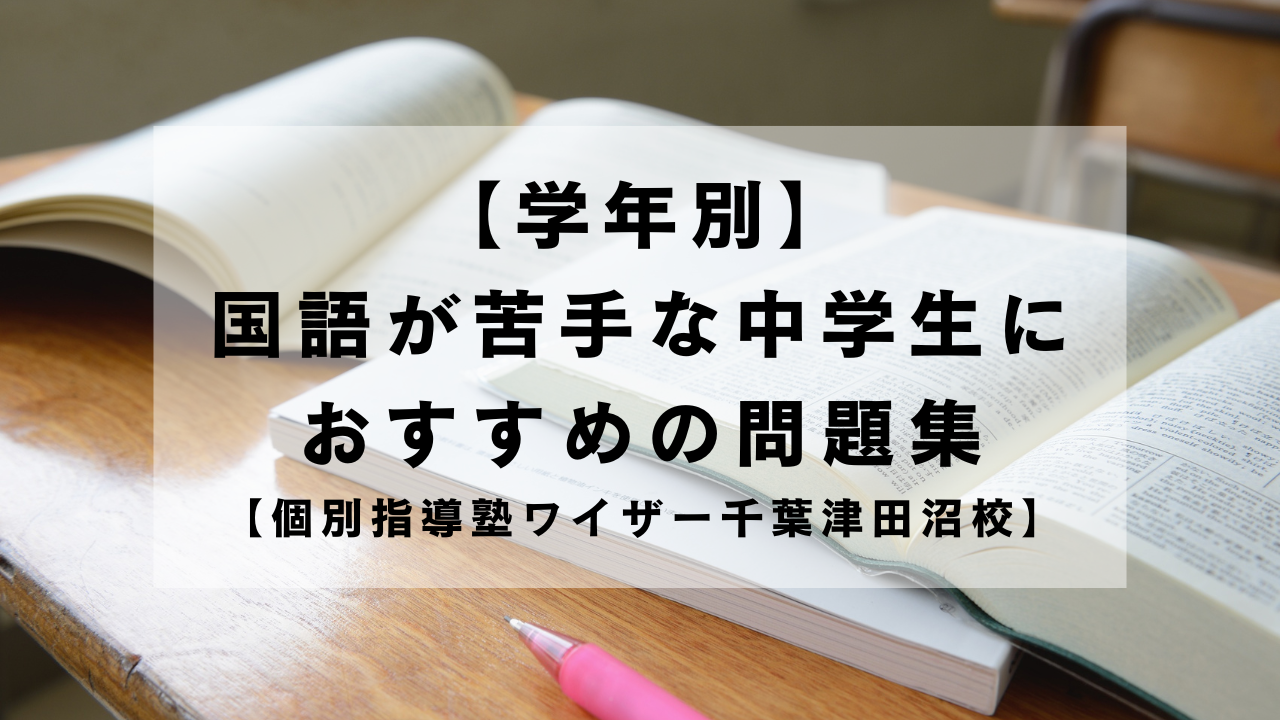
国語が苦手な中学生が増えている理由とは?
「国語の成績がなかなか伸びない」
「読んでも何を聞かれているのかよくわからない」
このような悩みを持つ中学生は、今とても増えています。
数学や英語のように「公式を覚えれば解ける」教科と違い、
国語は一見して勉強のやり方がわかりづらく、
努力がすぐに点数に直結しにくいという特性を持っています。
特に中学生になると、文章の長さも難度も一気に上がり、
小学生時代の「なんとなく読む」「感覚で答える」方法では通用しなくなってきます。
国語が苦手な中学生には、いくつか共通する課題があります。
まず、語彙力の不足。
知っている言葉が少ないと、本文を正確に理解できず、
設問も読み違えてしまうことが多くなります。
次に、文章を論理的に読む力が弱いこと。
接続語(たとえば「しかし」「だから」)や指示語(「それ」「このこと」)の働きを
正しく捉えられず、文章の流れを追えないケースが目立ちます。
さらに、「根拠を持って答える」習慣がないことも大きな問題です。
感覚で答えを選んでしまい、
「なぜその答えなのか」を説明できないままミスを重ねる生徒が多いのです。
こうした課題を克服するためには、ただ文章をたくさん読むだけでは不十分です。
正しい方法で「読解力」「語彙力」「論理的思考力」を鍛える必要があり、
そこに適切な問題集選びが非常に重要な意味を持ちます。
本記事では、
・なぜ国語の成績が伸びにくいのか
・どんな問題集を選べば効果的なのか
・学年別にどの問題集が最適なのか
を具体的に解説し、苦手な国語を得意科目に変えるための第一歩をサポートします。
学年別の課題と対策
中1・中2・中3、それぞれの「国語のつまずきポイント」と今やるべきこと
国語が苦手な中学生と一口に言っても、
学年によって抱える課題や必要な対策は異なります。
それぞれの成長段階に合ったアプローチを取ることが、国語克服への最短ルートです。
ここでは、中1・中2・中3それぞれの特徴と、
今取り組むべき対策を詳しく紹介していきます。
中学1年生向け|国語の課題と対策
中学1年生の段階では、「読めているつもり」になってしまうケースが非常に多いです。
小学校時代は短い物語文や説明文を感覚的に読んで解答できていたため、
きちんと本文根拠を押さえる習慣がないまま中学に進学する生徒が多く見られます。
しかし中学に入ると、文章量が増え、
テーマも抽象的(環境問題、社会問題、歴史論など)になり、感
覚読みでは通用しなくなります。
【中1でつまずく原因】
・語彙力の不足によって文章の意味を正確に捉えられない
・接続語や指示語(それ、このため、しかし)を読み落とす
・問題文に対する根拠探しをせず、直感で選んでしまう
【中1でやるべき対策】
・知らない言葉に出会ったら必ず意味を調べ、語彙力を強化する
・接続語・指示語に注目しながら文章構造を捉える練習をする
・問題演習の際は「なぜこの答えになるのか」を必ず確認する
まずは、「本文中のどこが答えの根拠か」を探しながら読む習慣を身につけることが、
中1の最優先課題です。
中学2年生向け|国語の課題と対策
中学2年生になると、国語の問題内容は一気にレベルアップします。
文章のテーマがさらに抽象的になり、設問も単なる事実確認ではなく、
「筆者の主張を理解し、自分の考えをまとめる」といった思考力型の問いが増えてきます。
また、1問1問の文章量が長くなり、
段落構成や文章全体の流れを把握しなければ正確に答えられない問題も増加します。
この段階でつまずくと、「読むこと自体に時間がかかり、問題を最後まで解ききれない」
という事態にもなりがちです。
【中2でつまずく原因】
・段落ごとの関係性(対比・因果・列挙など)が読み取れていない
・問題文の意図(筆者の主張を問う問題)に答えられない
・本文全体の要旨を捉えず、部分だけで答えてしまう
【中2でやるべき対策】
・段落ごとに「要点」を整理しながら読む練習をする
・質問の意図を意識して、「なぜこの選択肢なのか」を説明できるようにする
・長文に対する抵抗感をなくすため、少しずつ演習量を増やす
中2段階では、「文章全体を俯瞰する力」と「論理的に考える力」の
両方を育てていくことが、国語力向上のカギです。
中学3年生向け|国語の課題と対策
中学3年生になると、国語の勉強は「ただ読む・解く」だけでは通用しなくなります。
特に、模試や高校入試本番では、
本文の理解・設問の意図読み・記述力のすべてが総合的に問われるため、
国語力に差が出やすくなります。
中1・中2までは「なんとなく読んで、選んで」でも部分的には対応できましたが、
中3ではそれが通用しません。
本文に基づく論理的な根拠を持ち、正確に設問に答える力が求められます。
また、選択問題だけでなく、記述問題の比重も高まるため、
「自分の言葉で簡潔にまとめる技術」も必須になります。
【中3でつまずく原因】
・本文の根拠を明確にできず、選択肢に振り回される
・記述問題で何をどうまとめればいいかわからない
・問題を最後まで解ききれず、時間切れになってしまう
【中3でやるべき対策】
・問題演習時には、必ず「答えの根拠となる本文箇所」に線を引きながら読む
・選択肢問題では「なぜこの選択肢が正しいのか」「なぜ他が違うのか」を説明できる練習をする
・記述問題では、「主語+述語」を意識して簡潔にまとめる練習を繰り返す
・模試や過去問を使い、制限時間内で解ききる訓練をする
中3では、「本文根拠に基づく読解力」と「正確な記述表現力」を磨きながら、
実戦を意識したスピード感も同時に身につけていくことが重要です。
中学1年生向け|おすすめ国語問題集紹介
中学1年生は、国語の勉強を本格的にスタートする最初の勝負どころです。
この段階で「国語はなんとなく解くもの」という誤った感覚が身についてしまうと、
以降の中学生活で長く苦しむことになります。
中1の国語対策で重要なのは、語彙力を底上げすること、
そして文章の構造を意識して読む習慣をつけることです。
問題を感覚で読むクセを排除し、
きちんと「本文に沿って読む」姿勢をこの段階で確立することが、
後の成績アップに直結します。
【おすすめ問題集】
『くもんの中学基礎がため100% 国語読解編』(くもん出版)
・文章が短めで、1回1回の演習量が適切にコントロールされているため、
国語に苦手意識を持つ生徒でも取り組みやすい設計になっています。
・特徴は、「接続語を意識しながら読む」「指示語の指す内容を明確にする」といった、文章の論理構造を自然に意識させる作りになっている点です。
・解説が非常に丁寧で、なぜこの答えになるのかがしっかり言語化されているため、解きっぱなしにならず「納得しながら理解」を進めることができます。
【この問題集が合う生徒】
・基礎からじっくり国語力を伸ばしたい子
・解説をしっかり読んで自分のペースで進めたい子
『中学国語をひとつひとつわかりやすく。』(学研プラス)
・超基礎レベルから学べる、初心者向けの大定番テキスト。
・図解やイラストが豊富で、「文章をどうやって読めばいいのか」「問題文はどうアプローチすればいいのか」を視覚的に理解させる作りになっています。
・特に、「国語の勉強の仕方がまったくわからない」という生徒には最適。
・説明がかみ砕かれているので、独学でも挫折しにくく、1冊やり切るだけでも確実に国語への抵抗感が減ります。
【この問題集が合う生徒】
・勉強そのものに苦手意識が強い子
・丁寧な解説を読んで、じっくり理解を深めたい子
『出口汪の日本語論理トレーニング 中学基礎編』(水王舎)
・「国語はセンスではない、論理だ」という考え方に基づいたトレーニング本。
・国語苦手な生徒ほど、「なんとなくの感覚」で選択肢を選びがちですが、出口式は「文章の流れ」「論理的なつながり」をもとに確実に正答を導く力を養成してくれます。
・問題ごとに「なぜこの選択肢なのか」「なぜ他の選択肢は違うのか」が明確に示されており、国語をロジカルに学び直す最高のスタート地点になります。
・特に、説明的文章(論説文)を苦手に感じる生徒には抜群の効果を発揮します。
【この問題集が合う生徒】
・感覚で答えてしまうクセを直したい子
・読解力を論理的に鍛え直したい子
中1のうちに最も大切なのは、問題演習を「解いたら終わり」にしないことです。
必ず、なぜその答えになるのか、
どこに根拠があるのかを自分の言葉で説明できるレベルまで理解することを目指しましょう。
また、国語の勉強はどうしても後回しになりがちですが、
1日15〜20分でも問題集に取り組む習慣を作るだけで、
半年後の成績には大きな差が出ます。
「少しずつ、しかし確実に積み上げる」これが中1国語克服の鉄則です。
中学2年生向け|おすすめ国語問題集紹介
中学2年生は、国語の内容が本格的に難しくなり始めるターニングポイントです。
単なる「読み取り」だけでは対応できず、文章構造を捉え、
筆者の主張や文脈の意図を論理的に読み解く力が求められるようになります。
また、文章量が格段に増えるため、長文を整理しながら読む力、
問題の意図を正確に汲み取る力がないと、テストや模試で時間内に解ききれなくなります。
この時期に必要なのは、「量をこなすこと」よりも、
質の高い読解演習を積み重ねることです。
「なぜこの答えになるのか」を説明できる読解力を育てる問題集を選ぶことが、
飛躍のカギになります。
【おすすめ問題集】
『国語読解の標準トレーニング 中2レベル』(受験研究社)
・中2レベルに合わせたバランスの良い問題構成。
・特に、文章の段落構成や論理展開を意識させながら読み進めるスタイルが特徴です。
・単に正解・不正解を確認するだけでなく、「段落ごとに何を言っているか」→「それが設問とどう関係するか」を考える流れを自然に身につけられます。
・長文演習が豊富で、読解スピードと集中力を同時に鍛えられるのもポイントです。
【この問題集が合う生徒】
・長文になると途端にミスが増える子
・文章全体を俯瞰する読み方を身につけたい子
『出口汪の日本語論理トレーニング 中学習熟編』(水王舎)
・中学基礎編よりもレベルが上がり、より高度な論理構成(対比・因果・具体例と抽象)を扱う演習内容。
・特に説明的文章や論説文に強くなりたい生徒には必須。
・問題ごとに、「論理的に正しい選択肢はどれか」「根拠となる言葉は何か」を意識させる作りになっており、国語の本質=論理力を磨き上げることができます。
・記述問題対策にも効果的で、入試国語の土台づくりに最適。
【この問題集が合う生徒】
・感覚ではなく、論理的に答えを出す力を伸ばしたい子
・難関高校受験を意識している子
『ことばの力を育てる 語彙・文法・表現力ドリル』(旺文社)
・中2でさらに重要になる「語彙力・文法力」を徹底強化できるドリル形式教材。
・読解に必要な言葉の正確な意味理解、適切な文法使用をトレーニングできる。
・毎日10〜15分でできる分量設計なので、読解演習とは別に語彙・文法を短時間で積み上げたいときに最適。
・知識の穴を埋めるだけでなく、「文章を読む基盤」を盤石にできる。
【この問題集が合う生徒】
・語彙や文法の理解があやふやな子
・短時間でコツコツ実力を底上げしたい子
中2は、基礎だけで満足していては成績が伸びません。
演習を通じて「どこが問われているか」「本文のどの部分が答えに対応しているか」を
意識的に見抜く力を育てていく必要があります。
特に、問題を解き終わった後に、
「なぜこの選択肢が正解で、他は違うのか」を自分の言葉で説明できるかどうかを
毎回確認する習慣をつけましょう。
これを意識できるかどうかで、中3以降の国語力に大きな差がつきます。
中学3年生向け|おすすめ国語問題集紹介
中学3年生にとって、国語は「好き嫌い」や
「得意不得意」で乗り切れる教科ではありません。
高校入試においては、得点源にもなり、失点源にもなる教科であり、
1問の正誤が合否に直結することすらあります。
多くの公立高校入試では、
・長文読解問題
・複数資料を比較させる問題
・記述問題
が高い比重を占めており、
本文に根拠をもって正確に答えを出す能力+短時間で情報を整理する力が不可欠です。
中3では、単なる基礎演習だけでなく、実戦形式を意識した問題集を活用し、
「解くスピード」「正確性」「記述力」を一体的に鍛える必要があります。
【おすすめ問題集】
『くもんの中学基礎がため100% 国語応用編』(くもん出版)
・中学国語の総仕上げに最適な構成。
・説明的文章・文学的文章の両方にバランス良く対応できるよう設計されており、基本問題から応用問題への橋渡しにぴったりです。
・特に「記述問題」「本文中に根拠を探す問題」が多く含まれており、受験国語に必要な読み取り力+記述力の土台作りができるのが強みです。
・解説が非常に詳しく、「なぜその答えになるか」のプロセスが明示されているため、自学自習でも十分実力が伸びます。
【この問題集が合う生徒】
・入試に向けて国語力を底上げしたい子
・基礎は身についているが、実戦での得点力が不安な子
『出口汪の日本語論理トレーニング 中学完成編』(水王舎)
・中学論理トレーニングシリーズの最高レベル版。
・選択肢問題、記述問題のどちらにも対応できるよう、「本文構造を論理的に把握し、根拠をもとに答える力」を徹底的に鍛えます。
・長文問題では、段落ごとの論理展開(因果関係、対比、具体例など)を整理しながら読む訓練ができ、読むスピードと正確さが同時に養われます。
・難関高校を目指す生徒にも対応できる内容なので、記述・論理読解を本格的に磨きたいなら必須。
【この問題集が合う生徒】
・入試で長文記述問題を確実に得点源にしたい子
・国語を感覚ではなく論理で攻略したい子
『入試に出る国語語彙力1200』(桐原書店)
・国語力の基盤となる語彙力を、効率よく強化できる単語帳型問題集。
・中学入試~高校入試で頻出する1200語を厳選して掲載し、読解問題で意味を問われる言葉・表現を徹底的にカバーしています。
・1日10分程度の学習でも継続しやすく、読解演習と並行して語彙力強化に取り組むには最適。
・文章読解のミスの多くは「言葉の意味を取り違える」ことに起因しているため、入試直前期でも効果を発揮します。
【この問題集が合う生徒】
・読解以前に「言葉がわからない」ことに課題を感じている子
・国語だけでなく、英語や社会の語彙力も強化したい子
【取り組み方アドバイス】
中3国語対策では、単に「解いて正解する」だけではなく、
・根拠を持って答えること
・なぜその答えになるのかを自分で説明できること
・制限時間内に正確に解ききること
この3点を常に意識して取り組む必要があります。
問題を解きっぱなしにせず、
必ず解説を読んで「正解への思考プロセス」を言語化する習慣を持ちましょう。
このプロセスを繰り返すことで、入試本番での「迷わず選べる力」が身についていきます。
まとめ
国語は、一朝一夕で劇的に成績が伸びる科目ではありません。
しかし、正しい方向に努力を重ねれば、確実に読解力も記述力も身についていきます。
これまで見てきたように、
・中1は「語彙+読解の基礎固め」
・中2は「標準レベルの長文に慣れる+論理読解の強化」
・中3は「入試を意識した実戦力・記述力の養成」
と、学年ごとにやるべきことは明確に異なります。
逆に言えば、今の自分の課題に合った問題集を選び、着実に取り組めば、
国語力は必ず伸びるということです。
【国語克服のために今日からできる5つの行動】
① 自分の学年と課題に合った問題集を1冊決める。
複数に手を出すのではなく、まずは1冊をやり切る。
② 問題を解いた後、必ず「なぜこの答えになるのか」を解説まで読み込む。
正解した問題も、根拠をきちんと確認する癖をつける。
③ 「本文のどこが根拠か」を意識して読むトレーニングを始める。
接続語・指示語に注目し、文章の流れを整理しながら読む。
④ 記述問題は「自分の言葉」でまとめる練習をする。
短くてもいいので、主語・述語を明確にした文章を書く癖をつける。
⑤ 毎日15分でも国語に触れる時間を確保する。
国語は短時間でもコツコツ続けた方が効果が出やすい科目です。
国語が苦手な子の多くは、
「何をどう勉強したらいいかわからない」
「やっても成果が見えにくい」
という理由で後回しにしてしまう傾向があります。
しかし、この記事で紹介したように、
✅ 正しい問題集を選び
✅ 正しい取り組み方で学習し
✅ 毎日少しずつ積み重ねていけば
国語は決して「センス任せ」や「苦手なまま」で終わる教科ではありません。
あなたの国語力は、今日からでも変わり始めます。
まずは、1冊の問題集を選び、取り組みをスタートしましょう。
半年後、きっと「国語が苦手」という自己イメージが変わっているはずです。
この記事を読んで、
「国語の勉強方法が少し見えた気がする」
「でも、一人で正しく続けられるか不安…」
そんなふうに感じた方もいるのではないでしょうか。
国語は、ただ問題集を解くだけで伸びる教科ではありません。
・解き方を正しく身につける
・毎回の演習で「なぜそうなるか」を振り返る
・苦手分野を意識して補強する
こうした地道なステップを、ブレずに積み重ねていく必要があります。
しかし、これを一人でやりきるのは簡単なことではありません。
個別指導塾ワイザーでは、
・生徒一人ひとりの読解力、語彙力、論理思考力を診断し、
・その生徒に最も必要な「国語学習の設計図」を作成し、
・毎週の授業+365日の学習管理で、国語力の底上げを徹底サポートしています。
ワイザーの強みは、ただ授業をするだけでなく、
「正しい勉強のやり方そのもの」を一緒に身につけるサポートができることです。
「国語は苦手だから…」と諦めていた生徒が、
たった半年で「読める・解ける・書ける」力を手にし、
自信を取り戻す。そんな変化を何度も見てきました。
現在、個別指導塾ワイザーでは
✅ 今の学力診断
✅ あなた専用の学習アドバイス
✅ 目標設定とプランニングのご提案
を完全無料で行う「無料個別相談」を実施しています。
もちろん、無理な勧誘や強引な営業は一切ありません。
あなたの課題と向き合い、最適なサポートをご提案させていただきます。
「国語が苦手」だった自分を、半年後に笑顔で振り返るために。
個別指導塾ワイザーが、あなたの第一歩を全力で応援します。
▼無料相談はこちらをクリック▼



