
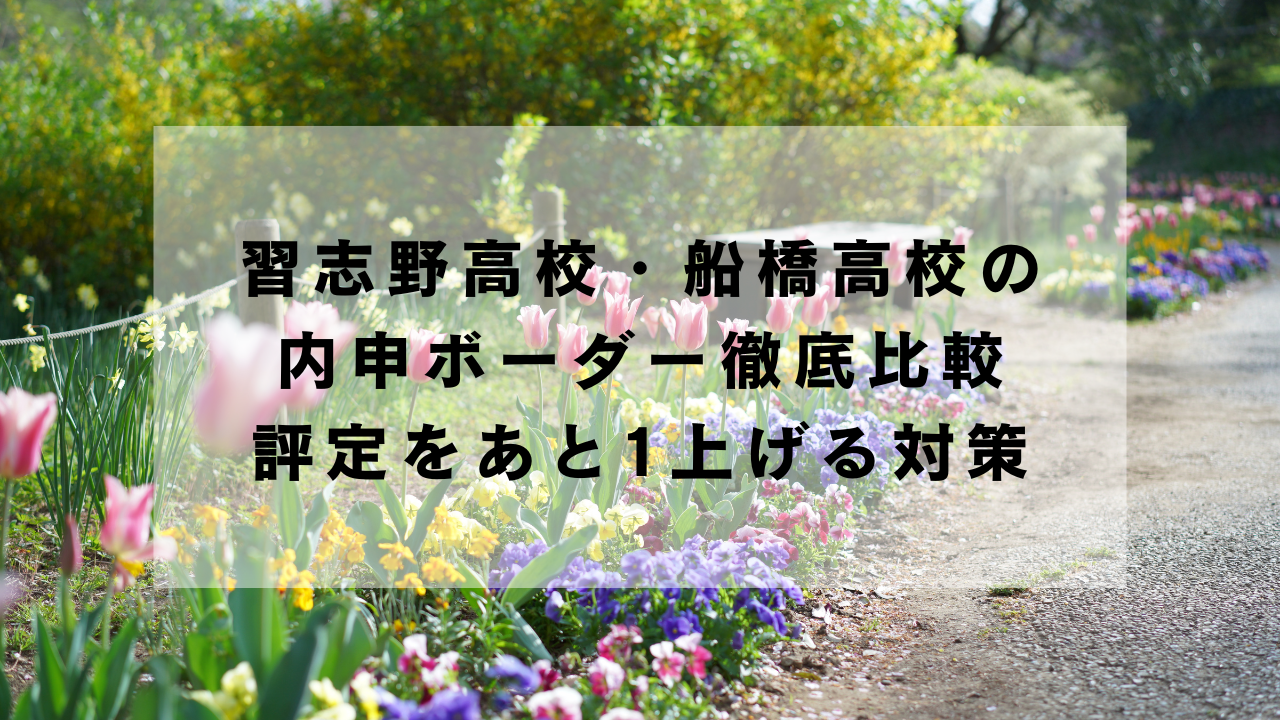
内申ボーダーが合否を左右する理由―習志野高校と船橋高校を比べる意義
千葉県公立入試では、各高校が「学力検査点」「内申(評定)」「学校設定検査」(面接・自己表現など)を独自の比率で総合し最終順位を決めます。
とりわけ第2学区の人気校である習志野高校と県立船橋高校は、配点の中で内申ウエートが高めに設計されているため、当日点が同水準でも評定差が1ポイントあるだけで合否が入れ替わる場面が珍しくありません。
実際に公開データを確認すると、直近(2025年度)の合格者分布は以下のように推移しました。
・習志野高校(普通科):合格者の調査書合計はおおむね 80〜128点の幅で分布し,中央値は 110点前後に位置。
・県立船橋高校(普通科):合格者サンプルの調査書合計は 117〜132点と高水準で,安定して 125点超えを取る層がボリュームゾーン。
両校とも満点は 135 点です。
数字だけを比べると、船橋高校は習志野高校より 平均で 15 点程度高いラインを要求していることが分かります。
評定1ポイントは9科目合計の平均評定で換算するとおよそ 0.07、つまり各教科であと1段階ずつ評価を上げるだけで2〜3点伸びる計算です。
しかし、定期テストの平均を5点高めても評定が動かない場合があるなど、評定改善は一筋縄ではいきません。
そこで本ブログでは,
- 評定計算の基本―9教科5段階評定をどう積み上げるか。
- 習志野 vs 船橋の内申配点の違い―「圧縮」や「加点制度」が及ぼす影響。
- 評定+1を狙う具体策―定期テスト・提出物・授業態度をどこまで改善すればよいか。
- 3か月逆算スケジュール―評定アップを本番に間に合わせる週次プラン。
- 無料相談の活用法―客観フィードバックで計画をブラッシュアップする手順。
以上5節構成で、内申をあと1上げるための現実的アプローチを提示します。
「当日点勝負だから内申は気にしない」という戦略は船橋高校では通用しにくく、
逆に「評定が低いから習志野にしかチャンスがない」と諦めるのも早計です。
正しい配点理解とピンポイント対策があれば、評定+1は3か月で十分狙えます。
評定計算のしくみと「K値」の違い――習志野はそのまま135点、船橋は半分の67.5点
千葉県公立入試の評定(内申)点は、9教科×5段階評定×3学年=135点満点を土台に、各校が設定する K値 を掛けて換算します。
公式は「評定合計 × K値 = 調査書得点」です。
県教育委員会が定めるK値の範囲は 0.5〜2.0。
学力重視校は 0.5、内申重視校は 2.0 を設定し、K=1 が標準となります。
1.習志野高校のK値=1(評定はそのまま)
市立習志野高校の選抜・評価方法要項には「各教科の評定合計に K=1 を乗じる」と明記されています。
つまり調査書点は 0〜135点 の範囲でそのままカウントされ、1点は1点として扱われます。
直近の開示データを見ると、合格者の評定帯は 80〜128点に広がっていますが、ボリュームゾーンは 110点前後。
評定4.0(9教科合計108点)でも合格圏に滞在できる一方、評定3.8(102点)あたりから当日点で大きく稼がないと厳しいラインへ下がります。
2.県立船橋高校のK値=0.5(評定を半分に圧縮)
県立船橋高校は「K=0.5」を採用する7校のひとつです。
評定合計を半分に圧縮するため、満点は 67.5点。
評定の影響が小さいように見えますが、合格者の実際の評定帯は 118〜132点(原点換算) と高く、K値で半減させても 59〜66点 がほぼ上限近くで推移します。
船橋ではオール4(108点)でも換算後 54点 にしかならず、当日5教科で450点近くを確保しないと安全圏に届きません。
逆に言えば「当日点勝負」を掲げる受験生にとっては評定不足を挽回できる設計ですが、国数英理社で平均90点という高精度が求められます。
3.同じ評定でも差が拡大するシミュレーション
| 評定平均 | 原点合計 | 習志野(K=1) | 船橋(K=0.5) | 差 |
| 4.0 | 108点 | 108点 | 54点 | 54点 |
| 4.3 | 116点 | 116点 | 58点 | 58点 |
| 4.6 | 124点 | 124点 | 62点 | 62点 |
同じ「評定+0.3」でも、船橋は換算後の伸びが 半分 になるため、当日点で埋めるべきギャップは広がります。
一方、習志野は評定1点をそのまま得点化できるぶん、5教科で3点上げるより評定1を上げるほうがコスパが高いケースもあります。
4.K値で変わる“内申+当日”の合格ライン
一般的に千葉県普通科の配点は〈学力検査500点+評定換算点+加点50点以内〉ですが、習志野と船橋を比べると合計満点は次のように異なります。
・習志野:500点+135点+α= 635点満点
・船橋:500点+67.5点+α= 567.5点満点
合計が違えば「1点あたりの価値」も変わります。
習志野では135点中の1点は満点比 0.16%、船橋では67.5点中の1点でも 0.18%。
割合で見れば船橋のほうが評定1点の重みはやや高く、“評定は軽い”わけではないことが数字上明確です。
5.まず自分の位置を可視化しよう
・STEP1:通知表3年分を足し、135点満点で現在値を算出。
・STEP2:習志野志望ならそのまま、船橋志望なら×0.5で換算点を求める。
・STEP3:過去合格者中央値(習志野110点・船橋125点相当)と比較。
・STEP4:不足点÷残り学期数=1学期あたり評定上げ幅を決定。
このギャップ分析を行うと「今学期で評定+1を取れば安全圏」「当日点+30点が必要」など、次の手が明確になります。
評定+1の最短ルート――科目別「評価項目逆算シート」で定期テスト・提出物・授業態度を同時に底上げする
内申をあと1段階上げるためには、9教科すべてで「評価3→4」「4→5」への分岐点を正確に押さえ、そこに資源を一点集中させる必要があります。
千葉県の公立中学校では 定期テスト(学習評価)60%前後+提出物20%+授業態度・発表20% を基本比率とする学校が多い傾向にあります。
比率の差はあっても「テストで平均+10点」「提出物を期限遵守+加点項目フル取得
「授業で1回は発言」この3本柱をそろえれば評定アップの条件を満たすケースがほとんどです。
1.定期テスト対策――「平均+10点」を最小労力で取る4ステップ
- 目標点の設定
各教科の学年平均点を配布プリントや学校HPで確認し、「平均+10点」を数値化します。
例:数学平均62点→目標72点。 - 配点逆算シート作成
テスト範囲表の大問ごとの配点を書き写し、得点源を可視化します。
「関数20点」「作図10点」「証明15点」と見える化すると、投下すべき演習量が一目で分かります。 - 70%演習の原則
目標点の7割を易化ゾーンで確保し、残り3割を差別化ゾーンで積み増す戦略です。
関数の基本問題で確実に16点取り、応用で4点加算するとブレが小さくなります。 - 48時間リピート
間違えた問題は48時間以内に再演習し、満点取得で“封印”マークを付けます。
この封印が5個たまるたびにご褒美(10分ゲーム、好きな動画)を設定すると継続率が上がります。
2.提出物対策――「満点+α」を狙うタイムスタンプ方式
提出物は“出すだけ”では加点が伸びにくく、期限厳守+完成度+自主欄の三位一体が重要です。
・期限厳守:大多数が出し渋る週末を避け、配布から48時間以内に7割完成→授業前日に見直し提出。
早提出は「計画性」の観点で加点対象になりやすい。
・完成度:解答を単に写さず「誤答→赤ペン訂正→再計算」を明示。
教科書参照ページや自分の所感を余白に書くと記入量が規定の1.2倍になり、教師の印象が上がります。
・自主欄:ワーク末尾の自由記述は“ノート貼り付け”で面積を拡張し、「疑問点3行+調べたこと3行」で簡易レポート形式に。
10分の検索で差が付くポイントです。
提出管理はタイムスタンプ方式が有効です。
ワークを開いた時点でスマホのメモに「Start 18:40」、閉じる時に「End 19:05」と記録。
1課題あたりの所要時間を見積もれるようになり、次回計画が立てやすくなります。
3.授業態度対策――「1授業1アウトプット」で存在感を残す
評価観点「主体的に学習に取り組む態度」は抽象的ですが、実際に加点が付く行動は明確です。
| 行動 | 加点例 | 実行ハードル |
| 授業開始1分以内に教科書・ノート準備 | 1学期で+1 | 低 |
| 発言・質問を週1回 | 2学期で+1 | 中 |
| グループ活動で板書・タイムキーパー担当 | 学期末+1 | 中 |
| 小テスト返却時に解き直し提出 | 都度+0.5 | 低 |
1授業1アウトプットを合言葉に、発言・質問が難しい日はノート欄外に「今日のポイント」を書き、先生の巡回時に見せてコメントをもらうだけでも加点対象となります。
「話すのが苦手だから内申が上がらない」という悩みは、書くアウトプットへ置き換えることで解消できます。
4.科目別重点強化プラン
・英語:教科書本文のオーバーラッピング音読×5回をテスト2週間前まで毎日。
音読履歴をスマホ録音し、授業での音読指名で滑舌と流暢さを示すと評価5への布石になります。
・国語:漢字小テストは「前日暗記→当日解答→5分後セルフ再テスト」の二段リピートで満点連続を狙う。
満点3回ごとに先生へ提出しておくと努力可視化が進む。
・数学:作図・証明など配点小問をテンプレート暗記→空書き練習で自動化。
提出ノートに「証明の型」見開きまとめを付録し、視覚的アピールを追加。
・理科:実験考察は「仮説→方法→結果→考察」の4段レイアウトでレポートを書く。
事前にテンプレートをノートに印刷して貼れば記入負担が減り、提出遅延を防げます。
・社会:地図・年代ゴロ合わせシートを班で共有し、グループ発表で使用。
発表資料を先生にコピーで渡すと“主体的活動”として一括加点される場合が多い。
5.3か月逆算スケジュールの概要
| 週 | 定期テスト | 提出物 | 授業態度 | 進捗確認 |
| 1 | 配点表作成 | ワーク2割終了 | ノート見開き質問1行 | ○×グラフ記入 |
| 2 | 70%演習 | ワーク5割終了 | 発言1回 | テスト点シミュ |
| 3 | 応用演習 | 自由記述記入 | グループ役割担当 | 封印マーク数 |
| 4 | 試験 | 提出完了 | 口頭質問1回 | 速報点入力 |
| 5 | フィードバック | 解き直し提出 | ノート余白コメント | 評定予測更新 |
| 6 | 弱点補強 | 次範囲ワーク開始 | 発言1回 | グラフ右肩上がり確認 |
このサイクルを学期×2回回せば、評定は平均+1.0以上伸ばす実例が多数あります。
特に習志野高校志望者は評定1点が合否に直結しやすく、船橋高校志望者でも当日点のプレッシャーを小さくできます。
評定アップは「テストだけ」「提出物だけ」では不十分です。
3本柱を計画的に回し、客観データで進捗を可視化することで、評価者である先生のノートチェック・授業観察・試験採点すべてに好影響を与えられます。
忙しくても回る「週次オートルーティン」――仕組み化で評定アップを時間割に組み込む
対策メニューを頭で理解しても、部活・習い事・家庭の役割で時間が寸断されると実行率が下がり、結局は元の生活に戻ってしまうことが多いです。
ここでは、第3節で示した3か月スケジュールを 1週間単位のテンプレート に落とし込み、「開始トリガー」「終了チェック」「自動リマインド」を組み合わせて 強制的に回る仕組み を作ります。
ルーティンは ①月曜プランニング → ②火水木の実行ブロック → ③金曜予備日 → ④土日レビュー の4相構造です。
1.月曜プランニング(15分)―「週間台本」を2枚書くだけ
- 定期テスト配点ボード更新(5分)
A4用紙に前週の○×結果を赤で反映し、平均+10点ラインとの差を太線で表示。
これがテスト演習のナビになるため、月曜の朝に必ず掲示板へ貼り替えます。 - 提出物タスクカード作成(5分)
ワーク名とページ数、提出期限を書いた付箋を3色で色分け。
必須課題=赤、加点課題=黄、自主課題=青としてノート見開き左側へ縦並べ。 - 授業アウトプット予定表(5分)
時間割を見ながら「国:質問」「数:発表」「英:指名音読」など、一日1アクションを仮決めします。
声を出すのが難しい教科は「ノート余白コメント」を代替手段として書き添えると実行率が上がります。
この2枚が 週間の台本 です。
月曜朝に完成させると、火水木の実行ブロックで「何をやるか」を迷う時間がゼロになります。
2.火水木の実行ブロック―「90分スプリット学習」で集中と回復を両立
部活日でも確実に回すため、 30分×3セッション=90分 を上限とし、曜日により配分を変えます。
| セッション | 火 | 水 | 木 |
| ①家庭学習開始直後30分 | 定期テスト演習(70%ゾーン) | 提出物進行(必須+加点) | 授業アウトプット準備 |
| ②夕食後30分 | 提出物進行(自主欄) | 定期テスト演習(差別化ゾーン) | 提出物仕上げ+自主欄装飾 |
| ③就寝前30分 | 音読・暗記系(英語教科書) | ノートまとめ+口頭説明録音 | テスト間違い直し+封印 |
ポイント
・①は脳がまだ疲れていない時間帯に「平均+10点」を稼ぐ定番問題を解く。
・②は勉強エネルギーがやや下がる時間帯に「手を動かす系」の提出物で脳負荷を下げる。
・③は寝る前の短期記憶固定タイムに暗記・誤答直しを行い、48時間リピートへ接続。
セッション開始前にスマホタイマーを 25分+5分休憩のポモドーロ でセットし、物理的に強制終了させると「やり過ぎによる燃え尽き」を防げます。
3.金曜予備日―「遅延ゼロ&ミス潰し」の安全装置
金曜日は部活や行事で不規則になりやすいため、実行できなかったセッションを埋めるリカバリー日 と定義します。
・ワーク未終の場合は +30分 を確保。
・テスト演習で正答率70%未満が残っていれば、差別化ゾーンを捨て 70%ゾーン復習 に切り替えます。
・授業アウトプットができなかった教科は ノート余白コメント+先生への質問メモ を書いて次週の授業で提出。
これにより「やり残し=内申失点」のリスクを週内に消し込み、精神的負担を週末へ持ち越しません。
4.土日レビュー―「見える化+アップデート」でPDCAを完結
(1)セルフルーブリック評価(30分)
| 観点 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| テスト演習進捗 | 予定範囲100% | 90% | 70% | 50% | <50% |
| 提出物完成度 | 必須+加点+自主完了 | 必須+加点完了 | 必須のみ | 途中 | 未着手 |
| 授業アウトプット回数 | 4回以上 | 3回 | 2回 | 1回 | 0回 |
自分で点付け→親や友達に見せる→改善点を付箋で追記、の3ステップで可視化します。
(2)フォーカスポイント更新(15分)
・テスト演習で 正答率60%未満 の単元を次週の70%ゾーンへ移動。
・提出物タスクカードの残件数を数え、翌週月曜プランニングで最優先に貼り替える。
(3)ご褒美&リフレッシュ設定(15分)
評価が 13 点以上なら 動画30分+スイーツ、10〜12 点なら 動画15分、それ以下は 翌週加点+2 点後に開放 とルール化し、自己制御とモチベ維持を両立します。
5.自動リマインド&進捗ログ――テクノロジーに“監督”を任せる
・Googleカレンダー
セッション開始10分前にプッシュ通知。
・LINEリマインド
提出物期限の48時間前/24時間前/4時間前に自分宛てメッセージ送信。
・Notionデイリーログ
予定どおり実行したらチェックボックスに✔を入れ、1週間で7割以上チェックが付けば自動で「GOOD」のバッジが表示されるウィジェットを使用。
・Classroomルーブリック(学校導入校のみ)
自己採点表をClassroomにアップし、先生コメントが付いたら即通知→次週プランニングへ反映。
デジタルツールを「監視役」にしておくと、計画倒れを半自動で防げます。
残り3か月で“評定+1・当日+30”を同時に狙うロードマップと無料相談のご案内
内申をあと1段階引き上げる方法と、船橋・習志野それぞれのK値に合わせた当日点戦略をここまで示しました。
最後に、「今日から入試3か月前までをどう切り取るか」を週単位で可視化したロードマップを提示し、客観的な軌道修正を受けられる無料相談の活用法をまとめます。
1.“90日=13週”を4フェーズに分けて管理する
| フェーズ | 期間 | 内申重点 | 当日重点 | 週次KPI |
| フェーズA | 90〜61日前 | 評定+0.3の土台作り(提出物・授業態度) | 基礎演習で平均+5点 | ルーティン完遂率70% |
| フェーズB | 60〜31日前 | 評定+0.6へ拡張(定期テスト) | 70%ゾーン完答率80% | 週間封印マーク15個 |
| フェーズC | 30〜11日前 | 評定+0.8の仕上げ(提出物+α) | 差別化ゾーン演習で+15点 | 過去問得点率75% |
| フェーズD | 10日前〜前日 | 評定提出済み | 解き直し→弱点潰し | 過去問得点率85% |
・A→B移行時点で提出物遅延がある場合は、当日対策を一時停止し赤付箋タスクを先に消化して内申落とし穴を塞ぎます。
・Cフェーズでは予定を「夜型→朝型」へ徐々にシフトし、本番当日の脳コンディションに合わせます。
・Dフェーズで新問題へ手を広げるのは失点リスクが高いので、封印マークの解き直しと睡眠確保を最優先にします。
2.“評定シフト表”で最終的な得点配分を決める
- 現在の評定を135点満点で入力し、船橋志望者は×0.5で換算。
- 過去5年の合格者中央値と自分の差を色付きセルで可視化。
- 差が15点以内なら当日点上乗せ優先、16点以上なら評定アップ優先へ舵を切ります。
- 毎週土曜にシートを更新し、フェーズごとのKPIが達成できたかチェックします。
3.当日点強化の“得点帯ルーレット”
・習志野志望:内申110点を確保できれば当日5教科合計340点で合格圏。
→ 1教科平均68点を目標に「苦手1科-5点」「得意1科+15点」の凹凸型配点で合計を合わせる。
・船橋志望:換算評定60点を取れない場合、当日420点以上が必要。
→ 週ごとに「理科+10点強化週」「社会+10点強化週」を設定し、5教科いずれも80点を割らない均等型配点で安全圏を狙う。
4.“内申+当日”チェックリスト(毎週末5分)
・ルーティン完遂率70%以上
・提出物赤付箋ゼロ
・授業アウトプット4回
・テスト演習 70%ゾーン正答率80%
・過去問1年分/週完了
チェックリストが3週続けてオールチェックなら、評定+1が射程圏。2項目以上空欄なら月曜プランニングで補強策を追加します。
5.無料個別相談で“第三者レーダー”を手に入れる
ここまでの計画を自分ひとりで回すと、盲点や甘めの自己評価が残りがちです。
個別指導塾ワイザーでは、評定アップと当日点戦略を同時にブラッシュアップできる無料学習相談を用意しています。
・ステップ1:現状分析
通知表と模試成績を画面共有し、評定・当日点ギャップを即時数値化。
・ステップ2:ルーティン診断
週次スケジュールをヒアリングし、実行率が下がる“穴時間”を洗い出し。
・ステップ3:カスタム計画提案
船橋・習志野いずれか専用の「フェーズ別KPI表」と「提出物チェックシート」をPDFで進呈。
6.行動を“数字”に換える最初の一歩
評定1ポイントの軽視は第一志望を遠ざけ、計画なき当日点重視は精神的負荷を跳ね上げます。
数字で現状を測り、小さく試して、毎週修正する。
このサイクルが今日からできれば、残り3か月でも合格ラインを確実に引き寄せられます。
「自分の計画が本当に合っているのか確認したい」
「まず何から手を付ければいいかわからない」
そう感じたら、無料相談を活用し、第三者のレーダーで航路を補正しましょう。
時間は限られていますが、戦略的に使えば評定+1も当日+30も十分に届きます。
▼無料相談はこちらをクリック▼



