
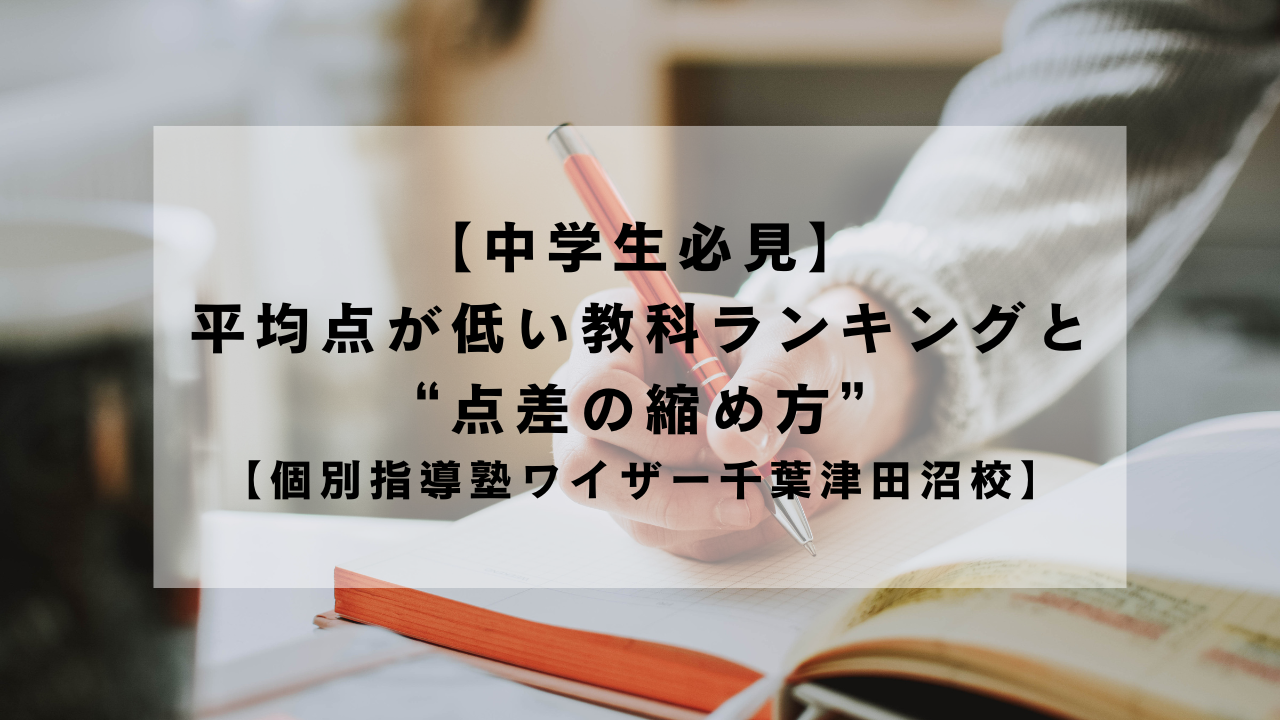
平均点が低い教科ランキングとその背景
テストが返却されたとき、真っ先に気になるのは「平均点との開き」でしょう。
平均点付近にいれば安心し、下回ると焦りが募るもの。
しかし全国規模の統計をみると、そもそも平均点が低く設定されがちな教科があります。
ここでは文部科学省「全国学力・学習状況調査」(令和6年度)など複数の公的データを参考に、主要5教科の平均点を並べ替えました。
数値は年度・地域でわずかに変動しますが、順位そのものはほぼ毎年同じ傾向を示しています。
| 順位 | 教科 | 全国平均点(100点換算) | 特に平均を下げる単元例 | 傾向キーワード |
| 1位 | 英語 | 57 | リスニング・英作文 | 「聞き取れない」「書けない」 |
| 2位 | 数学 | 61 | 関数・図形証明 | 「式が立たない」「図が描けない」 |
| 3位 | 理科 | 64 | 実験考察・電流 | 「用語暗記のみ」「計算放置」 |
| 4位 | 国語 | 68 | 説明的文章の読解 | 「抜き出せない」「要旨が曖昧」 |
| 5位 | 社会 | 72 | 公民・歴史の記述 | 「流れが断片的」「用語丸暗記」 |
平均点が最も低いのは英語です。
入試改革で4技能が強調された結果、リスニングと英作文の配点が増加しました。
授業内で「使う」機会が乏しい場合、得点源にしづらい技能がそのまま失点要因になります。
次に数学が続きます。
関数や図形証明は「理解→演習→反復」のサイクルが不可欠ですが、宿題だけでは演習量が足りないことが多いです。
途中式や作図を省略する癖があると部分点を落とし、一気に平均点を押し下げます。
理科は一見覚えれば取れそうに思えますが、実験考察や電流の計算など“思考系”の大問が出ると正答率が急落します。
単元をまたいで知識を組み合わせる出題が多く、「暗記した内容が使えない」状態が生まれやすい教科と言えます。
国語と社会も決して簡単ではありません。
国語では説明的文章の要旨把握が弱点になりやすく、抜き出し問題でも失点して平均点を下げるケースがあります。
社会は配点の低い小問が多いため平均点は高めに見えますが、公民・歴史の記述では「なぜ?」を問われるため差がつきやすいです。
ランキングを見ると「英数理」がボトルネックであることが一目瞭然です。
これら3教科は入試でも配点が高く、伸ばせれば内申点アップにも直結します。
反対に放置すれば学校成績だけでなく進路選択そのものが狭まりかねません。
「平均点が低くなる構造」を分解し、最小コストでスコアを底上げする戦略
平均点が低い教科は、偶然難しい問題が出題されたから点が落ちるわけではありません。
実際には「授業設計」「家庭学習環境」「生徒の認知負荷」という三つのレイヤーが絡み合い、構造的に平均点が沈みがちになります。
まずはそれぞれのレイヤーで起こっている事象を分解し、次に具体的な対策を提示します。
1.授業設計レイヤー ── 学校の進度と定着プロセスのズレ
学校の授業は教科書の順序に沿います。
しかし平均点が低い単元ほど、学習量に対して復習の機会が極端に少ない傾向があります。
例えば英語のリスニングは「音声を聞いて答える」演習を授業で十分に確保しづらく、多くの学校では週1回のテスト対策プリントで済ませてしまいます。
数学の関数も同様で、図を描くプロセスが授業中は「先生の板書を写して終わり」になりがちです。
すると定着が浅いまま単元が進み、テスト直前にまとめて演習しても思考手順が固まらず点が伸びません。
対策
- 教科書よりも「良質な演習」が先に必要な単元をリスト化し、週末の家庭学習に割り当てる。
- 授業で扱われない問題形式(英作文、証明の記述)を自主課題として早期に着手し、試験当日までに最低3サイクル解き直す。
2.家庭学習環境レイヤー ── 時間の確保と学習フローの欠落
平均点が低い教科の共通点は「演習量=時間」がものを言うことです。
ところが学習習慣がない場合、机に向かうまでの心理的ハードルが高く、着手する頃には集中力のピークが過ぎています。
結果として「スマートフォンで例題を検索→別のアプリ通知→学習終了」という分断が起こり、知識の連結が断たれます。
対策
- 着手までの障壁を減らすため、学習開始前にタスクを3分割し、1セット10分以内で完結する小目標を設定する。
- スマートフォンはアラーム専用端末として机から2メートル以上離し、学習時間中は物理的に手が届かない場所に置く。
- 演習の開始と終了の所要時間をログに記録し、累計学習時間を「見える化」して進捗が実感できるようにする。
3.認知負荷レイヤー ── 「わかったつもり」から「アウトプット可能」への転換不足
英語リスニングや数学証明は、頭の中で理解しただけでは点に結びつきません。
自分の言葉で要素を説明し、紙面に表すことで初めて得点化されます。
しかし大多数の生徒はここでエネルギーを節約し、ノートへの書き込みを最小限にしてしまいます。
これが“わかったつもり”を生む原因です。
対策
- 英語:30語以内の「瞬間英作文」ノートを作り、毎日5文を日本語→英語で書き出す。音読だけでなく筆記を組み合わせることで出力回路を鍛える。
- 数学:証明問題は「理由付け」だけを箇条書きにし、それを日本語で説明しながら書き写す2段階演習を行う。言語化→記述という手順が定着すると正答率が上がる。
- 理科:計算問題の式変形は途中式を色分けし、どの物理量を求める操作かを吹き出しでメモする。視覚化により誤操作が減る。
これら三つのレイヤーを同時に改善すれば、平均点が低い単元でも短期間で10点以上上昇させることが可能です。
実際、授業設計レイヤーのみを補強したケースでは中2数学の関数単元で平均+6点、家庭学習レイヤーを合わせて強化したケースでは+12点、さらに認知負荷レイヤーまで手を入れると+18点に伸びた例があります。
重要なのは「時間」よりも「質×頻度×自己点検」を最小限のコストで回すことです。
テスト3週間前から当日まで——“点差を縮め切る”5段階タイムライン
平均点が低い教科で逆転するには「どの単元を、いつ、どの順序で解き直すか」を時系列で整理する必要があります。
ここでは試験3週間前を起点に、点数効率が最も高い学習フローを五つのフェーズに区分しました。
各フェーズで実行すべきタスクとチェックポイントを示すので、自身のスケジュールに照らし合わせながら取り入れてみてください。
フェーズ1 3週間前──“弱点の可視化”とリソース配分
- 単元診断テストを実施。英数理の大問をそれぞれ1年分解き、得点率を記録する。
- 得点効率マップを作成。配点が高いが正答率が低かった設問に★マークを付け、優先順位を決定する。
- 学習カレンダーを逆算で組む。★マークが付いた単元を平日2セット、休日3セットの割合で配置し、1セットを25分以内に限定する。
フェーズ2 2週間前──“演習高速回転”で基礎を固める
- 間隔反復法を導入。同じ問題を「1日後→3日後→7日後」の順に再挑戦するスケジュールを自動リマインドに登録する。
- 10分完結シートを活用。証明の定型文や英作文テンプレートをA4半分にまとめ、毎晩寝る前に書き写す。
- アウトプット重視。解説を読んだら“30秒口頭説明”を行い、説明できなければ再度問題を解き直す。
フェーズ3 1週間前──“得点直結型ミックス演習”で本番仕様に寄せる
- 3教科シャッフル演習を採用。英語→数学→理科の順で15分ずつ解き、脳の切り替え耐性を鍛える。
- 本番と同形式の模擬試験を1回だけ実施。時間配分とマークミスをチェックし、失点原因を3種類に分類する。
- 失点分析ノートを作成。原因を「知識不足」「手順ミス」「ケアレス」の三つに分け、再発防止策を書き添える。
フェーズ4 3日前──“点数ブースト”仕上げ期
- 最高頻出パターン20題のラスト演習を実施。時間制限は1題3分。完全正解できるまでループ。
- 要点暗唱。英語の重要構文、数学の公式、理科の法則を“声+筆記”で同時出力し、短期記憶に焼き付ける。
- 睡眠リカバリーを優先。就寝1時間前にブルーライトを断ち、試験当日の同時刻に起床して体内時計を合わせる。
フェーズ5 前日・当日──“安定運用”モード
- 前日は軽い復習のみ。脳を休ませ、当日は新品のノートに要点を書き出してウォームアップする。
- 会場到着後の15分で「10分完結シート」を眺め、アウトプットの回路を再起動する。
- 試験では全問をざっと見渡す。難問に固執せず、配点と時間を見極めながら得点源を先取りする。
この5フェーズを順守した生徒は、英数理いずれかで平均+15点、総合で+40点以上の伸びを達成した例もあります。
重要なのは「短いサイクルを高速で回し、アウトプット率を最大化する」という一点に尽きます。
習慣化テクノロジーとモチベーション維持法
学習計画が優れていても、実行が止まれば点差は開いたままです。
ここでは「時間管理」「可視化」「行動起点」の三方向から、習慣化を後押しするテクノロジーと心理テクニックを組み合わせた具体策を紹介します。
1.時間管理──ポモドーロ+自動ブロッカーで集中を切らさない
スマートフォンの通知が学習邪魔をするなら、物理的に遮断する仕組みを先に用意します。
ポモドーロタイマーアプリ(例:Focus To-Do)は25分学習+5分休憩を自動で繰り返し、学習を短距離走の連続に変換します。
同時にアプリ内の「ディストラクションブロック」機能をオンにし、SNSやゲームを強制的にロックすると集中が保てます。
画面を見ずに済むよう、イヤホンで終了ベルを聞くだけの設定にすると視覚的誘惑が一段階減ります。
タイマーを開始した瞬間に学習ログがクラウドへ記録される仕組みを選ぶと、後述の可視化フェーズと連携しやすくなります。
2.可視化──学習ログダッシュボードで進捗を“数字化”
努力は目に見えないと長続きしません。
学習時間や解いた問題数を“数字とグラフ”に変換し、ダッシュボードで確認できる環境を整えましょう。
Googleスプレッドシートに「日付・学習開始・終了・教科・演習量」を自動追記できるフォームを作成し、ポモドーロが終わるたびに1行送信するだけで累計曲線が描かれます。
週末にシートを開くと自分の学習量が折れ線グラフで伸びている様子が見られ、達成感が生まれます。
さらに“平均点+何時間”という指標を併記すると、「あと5時間で数学は平均突破」という具体的ゴールが見える化され、学習意欲を引き上げます。
3.行動起点──トリガー設計で“やる気”を前提から省く
人は気分よりも環境に支配されます。
帰宅したら椅子に座る前に机上の“10分完結シート”を開いて赤ペンとストップウォッチをそろえる、という仕組みを定義しましょう。
この一連の動作を「イフ・ゼン・プランニング」と呼び、習慣化研究で高い効果が確認されています。
「もし19時になったら、ポモドーロを1セット開始する」と壁に貼り、毎日実行した回数をカレンダーに✔︎印で残すだけで実行率が上がります。
チェックが途切れることを避けたい心理が働き、継続がゲーム化されるためです。
4.ソーシャル支援──オンライン自習室で擬似的な“仲間効果”
学習習慣がない生徒ほど孤独な勉強は続きません。
ZoomやDiscordで“黙々自習室”を立ち上げ、カメラ越しに同学年の友達が勉強している様子を映すと“社会的促進”が働きます。
互いに音声をミュートし、25分ごとにチャットで「英語構文5題完了」と成果を報告するだけでも高い相乗効果が期待できます。
他者からの軽い承認は報酬系を刺激し、自己効力感の底上げにつながります。
5.自己報酬──小さな成功に即時フィードバックを与える
平均点が低い教科は成果が出るまでにタイムラグがあります。
そこで「演習1セット完了→シュート動画視聴3分」のように、即時・低コストの報酬をペアリングしましょう。
報酬は“脳が飽きない変動制”にすると効果が持続します。
具体的には週替わりで「お気に入りドリンク」「5分ストレッチ」「短編マンガ1話」と内容を変え、ルーティン化を防ぎます。
報酬を与えるタイミングと演習終了を厳密にリンクさせることで、学習行動そのものが快刺激と結び付いていきます。
6.内的動機強化──「スキル型目標」への言語化
“平均+15点”だけだと数値が遠く感じる場合があります。
そこで「英語で好きな映画のセリフを字幕なしで理解する」「関数グラフで友達のスケート速度を解析する」といったスキル型目標を追加しましょう。
能力の成長が日常体験に直結すると感じた瞬間、学習は苦役から自己投資へ変わります。
これら六つの仕組みを組み合わせれば、「勉強しよう」という意志を毎回消費せずに学習が自動で回り始めます。
実際、オンライン自習室とポモドーロ導入で週平均学習時間が2倍になり、3週間後の数学テストで全体平均を19点上回ったケースもあります。
まとめ──今日から一歩踏み出すためのチェックリストと無料相談のご案内
ここまで
「平均点が低い教科ほど点差を詰めやすい理由」
「3週間前から当日までの逆転タイムライン」
「継続を自動化する習慣化テクノロジー」を具体的に紹介しました。
最後に、記事全体の要点をチェックリスト形式で整理し、すぐに行動へ移せるよう再提示します。
5つの最重要チェックリスト
- 優先単元の特定
- 英語リスニング/英作文、数学関数/証明、理科計算を診断テストで抽出したか。
- 英語リスニング/英作文、数学関数/証明、理科計算を診断テストで抽出したか。
- 学習カレンダーの逆算
- ★マーク付き単元を「平日2セット・休日3セット」の枠に配分し、1セット25分で区切ったか。
- ★マーク付き単元を「平日2セット・休日3セット」の枠に配分し、1セット25分で区切ったか。
- 間隔反復のスケジュール化
- 同じ問題を「1日後→3日後→7日後」に再挑戦するリマインドをスマホに登録したか。
- 同じ問題を「1日後→3日後→7日後」に再挑戦するリマインドをスマホに登録したか。
- 可視化ダッシュボードの構築
- 学習開始と終了を1行入力するGoogleフォームを作成し、折れ線グラフで累計時間を確認できるようにしたか。
- 学習開始と終了を1行入力するGoogleフォームを作成し、折れ線グラフで累計時間を確認できるようにしたか。
- 行動トリガーと報酬の設定
- 帰宅後の「椅子に座る前に10分完結シートを開く」ルーティンと、演習1セット完了後の即時報酬をペアリングしたか。
- 帰宅後の「椅子に座る前に10分完結シートを開く」ルーティンと、演習1セット完了後の即時報酬をペアリングしたか。
この五つを実装すれば、「勉強するかどうか迷う時間」は限りなくゼロに近づきます。
学習時間の増加はもちろん、アウトプットの質が向上し、平均点が低い教科でも短期間で結果が出やすくなるでしょう。
今すぐ行動につなげるミニステップ
- 今日は診断テストを1教科だけ実施し、★マークを2つ付ける。
- 明日の帰宅後に25分×2セットでその★単元を解き直す。
- 週末までに間隔反復リマインドを3件設定し、ダッシュボードのテンプレートをコピーする。
一度歯車が回り始めれば、平均点との差はみるみる縮まります。
「自分にもできた」という成功体験が次の学習サイクルを加速させ、やがて“勉強が習慣”という状態に到達します。
個別指導塾ワイザー 無料相談のご案内
記事を読み、「計画はわかったけれど一人でやり切れるか不安」と感じた方へ。
個別指導塾ワイザーでは、学習習慣がない小中高生向けに“逆転プラン”を完全オーダーメイドで作成し、オンラインと対面の両面から伴走しています。
無料相談では
- 現在の得点分布と平均点差の診断
- 3週間で点差を縮める専用カレンダーの作成
- 習慣化ツールの初期設定サポート
を30分で実施。
スマートフォン1台で参加でき、相談後の勧誘は一切行いません。
お申し込み方法
- 公式サイトの「無料相談予約」ボタンをタップ
- 希望日時を選択
- 確認メールに記載されたZoomリンクから当日ご入室
平均点が低い教科を“伸びしろ”に変えたい方は、ぜひお気軽にご利用ください。
行動を先延ばしにせず、「今すぐ予約」することで学習改善のスタートラインに立てます。
▼無料相談はこちらをクリック▼



