
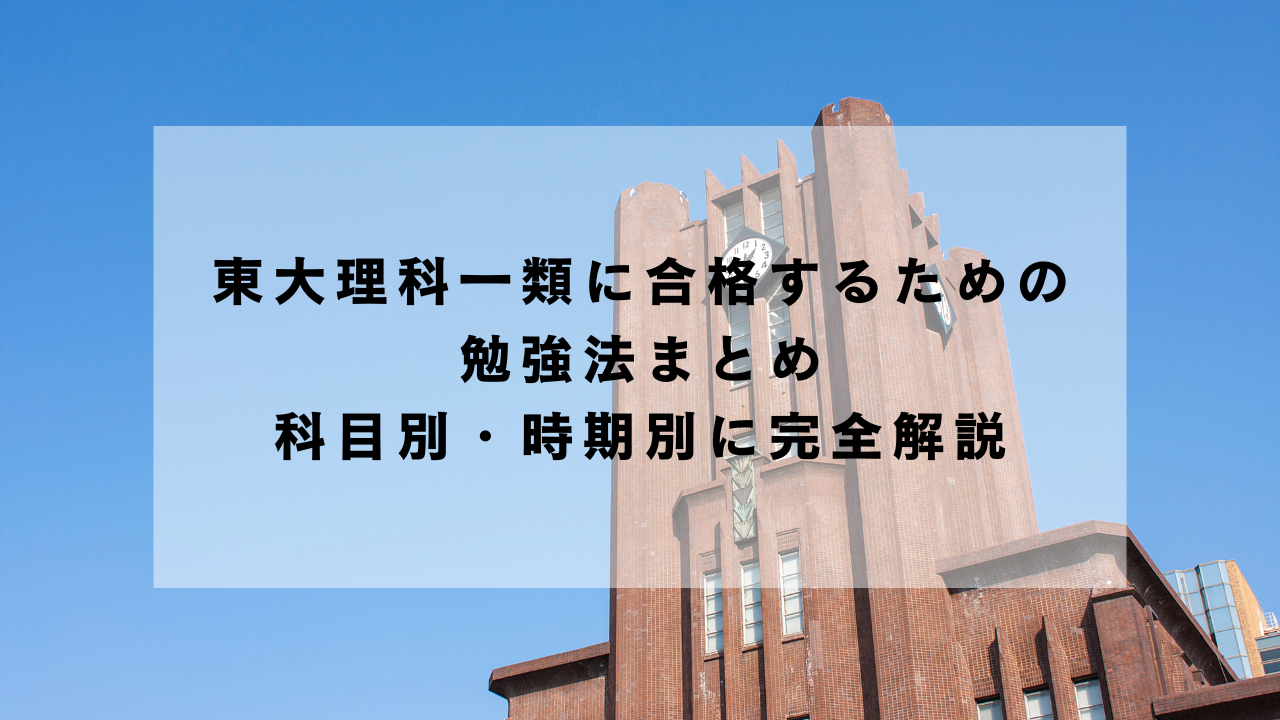
はじめに|東大理科一類に合格するために必要な「思考・戦略・習慣」のすべて
東京大学理科一類。
それは日本全国の理系トップ層が集い、最難関の学問を究めるための関門です。
しかし、「理科一類に受かる人は特別」
「自分とは違う世界の人たちだ」と感じていませんか?
実際にはそうではありません。
確かに合格者の多くは学力的に高水準ですが、
「地頭がいい」だけで合格するわけではなく、
正しい勉強法と時期に応じた戦略を積み重ねることで、
後天的に東大合格レベルに到達している人が大半です。
この章では、理科一類に合格するために必要な基礎理解と、
他の受験生と決定的に差がつく「考え方の土台」を徹底解説します。
理科一類とは何か? 受験制度の基礎構造を理解する
まず、東京大学理科一類の入試制度は以下の2つで構成されています。
・共通テスト(110点満点)
・二次試験(440点満点)
合計550点の中で、実に約80%が二次試験。
つまり、東大合格を狙うなら「共通テストで9割取ったらOK」ではなく、
「二次試験で6〜7割を安定して取れる実力」がなければ戦えません。
理科一類の配点(※2025年度時点)は以下のとおりです
| 教科 | 配点 | 備考 |
| 数学 | 120点 | 最重要科目。難問処理力が求められる |
| 理科(2科目) | 120点 | 物理+化学が王道。深い理解と論理力必須 |
| 英語 | 120点 | 高度な運用力と記述力が問われる |
| 国語 | 80点 | 評論・古文中心。現代文読解力が必要 |
このように、理系科目の比重は大きいものの、
文系科目の失点が命取りになることも珍しくありません。
つまり、「理系科目で勝負、文系科目で落ちない」が東大理一合格の鉄則なのです。
東大入試の本質は「思考の深さと論理の正確さ」
東大は難関ではありますが、「突拍子もない超難問」を出す大学ではありません。
むしろ特徴的なのは、「基礎の理解が本物か」を試す問題を、
非常に深く・丁寧に出題してくる点です。
たとえば数学では、東大特有の“誘導付き証明”が出題されますが、
これは「論理を積み重ねる力」と「記述で筋道立てる力」の両方がなければ
得点になりません。
英語でも「長文を読んで要約する」「意見文を書く」など、
英語での論理構成力が問われます。
つまり、東大入試とは思考力と表現力を使って、初見の課題に挑む訓練の集大成なのです。
このレベルまで思考を鍛えるためには、受験勉強を単なる暗記作業にしないことが大前提。
すべての勉強で「なぜそうなるのか?」を問い続け、
論理で物事を理解し直すクセをつけること。
これこそが東大合格に直結する勉強法なのです。
受験の成功は「時期ごとの目標設定」にかかっている
東大理一合格者に共通するのは、「無駄のない時期別学習戦略」をもっていることです。
以下は合格者に共通するおおまかなモデルです。
| 学年 | 主な学習目的 | やるべきこと |
| 高1 | 教科ごとの基礎定着と学習習慣の確立 | 英単語・英文法・基本公式・苦手分野の洗い出し |
| 高2 | 応用力の土台作りと典型問題の網羅 | 共通テスト型演習+思考問題の導入、論述記述の基礎 |
| 高3 | 二次試験レベルの実践と合格点の安定化 | 東大過去問演習・記述対策・分野別弱点補強 |
特に高1・高2の過ごし方が極めて重要で、
ここで基礎を徹底できるかどうかが勝敗を決定づけます。
逆に高3から慌てて対策を始めた場合、二次レベルの記述に慣れる時間が不足し、
仕上がりきらないまま本番を迎えるリスクが非常に高くなります。
「偏差値」ではなく「解答の質」を高めよ
模試の偏差値に一喜一憂する受験生は多いですが、
東大に受かる人はそこに振り回されません。
理由は明白で、東大の問題は模試と質がまったく異なるからです。
たとえば記述式の数学や物理であれば、「合っているかどうか」ではなく、
「途中の論理展開が的確かどうか」で点数が大きく分かれます。
つまり、偏差値を上げるためのテクニック的な学習ではなく、
“本質を理解し、それを丁寧に記述する訓練”を優先しなければいけません。
次章からの構成
ここから先は、以下のような流れで、科目別×時期別に完全攻略法を解説していきます。
- 英語(高1〜高3)
- 数学(高1〜高3)
- 物理(高1〜高3)
- 化学(高1〜高3)
- 国語(高1〜高3)
- 共通テスト対策(高3秋〜直前期)
- 東大二次試験対策(冬〜直前)
- 合格者の実例スケジュールとまとめ
まずは次章「②英語の勉強法」から。
読解・リスニング・英作文のすべてを高1からどう育てていくかを
徹底的に解説していきます。
英語の勉強法|高1〜高3で身につける東大レベルの総合英語力【完全版】
東京大学理科一類の英語試験は、配点120点のうち、
読解・和訳・要約・英作文・リスニングと、
英語のあらゆる運用スキルがバランスよく問われます。
とくに特徴的なのは、一つの問題で複数のスキルを同時に評価する設問構成です。
たとえば、英文の構造を正確に把握したうえで和訳し、
さらに要約で論理の本質を言語化し、
最後は自由英作文で自分の意見を述べる。
このように、「読む・書く・聴く・訳す・まとめる」の
連続動作に耐えうる訓練が必要です。
以下では、英語を【高1】【高2】【高3】の3段階に分け、
東大に合格する人が実際に取り組んでいる思考法・教材選び・練習方法まで、
徹底的に時期別で解説します。
【高1】文法・語彙・精読の土台を固め、毎日英語に触れる仕組みを作る
高1では、英文解釈・構文・語彙・文法の徹底マスターが最優先です。
この時期は東大レベルの問題にはまだ手を出さず、
むしろ「構文を読み間違えない」「語順感覚を育てる」ことを重視します。
この時期の必須タスク
単語帳を1冊極める(1日30語×3周転)
・『システム英単語Basic』または『ターゲット1900』などで語彙基盤を構築
・アプリやクイズレット等でアウトプット形式の反復学習を導入
英文法の体系的理解+演習(週4日ペース)
・『Vintage』『Next Stage』『Evergreen』などで文法の網羅的確認
・文法問題集は暗記でなく「なぜその選択肢になるか」を解説と一緒に吸収すること
構文読解の練習(精読力を養成)
・『基礎英文解釈の技術100』『英文読解入門基本はここだ!』などでSVOCの把握
・パラグラフ単位で品詞と文型を確認し、構文トレースを音読と併用
音読+シャドーイングで“音と文”の一致訓練
・教科書レベルの英文でもよいので、1日5分×2セットの音読を習慣化
・リスニングではNHKラジオ英会話や『速読英単語(初級)』付属音源の活用が効果的
英語を日常に組み込む:洋画/Podcast/YouTubeの活用
・「英語は毎日使うツール」だと脳にインプットすることで、学習負荷が軽くなる
この段階では、英語を嫌いにならないこと・毎日英語を使う生活を作ることが最大の目標です。
テストの点数に一喜一憂するのではなく、「習慣の質」を磨きましょう。
【高2】論理読解・英作文・リスニングの“実戦準備フェーズ”
高2では、基礎が固まっていることを前提に、
東大入試の骨格を構成するスキルの導入訓練を始めます。
この時期に伸ばすべきは、「速く読んで論点を把握し、意見を英語でまとめる力」です。
読解スキルの深化
東大過去問の長文をパラグラフ単位で精読
・過去問をいきなり“通し読み”するのではなく、1段落ずつ構文・主張・根拠を分析
・『英文解釈の技術100→70』→東大過去問の精読へ段階的にレベルアップ
要約トレーニング(50~70語程度)
・『英語要約問題演習』や過去問素材で、パラフレーズ力+論理要約力を訓練
・日本語で要点を整理 → 英語で論理を圧縮 → 表現力を磨く の3段階を繰り返す
英作文の強化
パターンプラクティスによる表現のインストール
・例:「〜は〜より重要である」「〜と私は考える」などの表現を100個ストック
・『ドラゴン・イングリッシュ』『竹岡の英作文が面白いほど書ける本』などの活用
週1回のテーマ型英作文(120〜150語)
・テーマ例:「AIと未来社会」「日本文化の魅力」「環境問題」など
・書いたら必ず自己添削+第三者添削(添削サービスや学校の先生活用)
リスニングの戦略導入
シャドーイング+精聴の組み合わせ
・短めのナチュラルスピード素材(NHK WORLD、TED)を2〜3回ずつ反復
・1語も聞き逃さない「精聴トレーニング」で東大のスピードに慣れる
高2の1年間で、“英語4技能を試験で得点化できるレベル”に近づけることが理想です。
受験生らしい勉強に切り替えつつも、「ただ解く」ではなく
「考えて英語を運用する」学習が必要です。
【高3】得点力の安定化・過去問演習・形式対応トレーニング
高3では、合格点に達するための実践と仕上げのフェーズに入ります。
とくに6〜8月で“思考型トレーニング”を徹底し、
9月以降は「本番と同じ形式+時間」で過去問演習を回していくのが理想です。
過去問の完全活用法
90分を計測して解く訓練(週1〜2回)
・初見素材での実戦型読解を行い、解答の組み立て方と時間配分の感覚を鍛える
記述答案の精緻化
・英作文・要約・和訳の答案を毎回添削し、改善点をログに残す
各形式への対応
| 出題形式 | 得点のポイント | 高3での対策例 |
| 長文読解 | 段落構造と主張理解 | 論説文の構成読解+段落要約練習 |
| 和訳 | 文構造と自然な日本語訳 | 句・節の構造把握→日本語化の練習 |
| 要約 | 内容の圧縮・構造の再構築 | 50〜80語の要約練習+講評反映 |
| 英作文 | 論理構成+自然な英文表現 | テーマ演習+模範解答比較+添削 |
リスニング対策の最終仕上げ
・東大の形式に完全対応した模試・教材で、過去問形式に慣れる
・会話文、説明文それぞれの論理構成を意識して聴く
・音源を自分でスクリプトに書き起こして、「聴けなかった部分」を徹底分析
英語対策の総まとめ
東大英語は、「受動的なインプット」だけでは戦えません。
読む・書く・聞く・訳す・まとめるといった
「能動的な運用スキル」を高1から3年間かけて育てる必要があります。
・高1:文法・単語・構文=言語の“骨格”づくり
・高2:精読・要約・英作文=“運用力”の準備
・高3:形式対応と“合格点獲得力”の仕上げ
数学の勉強法|東大数学を突破するための戦略と演習法(高1〜高3)
東京大学理科一類における数学は、合否を最も左右する最重要科目です。
配点は120点で、全5問中2問以上を完答することが目安。
標準〜やや難レベルの問題に加え、
思考力や構成力が問われる記述問題も多く出題されるため、
「なんとなく解けた」では得点につながらないのが東大数学の特徴です。
合格者の得点レンジは60点前後。
つまり、半分以上得点できれば優位に立てる一方で、
0完(1問も完答できない)では合格はほぼ不可能です。
完答2問+部分点2問が合格のモデルケースです。
ここでは、高1・高2・高3の時期別に、
どのように東大数学の実力を養っていくかを具体的に解説します。
【高1】数学的思考力の芽を育てる「基礎+理解+定着」の徹底
高1では、とにかく教科書レベルの完全理解と、標準問題の着実な演習が最優先です。
公式を丸暗記して当てはめるだけの学習では、東大数学にはまったく歯が立ちません。
「なぜこの解法を使うのか」「他の解法はあるか?」と自問自答しながら、
思考を深めることが重要です。
この時期にやるべきこと
学校の教科書を“完璧にする”ことを最優先
・例:教科書の例題・章末問題をすべて自力で説明できるようにする
・教科書ガイドやチャート式(白・黄)で確認演習を重ねる
標準問題の解法パターンを吸収
・『基礎問題精講』『青チャート』で定着確認
・問題の背景にある「考え方」を整理してノート化
ノート整理で“なぜこの手法を使うか”を言語化する訓練
・「この問題では数列の漸化式を使う理由」「なぜベクトルより座標を選んだか」など、自分の言葉でまとめる
ミス分析+やり直しノートを必ず作成
・解けなかった問題は「原因分析→再演習→類題で確認」という3ステップで対処
高1では焦って難問に手を出すのではなく、
基礎を理解し尽くす→“解法の選択眼”を育てることが最大のテーマです。
この土台がないと高2以降に伸び悩みます。
【高2】典型問題+応用問題への架け橋を構築する時期
高2では、典型問題の「瞬時解法」+応用問題への挑戦を進めていきます。
東大数学は、典型問題の知識を「どう加工して活用するか」を見られる試験。
つまり、「覚えた解法を応用して構成する力」が試されるのです。
高2で強化すべき内容
典型問題を時間制限付きで高速処理
・『1対1対応の演習』で1問20〜25分を意識して演習
・難問に取り組む前に「標準問題でミスしない」「早く解く」精度を追求
分野別の応用問題にトライ
・数列の漸化式誘導問題、複雑なベクトル、整数問題など
・『標準問題精講(上級)』『入試の核心(難関編)』などで多様な出題形式に触れる
答案構成力の養成
・「1問につき10行以内で答案を書く」練習
・途中式を論理的に並べる癖をつけ、他人が見て理解できる答案を目指す
週1ペースで東大過去問の要素分解
・過去問を丸々解くのではなく、「これは典型問題か」「何を応用した問題か」を読み解く分析力を養成
この時期に“思考型の数学”へ移行できるかどうかが、
理科一類で数学を武器にできるかどうかの分水嶺です。
【高3】本番形式での得点力強化+答案精度の最終調整
高3では、本番を想定した演習と記述答案の精密化にフォーカスします。
6月~8月は苦手分野の克服、
9月以降は東大形式の過去問・模試・類題を中心に演習を進め、
出題傾向・時間配分・答案構成に対する「感覚」を仕上げていきます。
やるべきこと
過去問10年分を最低3周
・初見で解く → 自己添削 → 模範解答と比較 → 書き直し
・記述内容の「抜け・無駄・不明瞭」をすべてチェック
時間配分シミュレーションを繰り返す
・本番と同じ120分で5問演習を繰り返す
・「完答する問題」「部分点狙いの問題」「捨てる問題」を明確に見極める
答案添削とブラッシュアップ
・解けたつもりでも伝わらない答案は得点にならない
・模試・塾・教師に添削を依頼し、より精密な記述へ進化させる
入試頻出テーマを特訓
・数列(漸化式・数学的帰納法)
・整数(約数・倍数・mod)
・図形(ベクトル・座標)
・複素数平面と関数融合問題
・確率(漸化式、期待値問題)
東大数学を得点源にするためのマインドセット
- 完答2問+部分点2問を常に狙う意識
- 模範解答を真似るのでなく、なぜそう書くかを理解する
- 記述を他人が読んで納得できるレベルまで磨く
- 時間の使い方(捨て問判断・途中までの処理)に慣れておく
- “考え抜く経験”の蓄積が合否を分ける
東大数学に王道はありませんが、「基礎の徹底→解法の選択力→答案表現の精度」
という3段階を段階的に積み上げることで、初見問題への対応力が飛躍的に向上します。
物理の勉強法|東大物理で得点源を作るための本質理解と計算力(高1〜高3)
東京大学理科一類の物理は、理系受験生にとって“勝負を分ける科目”の一つです。
配点は理科全体で120点、その半分(=60点前後)を物理が占めるため、
物理を得点源にできるかどうかで合否が決まるケースも少なくありません。
東大物理の特徴は、単なる知識暗記では解けない
「本質的理解と物理的思考力」が必要な問題が出るということです。
計算力だけでもダメ、公式丸暗記でも太刀打ちできません。
必要なのは、物理現象をイメージし、
それを式に落とし込む「論理の筋道」を構築する力です。
この章では、物理を“得点源”に変えるための時期別戦略を、
高1〜高3の3段階に分けて徹底的に解説します。
【高1】物理的なものの見方・考え方をインストールする段階
高1で物理を履修する学校は限られていますが、
先取り学習や探究活動を通じて「物理ってこういう学問なんだ」
という感覚を身につけておくことは非常に重要です。
この時期の目標
物理の考え方を理解する
・「自然現象を数式で表す」ことの意味を知る
・公式=暗記すべきもの、ではなく「関係式」であることを体感する
やるべき学習
高校物理のエッセンスに触れる
・『橋元の物理をはじめからていねいに』などで力学の基本に触れる
・「力のつり合い」「運動方程式」などを図とともに理解
数式と図像の対応力を育てる
・数式が何を意味するかを図にしてイメージ化する練習
・単位の確認や次元解析を癖づけることで「誤った式」を早期に見抜く力を養う
この段階では、正答率よりも理解の深さ・現象のイメージが何より大切です。
【高2】公式の運用力と典型問題処理能力の習得
高2では本格的な物理の学習が始まり、
力学・波動・熱・電磁気といった主要分野を履修します。
この時期にやるべきは、
「教科書レベルの物理を確実に理解し、典型問題の処理を高速化すること」です。
学習内容と進め方
各分野ごとの定義・法則の理解を徹底
・例:「運動方程式=加速度の定義」ではなく「力の釣り合いからの運動モデル構築」
・「ファラデーの法則=コイル内磁束の時間変化」における物理的意味を図解
『良問の風』『重要問題集』などで演習
・定義→公式→条件整理→立式→計算→検算の流れを徹底
・簡単な問題でも「図→立式→式変形」までの一連の流れを意識する
分野別に「間違える問題の傾向」を蓄積
・力の分解を間違える、初期条件の読み落とし、単位換算など
・自分の“物理的思考の弱点”を早期に可視化しておく
この時期に、「物理の型」と「典型問題の解き筋」を頭と体に叩き込んでおくことで、
後の応用問題や東大過去問にも対応できる“基礎の力”が完成します。
【高3】東大型問題への適応訓練と答案作成スキルの確立
高3では、「複雑な条件を読み取り、自分でモデルを構築し、答案に仕上げる」
という総合的な訓練が必要になります。
東大物理の問題は、「文章が長い」「図がない」「情報を自分で整理する」
という点で非常に特殊です。
具体的な学習戦略
東大過去問10年分を徹底演習+復習
・問題文の読み取り、情報の抜き出し、物理モデルの構築を1つずつ丁寧に行う
・解いたら終わり、ではなく「なぜその式?」「他のアプローチは?」を再検討
答案構成の型を確立する
・「与えられた条件→定義式・法則→立式→導出→結果整理」までを段階的に書く
・記述式では、式だけでなく“どのような考えで立式したか”を記述するクセをつける
頻出テーマの重点強化
・力学(運動方程式+保存則の組み合わせ)
・電磁気(コンデンサー・回路+エネルギー)
・波動(重ね合わせ、反射・干渉、図示問題)
・熱力学(熱力学第1法則、状態変化、グラフ問題)
演習ノートを“思考の記録帳”にする
・解けた問題も「どこで思考が切り替わったか」「どの条件に注目したか」を記録する
・思考の軌跡を言語化することで、初見問題への対応力が高まる
東大物理で差がつく“5つの鍵”
- 現象を頭の中で映像化できるか
- 与えられた情報から式を導けるか
- 立式の根拠を説明できるか(記述力)
- 計算力が正確かつ速いか
- 答案が読みやすく論理的に構成されているか
東大物理で合格点を取るには、1問完答+部分点2問を狙うのが王道です。
合格者平均は30〜40点台、逆に20点以下では他科目でよほど稼がないと
合格は厳しくなります。
化学の勉強法|東大化学を攻略するための理解力とスピードの両立(高1〜高3)
東大理科一類における化学は、理科2科目のうちの1つとして60点分の配点を持ちます。
物理より短文で与えられることが多く、
一見すると「取り組みやすい」と思われがちですが、
実際は膨大な知識・緻密な計算・論理構成力の三拍子が問われる極めて高難度の科目です。
東大化学の特徴は、単なる「暗記型」では通用しないこと。
たとえば、有機化学の構造決定問題や無機の反応記述問題では、
「なぜその現象が起きるのか」を根本から理解し、
それを数式や言葉で表現する力が問われます。
また、問題数が多く計算量も決して少なくないため、
「短時間で正確に処理する力」も合格に必須です。
この章では、東大化学で得点源を作るために必要な時期別戦略を
【高1】【高2】【高3】の3段階に分けて解説していきます。
【高1】化学への“理解の土台”を築くステップ
高1の段階では、化学をまだ履修していない学校もあります。
しかし、先取り学習や中学理科の延長線で、
「物質を構造や反応として捉える力」を育てることは可能です。
この時期の目標
原子・分子・イオンの構造的理解
・「物質は粒子でできている」ことを数値や図でイメージできる
・「電子配置」「イオン化エネルギー」「周期表の意味」を理解する
学習方法
・『橋元の化学』や『セミナー化学基礎』などで先取り
・YouTubeやNHK for Schoolの高校化学動画を活用
・中学範囲の発展問題(酸・塩基・化学反応式など)で演習
この時期に「化学は暗記科目ではなく、“関係性の学問”である」と認識できれば、
以降の成績が飛躍的に伸びます。
【高2】理論化学・無機化学・有機化学をバランスよく理解する段階
高2では化学の学習が本格化します。
この時期は、“知識の理解”と“問題処理能力”をセットで育てることが重要です。
理論化学(計算+理解)
計算系(モル計算・酸塩基・酸化還元・気体の法則)を徹底マスター
・ただ公式を当てはめるのではなく、「なぜこの計算式になるのか」を常に言語化
・『化学重要問題集(理論編)』や『化学基礎問題精講』を活用
グラフ問題・比較問題を通じて応用力を鍛える
・吸熱・発熱、溶解度曲線、電池の電圧変化など、計算と論理を融合した問題に挑戦
無機化学(知識整理+反応予測)
周期表に基づく反応性の比較を理解
・例:「NaとKで反応性が異なる理由」や「遷移元素の特徴」
色・沈殿・反応性を“構造と関連づけて”記憶
・ゴロ合わせではなく、電子配置・価数などの本質に基づいた理解を優先
『化学の新演習 無機編』『元素別ノート』などでまとめ直す
有機化学(構造+反応パターン)
・基礎構造(炭化水素・アルコール・カルボン酸など)を描けるようにする
・官能基ごとの反応パターンを整理し、グルーピングで記憶
・構造決定問題を通じて“化学的思考力”を鍛える
【高3】過去問・実戦演習で記述力と処理速度を仕上げる
高3では、知識と理解を活用し、
限られた時間で“正確な記述”ができるように仕上げる時期です。
過去問演習のポイント
10年分の東大過去問を3周
・1周目:情報整理と考え方をノートにまとめる
・2周目:時間を測って“実戦訓練”
・3周目:記述の練度と表現力に集中
答案構成は「論理 → 式 → 数値 → 結論」
・特に有機化学では、「推論の過程」を簡潔に、かつ明瞭に書くことが得点の鍵
出題形式別対策
| 分野 | 出題傾向 | 対策 |
| 理論化学 | モル計算・グラフ問題・電池 | 関係式を意味から導出する訓練 |
| 無機化学 | 反応式記述・性質比較 | 知識を反応機構とセットで記憶 |
| 有機化学 | 構造決定・異性体・反応予測 | パターン整理+過去問で反復 |
過不足のない答案を書く訓練(記述力のブラッシュアップ)
・簡潔に論理展開する→読み手に理解しやすい答案を作る
・採点官の視点で「読んでわかるか?」を自己チェック
東大化学に必要な3つの力
- 公式や知識の“背景”まで理解しているか
→ 単に覚えるのでなく「なぜそうなるか」を説明できる - 素早く正確な計算力
→ 定義・数式の整理を省略せず、手順を明確にする - 日本語記述で物質や反応を論理的に説明できる力
→ 本番で点数になるのは「説明できるかどうか」
国語の勉強法|東大理系でも差がつく!現代文・古文の得点安定化戦略(高1〜高3)
理科一類を受験する理系生にとって、国語は軽視されがちな科目です。
しかし、東大の配点を見ると、国語は80点満点と無視できないボリュームを持ち、
足切り回避・逆転合格・合格安定化のすべてに関わってきます。
特に、数学や理科が苦戦する年(易化せず平均点が低い年)には、
「国語でいかに取りこぼさないか」が合否を左右するケースも多く、
“理系こそ国語が武器になる”という側面があります。
しかも東大の国語は、いわゆる「なんとなく読んで答える」タイプの問題では通用せず、
論理的な読解・構造把握・言語化スキルがシビアに試されます。
現代文では要素の関係性を見抜く力、
古文では文法構造とストーリー解釈の両立が必須です。
ここでは、高1~高3にかけてどのように国語力を伸ばしていくかを、
現代文・古文に分けて時期別に戦略的に解説していきます。
【高1】語彙・文法・構造把握力の土台づくり
高1では、「国語が得意な人と苦手な人の差」が大きく開きはじめる時期です。
この段階では、“何となくの読解”から“構造的な読解”への脱却が最重要課題となります。
現代文の対策
論理構造を意識して読む訓練
・「筆者の主張→理由→例→反論→再主張」の展開パターンに注目
・接続語(しかし、つまり、たとえばなど)にマーカーを引きながら精読する
記述式の要約トレーニング(100字〜150字)
・教科書や問題集の本文を読んで、要点を文章化する練習
・『現代文読解力の開発講座』(Z会)などを活用して論理思考を強化
古文の対策
文法の完全理解(助動詞・助詞・活用形)
・『マドンナ古文』『望月光の古典文法講義』などで体系的に文法を固める
古語単語をストーリー形式で覚える
・『ゴロゴ古文単語』『有名私大古文単語』などを1日10語×3周で定着
音読+文構造分析で読解の感覚をつかむ
・主語・目的語・述語をマーカーで区別し、品詞分解しながら読み進める
【高2】記述力・設問対応力の育成とスピードの強化
高2では、東大型の記述問題に徐々に触れながら、
「書く→直す→伝える」という国語の実践訓練をスタートします。
現代文の対策
過去問の部分演習をスタート
・いきなり全文通しで解かず、設問単位で解答方針・根拠を明確にする
・「なぜその選択肢になるか/記述のどの部分で点が入るか」を分析
構文と論点の可視化練習
・本文に「主張」「例」「逆説」などのラベルを付ける読解法を習慣に
記述問題の“根拠→言語化”の訓練
・解答を写すのではなく、「なぜこの答えになるのか?」のプロセスを言語化して確認
古文の対策
主語・目的語の明示と敬語理解をセットで強化
・登場人物の「誰が誰にどうしたか」をストーリーと敬語表現で把握する
品詞分解と現代語訳のセット演習
・短文の現代語訳を毎日1問こなす→正確な文構造理解+語彙定着が図れる
共通テストや早慶型のスピード演習にも少しずつ対応
・文章量の多い設問で時間配分を試す
【高3】過去問実戦・記述安定化・読みの柔軟性の仕上げ
高3では、東大過去問を通じた答案作成訓練と時間内処理能力の確立がカギになります。
現代文の対策
過去問演習は“設問ごとの採点基準”を意識
・何を書けば点が入るかを分析 → 模範解答と照合して“言い回し”を吸収
採点官の視点で自分の答案を読み直す訓練
・客観性・論理性・明瞭さの3点を毎回チェック項目に入れる
段落ごとの要約+設問構造分析ノートを作る
・各年度の過去問で「本文構造と設問構造」のパターン化を行う
古文の対策
東大特有の“文脈把握型”問題に慣れる
・典型:「このときの登場人物の心情を述べよ」「なぜこの展開になるか」など
・選択肢で済む問題ではなく、「流れの中で主語が誰か」を把握する練習が必須
語句・接続表現・敬語の総復習(=記述の根拠づけ)
・根拠となる表現を見逃さない→記述に根拠がないと失点になる
東大国語で差がつくポイント
| 項目 | 要点 |
| 構造把握 | 論理展開・対比・因果をマークしながら読む |
| 根拠の明確化 | 答えは「本文のここにある」と説明できる必要がある |
| 書く力 | 余計な修飾を削ぎ落とし、筋の通った短文を記述する |
| 古文の人物関係 | 主語の把握・敬語の読み取りで得点差が出る |
| 演習の質 | ただ解くのではなく、本文・設問・解答すべてを構造的に見直す |
共通テスト対策|高得点を安定させる戦略と実践メニュー(高2冬〜本番直前)
共通テストは東京大学入試における一次関門として、
多くの受験生が「通過点」と捉えがちですが、
実際には合否に直結する非常に重要な試験です。
理科一類の共通テストの配点は110点。
たった20%と見えるかもしれませんが、その20%がボーダー上で大きく響くことは、
過去の合格者データからも明らかです。
とくに共通テストで大きく失点してしまうと、
「足切り」によってそもそも二次試験を受けることすらできません。
東大理一の足切りボーダーは年によって異なりますが、
目安として共通テスト8割後半〜9割超え(得点率88〜92%)が安全圏とされています。
では、二次重視の東大入試において、なぜ共通テストの得点力が重要なのか。
そしてどのように効率よく準備を進めるべきか。
高2の冬から高3本番直前までの時期別に、具体的な対策戦略をお伝えします。
共通テストで求められるのは「処理力」と「失点回避の徹底」
共通テストはセンター試験と異なり、
単純な知識の正誤よりも思考力・情報処理力・スピードのバランスが問われます。
設問形式も多様化しており、
「文章量が多い」「図表や資料を読み取らせる」問題が増加傾向にあります。
そのため、高得点を安定させるには、単に知識を詰め込むだけでは不十分です。
知識を「適切なタイミングで引き出し、正しく使えること」が前提となり、
加えて「時間内に解ききるための訓練」も必要です。
つまり、共通テスト対策とは
「基礎知識を高速で正確に運用するトレーニング」そのものなのです。
高2冬〜高3夏までに“型”を完成させる
東大受験生が二次試験対策に集中するためには、
共通テスト対策は前倒しで完成させることが鉄則です。
高3の秋から本格的に共通テストに取り組む受験生も少なくありませんが、
これでは二次の演習時間を削ることになり、総合力で不利になります。
理想的には高2の冬から共通テストの形式を確認し、
高3の夏までには「どの科目で何点取るか」という得点配分を決め、
実際に模試や演習でそれを安定して出せる状態に持っていくことが目標です。
たとえば数学や国語は、
「時間が足りずに最後まで解ききれない」というケースが非常に多いため、
早い段階から時間を測っての演習が必要です。
英語はリーディングとリスニングでバランスよく点数を稼ぐ戦略を、
高3前半に確立しておくべきです。
科目ごとの戦略的アプローチ
共通テストでは、すべての科目で8割以上の得点を安定させる必要があります。
ただし、満点を目指すのではなく、
「確実に落とさない構造を作る」という意識で対策に取り組むことがポイントです。
英語は配点が大きく、リーディング・リスニングともに高得点が求められます。
リーディングは長文量が多く、単語力だけでなく「速読+論理整理」が不可欠です。
ニュース形式、広告、図表など、非典型的な英文にも慣れておきましょう。
リスニングは毎日触れることが大切です。
YouTubeやNHKラジオ英会話などを活用して、日常的に耳を鍛え、
東大レベルの長文理解とは別軸で、英語音声への即応力を育ててください。
数学は得点源である一方、共通テスト形式では“罠”となりやすい科目です。
解法パターンのインストールとともに、「問題文の読み取り」「手順の整理」
「ケアレスミスの防止」の3点が重要です。
定番問題を10回以上繰り返し解いて、
出題傾向と数字処理スピードを高めておくと安心です。
国語は多くの受験生が苦手とする科目です。特に時間配分が難しく、
「現代文に時間をかけすぎて古文・漢文が手薄になる」という失敗パターンが頻出します。
これを防ぐには、事前に「設問形式に慣れる」
「接続語と要点にマーカーを引きながら読む」などの訓練が必要です。
古文単語と漢文句形は、基礎を早期に固めておくことで演習の効果が倍増します。
理科・社会については、「資料読解・グラフ分析・選択肢の比較」など、
表現形式への慣れが重要です。
理系科目でも知識偏重にならず、複数条件の処理や仮説の検証などを求められるため、
単純暗記の学習法を続けていると対応できません。
知識を“運用する”演習を繰り返しましょう。
直前期の追い込みと調整方法
高3の11月以降は、共通テスト演習を週1〜2回ペースで全科目回し、
実戦の時間配分・精神的持久力・答案作成力を磨いていきます。
特に「1日に複数科目を連続して解く」ことで、
共通テスト本番に近い疲労感と集中力のコントロールを体験できます。
これは二次対策の合間でも可能なので、
週末などを使って模試形式の自習日を取り入れましょう。
直前期は「やってない教材に手を出す」のではなく、
「過去に解いた問題のやり直し」「解法の確認」「ミスパターンの修正」
に時間を割くべきです。
追い込むより、失点を防ぐ仕組みの再確認が合格への鍵となります。
共通テストを制する=東大二次に集中できる“時間”を得る
共通テスト対策の本質は、「高得点を取ること」ではなく、
“得点を安定させて、二次対策に使える時間を確保する”ことです。
80〜90点を1点上げるために40時間をかけるのは非効率です。
それよりも「絶対に落とさないライン」でまとめ上げ、
東大独自の記述対策に全力を注ぐほうが、合格には合理的です。
理系科目が得意な受験生ほど共通テストを軽視しがちですが、
「準備不足による足切り」「失点によるボーダー割れ」は実際に毎年起きています。
必要なのは、共通テストを戦略的に早期クリアし、
東大二次に全集中できる環境を自分でつくることです。
東大二次試験対策|本番で得点する答案力を鍛える方法
東大理科一類の合格を決める最大の勝負所が「二次試験」です。
総配点550点のうち440点、実に8割を占めるこの試験では、
単なる暗記やテクニックでは通用しません。
必要なのは、「本質を理解しているか」「問われていることに的確に答えているか」
「論理的で採点者に伝わる答案を書けるか」といった、
受験勉強の集大成としての“記述力”です。
この章では、東大二次試験に向けて、英数理国の記述力を高め、
限られた時間内で「得点につながる答案を作る」ための思考法・訓練法・演習方法を
時期別に解説していきます。
東大記述試験の本質は“採点者との対話”
まず理解しておきたいのは、東大の記述問題は「正解を出す」ことよりも、
「どう考え、どう導き、どう伝えるか」を評価されているということです。
つまり、答案とは採点者とのコミュニケーションツールであり、
論理的で読解可能な“言語”として整っているかが合否に大きく影響します。
たとえば数学では、たとえ答えが正しくても途中の論理展開が飛躍していたり、
誤字・略記で意味が曖昧であったりすると、点数が大きく削られます。
英作文や国語でも、「読んで意味が通ること」は得点の大前提であり、
「うまく伝わる」答案はそれだけで有利になります。
この“伝える答案力”を高めるには、知識のインプットだけでなく、
「出力=書く」練習を通じて、答案構成力・論述力・表現力を磨く必要があります。
高3春〜夏:記述答案の“基礎フォーマット”を固める
この時期のテーマは、各科目での「答案の型を確立する」ことです。
たとえば数学であれば、「仮定→計算→証明→結論」という順序を明示する。
物理では、「状況設定→物理法則→立式→計算→解釈」という流れを崩さない。
英語の要約や英作文では、
「導入→理由・根拠→結論」の構成を常に意識する。これが“型”です。
この“型”を作ることで、記述答案の再現性が高まり、
どんな問題でも一定以上のクオリティを保つことができます。
実際、東大合格者の多くは「答案の型が体に染みついている」ため、
本番で初見の問題に出会っても、動揺せずにいつもの構成で答案を作ることができます。
また、演習においては、解けた問題だけでなく
「解けなかった問題の答案も必ず最後まで書く」ことが重要です。
途中で止めず、自分の思考過程を言語化してみることで、
「どこまでなら書けるか」「何がわからなかったか」が可視化され、
飛躍的に力がつきます。
高3秋:本番形式での答案力を養成する
9月以降は、「東大型の出題に、時間内にどれだけ点を取れるか」という
実戦力を磨く時期です。
この段階では、過去問を週1〜2回のペースで演習し、
“2時間で答案を出しきる”という感覚とペース配分”を徹底的に身体に叩き込みます。
過去問演習では以下の観点で振り返りを行いましょう。
・時間配分は適切だったか(1問に何分かけたか、飛ばす判断は正しかったか)
・書いた答案は読みやすいか(字の大きさ・語句の正確性・論理の繋がり)
・採点基準に沿って答えていたか(答えるべきことを外していないか)
この振り返りを通して、「答案の質」を高めていくのがこの時期の最大の目標です。
東大の問題は、1つの問いの中に複数の問いが隠れていることもあり、
表面的に答えたつもりでも本質に触れていない答案は減点されやすくなります。
高3冬〜直前期:部分点を確実に拾うための“最終答案調整”
直前期に焦るべきは「解けない問題を何とかする」ことではありません。
それよりも、
「解ける問題で確実に得点する」
「わからない問題でも途中点を狙う」
という“得点最大化の発想”が重要です。
数学では、最後までたどり着かなくても、
「正しく立式した」「条件をうまく整理した」などで部分点が得られることが多く、
“書かない=0点”になるのは極めてもったいないことです。
物理・化学も同様で、
「図を描く」「数式で法則を書く」「単位や傾向を書く」などの
“プロセスを見せる”答案が高得点の鍵になります。
記述試験とは、「できることは全部出す」「考えたことを余すことなく伝える」ことが
許された舞台です。
本番で白紙を作らない訓練を、直前期こそ重視してください。
また、過去問の2周目・3周目を行う際には、「模範解答を完コピする」のではなく、
「自分の言葉で模範解答を再構成する」ことが効果的です。
これにより、思考の中身まで消化・吸収され、
自力で使える“答案パターン”として定着します。
東大二次試験で得点する人の特徴
・記述に“空白”を作らず、自分の言葉で説明する癖がある
・問題の“意図”を読み取り、答えるべき内容を明確に区別している
・書く順番・構成・表現がブレず、「安定感」がある
・論理性・計算力・表現力のバランスが取れている
答案とは、学力の鏡です。
そして東大は「思考を言語で伝えられる人材」を求めています。
そのための鍛錬を、演習・添削・再構成を繰り返す中で積み重ねていくことが、
最後の勝負で“本当に差がつく力”を育ててくれます。
合格者の年間スケジュールと勉強戦略総まとめ|東大理科一類に合格する人の1年の歩み方
東大理科一類の合格を目指す上で、多くの受験生が抱く共通の疑問があります。
「東大に受かる人って、1年間でどれだけのことを、どうやって積み上げてるの?」
「いつまでに何を終わらせれば間に合う?」という問いです。
この章では、これまでに解説してきた教科別の戦略を時期ごとに整理し、
1年間の学習ロードマップとして再構成します。
単なる理想論ではなく、実際に東大に合格した受験生たちが実践していた
現実的な学習スケジュールをモデルにしています。
4月|受験戦略のスタート地点:「基礎の棚卸し」と「苦手の言語化」
新学年を迎える4月。
受験の1年はここから始まります。
この月にやるべきことは明確で、まずは「自分の現在地を把握すること」です。
焦って新しい問題集に手を出すのではなく、
まずは「これまでに学んだ内容を、どれだけ“使いこなせるか”」を見直しましょう。
特に理系受験生の場合、「知識はあるけど、記述答案として形にできない」
「解法は知ってるけど、なぜその方法で解くのかが説明できない」
という“理解と出力のズレ”が多く見られます。
このズレを修正することが、4月の最大のテーマです。
【科目別:具体的な勉強内容と方法】
数学:典型問題を“語れるか”で基礎をチェック
青チャートや『1対1対応の演習』の例題レベルを使用し、
1日2〜3問ずつじっくり解いていきます。
ポイントは「解法を思い出す」ことではなく、
「なぜこの解き方なのかを、言葉で説明する」こと。
友人や先生に口頭で説明する練習も非常に効果的です。
【おすすめ勉強法】
・例題を“解かずに”眺めて、解法の意図を予想 → 実際の解法と照合
・毎日1題、自分のノートに「手書きで完全解答+注釈」を記述
・「なぜこの順序で式変形するのか」など、論理構成の確認を習慣化
物理・化学:教科書とセミナーで「公式の背後」を徹底確認
物理では『物理のエッセンス』や『セミナー物理』、
化学では『セミナー化学』や『リードα』を使い、基本公式や現象を、
数式だけでなく言葉や図でも説明できるようにします。
特に物理の力学や波動、化学のモル計算・酸塩基・電池などは、
基礎に見えて実は穴が出やすい分野。
数式と現象の対応関係を意識しながらノートをまとめ直す作業を行ってください。
【チェックポイント】
・教科書の例題をすべて解き直す(空欄を埋めず、自力で説明)
・計算式を使わず、文章だけで現象を説明する訓練をする(特に物理)
英語:文法と構文の“使用感”を取り戻す
この時期の英語学習は、「文法知識の再構築」と「構文レベルの精読力強化」が中心。
『英文解釈の技術100』や『基礎英文解釈の技術70』を1日1〜2文ずつこなして、
「SVOC」や修飾関係を正確に意識して読む練習を行います。
また、文法は『Vintage』や『Next Stage』で
「1日2セクションずつ」などのマイルールを決め、毎日15分ずつ進めましょう。
短時間でも毎日継続することで定着が加速します。
国語:古文の文法と語彙、現代文の“論理読み”に着手
古文ではまず助動詞・敬語・助詞といった文法のルールを体系的に整理します。
おすすめは『マドンナ古文』『望月光の古文講義』など、文法中心の参考書。
これらを活用して、「なぜこの訳になるのか」を理解ベースで学びましょう。
現代文では、いきなり問題演習を始めるのではなく、
『現代文読解力の開発講座』などを使って、
「主張→理由→例」の構造をマーカーで読み取る練習からスタート。
文章構造にマークを入れる習慣をつけると、後の設問対応が一気に楽になります。
【補足:自習ルーティン例(4月のモデル1日)】
| 時間帯 | 内容 |
| 朝(60分) | 英文法1セクション+英文解釈1題(構文精読) |
| 午前(90分) | 数学例題(1対1)を2題記述+復習ノートまとめ |
| 昼(60分) | 古文文法講義→演習10問+古文単語20語復習 |
| 午後(90分) | 物理または化学の基本演習(公式の意味を言語化) |
| 夜(30分) | 模試の過去問を軽く眺めて、「自分にできること/できないこと」を記録 |
5月|答案力の育成開始:知識を“使う”フェーズへ移行
4月に学習の棚卸しを行い、自分の弱点や理解のズレがある分野を明確にしたら、
5月はそこから一歩進んで「知識を使える状態」に変えていく段階に入ります。
この時期から重要になるのは、「解けるようになる」ではなく、
「採点者に伝わる答案を書けるようになる」こと。
東大では途中点の配点が大きいため、たとえ最後の答えにたどり着けなくても、
考え方を言語化しながら進める訓練を始めることが、後々大きな差となります。
【科目別:具体的な勉強内容と方法】
数学:1問1問を“答案として完成”させる記述演習
この月からは、ただ解けたかどうかではなく、
「解法を筋道立てて説明できるか」を重視してください。
使用教材は『1対1対応の演習(東大レベルまで網羅)』や『標準問題精講』
『やさしい理系数学』などでOK。
大切なのは、解いた問題を答案として仕上げる訓練です。
【おすすめ勉強法】
・1日1題を記述形式で丁寧に解く(目標:30分以内に答案作成)
・解いたあとに「他人に説明するならどう書くか?」の視点で再構成
・模範解答の写経ではなく、「自分の言葉」で解法をまとめ直すことが重要
ポイント
答案の冒頭に「問題の型」と「使うべき道具」を一文で宣言して書き始めると、
論理がぶれにくくなります。
物理・化学:計算力より“思考プロセスの見える化”が重要
東大の理科では、「何を根拠に立式したか」「どの法則を、なぜ使ったか」
が明確に書かれていないと点数がもらえません。
つまり、“考え方の途中”をきちんと見せる必要があるということです。
物理では『良問の風』や『重要問題集(A問題)』、
化学では『セミナー化学』や『化学基礎問題精講』を使い、
以下のようなステップで答案作成を意識しましょう。
【物理の記述型プロセス例】
- 問題の状況を図に描く(力の向き・速度・加速度・境界条件など)
- 適用する法則を宣言(例:運動方程式、エネルギー保存則)
- 式の導出過程を丁寧に書く(途中式も採点対象)
- 単位・符号・境界条件のチェックをする
【化学の記述で狙われる視点】
・濃度やモルの意味を言語で説明できるか(単位を忘れない)
・電池の電圧、化学平衡、電離度など“変化の概念”に強くなる
・構造決定問題では、「何を手がかりにどこまで分かるか」を段階的に記述する
英語:精密和訳と英作文の“アウトプット訓練”本格化
5月は英語の勉強が大きく動き出すタイミングでもあります。
中でも重要なのが、「日本語で丁寧に訳す力(精密和訳)」と
「日本語を英語に直す力(英作文)」の2つです。
【おすすめ教材・進め方】
・『英文解釈の技術100』を1日1文、構文分解→精密和訳→自己添削
・『ドラゴン・イングリッシュ 基本英文100』や『英作文のトレーニング』で、1日1文のライティング
・英作文は最初は「自分で書く→模範解答と比較→書き直し」の反復。丸暗記ではなく「表現を再現する」意識が重要です。
また、時間に余裕がある日には、
『東大英語要約特訓』を使って70語の要約問題にも取り組みましょう。
まだ完璧にできなくても、
「主張+根拠+結論」の型を意識して書く習慣をこの時期から持つことで、
秋以降の得点力に直結します。
国語:現代文は“構造読み”、古文は“助動詞・敬語の正確な運用”を意識
現代文では、
東大特有の設問タイプ(段落指定なし・説明要求型)に対応する力をつけるために、
まず「構造把握」の習慣を徹底させます。
『得点奪取 現代文』や『現代文読解力の開発講座』を使って、
文章全体の「主張・理由・具体例・対比・結論」の配置を分析しながら読むと、
設問の意図が見抜けるようになります。
古文では、5月中に「助動詞の意味と活用」「敬語の種類と主語推定」が
“自力で運用できる”状態に仕上がっていることが望ましいです。
『マドンナ古文』や『古文上達』などで、
「文法を判別したうえで、意味を通して読む」段階へ進みましょう。
【5月の1日モデル学習ルーティン(例)】
| 時間帯 | 内容 |
| 朝(60分) | 英文解釈+ドラゴン・イングリッシュ1題 |
| 午前(90分) | 数学 記述問題演習(1題を答案仕上げ)+解説分析 |
| 昼(60分) | 古文助動詞・敬語演習+単語30語復習 |
| 午後(90分) | 物理 or 化学の記述対策(プロセスの見える答案) |
| 夜(30分) | 東大過去問の問題文を眺めて設問分析だけ行う習慣 |
6月|演習の「再現性」を確立する:記述力・得点力の仕上げ段階へ
6月は、受験学習の前期の集大成ともいえる重要な時期です。
基礎~標準問題の理解がある程度進んだ段階で、
次に求められるのは「本番で解ける力=再現性の高い答案作成力」です。
ここでのキーワードは 「答案の安定感」。
すなわち、「一度解けた問題を何度出されても正確に、論理的に、
時間内に解き直せる」状態を目指します。
そのためには、これまでに解いてきた問題の「解法の型」を
確実に自分の中に定着させる必要があります。
【科目別:6月の具体的勉強戦略とトレーニング法】
数学:答案の構成パターンを“体で覚える”フェーズへ
6月の数学では、「問題→答案」の変換プロセスを高速化・安定化させる訓練を行います。
解法の暗記ではなく、
「初手で何を使うか→論理展開→計算→結論」の一連の思考を
スムーズに行えるようにしなければなりません。
【実践ポイント】
・『標準問題精講』『やさしい理系数学』『東大の理系数学25ヵ年』を活用し、1日2題演習+1題復習
・時間制限つき演習(1題25分など)を入れることで、本番を意識した処理力を養成
・「式の導入」「変数の意味」「導出の意図」など、“説明しながら”書く訓練を継続
6月中に最低20〜30題の「記述完成答案」を積み上げましょう。
すべて“書いた答案を読み返す”ことで、論理破綻・飛躍のチェックも必ず行います。
物理・化学:答案に“説明”を添える練習で精度を上げる
この時期の理科は、単なる立式・計算ではなく、
「記述を加えて満点に近づける答案構成」が目標です。
たとえば物理であれば、
「なぜその公式を使ったのか」
「どの方向にどんな力が働いたのか」
まで日本語で添えることで、
部分点を拾うのではなく“満点を取りにいく答案”に変わっていきます。
【物理】
・『名門の森』『良問の風』で、1日1題を“日本語コメント付き”で解く
・解法の方針をノートの冒頭に1文で書く(例:「位置エネルギーの変化を使って速度を出す」)
【化学】
・『重要問題集』『化学の新演習(基礎)』を用いて、構造決定・計算・化学平衡を中心に記述力強化
・記述が必要な問題では、「この式はなぜ使えるか」「この反応が起こる理由は何か」を自問自答してから書き始める
英語:要約と英作文の“型”を覚え、量をこなす
英語は6月からアウトプットの量を意識的に増やす必要があります。
要約問題では「何を削り、何を残すか」の判断スピードを上げ、
英作文では「自分が使える言い回し」「使わない方がいい構文」を明確にしていきます。
【学習メニュー例】
・『東大英語要約特訓シリーズ』:1日1問、60語・70語で要約し、内容と語数制限に慣れる
・『ドラゴン・イングリッシュ』『英作文のトレーニング』:3日で10題→解き直し→“自作表現集”を作る
・『英文解釈の技術100』:1日1文を「構文→訳出→解説付きで音読」まで行い、定着率を上げる
また、「どのような場面でも使える表現・語彙セット」を
構築するノートづくりも効果的です。
たとえば「意見を述べる」「譲歩する」「例を挙げる」といった文脈ごとに、
自分が書ける構文例を複数記録しておきましょう。
国語:古文は主語把握、現代文は「設問分析力」に特化
現代文では、東大型の記述問題を「構造・文脈・設問意図」の3つに分けて
徹底的に読む練習を積みましょう。
特に「なぜそう言えるか」「どこが根拠か」を問う設問では、
本文の該当箇所に根拠を線引き→まとめ直し→記述という3ステップ演習が有効です。
【現代文の教材例】
・『現代文と格闘する』(Z会)
・『東大過去問(現代文記述パート)』:1日1問×週3回記述、週末に添削・書き直し
【古文】
・『古文上達基礎編→読解編』で「誰が何をしたか」「敬語が誰に向かっているか」の主語判別を重点訓練
・読解問題は音読・訳・要約の3段階で処理する習慣をつける
【6月の1日モデルスケジュール(応用演習中心)】
| 時間帯 | 内容 |
| 朝(60分) | 英作文(記述1題)+単語熟語20語確認 |
| 午前(90分) | 数学 記述1題(時間制限つき)+復習・答案改善 |
| 昼(60分) | 古文敬語・読解演習+現代文マーク読み |
| 午後(90分) | 物理 or 化学(記述演習1題+図+理由づけ) |
| 夜(30分) | 東大過去問の問題分析(英語 or 数学:設問構造の読み取り) |
7月|夏の“勝負期間”突入:過去問導入と実戦的アウトプットへの移行
夏休み目前の7月は、受験生活におけるギアチェンジのタイミングです。
この時期に入ると、どの教科も「点が取れるかどうか」だけでなく、
その得点力を“本番形式で安定して出せるか”が問われてきます。
今月からは徐々に過去問や模試形式の問題も取り入れ、
「制限時間」「問題構成」「本番での思考・答案の質」への意識を持つ必要があります。
また、夏期講習など塾・予備校の予定が入りやすい時期でもあるため、
自分のペースで“深く学ぶ”自習時間の確保が成否を分けます。
【全体方針】
・知識の定着から「実戦力」への切り替えを意識
・「得点できる問題」「取れるけど落としやすい問題」「無理に追わない問題」の3分類を各教科で設ける
・実際の試験と同じ感覚(時間配分・問題文の読み込み方・答案構成)で演習を行う
【数学】時間内に“初手→展開→結論”を描く練習を毎日継続
7月からは、東大の過去問や東大模試(駿台・河合塾)の過去問を部分的に導入します。
たとえば、2022年の第3問(整数)など、出題の意図を読み取りやすい問題を選んで、
「答案構成→試行→記述→添削→再構成」の5段階で演習します。
【演習メニュー例】
・1日1問:時間を30〜40分で制限 → 完答 or 思考途中まで必ず書く
・週末:1週間分の解き直し+自分の弱点パターンのまとめノート作成(分野別)
【教材】
・『東大の理系数学25ヵ年』:頻出問題パターンごとに攻略(数列・微積・図形など)
・『大学への数学』(1学期号・夏号):実戦的な答案作成力が養える添削形式
1問1問の“答案完成度”が勝敗を分ける時期。
部分点狙いの答案でも、「何点もらえるか?」を
自分で採点して記録する習慣をつけましょう。
【物理・化学】“融合問題”と“変化を説明する問題”で実戦力強化
東大の理科でよく出る問題には、
「グラフの変化から本質を読み取る問題」「複数条件の変化を説明する問題」
「日常的な現象に数式を当てはめる問題」が多く、
ここでは単なるパターン演習では太刀打ちできません。
【物理】
・『名問の森』の力学・波動・熱の融合問題を重点的に演習(週4題ペース)
・問題に取り組む前に必ず「図を書く→法則を当てはめる→見通しを持つ」プロセスを徹底
【化学】
・『重要問題集(難易度A〜B)』の構造決定問題、酸塩基平衡、酸化還元を強化
・問題を解いた後に「条件が変わったら何が起きるか?」を想像して書き出すトレーニングを加える
【英語】要約・英作文・読解の“質とスピード”を両立させる時期
英語では、答案の型がある程度できている人も、
速く・正確に・読み解いて・書くという4段階すべてを一度に処理する段階に移行します。
特に東大英語の問題構成に合わせた実戦演習を行うことで、
本番でのペース感・集中力が鍛えられます。
【演習内容】
・週2回:過去問1年分の要約・英作文のみ解く(60分以内で採点付き)
・毎日:精読1題+音読(構文確認→和訳→音読5回)
【教材】
・『東大英語要約特訓シリーズ』:テーマ別に70語→50語と段階的に練習
・『英作文のトレーニング 実戦編』:1日1題、10分で構成→書く→見直す
【国語】現代文は“根拠のない記述をしない”鉄則を徹底
現代文では、「本文のどの記述を、どのように組み合わせて書くか」を考えながら
答案を書くことが大前提になります。
この時期からは、自分の解答と模範解答の違いを明確に言語化できることが大切です。
古文は、「主語補完」「敬語判別」「文法的構造の把握」において、
ブレをなくす反復トレーニングを行います。
毎日20〜30分の古文読解をルーティン化しましょう。
【教材】
・『得点奪取 現代文』『古文上達 読解編』を併用し、週3題記述→添削→書き直し
・東大過去問(現代文)は2000年代前半からランダムで選び、部分的に演習
【7月の学習のコツ】
・模試や過去問に取り組んだ際は「感想を書くだけのノート」を作る
(例:時間配分、頭が止まった場所、手応えと実際の点差など)
・集団講習を受ける場合も、「その日学んだことを家で必ず1回書き直す」習慣をつける
・暑さと生活リズムの乱れによる“集中力の低下”に注意し、午前に重い学習(数学・理科)を、午後に軽めの科目(英語・国語)を置く工夫を
8月|受験勉強最大の勝負月:「300時間の使い方」で差がつく夏
8月は、東大受験生にとって最も自由に時間が取れる、かつ最も差がつく1ヶ月です。
学校の授業がほぼない分、自分の学習にフルで時間を使えます。
1日10時間学習を30日続ければ、それだけで300時間の“集中投資”になります。
ただし、時間があるからといって“やった気になる”のが最大の落とし穴です。
必要なのは「時間の長さ」ではなく「時間の密度と配分」。
ここでは「どこに時間をかけるか」「どこで得点を伸ばすか」を明確にしながら、
演習の質を最大化していくことが求められます。
【全体戦略】
・1週間を「演習:復習=6:4」の比率で組む
・朝:頭を使う教科(数学・物理)/昼:記述演習や暗記系(化学・英語)/夜:要復習分や国語
・学習記録を毎日つける(時間・教材・感想・次回やるべきこと)
【数学】1日2題記述演習+1日1題の弱点潰し
数学は8月で「本番形式の記述演習を量産する」ことを目標にします。
7月までに固めた「型」を使いこなしながら、
本番と同じ時間感覚で、初見問題に挑むことがポイントです。
【具体的演習法】
・毎日午前中に1題:東大過去問 or 東大模試過去問(30〜40分で解く→採点→書き直し)
・午後に1題:同じ分野の類題を短時間で解き、「他の問題で応用できるか」確認
・週末:今週の演習のうち「よく解けなかった問題TOP3」を丁寧に復習し、解法を言語化
【教材】
・『東大の理系数学25ヵ年』
・『大学への数学・1対1演習シリーズ』
・『過去問演習用の答案用紙』を印刷 or 自作して本番さながらの書き込みを意識
【物理・化学】過去問・模試問題で“読み取りと説明力”を鍛える
東大理科の難しさは「思考を説明させる記述量」にあります。
8月では、図を描き、条件を整理し、
日本語で説明しながら立式する訓練を徹底しましょう。
【物理】
・1日おきに東大過去問 or 模試問題(2000年以降)の記述問題を1問演習
・「図→条件の言語化→法則の明示→導出→単位チェック」の流れを完全に型にする
・『名問の森』『重要問題集』を並行して、分野ごとに穴を埋める
【化学】
・計算問題は「単位」「数値処理」を丁寧に見直し、ケアレスミスの傾向を可視化
・無機・有機の暗記だけでなく、「反応理由」「推定根拠」も記述する訓練をセットにする
【英語】過去問を通じて“答案の完成度”と“処理速度”を鍛える
英語も本格的に過去問演習へ移行。ポイントは、
「設問の意図を読み取り、自分なりの型で書ききる」こと。
そして、「実際に使える表現」「使えないけど書きがちな間違い」を
リスト化していくことです。
【演習計画】
・週3日:過去問(大問1~4)のうち2問を選び、60分演習 → 採点+言い換え練習
・毎日:1題の英作文 or 要約問題(自分の“書ける構文セット”の強化)
【教材】
・『東大英語リスニング』『東大英語要約特訓シリーズ』
・『英作文のトレーニング(自由英作文・和文英訳)』
【国語】東大現代文・古文の“記述の型”を仕上げにかかる
国語は後回しにされやすい科目ですが、
8月で一気に「記述の骨格」を固めておきたいところ。
特に東大の現代文記述では、
「何を根拠に・どんな言葉で・どう繋げるか」が採点の決め手になります。
【現代文】
・東大過去問の記述問題(2000〜2020年)を抜粋 → 回答 → 説明 → 模範と比較
・主張・理由・具体例・対比など「論理構造の型」を1問ずつ明文化する
【古文】
・出典・ジャンル・登場人物の関係を整理しながら「内容把握→現代語訳→設問対応」
・敬語・助動詞・主語補完のミスパターンを“間違いノート”に記録
【8月の自習スケジュール例(理科一類志望)】
| 時間帯 | 内容 |
| 7:30〜9:00 | 数学(記述過去問1題)+答案構成チェック |
| 9:30〜11:30 | 物理(演習+記述+図付き説明) |
| 13:00〜14:00 | 英作文 or 要約+音読5回+英文精読 |
| 14:30〜16:00 | 化学(構造決定・計算・理論問題)+暗記パート復習 |
| 16:30〜17:30 | 古文・現代文の記述演習+解説読み |
| 19:00〜20:00 | 「今日のミス」「明日の予定」をノートにまとめる |
9月|“合格点を取る訓練”への完全シフト:過去問×添削×修正のPDCA徹底月間
いよいよ9月。ここからは東大入試を本番形式で“攻略する”段階へと入ります。
夏に詰めた知識・基礎演習の成果を「得点化する訓練」に変換していくことが
最大のテーマです。
この月からの軸はただひとつ、「本番で、確実に、得点できる答案を書けるか」。
つまり、思考の正確さ・答案構成の明快さ・時間内に出し切る力、その全てが問われます。
【全体戦略】
・過去問・東大模試過去問を**“時間制限あり”で通し演習**
・書いた答案の自己添削→他人添削→再構成まで行う“答案PDCA”を1セットとする
・「取れる問題で確実に取る」ための得点戦略を、科目ごとに立てておく
【数学】“完答”よりも“部分点を積み上げる力”の育成へ
9月からは、1問を時間内にどれだけ“点数として形にできるか”が課題になります。
完答を狙うのではなく、
むしろ「難問でも最低でも5点をもぎ取る答案構成力」を養うべきフェーズです。
【学習の進め方】
・週3〜4日:本番形式(2時間、5問)の過去問を解く(1995年〜2023年からランダム選出)
・解いた後は、模範解答と比較→自分の答案に赤入れ→翌日、清書・再構成を実施
・解けなかった問題は「初手だけでも考え、書く」訓練を行う(白紙をゼロに)
【使用教材】
・『東大の理系数学25ヵ年』
・模試の過去問(駿台・河合塾・Z会東大模試など)
・自作「答案復習ノート」:問題・自分の解答・模範とのギャップ・改善後の再答案
【物理・化学】「何を」「どの順番で」「どう書くか」をパターン化
理科でも、「情報処理力」と「記述表現力」の融合が合否を分けます。
単なる計算力ではなく、図を描き、状況を説明し、方針を明示し、
ミスなく立式するこの一連の処理が得点化の鍵です。
【物理】
・週2〜3題の記述演習を過去問中心で実施。特に「グラフの意味を言語で説明」「図と法則の対応付け」の練習を重視
・単なる式の羅列を避け、「論理の筋道を日本語でつなぐ」訓練を入れる
【化学】
・東大頻出の「構造決定」「グラフ解析」「理論の理由説明系問題」を集中的に対策
・解説を読んで終わりにせず、「解法を“自分の説明で”再構成してノート化」する
添削してもらえる環境があるなら、
物理・化学も記述の添削を受けるのが効果的です。
添削内容を1週間ごとに見返すと、改善点が見える化されます。
【英語】過去問通年演習×自作表現ノートで「使える英語」を増やす
東大英語では、「読んで→要点を整理して→自分の言葉で書く」までを
60分以内でこなす処理速度が求められます。
そのため、長文→要約→英作文→見直しまでを通して1セットにする演習習慣が必要です。
【取り組み方】
・月〜金:1日1問の要約・英作文(60分以内で通し解答→見直し→再構成)
・土日:リスニング強化 or 長文2題+読解メモづくり(段落ごとの主張・理由・例の明示)
・「使える表現」「よく間違う構文」だけを集めた“自作の英語表現ノート”を随時更新
【使用教材】
・『東大英語要約特訓シリーズ』
・『ドラゴン・イングリッシュ』『自由英作文トレーニング』
・過去問(特に2020年以降の英語設問は“地味に形式が変わってきている”ため重点)
【国語】“読み取って、答える”実力を記述で表現する
現代文は「読み取れているのに、書けていない」受験生が非常に多い科目です。
9月では、記述設問に対して「問われている意図→使うべき本文の箇所→解答構成」の
プロセスを明確に再現できるかが鍵です。
【現代文の演習法】
・東大過去問から、1問15〜20分で記述答案を作成(制限字数厳守)
・書いた解答は必ず「本文のどの根拠を、どう構造的に使ったか」を横にメモしておく
・週1回:東大模試の記述問題で“論点の外し”をチェック
【古文】
・1日1題で良いので、「登場人物の関係性」「主語」「心情の移り変わり」を明示して訳す
・『古文上達』『古文読解ゴロゴ』などを用い、設問対応の“公式”を固める時期でもあります
【9月の自習スケジュール例(記述演習中心)】
| 時間帯 | 内容 |
| 7:00〜9:00 | 数学過去問2問(記述形式、40分+見直し) |
| 9:30〜11:00 | 英語要約+英作文(解答+添削+再構成) |
| 13:00〜15:00 | 物理または化学の過去問(記述式)+再解釈ノート記入 |
| 15:30〜16:30 | 古文 or 現代文の記述練習(本文構造のメモづくり含む) |
| 20:00〜21:00 | その日の答案の見直しと「改善メモ」記入 |
10月|“実力の踊り場”を乗り越える|本番想定の最終PDCA強化期
10月は、東大受験生の多くが感じる「実力の停滞期(踊り場)」のひとつです。
過去問や模試演習を進める中で、「思うように点が取れない」
「今さら伸びる気がしない」と感じやすい時期ですが、
ここをどう乗り越えるかが合格ラインへの分水嶺になります。
この1ヶ月は、知識を増やすよりも、「今ある力をどれだけ得点に変えるか」に
徹底的にこだわるべきフェーズです。
PDCA(計画→実行→確認→改善)の精度を上げることで、
着実なスコアの上積みが可能になります。
【全体戦略】
・過去問は“通し演習+再構成”をベースに週3〜4年分ペースで取り組む
・模試や復習の「振り返りノート」を蓄積し、自分のミスパターンを明文化
・モチベーションの管理・集中力の維持にも意識を向ける
【数学】問題タイプ別に“点が取れる型”をパターン化する
東大数学は「毎年似たようなテーマを、少しずつ捻って出してくる」ことで
知られています。
10月は、この“東大的発想”にどれだけ慣れているか、
どれだけ点を拾う構成が身についているかを確認・修正する時期です。
【具体策】
・テーマ別(整数・図形・確率・数列・微積)に「得点しやすい型」を自作ノートで整理
・「これは満点狙う/これは初手だけ書いて見切る」といった戦略的答案選択力を訓練
・本番形式での時間配分(60分で2問など)を自宅で実践し、焦り・判断力を強化
【教材】
・『東大数学プレミアム・セレクション』(過去問の出題傾向別分析本)
・模試の過去問(演習後→出題者の意図まで書き出す習慣を)
【物理・化学】「一度解いた問題を、より高精度で解き直す」
この時期の理科は、「新しい問題に挑戦する」のではなく、
「過去に解いた問題を、より正確に、より美しく、再現できるか」がテーマです。
【物理】
・過去問の復習では「初手ミス」「見落としの条件」「解釈不足の図」などを再チェック
・答案に使う用語を見直し、「加速度」「相対速度」「エネルギー保存」といった言葉を正しく使う練習を徹底
【化学】
・自作の「ミス頻出ノート」を使い、「よく間違える単位・計算・反応式」を10分で確認する“仕上げルーティン”を1日1回入れる
・『新演習』や『化学の計算問題100選』などで「基礎計算の速さと正確さ」も改めて整える
理科に限らず、「できなかった問題をどう扱ったか」が10月以降の伸びを決めます。
「なんとなく復習」ではなく、「できる状態で終える」ことにこだわりましょう。
【英語】“型を再現する”訓練で安定した答案作成を目指す
英語はこの月で、「思いつきで書く答案」から
「構成と型で得点を拾う答案」への最終転換を図ります。
特に英作文と要約は、
毎回一定の構成で書くことで点数のブレを最小化することが可能です。
【実践方法】
・自分の中で「要約の型(主張→理由→結論)」と「英作文の型(主張→根拠→具体例→結論)」を固定し、それに沿って書く訓練
・書いた後に「別解を模範解答で学ぶ→自分なりに言い換え→表現ノートに記録」
【リスニング対策】
・東大リスニングの過去問を1日1セット聞く
・聞き取れなかった部分を“音読→ディクテーション→要約”までセットでやると非常に効果的
【国語】記述問題の“安定した型”を体得する
現代文では、そろそろ「自分の記述のクセ」を明確に認識すべき時期です。
たとえば「抽象語が多い」「具体例が抜けやすい」「接続が曖昧」など、
自分なりの“記述癖”を客観視し、修正を重ねることで答案の安定感が格段に増します。
【現代文】
・解いた記述問題を読み返して「減点理由を明文化」
・模範解答との比較で「差異は情報量か?表現か?構造か?」を言語化して記録
【古文】
・問題の構文・主語・敬語・文脈判断を「書かずに答えず」読み飛ばしていないかを徹底チェック
・出典パターン(伊勢物語、源氏物語など)に応じた人物関係の推測法をまとめる
【10月の実践スケジュール例】
| 時間帯 | 内容 |
| 7:00〜9:00 | 数学:記述過去問(40分×2問)→自己採点→型ノート記録 |
| 9:30〜11:30 | 英語:要約+英作文(型どおりの答案を目指す)+復習 |
| 13:00〜14:30 | 物理:過去問(条件・図・説明にフォーカス)+答案添削チェック |
| 15:00〜16:30 | 化学:記述式演習→解説を再現できるまでノートまとめ |
| 20:00〜21:00 | その日のミス・改善点を“記録シート”にまとめて翌日に活かす |
11月|得点戦略の最終調整期|答案の完成度×共通テスト対策の両立へ
11月は、「過去問演習の質と精度をピークに近づける」と同時に、
共通テスト対策への本格着手が始まる重要な分岐点です。
東大理科一類の合格者たちは、この時期を「最終調整の月」として活用し、
志望校の出題傾向に完全適応しながらも、
共通テストでの失点を防ぐ準備を着実に進めています。
この時期の課題は3つあります
- 二次試験で点を“取り切る”答案構成力の仕上げ
- 共通テストでの“取りこぼしゼロ”戦略の構築
- 志望校に対する「得点戦略の確信」を持つこと
【数学】「取り切れる問題」を確実に取る訓練を継続
この段階で“解けるはずの問題を取りこぼす”ミスは命取りです。
11月は「どの問題を取るか」「どう取るか」を判断し、
短時間で最大点を確保する訓練に集中します。
【具体戦略】
・時間配分を本番想定でシミュレーション(例:大問ごとに20分、取捨選択を明示)
・自分の「得点源の型」(ベクトル・整数・確率など)を完全再現できる状態に
・「詰まった時にどう引くか」の判断基準をメモ化し、演習後に振り返る
【おすすめ教材】
・東大過去問(2015〜2023を優先)
・『東大模試の過去問+解説冊子』を用い、自分の答案との差分分析
【物理・化学】答案精度の徹底強化と“確認癖”の構築
理科では、“途中まで合っていたのに、
記述で減点された”というパターンをゼロにしていきます。
11月は記述答案の質の微調整に入り、
同時に「図・単位・因果関係」の見直しを意識的に習慣化します。
【物理】
・「与えられた情報を図に書く」→「必要な法則を選ぶ」→「論理でつなぐ」一連の流れを、口頭説明しながら演習
・時間を測って本番形式演習→添削→日本語記述の精査を徹底
【化学】
・構造決定は“書いて満足しない”。「根拠のない仮定をしていないか」を必ず確認
・化学平衡や電気分解などの頻出分野は、「問題文の条件変更に対して、どう影響するか」を紙に書き出すトレーニングも有効
【英語】“構成力”と“減点されない答案表現”の最終調整
英語では、読解・要約・英作文のすべてにおいて「減点されない言葉選び」
「崩れない構成パターン」を確立していきます。
英文の読解力に加え、
「どんな状況でもこの構成で書けば6〜7割は安定して取れる」
という鉄板構成を持つことが得点の安定化につながります。
【強化ポイント】
・要約・英作文ともに「主張→理由→補足(例)」の3点構成を型化し、内容を入れ替えて練習
・採点視点で自分の答案を見直し、「曖昧表現」「論理の飛躍」「主語のブレ」などを1つずつ修正
【リスニング】
・共通テスト形式で週3〜4回、過去問・予想問題を使用して実施
・聞き逃し箇所はディクテーションし、「音として聞こえない→語彙or文構造のどこで詰まったか」をチェック
【国語】答案精度の“引き算”と“簡潔な記述”を意識する
現代文では、「書きすぎによる減点」「説明の冗長化」に注意が必要です。
11月は、書いた記述の中から「不要な語句を削る」訓練を始め、
100字以内で言いたいことを的確に表現する力を磨きます。
【記述演習法】
・解いた後、自分の記述を「削るとしたらどこか?」を赤でマーク → 要約力アップにつながる
・模範解答の語順や使われている語彙を写経 → 自分の記述とのギャップを埋める
【古文】
・敬語・助動詞に関しては“主語のブレ”が最大の失点要因。毎日20分だけでも“人物整理”の演習を継続すること
・出典知識(源氏、伊勢など)は、「内容」「文体」「時代背景」の3つをメモにまとめておくと対応が早くなる
【共通テスト対策】基礎精度とケアレスミス防止に集中
共通テスト対策は、
11月から1日1セット(英数国 or 理社)を入れる形で徐々に頻度を増やしていきます。
目的は“満点を取る”ではなく、8〜9割を安定して出す力の構築です。
【実施例】
・午前:共通数学IA or IIB(時間制限あり)→午後:理科1科目演習
・英語リーディングは「精読→スラッシュリーディング→設問照合」の復習手順を固定化
・国語現代文は「問題文の要約→選択肢の照合メモ」を毎回実施し、処理スピードと根拠力を鍛える
【11月の1日モデルスケジュール】
| 時間帯 | 内容 |
| 7:00〜9:00 | 数学:過去問1年分(記述→自己採点→再構成) |
| 9:30〜11:30 | 英語:要約・英作文1問+長文精読1題 |
| 13:00〜14:30 | 物理または化学の記述演習+ミス分析ノート |
| 15:00〜16:00 | 共通テスト形式 英数国いずれか(30〜60分×1) |
| 20:00〜21:00 | 国語(現代文1題または古文+文法の即答チェック10問) |
12月|“共通テスト最終仕上げ”と“東大記述力の維持”をどう両立させるか
12月は受験直前の山場。
共通テスト本番(1月中旬)まで残り約1ヶ月となる今、
全国の受験生の多くが共通テスト対策に切り替えていきます。
ただし、東大志望者にとって重要なのは、
共通テストに集中しすぎて「記述の勘」が鈍らないようにすること。
この時期の東大理一合格者の多くは、
「1日1記述」「共通テストは朝練感覚」で乗り切っています。
つまり、“記述を中心軸に置きつつ、
共通テストは習慣として処理する”というリズムを確立しているのです。
【全体戦略】
・朝:共通テストの形式練習(60〜90分)
・昼・夜:東大記述演習1問(数学・英語・理科のいずれか)+復習
・模試結果・過去演習をもとに「取るべき点数ゾーン」を再確認し、点数の取りどころを明確にしておく
・「睡眠・体調・食事・集中環境」の調整も12月から本番仕様にしていくこと
【共通テスト対策】ミスを減らし、得点を安定させる反復練習が中心
東大を目指す上で、共通テストの目標得点は 85〜90%以上(理一で730点/900点前後)。
12月は新しいことを詰め込むよりも、
ケアレスミスの傾向を分析・潰すことに徹するのが鉄則です。
【実施プラン】
・英語(リーディング+リスニング):週3〜4回本番形式で通し演習(60分+30分)
・数学IA・IIB:本番通りに計算スピード・ミスの傾向を意識 → 見直しの時間確保も練習
・理科2科目(物理・化学):基本計算+選択肢処理のテンポを維持
・国語・地歴公民:過去問+Z会や駿台模試の解き直しで「選択肢の消去プロセス」の再確認
共通テストは“ミスしない人が勝つ試験”。
1日1セットで解き、その日中に
「どこで失点したか→なぜか→防ぐには?」のミス分析を必ず書き出すこと。
【数学・理科】記述の感覚を維持するための“1日1題習慣”
記述の感覚を維持する最良の方法は、「毎日1問でもいいから書く」こと。
12月はまとまった時間が取れないことも多いため、
30分以内で終わる東大型の小問or部分的な大問を選び、
「答案をつなげる感覚」を失わないようにします。
【具体演習法】
・数学:ベクトル・整数・図形など「型がある問題」を解き、型で得点できる実感を強化
・物理:力学や電磁気など、頻出テーマの記述パートだけ抜き出して演習 → 自己添削
・化学:構造決定・グラフ問題などで「説明→計算→単位まで」仕上げる意識を持つ
【英語】読解・英作文・要約を“短時間・高密度”で回す
英語も1日1セットの演習を継続。時間が限られる中では
「長文読解1題」または「要約+英作文1セット」を日替わりで行う形が効果的です。
過去問は部分演習に切り替え、「精度とスピード」を両立させることが求められます。
【ポイント】
・要約・英作文は「再現性の高い構成テンプレ」を持ち、そこに乗せる内容を変えていく練習
・読解では「段落ごとの主張メモ→設問対応」の2段構えで、設問とのズレをなくす
【国語】現代文・古文を“言葉の力”で押し切る答案を目指す
東大型の国語では、「内容の精密な読み取り」よりも、
「自分の言葉で、誤解なく伝える力」が問われます。
12月は過去問の記述を再演習しながら、
「どんな文体で書けば採点者に伝わるか」を磨いていきます。
【現代文】
・解いたら“声に出して読む” → 違和感がある部分を削る or 書き換える(文脈チェック訓練)
・主張・理由・例の構成テンプレを再確認し、「要素の欠落」がないかチェック
【古文】
・主語・敬語・心情の3点セットを軸に設問対応する癖を完全に体に染み込ませる
・出典を音読して「文脈と助詞・接続助詞・係り結び」の感覚を維持
【メンタル&生活面】“試験仕様”の生活リズムを固定していく
ここまで来ると、「集中力・判断力・平常心」を支えるのは生活リズムです。
夜型の人は朝型にシフトし、試験時間帯(午前・昼)の集中力を高める訓練を行います。
【推奨ルール】
・朝7時起床/夜23時就寝を習慣化(共通テストの時間に合わせる)
・朝イチ学習を英語・国語、昼〜午後に数学・理科を充てる
・模試や演習の自己採点は夜やらずに翌朝実施(メンタルの平静を保つ)
【12月の1日モデルスケジュール(共通&記述両立型)】
| 時間帯 | 内容 |
| 7:00〜8:30 | 共通テスト形式演習(英語 or 数学)+ミス分析ノート記入 |
| 9:00〜10:30 | 東大型数学1題(記述式)+答案清書 |
| 13:00〜14:30 | 理科(記述演習or共通対策)+スピード処理訓練 |
| 15:00〜16:00 | 英語(要約+英作文 or リスニング30分) |
| 20:00〜21:00 | 国語(古文読解+現代文の要約記述)+明日の予定確認 |
1月|本番突入期|共通テスト突破→東大二次に向けて“整える”最終フェーズ
1月は、いよいよ共通テスト本番(1月中旬)+東大二次試験1ヶ月前という、
まさに「本番ステージ」です。
この時期は、焦りと緊張、過去最高レベルの不安と戦いながらも、
“いつも通り”をいかに再現できるかが合否を左右します。
東大理科一類の合格者たちがこの1月にやっているのは、
「焦って新しいことを詰め込む」のではなく、
“自分を本番仕様に仕上げる”ことです。
過去問の繰り返し・答案の安定化・メンタルの調整、
すべては「試験当日の自分」を信じるための準備です。
【1月前半(〜共通テスト本番)】
共通テストを「最大得点×最小ストレス」で乗り切る
1月中旬に行われる共通テストは、
東大受験においては「突破すべき壁」であり、「超えればいいだけのハードル」です。
【共通テスト攻略の最終調整】
・形式慣れが何より大事:毎朝9時から共通演習(英語R/数学I・Aなど)を本番通りに解く
・ケアレスミスを防ぐための「自分だけの見直しルール」を決めておく(例:最後の1分は選択肢確認専用)
・リスニングは1日1セット(20分)+スクリプト確認+音読5回の固定ルーティン
【共通テスト当日の心得】
・「8割は取れて当たり前。取り切る科目は9割狙い、苦手科目は7割死守」の方針でOK
・会場に「不安な人」がいても気にしない、自分だけを整える
・目標点を意識しすぎない。“1問ずつ丁寧に”を最優先する
【1月後半(共通テスト後〜東大二次まで)】
「答案再現力」と「思考の再起動」を中心に記述演習を再開
共通テストが終わると、いよいよ「東大2次試験まで残り約40日」となります。
この時期に行うべきは、「思考する頭を記述仕様に戻す」こと。
そして「自分の解答に自信を持てる仕上げの確認」を行うことです。
【数学】
・過去問演習は2日に1セット(2〜3題)でOK。焦らず1問ずつ“型”の確認と再現に集中
・「解き直しノート」を最も使い込む時期。「1問解いたら→再構成→模範解答と差異比較」をルーティンに
・大切なのは“新しい知識”ではなく“安定した出力”
【物理・化学】
・「解ける問題を、満点に近い記述で確実に取る」ことをテーマに再演習
・特に化学では、「単位・条件・理由記述」をミスなく書く練習を徹底(2次では1つの言い間違いが10点減もありうる)
【英語】
・英作文・要約は“自分の型”を磨く仕上げ
英作文は「主張→理由→具体→結論」のテンプレを徹底
要約は「何を削り、何を残すか」を毎回振り返って整理
・リスニング対策は維持程度でOK。東大では配点が高くないため、他科目優先でよい
【国語】
・過去問の“古い年度”(1990〜2010年など)を1日1題程度演習して「型を忘れない」感覚をキープ
・古文は「主語補完+敬語の判別」が崩れやすくなるので、最低週3回は読解演習+口頭訳で確認
・現代文の記述は「文末まできれいに書き切る」訓練に集中(論理飛躍を防ぐ)
【メンタル調整・本番対策】
1月後半からは、「不安に振り回されず、自分を整える時間」が最も大切になります。
【おすすめ習慣】
・「1日1回、うまくいった演習を記録」する(成功体験で自己効力感を維持)
・「模試や過去問のベスト答案を3つ選び、“なぜ取れたか”を言語化」する
・「試験会場で最も落ち着いている自分」を毎晩イメージして寝る(言語より感覚が大事)
【1月の学習スケジュールモデル(共通テスト後ver)】
| 時間帯 | 内容 |
| 7:00〜8:30 | 数学:過去問1題(時間制限あり)→自己採点+型再構成 |
| 9:00〜10:30 | 英作文または要約(構成練習+模範比較) |
| 13:00〜14:30 | 物理または化学(記述演習+図+説明の確認) |
| 15:00〜16:30 | 古文または現代文(1題演習+論点整理) |
| 20:00〜21:00 | ミスノート・成功体験ノート更新 → 翌日の作戦立て |
【まとめ】東大理科一類 合格のための年間戦略総仕上げ
1年を通して“合格答案が書ける自分”をつくる
合格の本質は、「再現できる力を、1年間で構築する」こと
東大理科一類の入試は、
「思考力・表現力・論理構成力・情報処理能力」すべてが融合された、
国内屈指の“頭脳勝負の試験”です。
そして、どれだけ知識を持っていても、
それを限られた時間と文字数の中で、答案として出力できるかが合否を左右します。
つまり、求められるのは知っている力ではなく、“出せる力”。
その“出せる力”をつくるのが、1年間の受験戦略です。
年間スケジュールで築く「合格答案を支える6つの柱」
① 【基礎の棚卸しと型づくり】4〜6月
・解法暗記ではなく、「なぜそう解くのか」まで言語化して習得
・英数物化の“答案構成の型”をインプットし、アウトプットの練習に入る準備期間
・毎日の学習ルーティンを固定し、リズムと集中力を整える
② 【実戦感覚の定着】7〜8月
・1日10時間×30日=300時間の積み上げが武器に変わる夏
・東大型記述を導入し、「得点できる答案を作る」演習の反復
・「書いた→添削→修正→再構成」の習慣化で、答案の質が急上昇
③ 【答案精度と処理力の融合】9〜10月
・「あと5点」を取りきるための部分点戦略と答案の取捨選択力を強化
・全科目で“自分の型”を磨き、思考停止せずに書き切る訓練を継続
・同時に、共通テストの形式慣れを週に数回取り入れ始める
④ 【点数を落とさない技術】11月
・本格的に共通テストの対策を開始しつつ、記述力の鈍化を防ぐ「1日1記述」を継続
・「減点されない書き方」を言語化し、構成・表現の精度を極限まで高める
・ミスパターンをノートに集約し、“失点の芽”を潰していく
⑤ 【感覚を維持し切る習慣化】12月
・共通テストを午前中に“本番シミュレーション”、午後は記述型を1〜2題ずつ継続
・新しいことは入れない。「いつものことを、いつも通りにできる自分」を仕上げる
・睡眠・食事・勉強サイクルを完全に“試験本番時間帯”へ移行
⑥ 【自分の仕上げを信じる月】1月
・共通テストでは、取り切れる問題で確実に得点→ブレずに突破
・直後から記述演習を再開。毎日「本番シミュレーション+復習」のルーティンを崩さない
・“新しい知識”より、“安定した出力”を重視。整えるのは答案ではなく自分自身
科目別総括|合格答案を実現するアプローチ
| 科目 | 合格の鍵 |
| 数学 | 「どの問題を解くか」「どう書くか」を事前に決め、部分点で勝ち切る構成力 |
| 物理 | 条件を図にし、物理現象を論理的に記述。「なぜその式か」を言語で説明する力 |
| 化学 | 数字だけでなく、反応の理由・構造の仮定を根拠と共に示す記述トレーニング |
| 英語 | 要約・英作文の「構成テンプレ」を確立し、安定して60〜70%を得点できる型を持つ |
| 国語 | 「伝わる記述」を構成する型を身につけ、冗長にならず、論点を明確に書く練習 |
東大理一に受かるのは、“圧倒的な天才”ではない。
東大理科一類に合格する受験生のほとんどは、
“一問一問を、誰よりも丁寧に、誰よりも安定して解ける人”です。
・大きな飛躍ではなく、毎日5点ずつ、取れる問題を積み上げていく
・「正しい戦略」と「地に足のついた日々のルーティン」で、必ず届く場所にある
このまとめを読んでいるあなたは、すでにその入り口に立っています。
合格の瞬間、振り返ってみてください。
その時のあなたにとって、「この1年が、どれだけ意味のある時間だったか」。
きっと、すべてがつながっていたことに気づくはずです。
どうか、自分を信じて、最後まで走り切ってください。
あなたの合格を、心から応援しています。
東大理科一類を目指すあなたへ「合格戦略」を東大生と一緒に描いてみませんか?
ここまでこの記事を読んでくださり、本当にありがとうございます。
東大理科一類に合格するために、どんな勉強をいつ、どう進めるべきか。
1年間の道のりをここまで明確にしたあなたは、
もうすでに大きな一歩を踏み出しています。
ただ、その一方で…
・「この戦略を自分にどう当てはめればいいかわからない」
・「今の学力で本当に通用するのか不安」
・「やる気はあるけど、毎日の学習管理がうまくいかない」
そんなふうに感じている方も、きっと少なくないはずです。
実は、東大合格者の多くが「勉強法に迷わなかったから合格できた」と話します。
つまり、自分の現在地と目的地の間にある“最短ルート”を、
早く明確にできた人が強いのです。
個別指導塾ワイザー【オンライン校】では…
講師は全員、東京大学の現役生。
実際に理科一類に合格し、今も東大で学ぶ先輩たちが、
あなたの不安や悩みに一つずつ丁寧に向き合います。
受験期のリアルな体験をもとに、
「この時期に何をやるべきか」「どうやって継続したか」まで具体的にお話しできます。
東大志望でなくてもOK。
「自分のレベルだと無理かも…」と思っている人ほど、今、相談してほしいです。
志望校や模試の成績が固まっていない段階でも、
今やるべき勉強を一緒に組み立てられます。
無料相談はオンライン完結。
スマホやパソコン1台で、全国どこからでも受けられます。
顔出しなし・保護者同席もOK。
無理な営業や長時間の面談などは一切ありません。
お気軽にご利用ください。
「学び方に悩まない」という最強の武器を、あなたに。
合格の鍵は、才能ではありません。
“正しいやり方で、正しい順番で、
努力できる仕組み”を持っているかどうか、ただそれだけです。
あなたに合った学習戦略を、合格経験者と一緒に言語化してみませんか?
まずは無料で、「今の自分に必要な戦略」を聞いてみてください
個別指導塾ワイザー オンライン校は、講師が東大生というだけでなく、
あなたの努力が「点数」になるように、
毎日の勉強と感情に寄り添う塾でありたいと思っています。
目標は、「やり方がわかったから、今日すぐに動き出せる」状態を一緒に作ること。
そして、「これなら合格できそう」と、心の底から思えるプランを一緒に描くことです。
あなたの合格への挑戦を、私たちは全力でサポートします。
次に合格発表の前に立つのは、あなたかもしれません。
その最初の一歩を、ぜひこの無料相談から始めてみてください。
心より、お待ちしています。
▼無料相談はこちらをクリック▼



