
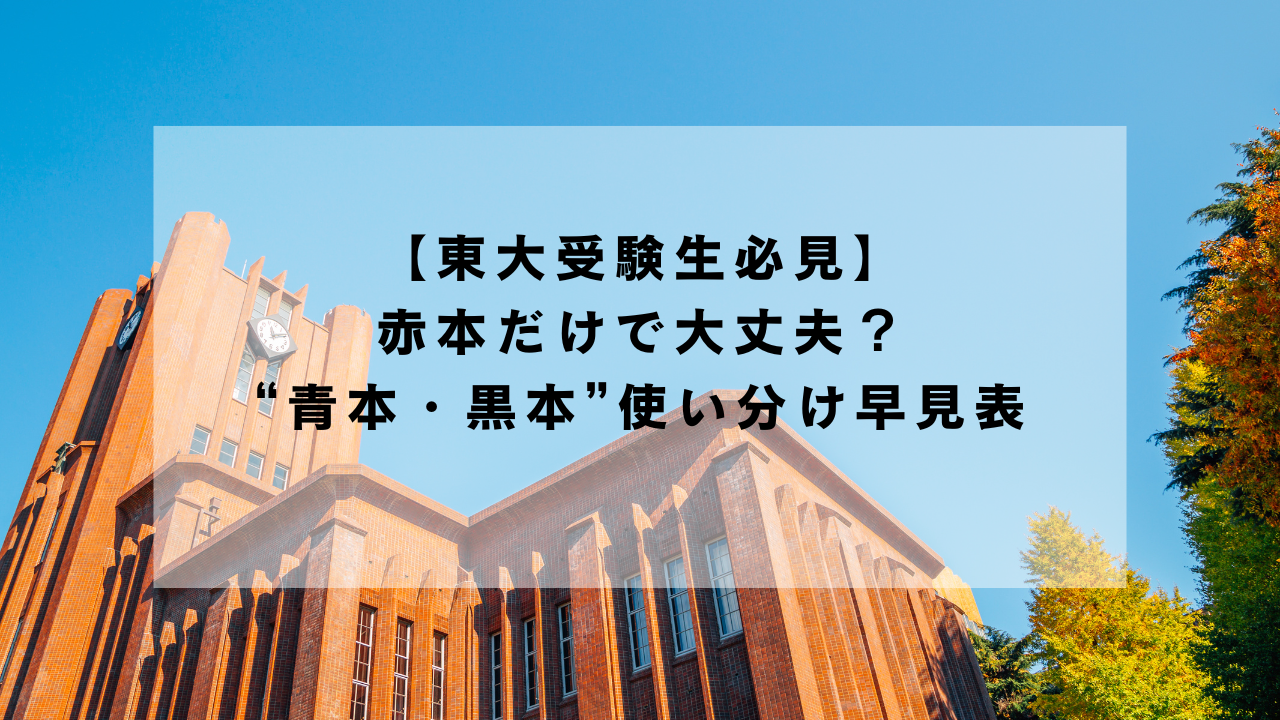
「赤本・青本・黒本って何が違う?」——東大志望者が最初に押さえるべき“過去問三種”の立ち位置と役割
東京大学を本気で狙うなら、過去問演習は演習計画の軸になります。
しかし書店に並ぶ赤本(教学社)、青本(駿台)、黒本(河合塾)はいずれも「東大入試問題集」と書かれており、初学者ほど「どれか一冊で十分なのか」「全部買うべきなのか」と迷いがちです。
ここではまず三シリーズの編集方針・掲載年度・付録解説の深さを整理し、東大合格者がどの順番で使い分けているかを解説します。
1.赤本(教学社)——“原典+標準解説”で全体像をつかむ出発点
赤本の最大の特徴は 掲載年度の長さ と 汎用的な解説 にあります。
5〜10年分を一冊に収録し、英数国理社すべてを網羅。
解説は基礎事項から入り、初めて東大形式に触れる段階でも読める柔らかい語り口で構成されます。
一方で数理科目の答案方針や別解の網羅度は青本・黒本に劣るため、「まず出題傾向と難度帯を把握するための全教科通読」に適しています。
赤本で重要なのは“俯瞰読み”という使い方です。
初年度にいきなり時間を測って解くのではなく、出題分野や採点基準をマーキングしながら“問題の雰囲気”を体で覚える工程に専念します。
これにより、後述の青本・黒本で個別分野を深掘りするときに「これは○年度のあの類題」と瞬時にリンクできる土台が作られます。
2.青本(駿台)——“最難関層向け別解大全”で答案完成度を高める指南書
青本は駿台の東大対策講座をそのまま紙上再現したような構成で、解答解説が講義ノート並みに詳細です。
数学は一問につき平均3ページ以上を費やし、答案作成のプロセス・別解比較・想定採点配点を細かく解説。
英語では長文と自由英作文の高得点表現リストを提示し、文法項目のミスまでチェックリスト化。
駿台模試偏差値65以上が対象層という設計のため、初見の段階では理解が追いつかない箇所も多いですが、「答案を磨くフェーズ」では圧倒的に役立ちます。
赤本で俯瞰→学校教材で基礎固め→青本で理論武装、という順序を踏むと学習効率が跳ね上がります。
3.黒本(河合塾)——“実戦形式”と“問題冊子レイアウト”で本番慣れを演出
黒本の特徴は 模擬試験仕様 の編集です。
解答冊子と問題冊子を分離し、本番さながらのレイアウト・紙質・余白幅で印刷。
年度別ではなく科目横断編成(英語全15年分/数学全15年分など)の冊子も選べ、実戦演習→自己採点→答案分析 を1セットで回しやすい設計です。
解説は青本ほど深くないものの、河合塾全統模試の採点基準に沿ってモデル答案が作られており、再現答案 を練習するのに最適。
「制限時間ピッタリで解く→即採点→得点率50%未満を青本で復習」というループが東大合格者に定番ルーチンとして浸透しています。
4.三本を並べて比較すると見える“学習ステージ”
| 目的 | 推奨問題集 | 推奨時期 | 活用ポイント |
| 出題形式を知る | 赤本 | 高2冬〜高3春 | 問題を読むだけ+傾向マーキング |
| 理論理解と別解習得 | 青本 | 高3夏〜秋 | 数学は手書き写経、英語は表現暗記 |
| 本番シミュレーション | 黒本 | 高3秋〜直前期 | 予備校模試日程に合わせ週1セット |
このように三シリーズは重複ではなく棲み分けで機能します。
「赤本だけで大丈夫か」という問いへの答えは「合格点を安全圏で超えるなら不足」。
逆に「どれから手を出すべきか」には「赤→青→黒の順」が王道となります。
“赤→青→黒”を学習カレンダーに落とし込む――12か月×4フェーズで無駄なく回す演習サイクル
東大合格者が三種類の過去問を使うとき、最も意識しているのは「いつ・何年分・どの順序で解くか」という時間配分です。
教材を買っただけで安心し、赤本を解き終えないうちに青本へ移り、黒本に手つかずのまま本番を迎えるケースは少なくありません。
ここでは高2冬から本番までの12か月を4フェーズに分け、各フェーズで扱う年度数・解き方・復習手順を具体的に示します。
フェーズ1 高2冬〜高3春(12〜9か月前)——赤本“俯瞰期”
・目的 東大型問題の分量感を把握し、苦手分野をマーキングする。
・月間タスク 赤本5年分を「通読+要素抜き出し」形式で処理。
時間は測らず、解答を読みながら「設問構造」「配点」「頻出キーワード」をノートに書き出す。
・週次プラン
月曜:英語大問2を音読し、段落要旨を書き写す。
火曜:数学第1問を眺め、使う定理を列挙。
水曜:数学第2問を同手順で分析。
木曜:国語現代文を読み、設問毎に問われる読解レベルを分類。
金曜:理科・社会の年表や実験設定をチェック。
土曜:1週分のノートを色分け整理。
日曜:何もしない日を設定し、脳の負荷をリセット。
フェーズ2 高3夏前(8〜6か月前)——赤本“解答写経期”+青本“導入期”
・目的 赤本で解法プロセスを手になじませ、青本の詳細解説で理論を補完。
・月間タスク 赤本3年分を制限時間の1.5倍で解き、青本同年度の解説を熟読。
・週次プラン
① 月曜・火曜:数学1年分を解く→青本で別解と比較→間違いタグ付け。
② 水曜:英語大問3と自由英作文を時間内で実施→青本で高得点表現をカード化。
③ 木曜:国語古文・漢文を赤本→青本で語彙・漢字まで確認。
④ 金曜:理科2科目を赤本→公式暗記とグラフ考察を青本で補強。
⑤ 土曜:間違えた問題だけ再答案作成→別解と配点欄を転記。
⑥ 日曜:翌週のスケジュール調整と目標点リセット。
フェーズ3 高3夏後半〜秋(5〜3か月前)——青本“徹底期”+黒本“導入期”
・目的 答案完成度を上げつつ、本番レイアウトで時間感覚を鍛える。
・月間タスク 青本2年分を完全解答→黒本1セットを本番時間で実施。
・週次プラン
月曜:黒本数学・理科を90分×2で解答→火曜朝採点。
火曜:採点結果を青本で復習→配点別に失点要因を表に書く。
水曜:黒本英語リスニング+筆記を実戦→語彙・構文を青本で補強。
木曜:国語を通しで実戦→青本で設問意図を確認。
金曜:自己採点をグラフ化し、得点帯の揺らぎを数値化。
土曜:弱点補強講義動画や参考書でテコ入れ→同分野の過去問を赤本から追加。
日曜:休養と軽い暗記、次週の計画更新。
フェーズ4 本番直前3か月(2か月前〜前日)——黒本“実戦期”
・目的 制限時間下で安定して合格点+20点を出す。
・月間タスク 黒本を週2セット、過去15年分を解き切る。
・週次プラン
月曜・木曜:黒本フルセットを午前・午後に分けて実戦。
火曜・金曜:答案提出→自己採点→得点率70%未満の大問を青本で再解説写し。
水曜:数学過去問を一問だけ60分で再挑戦し、最短ルートを試行。
土曜:理科・社会の公式暗記カードを高速回転。
日曜:メンタルと体調管理デー、睡眠時間を前倒しで確保。
カレンダー活用のコツ
- 固定枠+変動枠 黒本実戦日は固定、復習日は得点状況で変動させる。
- モニタリング指標 週末に「得点率・答案提出率・復習完了率」を色分けし、赤→黄→緑の三段階で進捗を可視化。
- 教科バランス 数学で時間超過したら翌週の英語演習量を増やし、総得点の均衡を保つ。
- 早朝シフト 本番と同時刻スタートの演習を月2回入れ、体内時計を調整。
- アウトプット重視 解説を読むだけで終わらず、必ず“自分の言葉で別解を説明”を書く。
この4フェーズを順守すれば、赤本で得た問題観、青本で磨いた別解力、黒本で鍛えた時間配分がスムーズに連結し、最終盤で得点のブレ幅を最小化できます。
得点を“見える化”するノート術――誤答分析テンプレートと得点管理シートで復習ループを自動化
演習カレンダーを回すうえで最も難しいのは「解きっぱなし」や「復習の先送り」を防ぎ、答案品質を右肩上がりに保つことです。
ここでは東大合格者が実践している三つの“見える化”ツール
①科目横断ノート術
②誤答分析テンプレート
③得点管理シート
を具体例つきで紹介します。
これらを導入すれば、復習にかける時間を最短化しつつ、失点パターンをリアルタイムで修正できます。
1.科目横断ノート術――A3見開き一枚で“年度・大問・テーマ”をリンク
(1)フォーマット
・紙面サイズ:A3を横向きに使用。
・縦軸(行):年度+大問番号(例:2023-数1)
・横軸(列):出題テーマ/必要公式・定理/得点率/所要時間/備考。
| 年度‐大問 | 出題テーマ | 得点/配点 | 所要時間 | ロス要因・メモ |
| 2023‐数1 | 極限・微分 | 12/20 | 45 min | 最後の不等式処理に5 minロス |
| 2023‐英3 | 要約&意見 | 19/25 | 30 min | 代案提示が冗長 |
(2)使い方
- 黒本や青本を解いたら即時記入。
- 得点率70%未満の行は赤ハイライト。
- 同テーマが二行赤になったら即復習キューへ移動。
- 復習完了後、得点率を青で上書きし、ロス原因欄を具体的行動に置換。
例:不等式処理ロス→「√a²+b²の大小比較は平方で即判断」と書き換え。
(3)効果
・「年度は違うがテーマが同じ」問題をレーダーのように捕捉でき、重複学習が消える。
・所要時間と得点率の相関が見え、時間超過の“犯人分野”が特定できる。
2.誤答分析テンプレート――“原因→処方箋”を30秒で書ける最小単位メモ
| 項目 | 記入例 | 時間制限 |
| 問題ID | 2022-数2 | 5秒 |
| ミスの型 | 計算省略→符号誤り | 5秒 |
| 真因 | 分母有理化で−を外に出す処理を飛ばした | 10秒 |
| 処方箋 | 有理化は「展開→符号→約分」のチェックリストを口頭で復唱 | 10秒 |
1問1枚のポストイットに書き、ノート余白やPCディスプレイ横へ貼付。
翌日同テーマに着手する前に口頭で処方箋を読み上げれば、手戻りゼロ化に直結します。
3.得点管理シート――“走行距離と燃費”を同時に測るダッシュボード
(1)シート構成
・列A:日付
・列B:演習セット名(青本2021、黒本英語など)
・列C〜G:英数国理社の得点率
・列H:合計
・列I:ブレ幅(前回比)
・列J:演習時間合計
(2)運用ルール
・演習当日にスマホスプレッドシートへ入力。
・ブレ幅が+10%以上の教科は緑、−10%以下は赤で条件付き書式。
・合計得点率を週末に折れ線グラフ化し、最高値—最低値の差が15%以内を目標に安定化。
(3)“燃費”指標
・得点上昇量÷演習時間=燃費ポイントを自動計算。
・燃費が低い日は「長時間勉強しても伸びない」シグナルとして教材や学習法を即見直す。
4.三ツール統合フロー
- 解答後10分
・得点管理シートへ入力。
・誤答があればテンプレ1枚作成→ノートへ貼付。
- 週末30分
・科目横断ノートの赤行を確認。
・同テーマを翌週フェーズの70%ゾーンへ割り当て。
- 月末1時間
・得点グラフを出力し、燃費低下教科を特定。
・学習リソース再配分(参考書変更・演習量修正)を実施。
このフローを回すだけで「なぜ得点が伸びないか」を言語化しやすくなり、部活や学校行事で忙しい時期でも復習優先順位に迷いません。
スマホ1台で“演習→記録→分析”を完結させる――Notion×Googleスプレッドシート連携テンプレートの実装手順
紙ノートと付箋の運用は視覚的に優れる一方、外出先での修正や共有に弱いです。
そこで本節では、Notionでノート術と誤答テンプレートを集約し、Googleスプレッドシートで得点ダッシュボードを自動更新させるオンライン環境を構築する手順を解説します。
スマホとPCが同期されるため、自宅学習が難しい日でも電車内で記録・分析が進みます。
1.Notionで“科目横断ノート+誤答テンプレート”を管理
Step 1:データベースページを新規作成
・タイトルは「東大過去問マスター」。
・プロパティを5つ設置。
①年度・大問(テキスト)
②科目(セレクト)
③テーマ(テキスト)
④得点率(数値%)
⑤所要時間(数値min)
Step 2:テンプレートボタンを追加
・ボタン名「誤答メモ」。
・ボタンを押すと自動生成されるページに以下のテンプレートを記入。
| 項目 | 記入欄 |
| ミスの型 | |
| 真因 | |
| 処方箋 |
30秒で入力できるよう見出しのみ。
Step 3:ビューを二種類作成
・カレンダービュー:演習日付で並べ、空白日が一目で判別。
・ギャラリービュー:得点率70%未満のカードに赤背景を設定し、弱点が可視化。
Step 4:モバイルウィジェット設定
・iOSならホーム画面へ「今日の誤答メモ」ウィジェットを配置。
・AndroidはクイックアクションにNotionショートカットを追加。
この小さな工夫で“開く障壁”をゼロにします。
2.Googleスプレッドシートで“得点管理シート”を自動化
Step 1:シート設計
・A列:日付。
・B列:演習セット名。
・C〜G列:英数国理社得点率。
・H列:平均。
・I列:ブレ幅(=H2-H1)。
・J列:演習時間。
・K列:燃費(=(H2-H1)/J2)。
Step 2:条件付き書式
・ブレ幅が−10%以下→赤。
・ブレ幅が+10%以上→緑。
・演習時間0分には黄色で警告。
Step 3:グラフ化
・週末に「挿入→グラフ→折れ線」を選択し、平均得点率の推移を可視化。
・タイトルに週番号を入れると比較が容易。
Step 4:Notionとの同期(自動)
・Google App Scriptを開き、onFormSubmitトリガーでNotion APIへポスト。
・スプレッドシートに新行が追加されるたび、Notionデータベースに同じ情報が作成される。
・10行分のスクリプトで完了するためプログラミング初心者でも実装可能。
3.演習ルーティンと連携ツールの一日フロー
| 時刻 | 行動 | 使用ツール | 記録タイミング |
| 06:30 | 黒本数学90分実戦 | 紙問題冊子 | 演習後すぐNotion入力 |
| 08:15 | 通学電車で誤答メモ補完 | Notionモバイル | その場で保存 |
| 19:00 | 青本解説で別解研究 | PDF+Notion | 新カード追加 |
| 22:00 | スプレッドシート更新 | スマホSheets | 自動でダッシュボード反映 |
このサイクルにより「解く→原因を書く→数値化→弱点再投入」が自動ループし、手動管理のストレスが消えます。
4.よくある導入トラブルと解決策
| 症状 | 原因 | 即効対策 |
| Notionの同期が遅い | モバイル回線で画像添付 | 画像はGoogleフォトに外部リンク。 |
| Sheets燃費がNaN表示 | 演習時間未入力 | タイマーアプリで自動記録→Zapierでセル入力。 |
| API連携がエラー | トークン権限不足 | Notionで「database:write」権限を再付与。 |
5.学習効率をさらに高める小ワザ
- 音声入力:スマホのマイクで誤答テンプレートを口述すると入力速度が3倍。
- ハイライト自動抽出:PDFリーダー「LiquidText」で青本解説をマークし、Notionへドラッグ。
- IFTTT通知:得点率が目標未達ならLINE Botでリマインド。
- カスタムアイコン:Notionカードに年度アイコンを設定し、視覚検索を高速化。
- 週次リセット日:日曜21時にNotionの「赤カード」総数をSlackへ自動投稿し危機感を維持。
これらのオンライン化は“記録系タスク”をほぼゼロクリックに近づけ、思考を「問題理解」と「答案改善」へ集中させます。
“失点パターン×参考書”マッピング表でラスト2か月に10%上乗せ――年度選定とピンポイント教材活用の最終戦略
直前期に黒本を解き切ったあと「弱点は分かったが、何を読んで埋めればいいか」で迷う受験生は多い。
時間が限られるこの段階では“やみくも復習”は禁物。
ここでは
①年度選定ルール
②失点パターン別リカバリー表
③2週間スプリント計画の三つを示し
得点率+10%**を狙う最終ブーストを設計する。
1.年度選定ルール——最新→古典→最新の“サンドイッチ”方式
・ステップ1:最新3年分
出題傾向の微妙なシフトを反映。
得点率が60%未満の大問だけ赤本・青本の同年度解説へリンク。
・ステップ2:古典5年(90年代〜00年代)
問題構成がやや長文化・難化している年度を敢えて選ぶ。
体力と集中力を鍛えつつ、古い年度特有のテーマ(数学の立体幾何、英語の長文和訳)で穴を検知。
・ステップ3:直近2年再演習
初回との差を測定。
各科目で「答案の文字量」「解答方針メモ」を比較し、具体的改善が数字へ反映されたか確認。
このサンドイッチ構成で“最新対策”と“骨太基礎”を1本の線にする。
2.失点パターン別リカバリー表——不足スキルに教材を一点投下
| 科目 | ミスの型 | 推奨教材 | 処方箋フレーズ |
| 数学 | 計算暴走→誘導無視 | 『東大25年 数学の軌跡』(河合出版) | 誘導文に赤マーカー→先に読み返す |
| 数学 | 記述量不足で部分点落ち | 駿台『数学実戦講評集』 | “解法の骨格→肉付け”を写経 |
| 英語 | 段落要旨ズレ | 『ポレポレ英文読解プロセス50』 | 主語‐動詞‐補足を鉛筆で区切る |
| 英語 | 和訳で失点 | Z会『東大英語 和訳徹底対策』 | 品詞名を書き込んで構造確認 |
| 国語 | 記述字数オーバー | 『得点奪取 現代文 記述・要約』 | 要素3→要素2へ圧縮練習 |
| 理科 | 設定読み飛ばし | 『東大理系攻略 化学・物理 実験考察』 | 図を先にノートへ模写 |
| 社会 | 具体例欠落 | 山川『詳説○○史図説』 | 図版キャプションを要約カード化 |
表の右列「処方箋フレーズ」をNotionの誤答メモ欄へコピペすると、復習時に“一行で対策を再想起”できる。
3.2週間スプリント計画――弱点を“教える側”になって潰す
- Day1〜2:教材インプット
上表の参考書該当章のみを読破。 - Day3〜5:アウトプット写経
数学は解答欄1行残し写経→空白を自力で補完。
英語は和訳例文を日本語→英語へリライト。 - Day6:擬似講義録音
スマホで10分の自分講義を録音し、翌朝聴き返して論理飛躍に×印。 - Day7:黒本同テーマ大問を再トライ
得点率をシートへ入力し、改善幅を色付きセルで可視化。 - Day8〜13:別科目同手順
2週間で主要3教科をひと回し。 - Day14:総合テスト
過去問1年分を本番同時刻に実施し、合計で+10%達成をチェック。
4.直前30日“やらないことリスト”で時間ロスを防ぐ
・新規教材に着手
・全年度一気解き
・採点基準を無視した“自己満答案”チェック
・徹夜学習
・3時間以上の動画講義 binge watching
やらないことを明文化して壁に貼ると、焦りによる暴走を抑制できる。
5.迷ったら“第三者視点”を注入する——無料オンライン相談のご案内
自力で演習計画を立てても
「得点が伸びない原因が分からない」
「優先順位が定まらない」
と感じたら、個別指導塾ワイザー オンライン校の無料相談をご利用ください。
難関大対策コースでは東大・京大生チューターがオンライン面談で
- 失点パターン×教材マッピングの個別提案
- 残り日数に合わせたフェーズ別KPI設定
を行い、翌日から修正できる具体ステップを提供します。
相談後に教材販売や強制入会は一切ありません。
「オンラインで学習管理まで完結したい」「赤本・青本・黒本の使い分けに不安が残る」と感じたら、下記フォームからお気軽にご予約ください。
あなたの演習ループを最短で合格点へ結びつけるサポートを、ワイザーが全力で行います。
▼無料相談はこちらをクリック▼



