
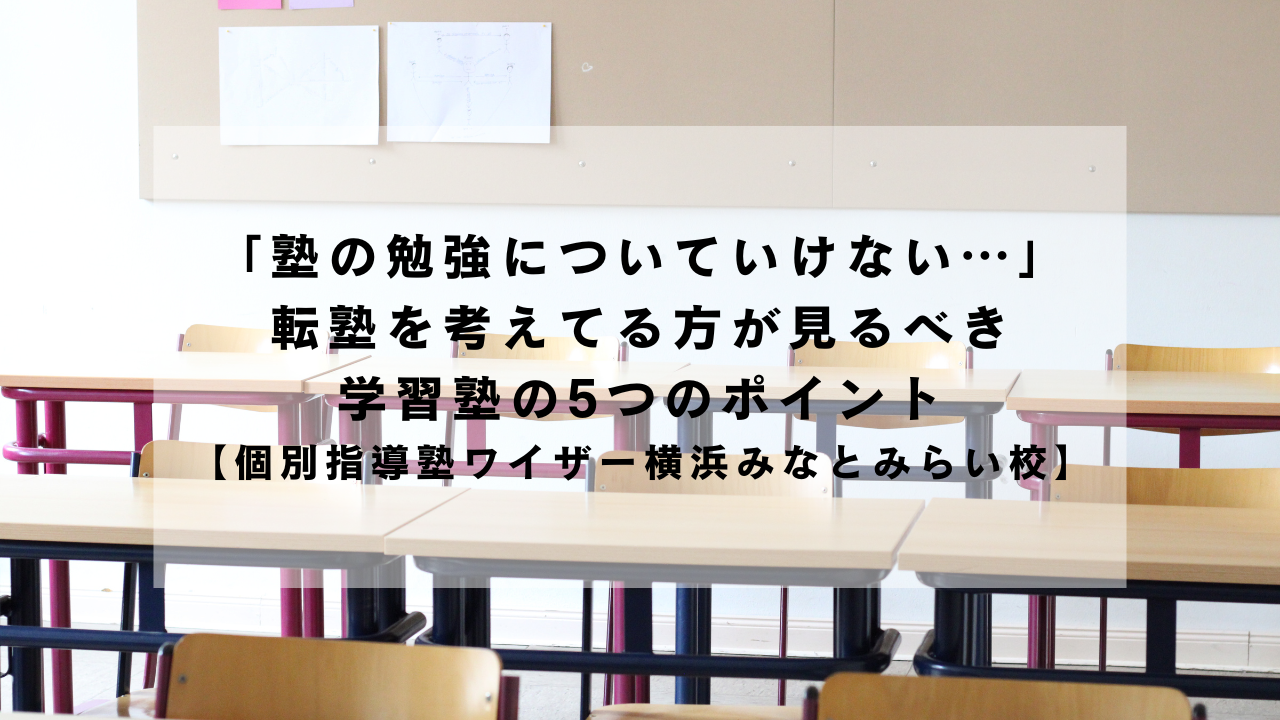
なぜ“塾についていけない”子が増えているのか?
「塾に通わせているのに、成績が上がらない…」
「宿題をやらないどころか、授業についていけてないみたい…」
そんな不安を抱えている保護者の方は、実は少なくありません。
特に近年、塾に通いながらも
「学習につまずいている子」
「勉強する習慣がないまま通塾している子」
が増えており、結果として転塾を検討するご家庭も目立ちます。
なぜ今、塾についていけない子が増えているのでしょうか。
最大の理由は
「学習塾が“勉強のやり方”ではなく、“勉強そのもの”を教える場所になってしまっている」ことにあります。
つまり、“塾に行けば成績が伸びる”という昔ながらの期待が、
現代の子どもたちには当てはまらなくなっているのです。
多くの学習塾では、学校と同じように授業形式で学習内容を解説し、
「理解できたか」「問題が解けたか」に重点を置いています。
しかし、そもそも学習習慣が身についていない子どもたちは、
その前提にすら立てていません。
例えば、家で机に向かう習慣がない子にとって、
授業を聞くだけの受け身の学習では定着しにくいのです。
しかも、授業中にわからない箇所が出てきても、自分から質問できない子も多く、
その疑問を放置したまま次の単元に進んでしまう。
この“わからないの蓄積”が、塾についていけなくなる第一歩なのです。
もうひとつの要因は、「通塾=自動的に成績が上がる」という保護者側の誤解です。
確かに、塾に通うことは学習環境として一定のプラスになります。
しかし、日々の家庭学習が伴っていなければ、
ただ“通っているだけ”で終わってしまいます。
学習塾は“勉強の場”を提供するだけであり、“家庭での学び”を習慣化させるには、
別のアプローチが必要です。
このような現状の中で、
多くの塾が見落としているのが「学習習慣の定着」という基礎部分です。
塾についていけないと悩んでいるご家庭の多くは、
「子どもに学ぶ姿勢がない」「塾の先生と合わない」と感じるかもしれませんが、
根本的な問題はそこではなく、
“学習を習慣として身につけるための仕組み”が欠けていることにあります。
つまり、転塾を考える上で重要なのは、
「より難しいことを教えてくれる塾」や「合格実績が高い塾」ではなく、
「その子の現状に寄り添って、学習習慣から育ててくれる塾」であるかどうかです。
このあと紹介する「塾を選ぶ5つのポイント」では、
こうした“学習の土台”をどう育てるかに焦点を当てていきます。
単なる授業のうまさや教材の豊富さではなく、「続けられる仕組み」があるかどうか。
塾選びの基準が変わる今、親として見ておくべき視点を一つずつお伝えしていきます。
①「“学習習慣”の有無を前提に塾を選ぶ」
「塾に通っているのに、まったく勉強するようにならない」
「授業中は聞いているようだけど、家ではスマホばかり」
こうした声は、今やどの家庭でも一度は聞かれる悩みです。
このようなケースに共通しているのが、
“学習習慣がない状態のまま通塾している”という事実です。
実は、勉強が苦手な子どもの多くが抱えているのは、学力の低さではなく、「日々の勉強を当たり前にこなす習慣がない」という根本的な課題です。
ここで重要になるのが、「その塾が学習習慣のない子を前提に設計されているかどうか」です。
多くの塾は、“ある程度自分で勉強できる子”を対象にしています。
週に数回の授業を受け、あとは自宅で復習・宿題をこなして成績を上げていくというモデルです。
このスタイルは、もともと勉強に対する抵抗がない子どもには有効です。
しかし、机に向かう習慣がない子どもにとっては、授業を受けても知識が定着しづらく、結局「わからないまま進む」ことになります。
だからこそ、塾選びの第1ポイントは、「この塾は、まだ学習習慣がない子どもでも成果が出る仕組みがあるか?」という視点です。
ここでの“仕組み”とは、
「家庭での学習を前提としないこと」
「通塾以外の時間も含めて習慣を形成できる支援があること」です。
そのためには、授業だけではなく、生活リズム全体に寄り添った対応が求められます。
具体的には、以下のような要素を備えている塾を選ぶとよいでしょう。
・毎日の生活サイクル(起床・就寝・食事・スマホ時間)をヒアリングし、それに合わせて勉強の時間を調整する
・いきなり多くの課題を出すのではなく、短時間の学習から始めて“やればできる”という小さな成功体験を積ませる
・学習内容よりも“学ぶ行動そのもの”を定着させるカリキュラムがある
ここで見落としてはいけないのが、“保護者側の意識”です。
保護者の方はつい、「授業がわかりやすい塾」「有名な先生がいる塾」「合格実績のある塾」などを重視しがちです。
しかし、それらは“勉強をする習慣がある子”に対して効果を発揮するものです。
一方で、勉強のやり方すらわからず、何をどこから始めていいのかも見えていない子どもには、それ以前の「習慣を身につけさせる」サポートが必要不可欠なのです。
もうひとつ重要なポイントは、“習慣化には時間がかかる”という現実です。
1週間、2週間で劇的に行動が変わることはありません。
最初のうちは抵抗もあるかもしれませんし、面倒くさそうな顔をされることもあります。
それでも、毎日少しずつ“できた”を積み重ねていくことで、「やらなきゃ気持ち悪い」と思えるような状態を目指すのが、習慣形成の本質です。
そのため、塾が「短期間で成果を出す」と過度にアピールしている場合は注意が必要です。
即効性よりも、“継続して少しずつ変化していく仕組み”がある塾のほうが、長い目で見たときに確実に結果が出ます。
学習習慣がないまま、授業だけを受け続けても学力は向上しません。
「勉強を教えてくれるかどうか」ではなく、「勉強する習慣を育ててくれるかどうか」。
これが、転塾を考えるご家庭がまず最初に確認すべき、本質的なチェックポイントです。
②「“毎日の学習を支援する体制”があるかを確認する」
塾選びをする際、「週に1~2回、授業を受ければ十分」と考えていませんか?
しかし、勉強が苦手な子どもや学習習慣がない子どもにとって、週数回の授業だけで学力を定着させるのは難しいものです。
むしろ、週に1回だけ授業があり、それ以外の時間が放置されているような状態では、授業の内容すら十分に理解できず、次第に遅れが生じていきます。
大切なのは、授業がない日も含めて、毎日の学習を支援する体制が整っているかどうかです。
その体制が整っていない塾では、次のような問題が起こりがちです。
・塾のある日だけ集中し、その他の日は完全に勉強しない
・宿題が出ても「どこまでやればよいか」が曖昧で後回しにしてしまう
・わからない問題をそのまま放置して次の授業に臨んでしまう
こういった状態が続くと、学習のリズムが安定せず、塾に通っているにもかかわらず「何も身についていない」と感じてしまうのです。
これを防ぐには、日々の学習を“習慣化”させる支援があるかがカギになります。
たとえば、「毎日やるべき学習内容を提示してくれる仕組み」がある塾なら、子どもは日ごとに“やること”が明確になるため、勉強に取りかかるハードルがぐっと下がります。
加えて、「やった内容を毎日提出・報告する仕組み」があれば、自然と“やらなきゃいけない”という意識が育ち、自発的な学習にもつながっていきます。
特に学習習慣がないお子様の場合、「時間割を自分で立てる」ことはまずできません。
だからこそ、塾側が“毎日の学習”を伴走してくれるかどうかが極めて重要なのです。
具体的には、以下のような支援体制がある塾が望ましいと言えます。
・毎日、学習の目標や課題を具体的に提示してくれる
・課題の進捗状況を報告・チェックする仕組みがある
・授業外でも、わからないところを質問できるサポート体制がある
・生活リズムや部活との両立を配慮したカリキュラム設計がされている
これらのサポートは、単なる学習指導とは異なり、「勉強するという行動自体を定着させる」ことに重点が置かれています。
こうした体制の有無によって、通塾の効果が大きく変わるのは言うまでもありません。
日々の積み重ねが苦手な子どもに必要なのは、気合いや根性ではなく、「続けられる仕組み」です。
塾を選ぶ際は、授業の質や講師の熱意だけでなく、「毎日の学習をどうサポートしてくれるのか」という視点を必ずチェックするようにしましょう。
③「“毎日単位”で課題を提示してくれる塾を選ぶ」
塾に通っていても、成果がなかなか出ない子どもの多くに共通するのが、「やるべきことが曖昧なまま放置されている」という状況です。
特に勉強が苦手だったり、学習習慣がない子にとって、「とりあえず宿題をやっておいてね」「来週までにここを進めておこうか」といった曖昧な指示は、事実上“やらない理由”になります。
こうした子どもたちに必要なのは、「やる内容が具体的に決まっていること」です。
つまり、「今日は何を、どこまで、どう進めるか」が、1日単位で明確に提示されているかどうか。
これが、“勉強する行動を起こせるかどうか”の分かれ目になります。
たとえば、「今週の目標は英語の文法を理解する」ではなく、
「5月3日(木):英語ワーク p.14~16を30分」といったように、具体的かつ現実的な量で提示されることで、子どもは初めて「これならやれそう」と感じることができます。
逆に、内容が抽象的だったり量が多すぎたりすると、やる前から気持ちが折れてしまい、机に向かうことすらできなくなるのです。
さらに重要なのは、こうした課題(タスク)が“毎日続いているかどうか”です。
週に1度まとめて課題を出す形式では、勉強の優先順位が下がり、結局最後の日に一気に片付ける「詰め込み型」になりがちです。
これでは知識も定着せず、「やっても伸びない」「面倒なだけ」という印象ばかりが残ってしまいます。
一方で、毎日少しずつ進めることが習慣になれば、「今日はこれだけやればいい」という安心感と、「昨日できたから今日もできる」という達成感が生まれます。
これは、行動心理学においても“習慣化の原則”とされており、特にやる気が安定しない子どもにこそ効果的です。
また、毎日課題が提示されるということは、裏を返せば「その進捗を見守ってくれる存在がいる」ということでもあります。
「やったら報告する」「できたことを見てもらえる」このシンプルなやりとりが、子どもたちにとっては非常に大きなモチベーションになります。
こうした“日々の積み重ね”が最も大切なのに、多くの塾では「授業をやること」ばかりに注力しており、「日常をどう支援するか」という視点が抜けていることが多々あります。
塾を選ぶ際には、ぜひ次のようなポイントを確認してみてください。
・課題は週単位ではなく、日単位で出されているか?
・内容は具体的に明示されており、量の調整もされているか?
・進捗確認の仕組みがあり、やったことが評価される仕組みになっているか?
・学年や成績ではなく、生活リズムや学習体力に合わせて設計されているか?
学力は一夜にして伸びるものではありません。
“毎日ちょっとずつ進むことが苦ではない”という状態をつくれる塾こそ、転塾先としてふさわしい選択肢です。
④「“わからない”をその場で解決できるサポートがあるか?」
「塾の授業では理解できたはずなのに、家に帰ったら一人では解けなかった」
「質問したいけど、次の授業まで聞けない。だから結局そのままにしてしまう」
そんな経験をしたことのある子どもは少なくありません。
学習が苦手な子どもほど、わからないことを“ためこむ”傾向があります。
そして、それを誰にも相談できずに時間が経ち、
最終的には「もういいや」「どうせ無理だ」といった諦めの感情に結びついてしまうのです。
この悪循環を断ち切るために必要なのが、“その場でわからないことを解決できる”環境です。
ここで重要なのは、「授業中に質問できるか」ではなく、
「授業以外の時間にも相談できるか」という視点です。
そもそも、授業中に手を挙げて質問すること自体がハードルの高い行動だということを、大人は忘れがちです。
自信がない子どもは
「こんなこと聞いてもいいのかな…」
「他の人はわかっているのに、自分だけできないって思われたら恥ずかしい…」
といった不安を抱えています。
特に集団指導型の塾では、その傾向が顕著です。
また、週に1〜2回の授業しかない塾では、
疑問が生まれたとしても「次の授業まで何日も待たなければいけない」という問題もあります。
その間に、やる気も疑問も冷めてしまうということはよくある話です。
この問題を解決するには、以下のような柔軟な質問対応体制がある塾を選ぶ必要があります。
・授業外でも質問を受け付けている(LINE、アプリ、オンラインなど)
・回答が返ってくるまでのスピードが早い
・回答内容が丁寧で、再質問にも対応してくれる
・学年や成績に関係なく、気軽に質問できる雰囲気がある
特に、リアルタイムでやり取りができるオンラインの質問チャット機能や、
講師が常駐している質問受付システムなどがある塾であれば、
子どもが疑問を感じた瞬間にすぐに解決できます。
「その時に聞ける」という安心感があるだけで、子どもたちは前向きに学習に取り組めるようになります。
そして、質問できる体制が整っている塾には、
自然と「聞いてもいいんだ」「聞けば教えてもらえるんだ」という空気が流れています。
この空気は、勉強が苦手な子どもにとって何よりも心強いものです。
「また質問していいのかな」と躊躇せず、疑問を解決しながら学びを進められる環境は、
勉強に対する自信を育てる土台になります。
また、保護者としても「うちの子、わからないことをずっと放置してないかな?」という心配がなくなり、安心して任せることができます。
塾選びでは「教える力」ばかりに目が行きがちですが、
「わからないを解決する力」こそが、学力を底上げする鍵になります。
⑤「保護者も“学習状況を把握できる”仕組みがあるか?」
お子様の学習状況について、次のような不安を感じたことはありませんか?
・「塾には行っているけど、ちゃんと勉強しているのか分からない」
・「塾の先生と話す機会が少なくて、どこまで進んでいるのか知らない」
・「テストの結果を見るまで、成績が上がっているか判断できない」
このような不透明さは、保護者にとって大きなストレスになります。
特に、勉強習慣のないお子様を抱えるご家庭では、
「塾に通わせるだけで大丈夫なのか」という不安が常につきまとうのが現実です。
だからこそ、塾選びの最後のポイントとして重要なのが、
保護者も日々の学習状況を“見える化”できる仕組みがあるかどうかです。
近年では、紙の簡易的な報告書だけでなく、
スマホやアプリを使って学習の進捗をリアルタイムで確認できる塾も増えてきました。
たとえば、以下のような仕組みがある塾は、保護者にとって非常に信頼しやすいと言えます。
・学習の進捗(どの教科を、どこまでやったか)を毎日確認できる
・授業ごとの内容や理解度が、報告書としてフィードバックされる
・カリキュラムの見直しが定期的に行われ、その内容を共有してくれる
・三者面談やLINE相談など、塾と家庭のコミュニケーションが密である
このような仕組みがあることで、
「この子は何を学んでいるのか」
「うまく進んでいない教科はどれか」
といった点を保護者も理解でき、家庭での声かけやサポートがしやすくなります。
一方で、報告が学期に1度だけだったり、面談が年に数回しか行われないような塾では、子どもの変化を見逃してしまうリスクも高まります。
「急に成績が下がった」「やる気が見えなくなった」などの兆候に、後手で気づくことになるのです。
また、報告の頻度だけでなく、その“質”にも注目する必要があります。
ただ「英語の授業をやりました」といった記録だけでは意味がありません。
「英語の長文問題で語彙力に課題が見られたため、来週からは単語練習のタスクを強化します」といったように、学習の成果や課題、今後の方針が明確に記されているかどうかが重要です。
そして、保護者が学習の様子を把握できることで、
塾と家庭が同じ方向を向いて子どもを支えることができます。
「最近、毎日ちゃんとやってるんだね」
「こないだの面談で言ってたこと、実践できてるみたいだよ」
と声をかけてあげることで、子どもは“認められている”“見守られている”と実感し、
自信やモチベーションにつながっていきます。
塾に任せきりにするのではなく、「家庭と塾が連携できる仕組み」があるかどうか。
これが、子どもの成長を安定的に支えるうえで欠かせない視点です。
“教え方”より“続け方”を整える塾こそ、伸び悩みから抜け出す鍵
ここまで、「塾の勉強についていけない」と感じたときに再確認すべき、
学習塾選びの5つの視点をお伝えしてきました。
勉強のやり方が悪い、塾の先生が合わない、教材が難しすぎる。
多くの保護者が悩む原因はさまざまですが、根本をたどれば、
いずれも*「学ぶ習慣が身についていないこと」に行き着くケースが大半です。
振り返り:転塾前に見直すべき5つのチェックポイント
- 学習習慣を“前提としない”設計か?
→ すでに勉強習慣がある子を対象とした塾ではなく、ゼロから習慣を作れる塾か。 - 家庭学習の管理体制が“毎日”整っているか?
→ 通塾日以外のサポートがなく、「自習を任せきり」の塾では変化は生まれません。 - 日単位・ページ単位で“やるべきこと”が明確になっているか?
→ 抽象的な目標設定ではなく、毎日の「今日やるべき内容」が具体的に指示されているか。 - わからないことを“その場で聞ける”仕組みがあるか?
→ 質問できないまま1週間放置される環境は、子どもの自己肯定感を下げる原因になります。 - 保護者が学習状況を“見える化”できるか?
→ 何をどこまで学習し、どんな課題があるのかが共有されていれば、家庭の声かけも効果的になります。
この5つの視点はすべて、「教える内容」ではなく
「続けさせる仕組み」に関わるものです。
そして、この“続ける”という力こそが、学力の土台になります。
習慣の有無で、1年後の成績は180度変わる
たとえば、毎日30分の学習を1年間続けるだけで、
1日もやらない子との差は180時間以上。
この時間差は、学力だけでなく、
「勉強に対する意識」「課題に向き合う姿勢」「将来への自己効力感」にまで大きな差を生み出します。
つまり、子どもが「やる子」になるか「諦める子」になるかは、環境の設計次第です。
もし今、お子様が「塾の勉強についていけていない」と感じているなら、
問題なのは“本人の能力”ではなく、“塾との相性”かもしれません。
もっと言えば、「その子にとって自然と続けられる環境」を選べていないだけなのです。
学習習慣がない状態からでも、生活リズムに合わせて“毎日できる”仕組みを構築する。
その設計に特化しているのが、個別指導塾ワイザーです。
・起床時間・部活・スマホ時間まで細かくヒアリングし、現実的なスケジュールを組み立てる
・毎日の学習タスクを明確に提示し、報告制度で習慣化を定着
・授業以外でも質問可能な体制が整っており、疑問をその場で解決
・保護者とはスマホで日々の状況を共有、三者面談も定期実施
このように、“やる気がない子”“勉強が嫌いな子”でも安心して始められるように、
環境設計そのものを徹底的に工夫しています。
実際に通塾している生徒の中には、以前は「毎日0分」だった学習時間が、
「90分以上」に伸びたケースもあります。
重要なのは、「何ができるか」より、「どうやって続けられるようにするか」なのです。
・「今の塾が合っていないかもしれない」
・「家庭だけでは、どうにも管理できない」
・「本人が“やる気を出す”仕組みを作ってほしい」
そう思われた方は、ぜひ一度、無料相談をご利用ください。
お子様の現在の生活リズム・学習状況・性格などを丁寧にヒアリングし、
“その子だけの学習戦略”をご提案させていただきます。
▼無料相談はこちらをクリック▼



