
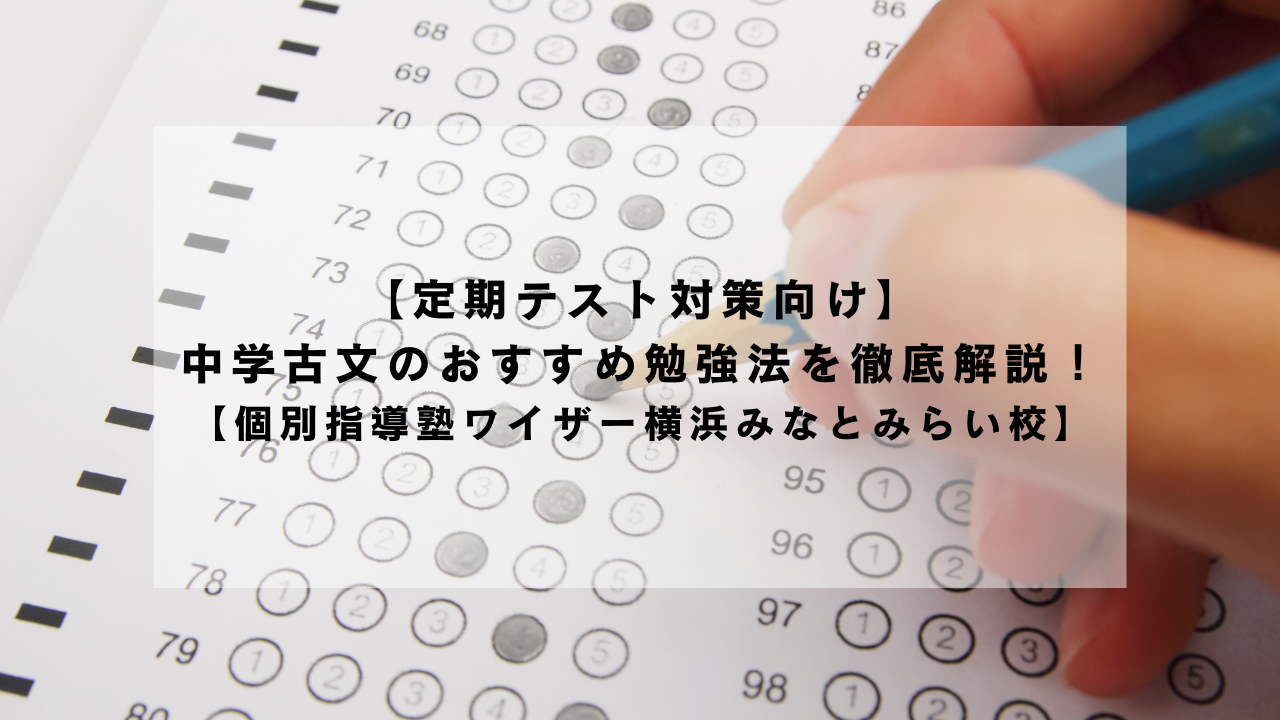
中学古文が苦手な理由と、成績が上がらない本当の原因
中学生にとって、古文はなじみの薄い分野です。
日常で使わない言葉、読みにくい文字遣い、現代と異なる言い回し。
それに加え、学校の授業でも「単語を覚えて、訳を書くだけ」というような作業的な学習に終始しがちです。
この結果、「古文は苦手」「意味がわからない」
「定期テストでも点が取れない」と感じてしまう生徒が非常に多くなっています。
では、なぜ古文はこんなにも理解が難しく、成績に結びつきにくいのでしょうか?
最大の原因は、“古文が言語であることを忘れている学習法”にあります。
英語と同じように、古文もれっきとした一つの言語です。
意味や構造を理解するためには、単語や文法をバラバラに覚えるのではなく、
「文章の中でどう機能しているか」を感覚的に捉える訓練が必要です。
にもかかわらず、現実には「文法だけを丸暗記」「現代語訳だけを写す」といった受動的な勉強に偏りがちです。
また、古文には“背景知識”の理解も欠かせません。
登場人物の言葉遣いや行動には、当時の風習や身分制度、価値観が大きく関わっています。
例えば、『枕草子』や『徒然草』を読んでいても、出てくる季節の行事や日常風景が現代とはかけ離れているため、イメージを持ちにくいのです。
背景を知らずに読み進めるのは、知らない国の文化を知らずに外国語の小説を読むようなもの。それでは理解が追いつかなくても当然です。
さらに、古文は“慣れ”がものを言う科目です。
言葉のリズム、助詞の使い方、文末の表現など、
現代語と微妙に異なる部分に慣れるまでは、
いちいち意味を考えながら読む必要があります。
この「慣れるまでの壁」が高く、つまずいたまま放置してしまう生徒も少なくありません。
加えて、定期テスト対策として「ワークの問題だけをこなす」学習が多く見られます。
もちろん演習は必要ですが、ワークの問題はあくまで“定着の確認”の役割であり、
基礎の理解がない状態でいくら問題を解いても「なんとなく当たった」「全部間違えた」の繰り返しで、応用力は一向に伸びません。
つまり、テストで点が取れない最大の理由は、知識の“定着”ではなく、“理解”の不足にあるのです。
このように、多くの中学生が古文に苦手意識を持ってしまう背景には、
学習法そのもののズレがあります。
しかしこれは、裏を返せば“適切な学び方さえ知れば、誰でも古文の点数は上がる”ということでもあります。
次の節では、その「古文の苦手を克服し、定期テストで得点できるようになるための具体的な勉強法」を紹介していきます。
定期テストで点が取れる!中学古文の効果的な勉強法5選
中学古文を得意にするためには、「丸暗記型」の勉強から脱却し、
「文の意味が自然と入ってくる状態」を目指す必要があります。
ここでは、定期テストに直結する効果的な古文の勉強法を5つ紹介します。
どれも特別な道具は必要なく、今すぐ始められる方法ばかりです。
1.古文単語は“セット”で覚えると驚くほど定着する
中学生の古文学習において、もっともつまずきやすいポイントのひとつが「古文単語」です。
古文は現代語とは語彙が大きく異なり、「聞いたこともない言葉」がいきなり文章に出てくるため、読むたびに引っかかってしまいます。
「あはれ」「いと」「をかし」など、単語の意味が分からなければ、文章の内容もぼんやりとしか理解できません。
意味が曖昧なまま読んでも、手応えのないまま終わってしまい、やがて苦手意識が強まっていくのです。
では、どうすれば古文単語を効率よく覚えられるのでしょうか?
最も効果的なのは、「単語を単語としてではなく、“文章の中の一部”として覚える」ことです。
つまり、実際に出てくる“使用パターン”をセットで覚えるのです。
たとえば、「いと」は「とても」「たいそう」といった意味で、頻出語のひとつです。
これを単体で「いと=とても」とだけ覚えるのではなく、
「いとをかし(とても趣がある)」「いとうつくし(とてもかわいらしい)」のように、使われる語と一緒にフレーズで記憶する方がはるかに定着します。
なぜなら、人間の記憶は「意味のまとまり」や「ストーリー性のある情報」の方が記憶に残りやすい性質を持っているからです。
また、「あはれ」という言葉も、「あはれなり=しみじみと趣がある、感動的だ」という意味を持ちますが、単に「しみじみ」とだけ覚えてしまうと、使われ方がイメージしにくく、文章の流れの中でピンとこないことがあります。「『あはれ』という語は、誰かの死や別れなど“心が動いた瞬間”に使われやすい」と背景知識とともに覚えれば、より深い理解につながります。
さらに重要なのは、「現代語訳と結びつける」のではなく、「古文の世界観の中でその語が持つ“空気感”を感じること」です。
たとえば、「あはれ」は単に「感動した」ではなく、
「言葉にできないような感情の揺れ動き」を表すこともあります。
このような感情のニュアンスまで把握しておくと、設問の選択肢の中で適切な意味を選びやすくなります。
実際の学習方法としておすすめなのは、「例文+訳」を見開きで掲載しているタイプの古文単語帳を活用することです。
文章の中でどのように使われているのかを知ることで、機械的な暗記から脱却し、「使える単語」としての知識に変わっていきます。
また、音読との組み合わせも非常に効果的です。
セットで覚えたフレーズを、声に出して繰り返し読むことで、音の響きと意味が結びつき、さらに定着しやすくなります。
例えば「いとめでたし」や「なかなかにおかし」など、実際に口に出すことでリズム感と語感のイメージが一致し、読解スピードも向上していきます。
なお、最初からすべての古文単語を完璧に覚える必要はありません。
まずは「頻出語30語」ほどを選定し、フレーズとともに繰り返し触れていくことを優先しましょう。
これだけでも多くの中学古文に対応できるようになり、読解のハードルが一段階下がります。
古文単語は“単語帳で1語ずつ覚える”というイメージが強いかもしれませんが、
実はそれでは効率が悪いのです。
文章の中で、他の語と“セット”で出てくる頻度が高いため、
単体よりもフレーズごとに覚えた方が現実の読解に活かしやすいという特徴があります。
繰り返しになりますが、古文は言語です。
言語を学ぶときは、「使い方ごと」覚えるのが鉄則です。
英語で「take」は「take a bath」「take a break」「take care」といった表現で覚えるのと同様に、古文単語もフレーズで捉えることで、実践的な語彙力が育ちます。
2.古文の音読を習慣にすることで“読む力”は飛躍的に上がる
古文が苦手な中学生の多くは、
「読んでも意味がわからない」「どこが大事なのかわからない」と感じています。
その原因の多くは、“古文の語順やリズムに慣れていない”ことにあります。
現代文と違い、古文は助詞や語尾の使い方、主語と述語の位置が異なることが多く、
それを“目で見て”理解するのはとても難しい作業です。
そこでおすすめなのが「音読」です。
音読は、一見シンプルな勉強法に見えて、
実は古文の読解力を高める上で最も効果的な方法のひとつです。
特に、古文に苦手意識を持っている生徒にこそ、この学習法を取り入れてほしい理由があります。
音読が古文に効果的な3つの理由
1. リズムに慣れることで語順の違いを自然に受け入れられる
古文は独特の語順を持っています。
たとえば、「春はあけぼの。やうやう白くなりゆく山ぎは…」という有名な一文も、
最初のうちは「何が白くなっているの?」「どこが主語?」と迷ってしまいがちです。
しかし、何度も声に出して読むうちに、この語順が“自然な形”として身体に染み込んでいきます。
そうすると、頭の中で文を現代語訳に変換せずとも意味がつかめるようになります。
英語学習において、リスニングやシャドーイングが効果的なように、古文においても「耳と口を使って慣れる」ことが非常に重要なのです。
2. “意味のまとまり”を感覚でつかめるようになる
古文を読む際には、文節や意味の区切りを把握する必要がありますが、
これを無理に文法的に考えながら読むと時間がかかりすぎてしまいます。
ところが、音読を繰り返すことで、
“ここで一区切り”“このあたりで場面が変わる”といった構造が、自然と身体で分かるようになります。
特に、学校の教科書で取り扱う古文は、
多くが“短い場面描写”や“比喩表現”で構成されており、
読み方にリズムを持たせることで記憶にも残りやすくなるというメリットがあります。
3. 読解スピードが速くなる
音読を習慣化すると、語順や語感に慣れるため、目で読むスピードも上がっていきます。
テスト本番では時間との勝負になることも多く、読むのに時間がかかると焦ってミスにつながるリスクもあります。
音読によって“古文に触れる回数”が増えると、読むこと自体に対する抵抗がなくなり、
結果として試験での処理能力が格段に向上します。
実践的な音読の方法
音読は1日3〜5分でも効果があります。
以下のようなステップで取り組むのがおすすめです。
・ステップ①:教科書の古文を選ぶ
慣れていないうちは、学校の授業で取り扱ったものから始めるのが最適です。すでに意味をある程度習っているため、無理なく取り組めます。
・ステップ②:意味は気にせず読む
最初のうちは、訳を考えず「声に出す」ことだけに集中します。音やリズムに意識を向けることで、身体に古文特有のリズムが染み込んでいきます。
・ステップ③:音読→黙読→現代語訳の順で繰り返す
音読のあとに意味を確認し、黙読で内容を思い出しながら読むと、理解の深度が上がります。1日5分でも、これを毎日繰り返せば、驚くほどスムーズに読めるようになります。
・ステップ④:録音して自分の読み方をチェック
自分の声を録音し、聞き返してみると「どこで詰まっているか」「読むスピードは適切か」が客観的に分かります。間違いやすい箇所に気づくこともでき、精度の高い音読が可能になります。
よくある失敗とその対策
音読を続けられない生徒の多くは、
「意味が分からないから、読んでも意味がない」と感じてしまう傾向があります。
しかし音読は、「意味が分かるから読む」のではなく、
「読むから意味が分かるようになる」ための学習です。
初めは意味が分からなくても問題ありません。
むしろ、「読んでいるだけなのに、なんとなく意味が分かるようになってきた」
という感覚を得られた時が、古文が“読めるようになってきた”サインです。
3.主語と述語にマーカーを引いて読むだけで、古文が“読める”文章に変わる
中学古文を学んでいると、
「誰が何をしたのか分からない」
「文章の流れがつかめない」と感じる生徒は少なくありません。
現代文であれば、主語と述語は比較的わかりやすく配置されており、文構造も明快です。
しかし古文では、主語が省略されることが多く、
文章の冒頭から最後まで読んでも「結局これは誰の話なのか?」と迷ってしまうことがよくあります。
この“読めない感覚”を解消するために非常に効果的なのが、
「主語と述語にマーカーを引いて読む」勉強法です。
これは一見地味な作業に見えるかもしれませんが、古文の文章構造を可視化し、
内容理解のスピードと正確さを大きく向上させる方法です。
主語が省略される古文の特徴
古文では、同じ登場人物の行動や思考が続いている場合、
繰り返し主語を明示しないのが一般的です。
たとえば、ある貴族が屋敷を訪れる場面で、
「〜して、〜して、〜なりけり」と続いたとき、
全体が同じ人の行動であると文脈から察する必要があります。
このとき主語を見失うと、どこから誰の行動に変わったのか判断できず、
内容の理解に大きな支障をきたします。
現代の文章とは異なり、読者側に“文脈を読む力”が求められる古文においては、
主語の識別は「文法」ではなく「思考」に近い作業です。
だからこそ、練習を通じて読み取る力を養う必要があるのです。
マーカーを使うだけで読解が劇的に変わる
主語と述語に色分けして線を引く、という単純な行動には以下の3つの効果があります。
1. 誰の視点かが一目でわかる
視覚的に主語が浮かび上がることで、「あ、この場面は女房の話だったのか」「これは帝の気持ちを描いているのか」といった人物像の把握が容易になります。
古文においては、登場人物の身分や性格が場面理解に直結するため、この「誰の視点か」を見抜くことはとても重要です。
2. 文章の構造が明確になる
主語と述語が線で結ばれている状態を見ると、「文の核」が視覚的に浮き上がります。
どこに装飾的な表現があるのか、どこが情報の中心なのかがひと目でわかるため、読解力に自信がない生徒でも“全体の構造”をつかみやすくなります。
3. 選択肢問題への対応力が上がる
定期テストや高校入試では、「このときの人物の心情として最も適切なのはどれか」「この行動をとった人物は誰か」など、主語の理解を前提とした問題が頻出します。
マーカー読みを習慣にすることで、こうした問題に対しても根拠をもって答えられるようになります。
具体的な実践手順
以下のような流れでマーカー読みを実践してみましょう。
・ステップ①:教科書または問題集の古文を選ぶ
学校で使っているテキストを活用しましょう。すでに授業で扱っているので、全くの初見よりも理解しやすくなります。
・ステップ②:1文ずつ、主語と述語を探す
文末の「けり」「たり」「む」などに注目すると、述語を見つけやすくなります。そこから逆算して、「誰がその行動をとったのか」を考えます。
・ステップ③:主語に青、述語に赤など、色を決めてマーカーを引く
色を変えることで、文構造が明確に見えます。慣れてくると、「主語が途中で切り替わる場面」などにも自然と気づけるようになります。
・ステップ④:同じ人物の行動に線でつないでみる
これは少し上級テクニックですが、連続した主語省略を見抜くための訓練になります。人物ごとに線をつなぐと、話の流れがぐっと見通しやすくなります。
よくあるミスと対策
この勉強法でよくある間違いは、
「主語を文の先頭にあるものだと決めつけてしまう」ことです。
古文では、述語が先に出てくることも多く、
「見た目の順序」と「意味の順序」がずれていることがあります。
そのため、必ず述語を起点にして、その行動を“誰が行ったのか”という視点で主語を探す癖をつけましょう。
また、「主語が誰なのか分からない」と感じたときは、
前後の文から人物の動きや言葉遣いを手がかりにすることが大切です。
一文で判断できない場合は、前の文章をもう一度読み直す柔軟性が求められます。
4.文法は“活用表”より“意味のパターン”で覚えると応用力がつく
古文が苦手な中学生の多くが、挫折するポイントのひとつに「文法」があります。
特に動詞や助動詞の活用を丸暗記しようとする学習スタイルは、すぐに限界が来ます。
五段活用、上一段、下一段、カ変、サ変…。
動詞の活用表を覚える作業は、機械的で面白みがなく、
しかもテスト本番では思い出せないケースが頻発します。
しかし本質的に大切なのは、「この助動詞はどういうときに使われるのか?」「どういうニュアンスを持っているのか?」という“意味と使い方のパターン”を理解することです。
活用表を覚えても、それが文中でどう使われるかが分からなければ、
点数には結びつきません。
逆に、意味のパターンを押さえることで、文中の助動詞や活用の役割を自然と理解できるようになり、読解力が飛躍的に向上します。
活用を覚えても意味が取れなければ意味がない
たとえば、助動詞「けり」は、文法上は「連用形接続・過去・詠嘆・ラ変型」と習います。
しかし、これをそのまま覚えただけでは、テストで「この“けり”はどんな意味で使われているか?」と問われたときに困ってしまいます。
大切なのは、文章の中で「けり」が使われているとき、どんな場面なのかを知ることです。
「昔〜けり」という形で使われるときは、単なる“過去”を表します。
「〜なりけり」「〜を見けり」などの形で文末に出てくるときは、
何かを見聞きして“ああ、そうだったのか”と感動している“詠嘆”の用法になります。
このように、意味のパターンとセットで覚えることで、文中での助動詞の意味がはっきりし、問題に対応できるようになるのです。
意味のパターンで覚えるべき助動詞の代表例
以下は、中学古文に頻出の助動詞とその意味パターンです。
活用表の暗記ではなく、具体的な使用例をもとに意味を捉えるようにしましょう。
・けり:
過去(昔の話)/詠嘆(今気づいた・感動)
例:「昔、男ありけり」→過去/「花の色は うつりにけり」→詠嘆
・たり:
完了(〜してしまった)/存続(〜している)
例:「花咲きたり」→完了または存続。文脈で判断。
・む:
推量(〜だろう)/意思(〜しよう)
例:「行かむ」→“行こう”という意志/“行くだろう”という推量
・らむ:
現在推量(今頃〜しているだろう)
例:「なにごとかあるらむ」→今ごろ何が起きているのか
・べし:
当然(〜べきだ)/意志(〜しよう)/推量(〜だろう)など多義語
例:「行くべし」→“行くだろう” or “行くべきだ” or “行こう”と文脈次第
このように、一つの助動詞が複数の意味を持つことも多く、
機械的に覚えていては判断できません。
文章の“場面”と照らし合わせて、意味を読み取る習慣を身につける必要があります。
助動詞の“パターン暗記”を習慣にする方法
以下のような手順で助動詞の学習を進めると、理解が深まります。
・ステップ①:意味ごとに分類した表を作る
助動詞を「過去」「完了」「推量」「意志」「詠嘆」などのグループに分けて、代表的な助動詞を整理します。覚える負担が減り、文中でも意味が推測しやすくなります。
・ステップ②:例文を一緒に覚える
「けり」だけでなく、「昔、男ありけり」のように実際の文章とセットで記憶することで、意味が定着します。フレーズで覚える方が記憶に残りやすく、テストでも活用しやすくなります。
・ステップ③:意味を判断するための“文脈読み”を練習する
助動詞の意味は、常に“前後の文章”との関係で決まります。そのため、単語帳的な暗記に終始せず、必ず文章の中で使われたときの意味を考える練習が必要です。
・ステップ④:同じ助動詞でも異なる意味の用例を比べる
「けり=過去」と思い込んでいると、「詠嘆」で使われたときに意味が取れなくなります。意味の違いを比較して覚えると、定着が早くなります。
文法問題が解けるようになると古文が楽しくなる
助動詞や活用形の意味が分かるようになると、
古文が“暗号文”ではなく“意味のあるストーリー”として読めるようになります。
それに伴って、設問の正答率も上がり、自信も生まれてきます。
「意味のパターンで覚える」という方法は、すぐに成果が出るというよりも、
積み重ねによって効果を発揮するタイプの勉強法です。
だからこそ、地道に続ける価値があります。
5.定期テストは「既出問題+類題」で徹底演習せよ
古文の定期テスト対策において、
知識のインプットと並んで非常に重要なのが「アウトプット=演習」です。
どれだけ単語や文法、読解の感覚を身につけていても、
それを実際の問題で使いこなせなければ点数にはなりません。
特に古文は、“見たことのある文かどうか”で得点に大きな差がつく教科です。
そのため、「演習量の確保」と「出題傾向に合わせた問題選定」が、テスト本番での得点力を左右します。
その中でも、もっとも確実で成果の出やすい方法が
「既出問題(過去の定期テスト)+類題(形式や内容が似ている問題)」を繰り返し解くというやり方です。
なぜ「既出問題」が最重要なのか?
学校の定期テストは、教師が作成するものであり、
その出題形式やレベルにはある程度の“クセ”があります。
毎年似たようなテーマ、同じ種類の設問、同じ文法問題が出ることは珍しくありません。
特に中学古文では、扱う題材もある程度限られており、出題範囲は予測しやすいのが特徴です。
したがって、過去に出された問題(既出問題)を一度解いておくだけで、
「この形式なら見たことある」「また同じような問題が出てきた」という安心感が生まれます。
これは、初見の問題に比べて理解スピードが速く、ケアレスミスも減るため、
安定して得点できるようになる最大の要因です。
類題を解くことで“初見の文章”にも強くなる
既出問題で基礎を固めたら、次は類題演習に取り組みましょう。
ここで言う「類題」とは、同じような助動詞・敬語・文脈の読解を問う問題や、
同一ジャンルの作品(随筆・物語・説話など)を題材とした問題を指します。
類題に取り組むことで、既出問題に依存せず、「似たような問題でも対応できる力」が養われていきます。
特に中学生の場合、同じ構文・意味の助動詞が登場する文章で演習を重ねることで、
「あ、この“けり”も前と同じ使い方だ」といった“使い回しの利く知識”がどんどん増えていきます。
これにより、初見の文章を前にしても、「何が問われそうか」を予測する力が備わるようになります。
3ステップ演習法で確実に得点につなげる
次に紹介するのは、多くの中学生が成果を出している「3ステップ演習法」です。
この方法に沿って学習することで、演習の質が格段に上がり、定期テストでのミスを大きく減らすことができます。
ステップ①:制限時間を設けて本番形式で解く
実際のテストと同じように、時間を測って問題を解きます。
時間を意識することで集中力が高まり、実践的な対応力も身につきます。
この段階では、「間違ってもいい」ので、自分の実力を正確に測ることが目的です。
ステップ②:間違えた問題だけをじっくり復習
正解した問題は飛ばしても構いません。
間違えた問題に絞って、なぜ間違えたのかを分析しましょう。
「単語の意味が曖昧だった」「主語を取り違えた」「選択肢を焦って読んでいた」など、
原因を特定しておくことで、同じミスの再発を防げます。
ステップ③:自力で全問正解するまで繰り返す
最終ステップでは、1回目と同じ問題を“自力で完答できるまで”繰り返します。
答えを覚えるのではなく、「意味の理解」や「文法の判断」ができる状態になるまで演習を重ねることが重要です。
この反復によって、知識が使える形で定着します。
ワークやプリントも“見直し方”次第で武器になる
学校で配られるワークやプリントは、内容そのものよりも「どう活用するか」が問われます。
ただ機械的に解いて丸つけをして終わり、では全く力はつきません。
以下のように見直しまで含めて使い切ることが、テスト得点に直結する力になります。
・解説を写さず、読みながら自分の言葉で理解する
・間違えた問題に「なぜ間違えたか」を赤でメモする
・1日置いて再チャレンジしてみる
演習の質を高めることは、何よりも確実な定期テスト対策です。
古文の勉強を“習慣化”させるための5つの工夫と環境づくり
古文の定期テストで成果を出すには、短期的な詰め込みだけでは不十分です。
単語・文法・読解・演習といった要素を日常の学習に自然に組み込む「習慣化」が不可欠です。
特に中学生の場合、古文を学ぶ時間がそもそも少ないため、週1回の授業だけで成果を出すのは困難です。
そのため、自宅学習を前提とした“継続できる勉強スタイル”を整えることが、定期テストで点を取るための近道となります。
ここでは、古文学習を無理なく続けるための「習慣化テクニック」と「環境づくりの工夫」を5つ紹介します。
1. 勉強する“時間帯”と“場所”を固定する
習慣化の基本は「タイミングと環境の固定」です。
人間の脳は、行動のパターンを記憶しやすいため、
「いつもこの時間・この場所で古文を勉強する」と決めることで、
やる気の有無に左右されずに行動できるようになります。
おすすめは「夕食後〜お風呂前」または「就寝前の10分間」です。
勉強としてのハードルが高くない時間帯を選ぶことで、習慣化の成功率が上がります。
また、場所についても、ベッドやソファなどリラックスしすぎる場所ではなく、机に座って行うのが効果的です。
2. 「古文だけ」にこだわらず“セット勉強”に組み込む
古文の勉強を単体で取り組むのは、心理的ハードルが高くなりがちです。
そこで、「他の教科のついでに古文もやる」という“セット学習”の考え方が有効です。
たとえば、英語の単語練習のあとに古文単語10個をチェックする、
数学の問題演習のあとに古文の音読を3分間だけ行う、
というように、“本命の勉強”にひっつけて習慣化するのがコツです。
こうすることで、古文だけを構えて勉強する必要がなくなり、負担感も軽減されます。
3. 「見える化」で達成感を積み上げる
古文の学習は地味な作業が多いため、モチベーションの維持が課題になりやすい教科です。
そこでおすすめなのが、「学習の記録を可視化する」方法です。
たとえば、カレンダーに勉強できた日には〇をつける、
ノートに“音読した日数”を記録する、単語の習得数をグラフで管理するなど、
自分の努力が見える形で残るようにすると、
達成感が生まれ、やる気が持続しやすくなります。
1日10分でも、それを30日続ければ“5時間”という大きな積み重ねになります。
4. 勉強内容を“簡単すぎるレベル”から始める
多くの中学生が古文の勉強を習慣化できない最大の理由は、
「いきなり難しい内容に手を出してしまうこと」です。
完璧主義で「文法も全部覚えてから読まなきゃ」と考えてしまうと、挫折してしまいます。
実際には、「とりあえず1語覚える」「1文だけ音読する」「主語と述語を1つだけ探す」など、小さなステップから始めてOKです。
むしろ“簡単すぎて物足りない”レベルから始めたほうが継続率は高くなります。
重要なのは“続けること”であり、“難しいことをやること”ではありません。
5. 周囲の協力と学習環境を味方につける
最後に、勉強の習慣化においては「環境の力」を借りるのが非常に有効です。
たとえば、保護者や兄弟に「今日は古文やったよ」と報告するだけでも、
継続の動機付けになります。
あるいは、スマートフォンの通知に「古文10分だけやろう」といったメモを設定するのも効果的です。
また、学校の先生に「古文苦手なんで毎日ちょっとずつやってみます」と宣言してしまえば、自然とやらざるを得なくなる“強制力”が生まれます。
自分の意思だけで習慣化を続けるのが難しい場合は、
周囲を巻き込んで“やらざるを得ない仕組み”を作るのが現実的な対策です。
古文は“読み方”さえ掴めば、誰でも点が取れる教科
ここまで、中学古文の定期テスト対策として
・古文単語の覚え方(セット暗記)
・音読の重要性
・主語と述語にマーカーを引く読解法
・活用表より意味のパターンを押さえる文法対策
・既出問題と類題による演習
・習慣化のための環境整備
の6つの視点から、実践的な勉強法をお伝えしてきました。
古文は、最初こそ「意味不明」「読むのがつらい」と感じる教科です。
しかし、これは裏を返せば「ほとんどの生徒が苦手意識を持っている=差がつきやすい科目」でもあります。
つまり、正しい方法で地道に学習を重ねれば、
短期間でもテストの点数をグッと引き上げることが可能です。
古文は“言語”であると認識することがスタート地点
古文を「特殊な読み物」「暗号のような古い文章」と捉えるのではなく、
「日本語の一種=言語」として捉え直すことが何よりも大切です。
英語においても、単語・文法・発音・文構造を総合的に身につけることで“読める・話せる・聞ける”ようになります。
同じように、古文も「単語の意味を感覚で捉える」「文章のリズムに慣れる」
「構造のパターンに気づく」といった積み重ねによって、読解が可能になります。
そして言語である以上、反復と習慣こそが力になります。
最初のうちは「単語の意味が出てこない」「助動詞の意味が選べない」
「誰のセリフか分からない」といった場面が必ず訪れますが、
それは“古文の文法ができていないから”ではなく、“慣れていないから”です。
この点を正しく理解し、焦らずに続けていくことが、古文克服のいちばんの近道です。
自分に合ったペースと方法で続けることがカギ
多くの中学生が、古文だけでなく勉強全般において「自分に合ったやり方が分からない」「どこをどう直せばいいのか分からない」と悩んでいます。
特に古文は、単元ごとの理解度が目に見えにくく、得意・不得意の差が曖昧な教科でもあります。
だからこそ、「個別最適化された勉強法」を確立することが、
継続と成果につながります。今回紹介した学習法を参考に、
まずは身近な単語や音読から始め、徐々に演習や文法理解へと広げていくとよいでしょう。
最初から全部を完璧にやろうとせず、5分でも10分でも、できることから始めることが何より大切です。
最後に|自分に合った“古文の学び方”を一緒に見つけませんか?
ここまでお読みいただき、本当にありがとうございます。
「もっと古文の点数を上げたい」
「今の勉強法が合っているのか不安」
「自分では続けられない」という方へ
もしあなたやお子さんが、古文を含む定期テストの勉強でお悩みでしたら、
ぜひ一度、個別指導塾ワイザーの無料相談をご活用ください。
個別指導塾ワイザーでは、以下のようなサポートを通じて、
“学習習慣がない生徒でも自然と続けられる仕組み”を提供しています。
・徹底した生活習慣のヒアリング
起床・就寝時間、スマホ使用時間なども把握し、無理のない学習スケジュールを設計します。
・365日毎日提示される「今日やるべきタスク」
古文の音読や単語の反復なども、1日単位で細かく指示。何をどう進めれば良いか迷いません。
・成果報告制度による継続支援
毎日のタスク達成を申告する仕組みがあるから、自然と“やるしかない”環境が整います。
・質問対応・カリキュラム調整・三者面談も全てオンライン対応
ご自宅にいながら、フルサポートが受けられます。
特に、学習習慣がなかなか定着しない生徒や、
苦手教科のモチベーションが保てない生徒にとって、
ワイザーの仕組みは“自分を変えるきっかけ”となるはずです。
今なら、オンラインでの無料学習相談を受付中です。
お子様の現在の学習状況にあわせて、最適な学び方を一緒に設計いたします。
お気軽にご相談ください。
▼無料相談はこちらをクリック▼



